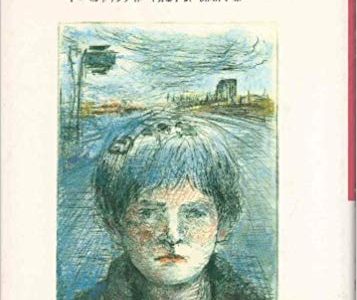モモンガ:これは『クローディアの秘密』と『ダンデライオン』の、ちょうど中間に位置する作品かしら。全体に暗い感じはするけど、味方になってくれる大人がいてくれて、そのパパフンフンとテオの心の結びつきが、とってもいい。これからテオが何かを見つけるっていう安心感、将来の希望が感じられた。
ひるね:私も、おもしろかった。テオの心情の移り変わりが、とても自然に描かれてるわね。パパフンフンだけではなく、途中で出会う人びとが印象的。ケマルとか、店番をしている女の子とかね。深刻になりすぎないで、ユーモアをまじえて描いているところがいいと思う。読んでくうちに、パパフンフンに惹かれていくのよね。テオの成長の過程も、きちんと見えるし。先代の三遊亭金馬の「藪入り」ってあるじゃない? 私、大好きなんだけど、家族から離れることで子どもが目覚ましく成長していくところなんか、あれみたいだと思った。メルヴィン・バージェスの『ダンデライオン』のジェンマより、テオの方がよっぽど自分で選択してると思うし、これから先しっかり生きていけそう。明るさを感じるわ。でも、これはテオが10歳だったからであって、もしもっと年齢が上だったとしたら、こんなふうにはいかなかったんじゃないかしらね。テオの両親が離婚しちゃったのにも、どきっとさせられたわ。あまく流されていないっていうのかな。
この作品も『ダンデライオン』も、作者の社会を見る目、子どもを見る目が、しっかりしてる。真実を誠実に伝えようという姿勢が伝わってくる。主人公だけでなく大人の描き方にしても、それを感じた。パパフンフンに家族のことをたずねたら、「いない」とすぐにきっぱり答えた、というところがあるでしょ。この1行だけで、パパフンフンのそれまでの人生が、よくわかる。それとか「学校ではヒョーキンもののテオが、家に帰ると変わってしまう」っていうところなんかも、作者はきちんと見てるんだなあと思った。今、ティーンエイジャーの犯罪が社会問題になってるけど、犯人の少年についてまわりの大人は「彼がこんなことをするなんて信じられない。ヒョーキンで明るい子だったのに」なんて、簡単に発言したりするでしょ。親も先生も、子どもに対して無関心で、表面的なことしか見てない大人が多いんじゃないかと思う。だって実際には「ヒョーキン=明るい」ということには、ならないのにね。ヒョーキンを「演じてる」ってことだってあるから・・・。誤解だよね。そういうところ、ヘルトリングはちゃんとわかってるんだなあと思ったな。
ねねこ:今回の4冊の中で、心情的にはこの作品がいちばん自分の家出に近いと思った。テオは自分が死んで、両親が嘆き悲しんでるときのことを想像したりするでしょ。これなんて私もよくやったし、その気持ちはよくわかる。子どもの無力感みたいなものが、よく描けていると思う。テオみたいな、苛酷な状況にあったとき、子どもに何ができるの? って考えてみると、どうしようもないのよね。結局、子どもには何もできないわけじゃない? 子どもは、どんな状況でも受け入れるしかない。そういう厳しさが、とてもよく描けていると思った。子どもの内面の深みとか、そのつきつめ方が『クローディアの秘密』とは全然違う。どんなに苛酷な状況だったとしても、がまんしなくちゃいけない期間ってあるでしょ。子どもは、その時代をなんとかやりすごす術というのを、身につけなくてはいけないのよね。
愁童:ぼくはこの本を読んで、「なんで本を読むのか」というか「本を読む原点」みたいなものを、思い出した。読んでよかったと思える本。やっぱりパパフンフンに会えるっていう体験・・・人生の先輩、尊敬できる先輩に会えるというのかな。疑似体験だけど、それが楽しめるから、本を読むんだと思うんだよ。今回の4冊の中では、いちばん安心して読めた。
ウォンバット:私も、おもしろかった。やっぱりパパフンフンが好き。風貌もふくめて、とっても魅力が感じられた。全体的なトーンは、グレーではじまりグレーでおわるって感じなんだけど、暗すぎないし、嘘っぽくないと思うな。
オカリナ:テオみたいな、こういう状況だからこそ、家出するのよね。閉塞状況がとてもよく描けていると思った。「ここじゃないどこか」に行きたくて、転々とするわけだけど、そこで起こる出会いのひとつひとつについて、もうあとひと筆でも、あったらもっとよかったのにと思った。そこが、ちょっと物足りなかった。残念。それに絵も・・・暗すぎると思うんだけど。
ウォンバット:同感。
愁童:ぼくは好きな絵じゃないけど、効果的な絵だと思ったよ。
ウンポコ:ぼくは、この絵、好きだな。とくにパパフンフンがテオを抱きしめるところ(p180)なんて、いいなあ。成功してると思うよ。他の絵描きさんでは、この雰囲気を出すの、難しいんじゃない? 物語もよかったよ。ぼく、ヘルトリング好きなの。『おばあちゃん』(上田真而子訳 偕成社)と『ヨーンじいちゃん』(上田真而子訳 偕成社)が、とくに好き。ヘルトリングは大人を描くのが、うまいと思うんだよね。子どもは残念ながら、自分で家族を選べないわけだけど、パパフンフンみたいな大人もいるんだよっていうのは、子どもを勇気づけると思う。テオみたいな子どもに対する応援歌になってるんじゃないかなあ。エレベーターで出くわす「安ものの香水の女」も、いかにもいそうな感じ。現実には、好き嫌いに関わらず、こういう人に会っちゃうことってあるだろ? いかにもありそうなことなんだけど、こういうことまで書く人、日本の作家にはいないよね。現実には、こういう人ともうまくやっていかなくちゃいけないのにね。
ねねこ:ねえ、親ってなんなんだろうね。
ウンポコ:どんな親であれ、子どもは親に対して満足できないもんだと思うよ。それにしても、ヘルトリングって「この人こそ、少年の物語を書く人」っていう気がする。健全な作家姿勢を感じるね。メッセージも、しっかり伝わってくるし。
オカリナ:私も、ヘルトリングって誠実な人だと思う。最近の彼の作品は、ちょっと暗いものが多いんだけど、社会状況が悪くなってるから、しかたないって部分はあるんじゃない? こんな世の中で、嘘っぽくなく、つくりものっぽくないものを書こうとしたら、どうしたって暗くなっちゃう。そらぞらしいことの書けない、まじめな人だから、現実を書こうとすれば、暗くなってあたりまえ。
ウーテ:これは1977年の作品だから、まだパパフンフンが存在してたんだけど、今はパパフンフンみたいな人って、いなくなっちゃったでしょ。このごろのヘルトリング作品に、温かさが感じられなくなったのは、ヘルトリングが変わったのではなく、社会が変わったんだと思う。ヘルトリングの生い立ちは、悲劇的なのよね。彼は1933年生まれで、お父さんは弁護士だったんだけど、ちょうどヒットラーの全盛のときでしょ。アンチ・ヒットラーだったお父さんは収容所に送られて亡くなり、お母さんは、その後やってきたソ連兵に子どもたちの目の前でレイプされて、自殺。結局、孤児になってしまったのね。そんなふうに小さいときに家族を失ってしまったから、「家族」というものに対する憧れとか思い入れが、人一倍強いんじゃないかしら。もともとは詩でデビューした、大人向けのものを書く作家だったのよ。それが、自分に子どもが生まれてみたら、子どもに読ませたい本がない、だったら自分で書こうって、子どもの本の世界に足を踏み入れた人なのよね。とっても良心的で、適当なことなんて書けない人。詩人だから、「行間で勝負!」という感じで、言葉が少ないのね。だから、翻訳はとても難しいと思う。詩人的な要素のある人の作品は、難しいものよね、翻訳するのが。反対に、ネストリンガーなんかはとっても饒舌だから、訳しやすいと思うけど。
ねねこ:「無口な男ほど理解しにくい」ってのと、一緒よぉ。
愁童:『ダンデライオン』に出てくる煙草屋さんって、ちょっとパパフンフンと似た存在なんだけど、ジェンマやタールに対してもっと冷たいし、まるっきり無責任だよね。彼のような存在に対する扱い方が、ヘルトリングとバージェスでは全然違う。作家の姿勢の違いを痛感するところだね。やっぱり子ども読者を意識してる作家だったら、作品のどこかに明るさがなくっちゃね。いろいろとつらいことはあるだろうけど、がんばって生きていけよっていうようなさ。
オカリナ:絵空ごとになっちゃいけないわけだから、良心的であろうとすればするほど、時代とともに作品は暗くなっちゃうんじゃないかな。
ウーテ:フィクションには普遍性が必要だから、難しいわよね。ノンフィクションだったら、ちょっとくらいヘンでも「事実です」ってことで、すんじゃうけど、フィクションは、そうはいかないから。ヘルトリングって、ほんとにまじめないい人なのよ。
愁童:テオが街の子に会って元気づけられるっていうところ、あったね。あそこもあったかい感じがして、よかったな。一方『ダンデライオン』は、街の子に会って落ち込んでいくんだよ。この違いも大きい。
ひるね:『ダンデライオン』と『テオの家出』では、主人公の年齢による差もあると思うわ。テオがタールの年だったら、またちがったでしょうね。
ウンポコ:翻訳者が苦労して訳してくれたおかげで、日本の子どももこのすばらしい作品を読むことができるんだ。ぼくは、日本の子どもを代表して、訳者にお礼をいいたい気持ちだよ。
(2000年05月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)