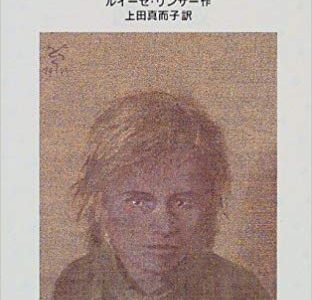紙魚:今回読む本は2冊だったんだけど、先に『波紋』を読んでおいて、ほんとよかった! おかげで『象のダンス』は、楽々だった。この2冊は、またぜんぜん違う本ね。『波紋』は、シークエンスにくぎって、こうだったこうだったと、驚くほど緻密に描写してるんだけど、自分のことをふりかえってみると、子ども、というか、10代のときって、至近距離のものしか見えていなかったと思うのね。「予測」ってものができてなかった。でも今は、多少なりとも成長したから、枠組みの中でものをとらえるのが、ちょっとはうまくなってる。だから、建物の描写にしても、今だったら、全体像を頭においてその部屋の一部を想像するっていう読み方ができるけれど、中学生のときだったら、大枠なんて考えずに、その部屋にぽーんととびこんでいたと思う。リンザーって、非常に筆力のある作家よね。大人になって、この作品を書いたわけだから。子どものころの目線を失わず、ここまで描ききるというのは、大変なことだと思う。それでね、つい自分のやってきた仕事、「編集」について振り返ってしまったんだけど、私はもう、子どものころの目線を失っちゃってるんじゃないの? って思えてきて、反省しながら読んだの。あと、気になったのは、この本を読むのはどんな人たちなんだろうかということ。『象のダンス』と『波紋』の読者層って、重なるのかしら。読者の中で、どんな心の動きがあるんだろうか、とかね。だってこれは、中学生のあいだで「この本、おもしろかったよ」なんて、話題になりそうな本ではないでしょ。『象のダンス』は、友だち同士で「これ、おもしろかったから、読んでみる?」なんて会話が成り立ちそうだけど。『波紋』読者の生態は、いったいどうなんだろう・・・というふうに、読者層がたいへん気になる作品でした。
アサギ:私も『波紋』を先に読んでたから、『象のダンス』は楽だったわぁ。これは、密度の濃い物語ね。電車の中で、とびとびで読んだりすると、すぐ筋がわからなくなっちゃう。最初の「僧院」なんて、雰囲気がよく出てて、ほんとすばらしいんだけど、読むのに疲れた。「見知らぬ少年」も、主人公が野性的なものに憧れる気持ちがよくわかる。確かな筆力を感じたわ。あとね、「エリナとコルネリア」の章は、映画「制服の処女」の世界だと思った。
ウォンバット:えっ? 知らない。いつごろの映画?
アサギ:1930年代。あら、もちろんリアルタイムで観たわけじゃないわよ。ウーファという映画会社の全盛期だったのね、このころって。その後、ナチの台頭で、ドイツ映画はだめになっていくんだけど・・・。「制服の処女」は、カトリックの女子寄宿学校を舞台にした映画で、やっぱり偽善的な校長が出てきたりしてね、雰囲気がこれととてもよく似てるの。
ひるね:そう、似てるわね。「制服の処女」って、戦後、リメイクもされてるわね。ロミー・シュナイダー主演で。あら、私もリアルタイムではないのよ。念のため、言っとくけど。
アサギ:それにしても、この本を読む子どもって、いるのかしら。この主人公と同じ年代の子どもが読むかどうかは、疑問だわ。大人は読むかもしれないけど、現役の子どもには、ちょっとね・・・。濃密、緻密な描写で、ていねいにていねいに描いているから、まさにその場面が目に浮かんでくるんだけど、でも、読むのはたいへんよね、こういう作品って。私は、全体としては「おもしろい」というより「勉強になった」というか、「興味深い」という感じだったわね。
裕:すごくドイツ的な作品。あとがきを読んだら、そういう読み方もできるのかと思ったんだけど、ナチに文学で対抗しようとした、という姿勢にハッとさせられた。このあいだ、シンポジウムに参加するためにウィーンに行ったんだけど、そのときも考えさせられたのね。やっぱりウィーンも、ナチの支配下にあったわけでしょう。そういう戦中戦後の難しい時代に、文学者がどんなふうに発言してきたか、政治から一歩ひいて、文学にしかできない方法で表現しようとしていたことがあったという事実を、今になって、振り返ることができるようになった。リンザーも、少女の心の中の複雑で入りこめない意識を描いているようだけど、実は非常にポリティカルなのよね。それで、投獄されたりしていてね。そういう複雑な意識がバックグラウンドにあるんだけど、作品の作り自体は、とてもクラシカル。主人公をわかってくれる大人、あの「叔母さま」とかね、そういう人が、ちゃんと存在している。そういうところ、現代の読者からしたら、陳腐に見えるかもしれないわね。体制に対する意識も、ちょっとついていけないかも。私は今回、『象のダンス』は読んでないんだけど、総じて日本の作品って、ファジーでふわふわふわぁって感じでしょ。読みこむ必要がない。でも、この作品はずっしりと書きこんでるから、しっかり読みこまないとだめ。とっても重厚な作品よね。
私は『悪童日記』(アゴタ・クリストフ著、堀茂樹訳、早川書房、1991)を思い出したの。雰囲気がとてもよく似てると思って。私はこういう世界、非常に好き。読者については、翻訳作品としては問題あるかもしれないけど、ドイツだったら、この作品を読む子どもって、いると思う。たしかに、日本の子どもには、ちょっと難しいかもしれないけどね。
アサギ:私、リンザーって、日本でいうとだれだろうって考えてみたんだけど、思いあたったのは、三浦綾子。ま、根拠のない、独断だけど。ほら、純文学ではなくて、主流では認められていないんだけど、熱狂的なファンがいて・・・というあたり、文学界での立ち位置、そのズレ方が、三浦綾子! と思ってね。
ひるね:とても耽美的な作品よね、これ。こういうのって好きな人は好きだけど、嫌いな人はもう生理的にだめよね。ぱっと意見が分かれそう。私はといえば、どうも「美しい」というより、「気味が悪い」と いうほうが先に立っちゃって。好きか嫌いかといったら、嫌いの部類。まず、ユーモアがないでしょ。「ゆとりがない」というのかしら。 だれかが松田聖子のこと、「恋はするけど、愛せない人」って言ってたけれど、この主人公もそういう性格の女性だと思うわ。
裕:聖子は、体温が低いって感じ。
ねねこ:えー、体温じゃないと思うなー。自己愛の問題じゃない?
ひるね:「エリナとコルネリア」の章は、少女漫画好きにはいいかもしれないわね。ちょっと私には、ついていけない感じだけど。あと、花の名前がたくさん出てくるでしょ。そうそう、それで、日本名とカタカナがごちゃまぜなのが、気になったの。とくに、これだけは言っておかなくちゃと思ったのは「日本アネモネ」。「日本アネモネ」って、「秋明菊」のことよ。「秋明菊」のほうが、だんぜんポピュラー。「貴船菊」とも、いうんだけどね。
モモンガ:この本、私にしてはめずらしいことなんだけど、読めなかったの。いつもカバンに入れていて、電車に乗るたびに開いたんだけど、どうも眠くなっちゃて。
ウォンバット:これ、電車の中では無理かも。
ウンポコ:「祖父」の章を、先に読んでくれればよかったのに。
ひるね:あの章は、体温が感じられるわよね。
ジョー:私は「森のフランチスカ」まで。軽井沢の木かげで、一日じゅうのんびり読んだら、堪能できるであろう作品。日本語も、難しい言葉を使ってるでしょ。さすが岩波書店! という印象。そして、ドイツ的。
アサギ:私も、ドイツ的だと思う。
ジョー:背景にある、民族的なものがよくわかる。異文化を知るとっかかりとしては、よいのでは? たいへん美しい作品だし。
ねむりねずみ:ドイツって、ボリュームのある作品を書く作家が多いよね。私は、一時期ドイツものに凝っていた時期があったの。ヘルマン・ブロッホとか、ギュンター・グラスとか読んでたんだけど、久しぶりにそういうドイツ的な雰囲気が感じられて、なつかしかった。日本語でだって難しい、観念的な世界に入っちゃってるんだけど、その手応えもまた、よくってね。ドイツものにハマる前は、フランスものを読んでたの。ドイツとフランスって、ほんと違うでしょ。雰囲気が。ドイツものって、個人の心理になだれこまず、視野を広くもって 物語世界に入っていくから、どーんとしたものが感じられる。この作品もまた、そういうドイツの骨太な感じを強く受けた。すっごく読みにくいんだけど・・・。最近は「すらすら読める系」ばかり読んでいたから、久しぶりに、アタマ使って読んだって感じ。クラシックな僧院の様子と、思春期の少女の心の動きのアンバランスなところも、とてもよく表現してると思う。ところで、この作品の対象年齢は、いかに? どういう人に、人気あるの?
モモンガ:岩波少年文庫ファンって、たっくさんいるのよ。
ひるね:ファンにとっては、「待望の作品」って感じじゃないのかしら。
ねむりねずみ:ヘルトリングもドイツっぽいと思ってたけど、これとはまた、違う雰囲気。
モモンガ:岩波少年文庫、ドイツ、上田真而子訳の3拍子そろってるんだもの。迷わず買っちゃうっていう人、いるわよ。
ひるね:いわゆる子ども向けの文学、「児童文学」ではないかもしれないけどね。
ねむりねずみ:挿絵がモノクロなんだけど、ぼやーっとしちゃってよく見えないのが、残念。せっかくムードのある絵を使ってるのにね。カラーで見たかったな。
ひるね:あら、わたくしは、絵はなくてもよかったと思ったけど。
ねねこ:少なくとも、キャプションはいらなかったわね。
アサギ:リンザーの作品、日本では『噴水のひみつ』(ハンス・ポッペル絵 前川康男・高橋泉訳 佑学社)が有名よね。
ウェンディ:私は情景描写が続くのって、どうも苦手なんだけど、「波紋」の章の“聖なる泉”の描写は、そのひとことひとことから風景がわきあがってくるようで、とても好きだった。
アサギ:私も! あそこの描写、すごく好き。詩のような美しさがある。
ウェンディ:そういえば、私、いちばん最初に担当した本が、リンザーの『なしの木の精スカーレル』(遠山明子訳 福武書店)だったの。久しぶりに、もういちど読み返そうと思ってるんだけど。
ウンポコ:さて、次は愁童さんだ。絶賛の弁が聞けるかな?
愁童:ちなみに言っとくと、ぼくも「制服の処女」はリアルタイムではないんだけどさ、ぼくたちの高校時代ってのは、ヘッセブームだったんだよ。この本にも、ヘッセに似た雰囲気を感じたね。今どき読もうとすると少々しんどいけど、なつかしかった。重厚で、綿密な描写。糸を織るように心情を描いている・・・。わが青春時代には、そういう本をたくさん読んだものだけど、今の子どもに、読めるかねぇ。
裕:この本、Tさんが担当したんでしょ。あとがきに書いてあるけど。Tさんらしい本よね。
愁童:と、いうと?
ねねこ:Tさんって、トラディショナルな本を多く手掛けてる編集者でしょう。やっぱり、この本は「岩波少年文庫・ドイツ・上田真而子訳」で成立してる本だと思う。出版社によって、それぞれ「合う本」って、あると思う。たとえば、ミヒャエル・エンデの作品は、最初、講談社からいくつか出たんだけど、岩波書店ではうまくいった。それってつまり、エンデは岩波向きというか、岩波の本が好きな読者にうまく届いたってこともあると思うんだけど。この本、風邪でぼーっとした頭で読んでると、眠くなっちゃうね。なんかこう、たゆたう感じで。今の子どもには、ちょっと難しいかも。『象のダンス』が「映像的」だとすると、この作品は「感覚的」。少女の感覚が、よく描けてる。具体的には、よくわからないところが、いろいろあるのよね。主人公の両親とかさ。この祖父も、なんだかよくわからない。
アサギ:この祖父、唐突に「仏教徒で」なんて出てくるけど、何をしてた人なのかは、まるっきり不明。
ねねこ:全体にキリスト教の教養がないと、物語世界に入っていけないでしょ。もどかしいような感じは一種、自虐的な楽しさでもあったんだけど。でもやっぱり、それぞれの民族の歴史の違いというか、民族的なものの中で蓄積されてきた表現描写の違いというのを、意識しちゃったな。日本人がずっと慣れ親しんできた描写とは、テンポが違うでしょ。だって、ほら「春はあけぼの」のたたみかけの心地よさとは、基本的に違う。だから、読むのがたいへんといえば、たいへん。でも、苦労して読んだ甲斐はあって、その点、「ハリー・ポッター」とは違ってた。「時間、ソンした!」とは、ぜんぜん思わなかったもんね。あとね、「オフィーリア」の絵(ジョン・エヴァレット・ミレー作)を思い出したの。
ねむりねずみ:あ、あの女の人が仰向けで水に浮かんでいる絵! よくわかる、その感じ! 印象的な絵だものね。
ひるね:オフィーリアをタイトルにもってきてる本、あったわね。そうそう死と少女を語った『オフィーリアの系譜 あるいは、死とて女の戯れ』(本田和子著 弘文堂)というおもしろい本があるけれど、『波紋』もその本のリストに加えられるといいと思ったわ。
ねねこ:神沢利子さんの「いないいないばあや」の世界にも似た印象。それにしても、この主人公、頑固よね。
愁童:最後のほうでさ、あの男の子たち、レネとゼバスチアンとずっと楽しく遊んでいたのに、突然主人公がすっと冷める場面、あったよね。こないだまで夢中でやっていた遊びなのに、「こんどこそという期待にみちて試してみるのだが、すぐに飽きてやめてしまった」というあたり。女の子の、そういう心の成長の過程が、よく描けていると思ったな。
裕:たしかにそうね。でも、男の子の読者は、こういうの読まないんじゃない?
ひるね:わかんないわよー。ほら、ヘッセだって……。
アサギ:でも、ヘッセとは、抱えているものが違うからね。
ウォンバット:私はこの作品、タイトルがいいなあと思って。とってもインパクトがあるでしょ。『波紋』って。今回読む本に決まる前から、気になってたの。このタイトル。池波正太郎のエッセイを思い出してね。どんな話かというと、「俺は、小説を書くことにした。タイトルはもう決まってるんだ。それは『断崖』というのだよ」っていう友だちが出てくるのね。で、正ちゃんは「うむ、いいタイトルだ。がんばれよ」っていうんだけど、その友だち、タイトル決めただけで、ぜんぜん書かないのよ。それで、せっかくいいタイトルなのに、惜しいっていう話。この『波紋』ってタイトルを見たとき、その話が頭に浮かんだの。ま、内容とはなんにも関係ないんだけど。言いたかったのは、言葉のもつイメージ、『波紋』っていう言葉のもってるイメージが、『断崖』と同じくらい強烈で、うっわー、読んでみたいという気持ちを、非常にそそられたということなの。だけど、これって、大人の感覚だと思うのね。子どものとき、たとえば私が中学生だったら、『波紋』っていわれても、ピンとこなかったと思う。今の一般的な中学生も、『波紋』っていわれたって、「なんのこっちゃ」じゃないかな。さっきから読者対象の話がいろいろ出てるけど、タイトルからも、どんな読者に向けて作られた本なのか、いまひとつわからない感じ。ところで内容はというと、最初のほう「僧院」「百合」の章は、文字をいっしょうけんめい追いかけるんだけど、つるつると表面だけをうわすべりするようで、物語の中にぜんぜん入っていけなかったの。でも、3章の「見知らぬ少年」で、外の世界、いけないとされているものへの憧れとか、盲目的に従ってきた戒律への反抗心が頭をもたげるところとか、テレーゼへの憎しみや人形のエピソードがつぎつぎ出てくるでしょ。そこで、それまでが嘘のように、主人公の感情の動きにぐいぐい惹きこまれて、物語世界にすぽっと入っていけたのね。そうしたらその先は、もうどっぷり楽しめた。「エリナとコルネリア」の章も、女子校のエスな雰囲気が、とてもよく伝わってきて、わかるーって感じ。これは恋ではないと思うんだけど、だれかにモーレツに憧れる気持ちとか、モーレツな嫉妬とかって、その対象が男であれ女であれ、10代のころにはよくあることだなぁと思いながら読んだ。
ウンポコ:ぼくは「恒例ウンポコ読み」だけど、おもしろかった。これは、一種の私小説だと思ってさ。で、私小説には、「和食の私小説」と「洋食の私小説」があると思うわけ。これは「洋食の私小説」だな。ぼくは、この作品の出版された年、1940年生まれなの。1940年ごろって、大人は子どもの成長にいっさい関知しない、というか、大人が子どもと無関係に生きてた時代だと思うんだ。大人の存在感が大きい。この作品には、そんな時代性を感じたね。とりわけ、祖父の存在が気になった。なんというのかな、謎めいてるでしょ。バガボンドでさ。
ねねこ:このおじいちゃん、「明治生まれの男」って感じ。あの庭を歩く場面、とってもよかったわ。
ウンポコ:あの建物の描写なんかも、めくるめく感じで、想像の世界を刺激されるよね。子どもの想像力のすばらしさも、感じたな。めずらしくウンポコは、主人公に寄り添ってみたのだった・・・と。
アサギ:さっき、ひるねさんがこの作品には「ユーモア、ゆとりがない」って、おっしゃったでしょ。ちょっとそこにもどりたいんだけど、その「ユーモア、ゆとりのなさ」こそ、「ドイツ的」ってことだと思うのね。本来的なドイツ文学の書き方だと思う。どういうことかというと、距離をおかないっていうことなの。映画にも同じことが言えるんだけど。「ラン・ローラ・ラン」や「ノッキング・オン・ザ・ヘブンズ・ドア」とか、このごろは今までのドイツ映画とは、ちょっと違った感じのものが登場してるけど、対象とのあいだに距離をおかないというのが、本来的なドイツ映画の特徴なのね。「ドイツ文学らしいドイツ文学」もそれと同じで、「自分自身」と密着してるから、ゆとりもないし、客観性やユーモアは生まれにくい。
ひるね:前にここで読んだ『朗読者』(ベルンハルト・シュリンク著 松永美穂訳 新潮社)は、またちょっと違ったわね。
アサギ:あれは、純文学というより、エンターテイメントに近いから。基本的に、ドイツの作家って「オレは書きたいものを書く。読みたい者は読めッ!」って姿勢なのよ。フランス文学との大きな違いは、「観客を意識してるかどうか」という点。とても対照的だと思うのね。ドイツ文学とフランス文学って。ドイツ文学は距離をおかないぶん、主人公が読者の状況と合うと、この上なくぴったりきて、「これは私のもの!」となって、ハマっちゃうのよ。だから、独文好きってオタクが多いのよね(笑)。昔、青春ものっていうと、ヘッセとかカロッサとか、ドイツ文学がとてもよく読まれたのも、ひとつにはそういうことだと思う。
ねむりねずみ:本国ドイツでは、どうなの? たとえば、ギュンター・グラスの『ブリキの太鼓』(高本研一訳 集英社)は?
アサギ:あーら、ギュンター・グラスの好きなドイツ人なんて、いないわよ。彼はポーランド北部のダンチヒ生まれで、テーマは何かと言えば、「マイノリティ」。『ブリキの太鼓』は別格だけど、その他の作品は、多くのドイツ人にとって、「わからん」って感じじゃない? でも、いいのよ。さっきも言ったけど、「読みたい者が読んでくれれば、それでよし。あとはもうどうだっていい」っていうのが、ドイツ文学だから。
ひるね:久しぶりに外国の文学を読んだって感じがしたわ。
アサギ:50年前の作品だしね。学習によって、当時の雰囲気はよくわかりましたわって感じ。だけど、おもしろかった? っていわれると、ちょっと違う。
ねねこ:この前、久しぶりに二葉亭四迷を読み返したら、何だか妙におもしろかった。『波紋』よりは、ずっとずっと前の小説で比べものにはならないかもしれないけど。若いころはちっとも理解できなくて、「なにこれ、ヘンなの」と、思ってたんだけど。田山花袋の「蒲団」なんかも今読んだら、とっても新鮮! そんな自分に驚いてしまった。
ウンポコ:考えてみれば、日本の近代はみんな私小説だね。
ねねこ:どんなに外国ものに慣れてきたといっても、先祖から代々受け継いできたものって、やっぱり根強いのかも。遺伝子に組みこまれていた感覚が、年齢とともにあらわれてくるのかしらねぇ。
(2000年12月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)