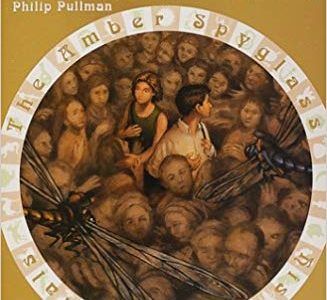すあま:1巻、2巻を読んでから時間がたっていて内容を忘れているせいもあり、3巻は200pくらいまでしか読めていないが、ここまでだとあまり面白くなかった。3巻に至るまでの道筋を忘れているせいかな。主人公に共感できないし、この子たちが面白くないです。1巻、2巻を読んでいる時も好きになれなかったし、世界が交錯しすぎていてパンクしそうになってしまう。1巻から2巻では世界がガラッと変わっているが、キリスト教の話に至ってからは、作者の狙いが大きすぎるためか、宗教的根元にまで持って行かれるとついて行けない。登場人物も良い人か悪い人か良く分からない。私はキャラクターを好きにならないとついて行けないし、評判になっていることに驚いているくらい。図書館では、一般書とするか児童書とするか、置き場所にも迷う本ですね。
アカシア:このシリーズは最後まで読まないと、作者が言いたいことや構築した世界が見えてこないわね。私も1巻と2巻は主人公に感情移入できなかったの。構築している物語世界には興味があったんだけど、おもしろいと思って読めなかった。でも、3巻の後半になっておもしろくなってきた。
「ホーンブック」の2001年11/12月号にプルマンが「天の共和国」というエッセイを載せているの。そこでは、プルマンはまず、「神の死」によって現代人は生きる意味や、自分と宇宙のつながりを宗教に求めるわけにはいかなくなったと言うのね。そして、宗教のかわりに「天の共和国」という概念をもちだしてきて、どこか別のところに理想の世界があるのだと考えるのではなく、今、この現実界にその共和国をつくるということが重要なのだと言うの。そして、グノーシス派やC.S.ルイスやトールキンのファンタジーなどは、どれも現実界に意味や喜びを見出すという考え方を否定することにつながるから駄目だと、批判するわけね。この「天の共和国」というのは、個々の人間がそれぞれ孤立して生きるのではなく、他の人々や自然や宇宙をかかわりを持ちながら生きる場所ってことらしいんだけど、このエッセイを読んで、私は、「ああ、プルマンはこの『天の共和国』の一つのかたちを書きたかったんだなあ」と思ったんですね。「そうか、そういうことが言いたかったのか」と。
ただね、プルマンは、「ファンタジーに書かれる登場人物は、現実界の人間の特徴を映し出していなきゃいけない」って言ってるんだけど、〈ライラの冒険〉シリーズの登場人物は、私にはあまり現実界の人間というふうには感じられなかった。とくにライラのお父さんとお母さん。ライラやウィルは、終わりの頃になって生き生きと動き出したんだけど、お父さんとお母さんは最後にライラを生かすために犠牲的になって死ぬってところだけしか実体がない。だから私は、ストーリーとしてはあんまり成功してないんじゃないかな、と思ってしまった。訳の問題もあるのかな? リアルに生き生きと浮かび上がってこない点、不満が残った。
ペガサス:1巻を読んだ時は、〈ハリー・ポッター〉よりずっとおもしろいと思いました。長い物語を丹念に書いてあるので、映画を見ているように想像することができ、全くはじめての世界を楽しめました。2巻、3巻と進むにつれて、だんだん多くのことが盛り込まれてくるし、1巻よりも登場人物も増え、場面もくるくる変わるので、ゆっくりと味わうよりも、とにかく先へ進まなきゃ、って感じになる。訳者の解説に書いてあるように、まさにジェットコースターなみの展開ですね。全巻を通して感じたこの作品の特徴は、とにかく異界・不思議世界の構築に独自性があるということ。ダイモンの存在もユニークでひきつけられる。3巻目になるとちょっと飽きてきたけどね。鎧を着たクマ、トンボを乗り回す戦士、ダイアモンド形の足を持つ生き物など、キャラクターにもオリジナリティがある。けれども、これだけ大部で評判も高い作品なので、作者プルマンはこのなかできっと何かを言おうとしているんだぞ、それがわからなきゃあ、だめなんだぞ、ってちょっとプレッシャーを感じてしまう。
それが少しわかったかな、と思ったのは、3巻の464p死の国でウィルが父親と会った場面で、父親の言う「われわれは、地上の共和国—楽園を自分の世界にきずかねばならない。われわれにはほかの場所はないからだ。」というところや、572pでライラに「神を信じるのをやめたとき、善悪を信じるのをやめたの?」と問われたメアリーが「いいえ。ただ、わたしたちの外に善の力と悪の力があると思うのをやめたのよ。そして、善と悪は、人間のおこないについていえることで、善人と悪人がいるんじゃないと信じるようになったの。」という部分で、ああこういうことが言いたいわけなんだな、ってわかってきた。善悪の区別のできないキャラクターを登場させるわけもわかった。でも、何か意味をみつけなきゃ、と思いながら読んでいくってしんどいから、あまり考えずにお話を楽しもうとしたほうがいいけどね。とにかく、たくさんの世界を体験し、果ては死の国まで連れて行かれてしまう。またいろんな切り口で人間をみせてくれる。結果的には、人間って何だろう?この世界は一体この先どうなってしまうのか?というようなことまで、考えさせられた。それは漠然としたものだったけれど、あとがきを読んで、また今紹介してもらったプルマン自身の考えを聞いて頭が整理できました。大きな作品だと思う。
不満な点は、ライラって最初は元気で魅力的だと思ったけど、だんだんそれが鼻についてきて、自己中心的で嘘つきでいやな子どもに感じられてきたのね。それは彼女のせりふの訳し方にも影響されてると思う。「〜〜だわ。」を多発しているのがすごくうるさい。
トチ:訳者は今時の女の子の話し方をよく知らないのでは? 「〜〜だわ」という話し方をするのは、おばさん世代。いまは、男の子と女の子の口調がどんどん近づいてきている。でも、微妙に違うんだわよね。
ペガサス:男の子と女の子の口調の違いがはっきりしていなし、口調のせいもあってすごく子どもじみている。3巻の最後で大人に成長するでしょ。でも成長の途中の過程があまり感じられなかったから、突然ライラがウィルに愛を告白して、なんだか唐突だと思った。こんなに長いことライラに付き合ったのにその成長がいまいち納得できないのは残念でした。ライラとウィルをアダムとイヴになぞらえているんだけれど、キリスト教を知っていないと日本の子どもたちには分からないんじゃないかしら。アダムとイヴのパロディのおもしろさが分からないんじゃないかしら。
トチ:口に赤い実をふくませるところなど「あっ、知恵の木の実!」と創世記の記述を思い浮かべ、その色の鮮やかさにこめたプルマンの心に感動もしたけれど、聖書に親しんでいない日本の子どもは分からないかもしれないわね。
ペガサス:3巻の各章にウィリアム・ブレイクやジョン・ミルトンの言葉が書かれているけど、それぞれに意味を持たせているはずで、そういうところももっと理解できれば良いのかもしれない。
アカシア:ダイヤモンド形の骨格の生き物が出てくるでしょ。こういう姿のものをプルマンが敢えて創造したところに、何か意味があるわけ? 私はその辺もよくわからなかった。
ねむりねずみ:プルマンは、パラレルワールドの作り方がすごくうまいと思う。ダイヤモンド型の骨格の生き物にしても、エデンの園を思わせるのどかさと機械的な部分がない交ぜになっていてオリジナリティがある。どこかで見たようでいて、プルマン独自の世界になっている。
トチ:ダイモンは、中近東の昔話によくでてくる守り神によく似ているわね。たとえば、魔物が悪いことばかりしているので滅ぼそうとするけれど、絶対に滅ぼせない。ところが、海のむこうの小島に魔物の守り神である鹿が住んでいることがわかる。その鹿を殺せば、魔物も滅ぼすことができる。
羊:私は、1巻の表紙のライラと熊の絵が気に入って期待して読み始めたのですが、ライラがいたずらっ子で『モモ』(ミヒャエル・エンデ著/大島かおり訳/岩波書店)みたいな女の子かなって思ってワクワクして読んでいったら、なんとも複雑で。登場人物も多いし。ダイモンは魂のようなものかな? ダストは何? 気配の事? 深いものがありそうだ、などと考えていると訳わからなくなってきたけど、「?」を考えない事にして読めば、今までになかった世界を面白く読めた。2巻の中くらいでウィルとグラマン博士と出会うあたりから、「?」が分かってきて面白くなってきました。キリスト教の事や聖書の事が生活の一部のようであれば、すんなりと読めるのでしょうね。急ぎ足で読んでしまったけど、もっとじっくり読むべきだと思ったし、細切れで読まずに腰を落ち着けて読まないと大切な事が読み取れないと思った。深い意味のあることがたくさんちりばめられていて、息つく間が無い感じで。もう一度読みなおしたいし、読みなおせる本だとと思います。
トチ:この作品は〈十二国記〉以上にオリジナリティあふれる世界を創造している。そのうえ、テーマが誰にも共感できるものであり、1巻から3巻までしっかり筋が通っている。オリジナリティあふれるファンタジーというだけだったら、他の作者も書いているかもしれない。テーマにしたって、たとえば評論という形だったら他の人も書いているかもしれない。でも、作者が心から言いたいこと、子ども達に伝えたいことを、こういうファンタジーを作ることで成し遂げたというのが、この作品のすごい点だと思う。死者の国から死者が別の世界へ出て、粒子となって世界に溶け込んでいくところに私は感動したけれど、これは宇宙の星の終焉の有様と似ているわよね。ひとつの星が爆発して、人も、石もなにもかも、ばらばらになって、暗い宇宙のなかでタンポポの綿毛みたいになる。やがて、それがまた結びついて、もとの星の粒子が違う結びつきをして、新しい星になる。
それから「万物に神が宿る」という日本人の考え方……というか感性にも近いものがあるわね。養老孟司さんが、「海外で『千と千尋の神隠し』が評価されたのも、唯一神の信仰が文化の土台にある国々の人にはこういう物の見方が新鮮だったからではないか」と言っていたけれど、プルマンの作品も同じような意味で新鮮だったんじゃないかしら。
以上が評価できる点だけれど、翻訳もふくめて本づくりには大いに不満があります。英語にかぎらないと思うけれど、外国語にはたとえば「お母さん」を次の文章では「ミセス・スミス」と言ってみたり、いろいろに言い換えることがあるでしょう? それをそのまま訳してしまうと、文化のギャップなどでただでさえ読みにくい翻訳物がますます読みにくくなる。翻訳者は誰でもそういうところを原作の味を損なわない程度に工夫していると思うけれど、この本ではそういう配慮がみられない。「あー、大変だったろうな」とは思うけれど、楽しんで翻訳しているとは思えないわね。もう一度、じっくり訳しなおしたものを読みたい。それから、訳者後書きで、「ハリー・ポッターを読んだ子どもがこの本を手にとってくれたら……」というようなことを書いているけれど、それはちょっと違うのでは?
アカシア:小谷真理さんもハリー・ポッターとこれを同じところで読んでいるけれど(4/6付けの読売新聞(夕刊)本よみうり堂ジュニア館)、私はこの二つの作品は異質だと思う。
杏:私は前の作品もまだ読んでなかったので、1巻はじっくりと読んだけど、時間がなかったせいで2巻、3巻は駆け足になりました。テーマが壮大で、構築力のある作家だと思う。まだ私のレベルでは読み切れないところがたくさんあると思うので、時間がたってから読み直せば、新しい発見や、「ああ、そうだったのか」とわかることもあると思う。マルチな文化にいた人かしら? 博学で宗教、物理、文学、中国の易、詩、と、それらを自分流に構築していてすごいと思った。作品全体を通しての印象は、以前『黄金の羅針盤』の読書会で出てきた「頭では面白いのに、心では面白くない」というのが、とてもうなずけるコメントですね。かなり難解なのに、何か読ませる力がある。何がここまで読ませるのか?と考えましたが、それは、誰もがもっている真理を求める心なのではないかと思う。普遍的な何か、真理を求める心があればこそ、神を信じる人もいれば、宇宙の神秘を探ろうとする人もいる。普段は、そんなに考えないことであっても、誰でももっている心のあり方なんだと思う。深い部分を探るような作業になるから、疲れるけれど、もっと先を知りたいという気持ちになる。この人は何が言いたいのか、この先には何があるのか、どんな宇宙観を持っているのか、そんな気持ちが強くなる。宗教的知識も体験もないけど、人を超えた存在はあると信じているし、物理学でいう「揺らぎ」とか「フラクタル現象」のようなものにも興味はある(よくはわかりませんが……)。宇宙に意思というものがあるようにも思う。でも、自分のこの作品の読み方は、頭で読む大人の読み方だなあと思う。子どもだったらどういうふうに読むんだろう。よくありがちだが、羅針盤や剣や望遠鏡などの道具を巧みに使うところは、子どもたちも楽しく読めるところだと思う。ライラが羅針盤を読むときのトランス状態の感じはおもしろい。そんな風に、宇宙の意志のようなものを感じてみたい。
ねむりねずみ:2巻目がここで取り上げられたときに、「おもしろいのは原作のおかげ、わからないのは訳のせいじゃない?」という声もあったので、かなり前に原文を読んでいたこともあり、訳を意識して読みました。原文はともかく先が楽しみで、じっくりと楽しみながら読もうと思っていたのに、ついついどうなる、どうなると、どんどん読んでしまった記憶があります。スターウォーズみたいな活劇場面が出てきたり。でも、なるほど、なるほど、とオリジナリティに感心する一方で、大風呂敷を広げすぎて収拾がつかなくなって無理矢理終わらせたんじゃない?っていう感じがしたし、コールター夫人の行動はやはり理解できなくて、そのあたりは、訳書を読んでも変わりませんでした。
それはそれとして、今回訳書を読んでみて一番印象深かったのは、「児童文学の古典」と帯に銘打ってあるわけだけど、それをこんな訳で出したらかわいそうだ、ということでした。こんな生意気をいうのは気が引けるけれど、ほとんど直訳かと思わせるところがあるし、訳のせいでよくわからないところも多々ある。せりふもなんかしっくりこなくて、訳書の204ページで、コールター夫人が「ウィル坊っちゃま、どうするべきだと思う?」というところなんか、とてもコールター夫人の言葉とは思えない。ダイモンの言葉やウィルの言葉にも不自然なところがある。わかりにくいという点でいえば、たとえば544ページの「その道は風景の一部で、税の負担もないのだ」っていう文ですが、こんなところに唐突に税が出てくるはずがない。ここは、自然を破壊したりして作ったのではない、「ごく自然で風景にとけ込んでいる道路」の意味だと思うんです。それに、最後のライラのせりふでも、「だけどどんなにがんばたって、自分のことをまず第一にしていたのでは、絶対にできないの。」という意味だと思われるところが、「自分のことをまず第一にしていたのでは、」の部分がそっくり欠落しているので、まるで無意味な文章になってしまっている。こんなふうに訳が足を引っ張って物語世界がくっきりと浮き上がってこないので、読みにくさが倍増している。ただでさえ、厚い本なのに。でも元々の作品はやっぱりすごいと思うんです。オリジナリティーの点でも、目指すところについても。だからますます残念で……。わたしは前からキリスト教に興味があったので、なるほどなるほどという感じのところが随所にありました。逆にこの本からプルマンのキリスト教への強いこだわりを感じ、それを鏡像のようにして、ヨーロッパでいかにキリスト教が強いのかを実感させられたというところもあります。キリスト教が強いからこそこういう本が書かれるんでしょうね。死者が解放されて自然に帰るいわば輪廻のような感じも、キリスト教文化からすると新鮮なんでしょうね。ライラの両親についてですが、お父さんはあんなものだろうと思うんですが、お母さんの造形はやっぱり物足りない。プルマンって女性を書くのが苦手なのかな。母性とか、いわゆる女性的なものになると、うまく書けていないような気がします。男の人はそれなりに男っぽく書けているのに。それにしても、ダイヤモンド形の生き物はイメージしにくい。確かに原作にもそう書いてあるけれど、訳の段階で読者にもっと親切にしてもいいんじゃないかな。
ペガサス:115pのメアリーのそばにすさまじい音で落ちてきた物体のことだけど、直径1メートルほどの丸い物体で、「……地面をころがりづづけ、とまり、横ざまに倒れた。」と書いてあるから、巨大な円盤状のものを想像するけど、これを見たメアリーが「これってなんなの?種子のさや?」って言うの。どうしても「さや」っていうイメージではないと思うけど?
アカシア:訳者は、3巻まで読んで全体像をつかんでから訳しているわけではないから、きっと大変だったと思うのね。途中の段階では、きっと頭の中にいろいろな疑問がわいてたんじゃないかな?
トチ:汗をかきながらやっている気がする。プルマンは「この本は賢い人に読んでほしい。愚かな人でなく。こんなことを私がいうと、また誤解されるけれど、世の中には賢い人と愚かな人がいるといっているわけではないのです。人間の頭の中には賢い部分と愚かな部分があるけれど、その賢い部分で読んでもらいたいという意味です」とAchuka のインタビューで言っているけれど、脳に賢い部分が少なくなった私には、妙に納得できる言葉でした。分かりやすい本だけでなく、格闘するような本が読みたい。子どもたちにもそういう本を読んでもらいたい。賢い部分で読む本を読みたいと思っている子どもも、世の中にはけっこういるんじゃないかしら。
*なお〈ライラの冒険シリーズ〉については、『黄金の羅針盤』を2000年2月、『神秘の短剣』を2000年10月の「言いたい放題」で取り上げています。
(2002年04月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)