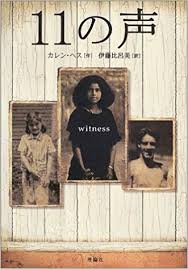トチ:内容はとても良いし感動したけれど、決して読みやすいとは言えないですね。11人という数はかなり多くて、すぐに誰が誰だかわからなくなる。ヴァージニア・ユーワー・ウルフの「バット6」(未訳)という作品も、ふたつのソフトボール・チームのメンバーの手記で構成されていて、内容はとても素晴らしいんだけど、ともかくわかりにくかった。アメリカではこういう書き方の小説が流行っているのかしら。読者がそれぞれの登場人物の語りを想像力でつないで物語を作っていくわけだから、相当の読書力がないと、なかなか理解できないでしょうね。クークラックスクランに入っていた男の子が、だんだんに変わっていくさまが、ひとつの大きな物語になっているわけよね。でも、大人の男の人たちの違いが特にはっきりしなくて、ごっちゃになってしまう。
ペガサス:写真も古いし小さいから、はっきりしないのよね。
トチ:帯には、ヘレン・ケラーとの文通なんてうたわれてるけど、手紙を受け取っただけだわよね。志は高いけれど、それに読者がついていけないという感じ。内容的には、文学的な志にしても、伝えたいことの志にしても、私みたいによき読者じゃないと、意が通じない。詩人が訳したものにはどうしても遠慮があって、訳語がどうこうとこっちも言いにくいけれど、エステルの言葉遣いに違和感があったわ。セアラも「妙な話し方」と言っているけれど。
ケロ:「いったです」とか。
アカシア:セアラは少しネジがゆるんでるっていう設定だから、わざとそういう言い方になってるんじゃないかな。
ブラックペッパー:私は、ユダヤ系だから英語が上手じゃないのかと思った。
アカシア:小さな子はすぐに上達するから、それが理由ではないんじゃない?
ペガサス:ピュアな存在には思えるけど。全体に、ちょっと芝居を見てる感じよね。最近見た新劇で、1つの場面に入れ替わり立ちかわり人が出てきて、それぞれに全然違うことを言うので最初は意味がわからないんだけど、だんだんそれが1つの事件に関係してるとわかってくるっていうのがあったの。これも、そういう感じなのよね。題名が『11の声』っていうから、ドキュメンタリー風なものを予想していたんだけど、原題はWitness。だったら、もっと初めに事件があったほうが、よかったんじゃないかな。なんなんだかよくわからなくて、行きつ戻りつ、読むのが難しかった。この時代のアメリカに興味はもったんだけど、そういう興味がなければ、子どもにおもしろいから読んでごらんとは言いにくい。子どもはおもしろいと思うかな? 英語で読むのと、翻訳書として日本の若い子が読むのでは、ずいぶん隔たりがあるように思う。試みとしてはおもしろいけど、それも作者が思っているほど日本人の私たちには届きにくいのではないかしら。
アカシア:私はすごくおもしろかった。アメリカの社会にいろんな立場の人がいるっていうのが、よくわかった。この作者は、まあいわば性善説ですよね。そして、いろんな人が1つの社会をつくらなければならない状況で、どうしていったらいいのかを複合的な視点で描いている。ひとりひとりをもう1度見ていくと、それぞれにドラマを抱えているのもわかってくる。ただ原文は口調や言い回しにそれぞれ特徴があるのかもしれないけど、日本語だけだとそれがあまり浮かび上がらないので、いちいち人物紹介と引き合わせながら読まなくちゃいけない。やっぱりそれは大変でしたね。
ペガサス:芝居ならもっとわかりやすいけど、これは浮かびあがるまでに時間がかかるじゃない。
トチ:ひとりづつ、もう一度たどって読み直してみればわかるだろうけど、通して読んでいると間違えちゃうのよ。
アカシア:たしかに子どもが読むにはしんどいかもね。高校生くらいでアメリカに興味がある子だったらおもしろいと思うけどな。
ペガサス:この写真も、アメリカの子が見ればもうちょっと特徴がわかるかもしれない。日本の子どもだって日本の大正時代の風俗だったらわかるけど、これ見せられても一人一人の特徴はわからない。そういうところがハンディだよね。
トチ:時代背景だってわかりにくいからね。あと、タイトルを変えちゃったのも問題よね。
ペガサス:いろんな声が聞こえてくるってだけじゃないのよね。
ケロ:一つのドラマとしてみたとき、もうちょっと盛り上がりがほしい気がしました。また、みなさんのおっしゃるとおり、登場人物が一人一人浮き立ってこない。写真があるのに、ジョニーはあまりいい男じゃないとか、そのくらいしかわからない。わざとわかりにくくしているのかな? でも、会話だけというのは、少し距離を置いて読めるところがあるなと思います。夫婦のボケとつっこみもおもしろいし、エステルを預かるセアラが、差別について意識していく過程もわかりやすいですね。わたしは、レアノラとフィールズさんの関係で、フィールズさんが分かっていてくれているのが感じられるところが、とても好きでした。あと、202ページで、死んだはずのジョニー・リーヴスが生き返っているかのようになっているのは、どうしたわけなのでしょう?
ブラックペッパー:「念」みたいなものかしら。
むう:この本には、KKKで実際に人を吊したり殺したりする極悪人は出てこないですよね。出てくるのはちょっと気の弱いところもあるジョニー・リーブスくらいで。
アカシア:北部が舞台なので、KKKも南部ほどしっかりした拠点がなかったんでしょうか。
ケロ:「差別する人」に特定性はなく、ごく一般の、尻馬に乗っちゃう人の集まりだってことですよね。
むう:それを書くのがうまいよね。
ケロ:だから、わざと登場人物が、わかりにくく描かれているのかな? 「一般人」ということで。
トチ:帯には「アメリカの良心」ってあるけど、ちょっときれいごとすぎるんじゃない?
アカシア:ふつうのアメリカ人のなかには、今のイラク戦争についても疑問視してる人はたくさんいると思うのね。アメリカの良心はどこにいったかと憂えてる人にとっては、こういう本にも存在価値があるんじゃない?
ブラックペッパー:最初は、この人はええっとだれだっけ、とやっていたのですが、途中から細かいのを見るのはやめて、自分のインスピレーションで読んでしまいました。全体の雰囲気とか空気がそのおかげでわかったような気がする。『GO』と共通して思うのは、「人間ってやつ……」はほんとにもう、ってことです。どうしてこんなに生きにくくしてしまうんだろう。KKKもよく知らないのだけど、その辺共通の印象を受けるってことは、パワーがあるからかな。ただ、ぐぐっと中まで入って何かもわかるというタイプの本ではないですね。
むう:ロイス・ローリーにも古い写真をもとにつくった話(『サイレントボーイ』中村浩美訳 アンドリュース・プレス)がありますね。古い写真は作家の創作意欲を刺激するのかもしれないけれど、子どもが読むとなるとちょっとしんどいかな。
ブラックペッパー:あんまりつきつめなければ、読めちゃうかも。理解度は低いかもしれないけど。
むう:なんといったらいいのか、この本には自信満々の悪という人間がほとんど出てこなくて、それでいて悪いほうにぐっとうねっていき、すれすれの所まで行くかと思うと、そこから立ち直る。その流れをきちんと描けている点が、すばらしい。別に全員が個性的だったりするわけではなく、ごく普通の人たちなのだけれど、ひとりひとりがリアリティを持った個人としての声で語っていて、そういう声がいくつも集まって大恐慌時代の小さな町の差別がらみの事件を語るから説得力がある。それと、この構成力に感心しました。翻って今のアメリカを考えたとき、ブッシュを支持してない人がたくさんいるとはいっても、マスコミを通して伝わっていることと、ここに書かれているようなアメリカの良心とはどうつながるのかなあ、と考えてしまう。もうひとつ、エステルの言葉などを見て、いったい原文はどういうふうに書かれているのだろうと、とっても気になりました。
紙魚:部分的な地図をわたされて、それをつなぎあわせて1枚の地図にしていくのがしんどい読み物ですね。バスの中で読みながら、めんどくさいながらも何度も人物紹介ページをめくっていたのですが、途中であきらめて、あまり厳密さを求めない読み方にきりかえたところ、なんだかそれぞれの差別の認識のちがいがうかびあがりました。バスの揺れも影響したんでしょうか、それがまた乗り合わせたバスの乗客たちと重なって、不思議な心地になりました。エステル・ハーシュがかわいらしくて、彼女の言葉に導かれて最後まで読んだようなものです。
アカシア:あとがきを読んでわかったんですけど、伊藤さんが最初から訳しているんじゃなくて、ほかの人が全体の下訳をしてるんですね。
トチ:翻訳って仕事は、原文を読むところから始まっていくのに……。
アカシア:下訳者がまず最初に解釈をして……
むう:いったん他の人が解釈したものをもう一度解釈することになるから、いわば重訳になってしまいますよね。
『11人の声』では、町のほとんどの人は、KKKみたいな大上段に振りかざした信念でなく、結局は自分の日常の感覚にこだわって動いていますよね。だからどうっと雪崩を打ってリンチ!とならない。雑貨屋の夫婦の場合でも、おじいさんは簡単にKKKにかぶれるけれど、おばあさんはそれまでの周囲の人との関係の中で培ってきた感覚を大事にしようとして、結局はおばあさんの路線に落ち着く。『GO』の中でも、主人公は頭でっかちにイデオロギーや運動に絡め取られるのではなく、日常を生きている個人としての実感に立脚して動いている。あのたくましさや明るさはそこから出てきてると思うんです。この2冊に共通して、社会というのは高邁な思想やなにかで動いていくのではなく、日常に根を張って地べたを這いずるように生きている人々が集まって動かしていくんだ、という視点があるような気がします。
*『11の声』の翻訳については、理論社編集部から以下のようなご指摘をいただきました。「言いたい放題」だけをお読みになって誤解なさるといけないので、こちらもお読みください。
前回、同じカレン・ヘスのOut of the Dustを伊藤比呂美さんが訳したときにも、主人公のビリージョーと同年代ということで娘さんに下訳を(アルバイトとして)やってもらったそうです。もちろん英文読み自体は訳者本人もやっているのですが、その下訳文が日本語として青臭くてすごくおもしろく刺戟になったということがありました(といってもそこから詩人の語感でどんどん手をいれていくのですが)。そういったいきさつは、前作『ビリージョーの大地』の「あとがき」には少しくわしく書かれています。その流れがあって今回も娘さんに下訳をたのんだわけです(理論社編集部)。
(「子どもの本で言いたい放題」2003年10月の記録)