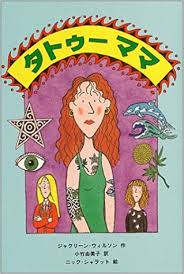ケロ:壊れていく母親を見ているドルの気持ちがつらいなあと思いながら読みました。子どもは親を選べないのに、こんな母親でも好きでいるという現実がきちんと書かれているだけに、つらい。こういう状況にある子どもが読んだとき、果たして助けになるのかなあと、疑問を持ちながら読んでいきました。でも、最後にカタルシスがありましたねー。客観的に母親を抱きしめるというところが、主人公本人の救いにもなっていて、これなら「子ども向け」の作品としてオッケーだ、と納得できました。全体の中では、ドルとスターの父親が両方とも見つかるのは話として出来すぎという感じがしましたが、自分の中にもお父さんはどんな人なんだろう、という興味があったので、ご都合主義な感じを受けずに楽しんで読めました。お母さんのマリゴールドは、精神的にも不安定で、かなり特殊な存在。でも、お母さんがひとりの人間として満たされず特別な存在になりたいと思っている、というのはよくあることだと思うと、ひいてしまわずに感情移入しながら読めたかな。
ハマグリ:ジャクリーン・ウィルソンの作品は、今までもたくさん読んでいますが、どれも困難な状況におかれた子どもを書いている。結末は安易なハッピーエンドではないけれども、必ずどこかに未来への道がついているのがいいですね。それからどんなにすごい状況でも、ハハハと笑える部分が必ずあって、楽しませてくれるところもすごい。この明るさは、イラストによるところも大きいでしょうね。ドルとスターという姉妹は、大好きでお互いをとっても必要としているんだけど、それゆえに許せない部分があって、ぶんなぐりたいくらいの反感ももっている。そうした関係もよく描かれています。リアリスティックな作品のなかでは、この作者のものは子どもに勧めたいわね。
むう:うまい人だなと思いました。出だしからこっちを引き込んでぐいぐい引っぱっていくあたりも、この家族のある種のチープさもよく出ていて面白かった。ただ、わたしの視点がどうしてもふりまわされる側の子どもたちに寄ってしまって、「このお母さん、なんだかなあー」と思うところもありました。だめ母さんでも好きで好きでしょうがないという子どもの気持ちはとてもよく描けているし、それが切ないんだけれど。ミッキーが見つかったり、主人公のお父さんが見つかったりで、どうなっちゃうんだろうと最後まで引っぱられたし、この子たちがそれぞれに家族とは別の世界に触れたうえでふたたびママを抱きしめるというのもいいと思ったけれど、最後の338ページのお母さんの台詞にはすごく引っかかった。病院のカウンセリングの時間の話で、「しつこくしつこく、小さなころのことをきかれたわ。で、しまいに、ひどい話をぜんぶぶちまけちゃった。お母さんのこと、お母さんがあたしにしたこと、どれだけお母さんをにくんだか。そしたら、気がついたの。あたしもおなじだって。あたしも、おなじようなことをあんたたちにしてきた。ふたりとも、きっとあたしのこと、にくんでるわよね」って言うんだけど、こんなふうに説明しちゃうのはお手軽だなあ、と思って。この台詞、いらないですよね。ここまでで、このお母さんはまるで信用できなくて、それでも子どもたちはこの人が好きでということがわかるんだから、それでいいじゃない。
アカシア:私は、この台詞がすごくきいてると思うんです。お母さんは初めて精神科病棟で治療を受けてるわけだから、この台詞がないと、これからはまともな母子関係になるのかな、と読者は思ってしまう。でも、このお母さんは、これまでも時には「自分はだめな母親だ」って言ってきたけど、状況はちっとも変わらなかったんですね。ここも、この台詞があることによって、読者に「また言ってるけど、これからも変わらないんだろうな」と思わせる。だから、娘たちは、ここで心底悔い改めたお母さんを選び取ったんじゃなくて、お母さんは変わらなくてもそれでも好きなんだ、という設定がより強く浮かび上がってくる。
むう:つまり、だめ押しみたいなものということかな。でも、そこまでする必要があるかなあ。この本を読み終わって、まず、力があるなあ、うまいなあと感じたんだけれど、同時に、「でもなんかざらざらしてる。なんだこの違和感は」と思ってその原因を考えるうちに、このお母さんの台詞に行き当たったんです。自分のなかでここだけが消化しきれない感じで。
ケロ:でも、キルトづくりをさせられて、パーツが合ってないと娘に言われ、「どんなキルトになると思う? 信じられる? クレイジー・キルトっていうのよ」って台詞、やっぱりこのお母さんならではって感じですよね。状況的な大変さは変わらないけれど、あきらかにこの子たちの心境は変わっている。
愁童:ぼくも、むうさんといっしょ。心理学ブームだからって、セラピストの定番みたいなところによっかかるのはどうかな。こういう子どもを幸せといえるのかなとは思うんだけど、原題のThe Illustrated Mumには、作者のメッセージがうまく込められているように思った。Illustrateされちゃったママで、それに振り回されるけど、それでもママはかけがえがないという、のっぴきならない母子関係。その中で、主体的に生きざるを得ない子の、母が居てこその幸せみたいなことについて考えさせられちゃった。
アカシア:この作家は、本当に子どもに寄りそって書いてますよね。現実にこういう子どもはいっぱいいるんでしょうけど、その子たちが気持ちの出口をさがしていくところが書かれている。ハマグリさんはリアリスティックな作品として子どもに勧めたいと言ってたけど、私は純粋にリアルなんじゃなくて、エンタテインメント的な要素がとても強いと思う。娘たちのお父さんがそれぞれ都合よく見つかるなんて、リアルじゃないですよ。ただ心理的な動きはリアルで、読者の気をそらさない。うまいです。子どもたちに大人気なのも、当然ですね。
これだけひどいお母さんだったら家出するのがふつうで、なかなかお母さんを受け入れるところへは行き着けない。でも、家出したスターのことが心配なあまり、スターがきらいだったタトゥーを消そうとして、お母さんは体中に白ペンキをぬりたくってしまう。その異常な行動から、最後に娘たちがお母さんを抱きしめるところまでは、下手な人が書いたら嘘臭くてとても読めない。でも、この人が書くと、ついていけるんですよね。うーん、すごい。
あとね、さっきのお母さんの台詞について、もう一言。マリゴールド自身の母親との関係がここで初めて出てくるんですよね。文学好きな読者にとっては、なくもがなと思う気持ちもわかるけど、これがないと、マリゴールド=クレイジーですませてしまう子どもの読者もいるような気がします。
カーコ:お話としてはおもしろくて読ませられたんですけど、いったい誰が読むのかなと思いました。実際にこういう状況にいる子の力になるのでしょうか。どんなに悲惨な状況に置かれていても、子どもがお母さんを好きなのは当然のこと。10歳の子がこんな目にあって、健気に母親を支え、精神的に自立していなければならないというのが、あまりにもかわいそう。わざわざ子どもに読ませたいとは思えませんでした。大人に対する理解を子どもに強制しているように感じました。
アカシア:渦中にいる子は読むだけの余裕がないかもしれないけど、まわりの子がそういう子を理解するのにはとても役立つ。それに、オリヴァーとか、ドルのお父さんとか、里親のジェインおばさんとか、味方になって支えてくれそうな人物も登場し、ドルの世界も広がって孤立無援ではなくなっている。10歳の子に「健気」を押しつけることにはなってないと思うけど。
ケロ:これほどスゴイ状況まではいかなくても、今のお母さんって少なからずこういう部分があるので、子どもとしては、少しシンクロできるのではないでしょうか? 映画『誰も知らない』(是枝裕和監督)は、救いがまったくないけれど、これはユーモアがあり救いがあると思うので、母の「こういう部分」を理解するなり判断するなりする材料になるのではないでしょうか。
愁童:下の階のおばあさんの描き方がうまいね。批判的な世間の目の代表みたいな存在なんだけど、文句を言いながら電話を取り次いだりと、結構助けたりしちゃう。このおばあさんの存在感で、主人公一家のハチャメチャな生活に立体感が出てくるよね。
アサギ:私は時間切れで、まだ半分しか読んでないんです。イギリスならともかく、翻訳して日本の子どもにこういう物語を読ませる必然性がわからない。せつない感じがしちゃってね。
トチ:それはまだ読んでる途中だからじゃない?
アサギ:日本の状況とは、ずれていると思いません?
アカシア:日本も、もうすぐこうなるんじゃない? お金もうけのために自分の子どもに売春させる親だって出てきたくらいだから。
アサギ:まあ、このお母さんの場合、憎めないところもあるけれど。
トチ:子どもには、なにがあっても親についていくという生物的な本能もあるし、親から離れられないってこともあるしね。
愁童:姉妹の母親への思いの、それぞれの年齢による微妙な差が、うまく書かれているよね。
トチ:まず、これほど暗くて悲惨な状況を、これほど明るく、ユーモアもまじえて書ける作者の力量に感心しました。書きようによっては限りなくいやらしくなる母親も、切なく、かわいらしく描けていることに、またまた感心。昔の児童文学って、『小公女』のように不幸な主人公が状況が変わることによって幸せになるというのが典型だったけど、この作者は環境が変わらなくても、主人公の内面的な変化や成長で救われるということを一貫して書きつづけている。このほうが読者である子どもにとってずっと現実的だし、救いにもなるわよね。それから、作家であれば誰でも一度は「狂気」を書いてみたいのでは、と思うんだけど、ウィルソンもそうだったのでは?そんな作家魂が垣間見えるような気がして、おもしろかった。
羊:はらはらしながら読みました。でも、お母さんの幼さが、わりに魅力的に書かれていて、学校にショートパンツ姿で迎えにいくシーンなんかもおもしろかった。みんなから鼻つまみにされている母親でも、娘である当人だけにわかる愛情を抱いているのは伝わってきましたよ。スターに父親が見つかり行き場が出来た時から、お母さんが崩れていくという流れはすごかったですね。そのスターが距離をおいて離れて暮らしたことで、また優しくなれるというのもわかります。このままの暮らしを続けていたら破滅するしかないですよね。
紙魚:主人公の環境があまりにもひどいので、読むのがつらかったです。アルコール依存症の親とかに読んでもらうと、子どものつらさがわかっていいかもしれないと思ったくらいです。作中ときどき顔をのぞかせる、オリヴァーのやさしさとドルフィンという美しい名前には、かなり励まされました。スターとドルの姉妹って、年齢の差や性格のちがいから、母親への接し方が全くちがうのですが、その時々どちらの気持ちにも共感できて、どちらの方によって読んでいっていいのか、かなり振りまわされました。だから最後までお母さんへの好き嫌いが決められなかったのですが、それもやっぱり、この作家のうまさなんだと思います。家族ならではの、ひとつのところにとどまらず常にぐるぐるとスパイラルして動いている感じが、とてもうまく表現されていたと思います。
トチ:大人は怖いもの見たさで悲惨な物語を読みたいということがあるけれど、子どもはどうなのかしら?
アカシア:極端な設定を使うと、はっきり見えるてくるものもあるんだけど、それをどう描くかというところが大切よね。
(「子どもの本で言いたい放題」2004年12月の記録)