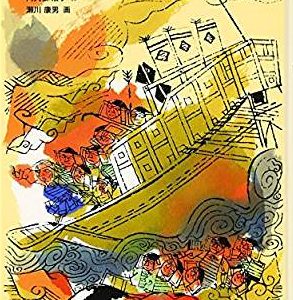トチ:最初に夢のお告げが出てきたり、美しい着物の描写が出てきたり、どんな風に展開して行くのかとわくわくしながら読みだしたのですが、いつまでたってもつる姫がどんなに優れた、男勝りの少女かということばかりで、いっこうに面白くならない。もう読むのをやめようかなと思ったら、4分の3あたりで、やっと戦いが始まった。ところが、それまでのつる姫は弓や剣道の修行をした、普通のお姫さまとは違う存在だったのに、恋をし結婚をするとなると、もう戦いなどどこへやら、ふにゃふにゃの女になってしまう。中学か高校のとき、上級生に「いくら能力のある女の子でも、恋をすると、とたんに詰まらない女になってしまうから、十代のころには男に近づかないほうがいい……」などと、したり顔で言われたのを思い出して、この本はそういうことを書いているのかな、まさかね……などと思ってしまいました。
そして、結婚相手の少年は自爆するわけだけど、自分たちの国を守るとか、民草を守るとかいうより、ひたすら「つる姫を守りたい」一心なのね(国のために自爆するのも危ない考え方だけど!)。戦いっていうものをどう考えているのか、そのために踏みにじられる庶民のことはどう思っているのか、そのへんの目配り、気配りがまったく無いのも気になりました。
けっきょく、作者は何を書きたかったのかな? 何を子どもたちに伝えたかったのかしらね? 悲恋物ってことはわかるけど。名所旧跡に行くと、よく「ここはナントカ姫が身を投げた淵です」なんて由来を書いたパンフレットがあるでしょう? そんな感じでした。
ハマグリ:面白く読みました。どういうところが面白かったのかというと、このなんとも大仰な文体や、手に手をとった二人の瞳がきらきら、みたいな書き方ね。今子どもたちの読むものは似たようなものが多くなっているけど、たまにはこんな毛色の変わったものを読むのもいいんじゃないかしら。両親がかわいらしい姫として育てようとしているのに、馬にも乗りたい、剣も使いたい、戦にも出たいと、何でも兄さんたちと同じようにしたいという気持ちは、読者の共感を呼ぶわね。でも、最後は愛する人の後を追って死ぬ、というところ、今の子はどう思うんでしょうね? 愛する人を守って自分を犠牲にする明成の死に方や、悲しみのなか婚礼衣装を用意して独り海に向かう姫、というのはどうなんでしょう?
トチ:大人の時代物の書き方よね。
ハマグリ:昔は分厚くて、図書館の棚に鎮座ましましていたような本だったわね。福音館文庫で復活して、手に取りやすくなったけれど。
カーコ:最初は、明るく積極的で好奇心に満ちたつる姫が描かれていて、しかもその子がいつか重大な役目を担いそうだというのが父親の夢に出てくるので、どうなるのだろうという気持ちで読みました。でも、終わり方が古くさい。途中、一人で母親のもとに戻ったときも、明成と再会したときも非常に冷静なつる姫が、どうして最後、命を絶ってしまうのか、しっくりきませんでした。お涙ちょうだいの昔の恋愛小説みたいで、こういう終わり方にしようとするところに、時代がかかったものを感じました。また、これは初版と同じ絵なのでしょうけれど、この挿絵は、物語を理解する助けになっていないと思いました。『狐笛のかなた』(上橋菜穂子作 理論社)の絵が、作品のイメージをふくらませてくれていたのと比べてしまって。223ページの絵をはじめ、人物がお人形みたいで、見てわくわくする感じがないのが残念でした。
トチ:絵巻物ふうなのね。どれも同じ絵に見えてしまって、とばしてしまったわ。
すあま:子どものころ読んだという友達が「ずっと読み直したいと思って探していた」と話していたので、そんなに印象に残る物語なのかと気になっていました。題名は地味だけれど、それなりに面白かった。今の子も、古代ファンタジーを読んでいるので、日本の歴史を題材ににしたものも読めるはず。こういう本があれば、歴史にも興味を持つし、昔も自分たちと同じような女の子がいたんだなと共感を持てるんじゃないかな。物語としては、つるちゃんがとてもよい子で、非のうちどころがないのが物足りない。誕生の時には神様の化身のような描かれ方をしていたので、最後は神様になるのか、つる姫の方が殉職して明成が残るのか、と思ったけど違いましたね。最後、つる姫が死んでしまったのがわからなかった。
うさぎ:「史実に基づいた歴史ロマン」とあったので、楽しみにして読んだんです。最初のほうで、つる姫のお父さんが夢を見るというのがあって、つる姫の運命はさあどうなるかと読み進めていくのだけれど、なかなか何も始まらない。ようやく物語が動き出しても、明成の自爆から最後のところまでは大きな疑問が残りました。お父さんの夢の暗示のように、つる姫は神格化して竜神にでもなって何か起こすかと思っていたら、明成の自爆があってから、ものすごくふつうの人間というか、それまでの男勝りは跡形もなくなり、妙に女くさくなって終わってしまった。最後、死んだのがわかって、物語がますます尻すぼみになった印象。悲恋の定石みたいなのを時代ロマンというんでしょうか? 史実にひっぱられてこういう形でまとまったのでしょうか?
アカシア:竜神のエピソードは何で出てくるのかしら?
うさぎ:作者が何を書きたかったのかと、意味づけをしようとしたけれど、しっくりきませんでした。
アカシア:時代は戦国時代で、つる姫が男の子と同じことをしたいっていうキャラなので、どんなふうに社会との軋轢が描かれるのかな、つる姫の勇ましさはどこまで受け入れられるのかな、という点に惹かれて読んでいきました。それなりに面白くは読んだんですけど、最後が死の美学を提示するような形になっているのは問題よね。それに202ページではつる姫が実戦のむごたらしさを初めて目にして「目の前にするたたかいとは、なんとむごいものか。おそろしいものか。/城できく、たたかいの話の勇ましさ、はなばなしさは、うそじゃ、うそじゃ、うそじゃ。/つるは、知らなんだ。/ほんとうのたたかいを、知らなんだ」と言い、206ページには(どんなことがあろうと、罪もないひとびとを、たたかいから守らねばならぬ。/たたかいとは、決して会ってはならぬ物じゃ。ならぬ物じゃ。)と、胸の中で繰り返し叫ぶ、と書いてあります。でも、ここで「罪もないひとびと」と言うのは、味方のことだけなんですよね。つる姫が出陣して戦に勝利を収めると、今回は負けなかったのでむごたらしくならなくてよかった、よかったとなっている。味方さえ勝てば戦はむごたらしいものではなくなるんですか? と突っ込みたくなります。時代の制約を受けている主人公の心情としては仕方がないとしても、現代の人間である作者は、もう少し考えてほしいところです。作者の視点がご都合主義的なんでしょうか。
トチ:でも、時代物だから、今の価値観で書くと嘘っぽくなってしまう。そのへんの兼ね合いが難しいのよね。
アカシア:つる姫が、時代につぶされていくんならつぶされていくで、一貫した物語になるんでしょうけど、単に悲恋の主人公で終わらせてしまっているのが残念。小説のつもりで読んでいると、途中から講談になってしまう。いっそ、つる姫が最後竜神になるんなら、かっこよかったのにね。
ハマグリ:最後の海鈴が鳴るっていうのを、作者は書きたかったんじゃないの?
アカシア:美しく死んで終わりっていうのは、危険な思想よね。
(「子どもの本で言いたい放題」2005年7月の記録)