| 日付 | 2012年10月25日 |
| 参加者 | タビラコ、カイナマ、プルメリア、ウアベ、レジーナ、アカシア |
| テーマ | ノンフィクションを読む |
読んだ本:

湯本香樹実/著
新潮文庫
1994
版元語録:町外れに暮らすひとりの老人をぼくらは「観察」し始めた。生ける屍のような老人が死ぬ瞬間をこの目で見るために。夏休みを迎え、ぼくらの好奇心は日ごと高まるけれど、不思議と老人は元気になっていくようだ――。いつしか少年たちの「観察」は、老人との深い交流へと姿を変え始めていたのだが……。喪われゆくものと、決して失われぬものとに触れた少年たちを描く清新な物語。
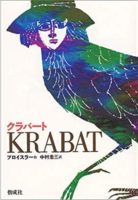
原題:KRABAT by Otfried Preussler, 1971
オトフリート・プロイスラー/著 中村浩三/訳 ヘルベルト・ホルツィング/絵
偕成社
1980
版元語録:クラバート少年は水車場の見習いになり、親方から魔法を教わる。3年後、自由と少女の愛をかちとるため、親方と対決を迫られる。
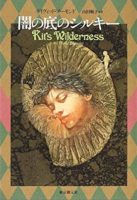
原題:KIT'S WILDERNESS by David Almond, 1999
デイヴィッド・アーモンド/著 山田順子/訳
東京創元社
2001.10
版元語録:寂れた炭鉱町にこしてきた僕は、風変わりな少年に誘われ、死という名のゲームに加わる…。英国児童小説界の新鋭が、不思議な世界を見た2人の13歳の少年を描く物語。
夏の庭〜The Friends

湯本香樹実/著
新潮文庫
1994
版元語録:町外れに暮らすひとりの老人をぼくらは「観察」し始めた。生ける屍のような老人が死ぬ瞬間をこの目で見るために。夏休みを迎え、ぼくらの好奇心は日ごと高まるけれど、不思議と老人は元気になっていくようだ――。いつしか少年たちの「観察」は、老人との深い交流へと姿を変え始めていたのだが……。喪われゆくものと、決して失われぬものとに触れた少年たちを描く清新な物語。
タビラコ:何年かぶりに読みました。最初に読んだときにいちばん感動した箇所で、今回もじーんとなりました。p89の、雨のあと、おじいちゃんが「秋になったら、何か種を蒔こう」というところです。ひとり暮らしのおじいちゃんのところに、子どもたちが死んだ人を見たいという好奇心だけで押しかけ、その結果おじいちゃんが、しおれてた草が雨で息を吹きかえすように生きる力を取りもどす……それがおじいちゃんのこの一言にこめられていて、すごいなあと思いました。最初に読んだときは、おじいちゃんの結婚していた人を老人ホームに訪ねるところなど、ちょっとやりすぎかなと思ったのを覚えていますが、いま読むと、この物語の大切な1部分だと思うことができました。それから、おじいちゃんの戦争の話ですが、児童文学で戦争を取りあげると、子どもが主人公になることから、どうしても被害者としての側面から物語ることが多いように思うんですけど、この作品では加害者としての戦争の真実を語っているところが素晴らしいし、児童文学にかかわるものとして忘れてはいけないことだと思います。たしかこの作品がホーンブック賞を受賞した直後だと思いますが、アメリカの児童文学研究団体であるCLNE(Children’s Literature New England)主催のカンファレンスの課題図書になったことがあるんです。そのときに、アメリカの小学校や中学校の先生たちの中に「子どもたちが、死んだ人を見たいという好奇心から老人に近づいていくというのは、なんとも残酷で、嫌悪感をおぼえる」という人たちがいて、へえ、そういう読み方をする人たちもいるんだと、かる―くショックを受けました。ただ、英語のタイトルは“The Friends”だけですが、もともとの日本のタイトルは「夏の庭」っていうのよと話したら、「とってもすてき!」なんて言ってました。
カイナマ:何度も何度も読み返した作品です。また中学生にも繰り返し読ませてきました。1クラス分文庫本を用意して、全員に読ませてから「読書へのアニマシオン」の中の「前かな、後ろかな」という作戦を行っています。大人の読書会でも取り上げたことが何度かあります。大人の方は、おじいさんを死ぬところを見たいという出だしで、もうこの作品は嫌だという人が必ずいました。内容についてですが、3人の男の子のうち河辺は、親が離婚し父親はよそで再婚し子どもがいる。山下はお母さんから魚屋のお父さんみたいになっちゃだめといわれ、主人公はお母さんがアル中ぎみ、とそれぞれ家庭に問題を抱えています。それがおじいさんとの出会いでそれぞれ乗り越えていくというか、自分なりに受け止めることが出来るようになります。それから意外と男と女のことが随所に出てきているんですね。おじいさんの戦場での壮絶な体験、花火の時に出てくるカップル、味噌蔵での話など、そういうのをうまくちりばめているとも思います。
アカシア:死ぬところを見たいというのは、子どもらしい反応だと私は思ったんですが、読者の子どもはどうなんですか?
カイナマ:子どもの感想ではあんまり聞いたことはないですね。
プルメリア:この作品は出版された時に読み、今回また久しぶりに読みました。時間がたったあとで読むと、けっこう字が小さかったんだなと感じ、また作品の内容も以前読んだ時の感想が薄れていて今回新鮮な感じで読むことができました。一人暮らしのおじいさんに興味を持ち、おじいさんの死を待っている少年達の心情や行動がおじいさんとの交流を通して徐々に変わっていく過程が作品を読ませるのかな。生まれた環境も性格も違っている3人の少年、どこかでつながっている友だち関係もおもしろいです。3人がおじいさんの家で水を巻き虹が出る場面、おじいさんが用意した丸ごとのスイカに少年たちは驚き、一人はスイカを切る包丁を研ぐために包丁研ぎをとりにいく場面、台風の夜、おじいさんが心配で3人がそれぞれ集まってくる場面など印象に残りました。コスモスは見た目は細いですが、けっこうたくましく台風で倒されてもしっかり花を咲かせます。少年たちが死と向き合う火葬場、怖いというよりも現実を受け止める場面など、湯本さんは子どもの心情がよくわかり作品を書ける人なんだなと思いました。6年生でも読めるけれど、中学生向きでしょうか。1993年の読書感想文全国コンクール課題図書(中学校)でしたね。
アカシア:たいていの作家は、子どもが書けていると大人が書けてない、大人が書けていると子どもが書けてないのかもしれませんが、この著者は両方を書ける人だなと思いました。おじいさんがだんだんに具体的な存在になっていく過程がとてもよく書けています。『闇の底のシルキー』は、本当に死が間近にある子どもだけれど、こっちは死が遠くにある子どもなんですね。あちこちに、うまいなあと思う表現がありますね。たとえばp192の「おばあさんは目をとじてゆっくりとうなずいた。大きくて年取った考えぶかいカエルみたいに」とかね。ちょっとした表現が、常套句じゃなくて、しかもああ、なるほどとわかるように書けてるっていうのはすごいです。
ウアベ:スペインの児童文学の中の日本人像というのを大学院のときに研究したので、この作品はスペイン語版を丹念に読みました。スペイン語とカタルーニャ語で、どちらかがドイツ語から、どちらかが英語からの翻訳なのですが、翻訳だと名字で呼び合う男の子たちの微妙な距離感がでなくて、残念だなって思いました。塾とか説明はしているんですけど。「死を探す3人の少年たち」というようなタイトルがついていて、ミステリーだと思ってしまうとネイティブの人に言われました。今もう絶版になっていると思うんですけど。お葬式で死んだ人の顔を見てすごくこわくなる、あのおじいさんだったら死ぬかもって思って見にいくというのは、私は違和感なく物語に入っておもしろく読みました。遠かった死が、プールでおぼれた出来事を通して鮮明になるところや、それぞれの抱えている問題に踏みこみはしないけれど、互いに大事にしあっているこの世代の子たちの友だちとの関係の書き方など、とてもうまいと思います。10年前ですが、当時小学校6年生だった息子もおもしろく読んだようでした。
レジーナ:小学校の高学年か中学のときにはじめて読んで以来、心に残っている作品です。中学の友人が目を真っ赤にして学校に来たのに驚き、わけを聞いたところ、朝、電車の中で『夏の庭』を読んでいたら、涙が止まらなくなったと言っていたのを、今も覚えています。印象的なのは、亡くなったおじいさんの唇にブドウを押し当てて、「食べてよ」という場面です。嬉しかったことや悲しかったことをもっとおじいさんに聞いてほしかったのに、もうそれができないと気づく場面は、大人になって、大切な人の死を経験した今、よりいっそう心に響きました。シンプルだけど、心を動かす言葉が多いのは、作者の人間性によるところも大きいのではないでしょうか。主人公は、夜寝る前に呼吸の数を数えているうちに、自分が死んでしまうのではないかと恐れを抱きますが、そうした死への恐怖心は、身近な人の死を知らない幼い子どもでも、本能的に感じると、詩人の工藤直子さんが自身の生い立ちや息子さんのことを書いたエッセイの中で語っていました。副題の “The Friends” は、子どもの目にはお洒落に映りますが、なくてもいいのではないかと、今は思います。
タビラコ:ついでに。おじいちゃんと種屋のおばさんがいっている「ユキオコシ」っていう花、ネットで調べたら、とってもすてきな白い花でしたよ。
(「子どもの本で言いたい放題」2012年10月の記録)
クラバート
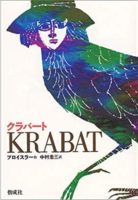
原題:KRABAT by Otfried Preussler, 1971
オトフリート・プロイスラー/著 中村浩三/訳 ヘルベルト・ホルツィング/絵
偕成社
1980
版元語録:クラバート少年は水車場の見習いになり、親方から魔法を教わる。3年後、自由と少女の愛をかちとるため、親方と対決を迫られる。
アカシア:好きな作品です。前に読んで、今回また読んでみたんですけど、独特の雰囲気を持っていますね。伝承の物語を作家が脚色して書いたものですが、子どもの読者にはわからない部分もありますね。粉屋とか水車小屋はいろんな象徴的な意味合いを持っているけれど、日本の子どもだとドイツの子どものようにわからないかなと思いました。雰囲気のおもしろさは日本の子どもも楽しめるでしょうけど。訳に少し補いがあると、その辺のおもしろさがもっと伝わるかな。
レジーナ:小学校6年生のときから、何度も読み返した作品です。アウグスト殿下との密談や、デカ帽伝説など、もとの伝説にプロイスラーがつけ加えた部分は作品全体の流れの中で唐突な印象を与えますが、それでも読ませてしまうのは、物語の力ですね。『闇の底のシルキー』もそうでしたが、これ以上進んだら帰れなくなるというぎりぎりの深さまで突きつめた少年が、最後にふっと現実の世界に戻り、大人としての人生を生き始める物語です。そうした刹那的な危うさに、少年特有の成長のあり方を感じました。
カイナマ:これを読んで最初に思い浮かんだのは、シューベルトの歌曲「美しき水車小屋の娘」です。ドイツ的なお話なんだろうなと思いながら読みました。実際はヴェンド人というドイツ的世界とはまた異なった文化圏の伝説だそうで、おもしろいですね。ストーリーとしては飽きさせずおもしろく読ませると思います。最後は少女とクラバートとの愛。目隠しをされたけれども、心配している心が伝わってこの人だと分かったというのは、いい終わり方だなと感心しました。歴史的には北方戦争の時代の話とか。ちょっと調べてみる必要がありそうです。親方のもう一つ上の大親分の存在など、よく分かりません。最後に予想外のことが起きて、読者をドキドキさせ最後はうまくいくというのは、いい物語のおさめ方だなと思いましたね。
ウアベ:物語としてすごくおもしろい、何年もかけて書いたとありますが、書き込まれた物語だなと思いました。今の日本とは遠い世界のことだけれど、景色とか水車小屋の様子とか情景が浮かんでくるのがよかったです。食べ物にありつけるというので水車小屋に行くんだけれど、親方が魔法使いだということとか、1年にひとりずつ死んでいく意味とか、ユーローの2面性とか、読むうちにわかっていくのがおもしろい。地位にしがみついている親方の、自分中心のあり方は政治家みたいですよね。終わり方が小気味よいというか、娘がよくやってくれたなって、物語として安心できてよかったなって思いました。
タビラコ:たしか1980年ごろに初めて読んだとき、とても感動して、こんなにおもしろい本はないと思ったのを覚えています。今回、なんであんなに感動したのだろうと思いつつ読みかえしたのですが、やはりプロイスラーの卓越した「物語る力」なんですね。それから、自然の描写や、日本ではなじみのないキリスト教のお祭りといったドイツ的なものに魅了されたのだと思います。もちろん、伝説の力もありますけれど、それをこれだけ自分のものにして書き切るとは、やはり素晴らしい作家だとあらためて思いました。いま、ウアベさんから政治家の話が出ましたけど、私も読みながら政治家のあの人やら、この人やらの顔を、親方の顔と重ねていました。二言目には、強い日本とか、いざとなったら戦争も辞さないといいながら、自らは戦地に行くこともないのに若者を戦争に、死に追いやる危険にさらしている人たちのことです。昔話は、いろんなメタファーとして読めることから語りつがれ、読みつがれてきているのだと思いますが、この物語もいつまでも読みつがれていってほしい1冊だと思います。昔は、最後の愛の力で死や悪に勝つという結末に感動したのですが、今回はたぶん歳のせいでしょうか、結末に至るまでの物語に魅せられました。
レジーナ:『夏の庭』には骨を拾う場面がありましたが、『クラバート』は、遺体を埋める文化の中で書かれた作品ですよね。東洋や西洋の死生観が、児童文学の中にどう表れているかを考えていくと、おもしろいのではないかと思いました。
(「子どもの本で言いたい放題」2012年10月の記録)
闇の底のシルキー
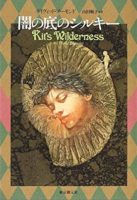
原題:KIT'S WILDERNESS by David Almond, 1999
デイヴィッド・アーモンド/著 山田順子/訳
東京創元社
2001.10
版元語録:寂れた炭鉱町にこしてきた僕は、風変わりな少年に誘われ、死という名のゲームに加わる…。英国児童小説界の新鋭が、不思議な世界を見た2人の13歳の少年を描く物語。
カイナマ:おもしろく読んだって言えばおもしろく読みました。廃坑になった炭坑の町を舞台に、かつて炭坑の事故で死んだ子たちの名前が彫られている中に全く同じ名があるというのはちょっとドキっとする設定です。物語としてはよくできてるなあと思いました。死のゲームっていうのは時代や場所が違っても、子どもたちはよくするものなのでしょう。そして13歳で死んでしまった子どものたちの姿が見えるというのも、なんだかスッと受け入れやすく書いてあるように思います。ジョン・アスキューという問題を抱えた子を救う物語でもあるし、キットが自分の存在を確認する物語でもあるのかなと思います。最後おじいちゃんが亡くなるんですけど、そのおじいちゃんにかわいがられた女優志望の娘アリーも、人物がよく描かれているなと思います。
プルメリア:最初に書かれていた「時計の針を戻して・・・」を読んで、神隠しから戻ってくる話なのかなと思いましたが、まったく違いました。茶色く色あせた本、字も細かくて読みにくいなと最初作品を手にした時思いましたが、1章があまり長くなく次の章を読みたくなるような終わり方。死のゲームがあり、途中からラクの冒険物語があり、怖い存在のシルキー少年がときどき出てくる。重たい部分があっても明るさがある作品に惹きつけられて一気に読みました。登場人物では少年のおじいちゃんにすてきな印象。読み終えたとき、重い作品というより大きな山を乗り越えたおだやかなさが残りました。同じ作家の『パパはバードマン』(金原瑞人訳 フレーベル館)は、絵はすてきでしたが難しかった。でも今回の作品では、この作品がいちばんよかったです。残念なことは、出版されて10年あまりなのにこんなに紙が変色していると手にとられにくいかな。
アカシア:ストーリーが単純ではないですね。テーマの一つは死だと思いますが、とても重層的に描かれています。現実世界ではおじちやんが死に向かっていて、子どもたちは死のゲームをしていて、アスキューは自分は死のうとある時点で思っているわけだし、それにキットをひきこもうとしているわけだし、キットはラクの物語を書いて乗り越えようとしているし、アリーは「雪の女王」という子どもを死に誘う物語の役をしている。そういうものが複雑にからみあっているので、それがおもしろいところだなと思いました。この作家はリアリズムともつかず、ファンタジーともつかない部分がありますね。シルキーという不思議な存在が出てきて、それがリアリズムの中に入り込んでくる。そういうところが、ほかの作家と違う、おもしろいところだと私は思いました。
レジーナ:これ以上進んだら、死の世界に足を踏み入れてしまうというぎりぎりのところで子どもたちを救うのが、目に見えないものの存在なんですね。おじいさんが炭鉱夫というのは、アンモナイトなどの太古の遺物が入り混じった闇を旅するタイムトラベラーだと語る場面がありますが、死の世界を行き来しつつあるおじいさんもまた、過去の記憶をたどるタイムトラベラーの段階にあります。そのおじいさんによって、炭鉱に象徴される闇の中にいるキットが助けられ、新たな人生を生き始める過程が、美しい寓話として描かれています。ラクの物語も心に残りました。キットは、ラクの物語を自分の物語として語ることによって、過去と現在、想像と現在、闇と光をつないでいくんですね。それと対照的なのが、闇の底をのぞきたいという欲望は危険なことだと考える校長先生です。しかし子どもは、一度心の闇に入って、子どもとしての自分を殺すことで、大人になっていく。一方、女の子のアリーは、『雪の女王』を演じることで、そこまで危ういところまで踏みこまずに、成長のプロセスを上手に乗り越えているように感じました。
タビラコ:思春期の人たちが半ば暴力的に死に近づいていくというのは確かだと思うけど、男女の差があるのかしら? それはともかく、アーモンドの作品には『肩甲骨は翼のなごり』(山田順子訳 東京創元社)もそうだけれど、とても魅力的な女の子が出てきますが、この作品のアリーも生き生きとしていて魅力的ですね。わたしがアーモンドの作品を読んでいつもすごいなと思うのは、登場人物の内面を深く掘りさげて書きながら、とても大きな世界を同時に描いていることなんですね。『火を喰う者たち』ではキューバ危機、この作品も太古の大陸が一つだけだったときのこととか……。ただ、翻訳は、とても難しい作品なんだろうなと思います。おじいちゃんが「闇」について語るところなど英語ではdarkness だけど、「闇」っていうととたんに深遠で、高尚な感じになってしまうし……。
ウアベ:すごく重層的で、情景や人物描写が本当にうまい。優等生じゃない人たちの描き方がうまくて、人物が魅力的だと思いました。生命とか生きることの不思議、人間の存在の不思議、時間が積み重なっていくことか、表面的ではなく、深いところまで入っていく感じがしました。それと土地の雰囲気。炭坑あとの、夜になると真っ暗になりそうな荒野の感じがすごく伝わってきて、真っ暗な穴の中にふとシルキーが浮かび上がってくるイメージがすてきだなと思いました。日常の中にふと不思議な物がでてくる、現実に足がついているからこそこういうファンタジーが生まれるんだと思いました。貧しい人々が多いラテンアメリカではプリミティブなものから発生したファンタジーはあっても、ハイファンタジーは生まれにくいとこのごろ思うのですが、アーモンドの作品は土地に根ざした感じに類似性を感じました。
アカシア:ハイファンタジーというのはどんなのですか?
ウアベ:この世界とは別の1つの世界をつくって、その中で現実ではない物語が展開するというようなものじゃないですか。それから、p145「だから、あたし、演じるのが好きなんだよ、キット。魔法みたいだもん。」の書き方が好きだなって思いました。この子は演じることで、そして主人公は書くことで救われているんだろうなって思って。それにアスキューの描き方を見て、この作家はいろんな人を見て生きてきた人なんだろうなって思いました。こういう人物はなかなか描けないでしょう。アスキューのお父さんは、アスキューが自分を認めることができなくなるくらい、ひどい行動をとってきた人なのに、最後は希望を見せてくれてますね。
タビラコ:アスキューの一家も、お父さんは飲んだくれで暴力的だしどうしようもない荒んだ家族だけれど、周囲の人たちが排除しないで、それとなく見守っているという感じがいいですね。
ウアベ:人生の複雑さが垣間見える小説ですね。
カイナマ:さっき校長先生の話が出たけど、イギリスの学校の先生はムチを振るったりして厳しいんでしょ。
アカシア:昔はそうでしたが、今は違うんじゃないでしょうか。
カイナマ:学校の先生という点から見ると、校長はアスキューなんかに近寄るな、とはっきり言い、事件後には放校処分にしちゃう。一方芝居に力を入れる子、絵の才能がある子は先生としても認めている。やっぱりある種の枠があって、そこから外れるのはだめっていう判断は、今でもあるでしょう。アスキューのような生徒はきっと今でもいて、学校という組織が救うのは難しいんじゃないかな。残念ながらその子のよさを認めて伸ばしてやれない生徒がいるというのは今もありますね。
(「子どもの本で言いたい放題」2012年10月の記録)