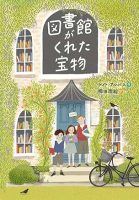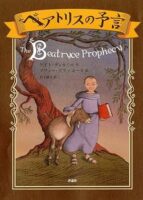ユリ・シュルヴィッツ/著 さくまゆみこ/訳
玉川大学出版部
2025.09
とうとうこの本を出してもらえました。いくつかの出版社で「出しましょう」と言われたけれど、主に画像掲載の許諾取得(センダックなどの絵が入っています)が大変だということから棚上げにされていました。でも、編集プロダクションの「本作り空Sola」さんが出版に向けて大いに努力してくださり、ようやく出ることになりました。
ワルシャワで生まれ、空爆で家を失い、世界を転々としたシュルヴィッツは、アメリカにわたって絵本作家になりました。この本は、さんざん試行錯誤しながら絵本をつくってきた自身の体験や、若い絵本作家の卵を教えた長年の経験から書かれています。古今東西の美術作品の図版が多数入っています。日本の絵画をたくさん集めていたシュルヴィッツは、日本の画家たちからもずいぶんと学んでいたのですね。著者まえがきでは、そのことにも触れています。
『よあけ』がどのように発想され、制作されていったかの具体的な過程も書かれています。今、絵本界に勢いのある韓国ではとっくに本書の韓国語版が出ていて、韓国の絵本作家たちは、この本を参照して絵本づくりを進めたりしています。
内容は以下のとおりです。後付についてはsolaの熊谷さんが頑張って作成してくれました。
*****
日本の読者のみなさまへ
はじめに
第一部 物語を語る
第1章 絵本と読み物の本のちがい
第2章 絵のシークエンス
第3章 物語――アクションの完結
第4章 物語の内容をどう考えるか
第5章 絵本の特徴
第二部 本のプランを立てる
第6章 絵コンテと本のダミー
第7章 本のサイズと形とスケール
第8章 本の構造
第三部 絵を創造する
第9章 イラストレーションや挿絵の目的
第10章 人物や物を線で描く
第11章 絵を描くための参照資料
第12章 画面空間と構図
第13章 テクニックの基本
第14章 スタイル
第15章 出版に向けての準備
訳者あとがき
ユリ・シュルヴィッツ著作一覧
図版一覧
参考図書リスト
タイトル索引
人名索引
事項索引
(編集:熊谷淳子さん 装丁:佐藤レイ子さん)