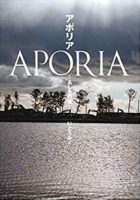ウルフ・スタルク/作 キティ・クローザー/絵 菱木晃子/訳
徳間書店
2020.09
アンヌ:私はおじいちゃん子だったので、主人公と祖父が性格の一致を喜ぶ場面には、心がギュッとつかまれました。船の中で、手と手を重ね合わせるところとかを読んで、相手の温かさを感じるだけで幸せな気分になる感じとか、いろいろ思い出してしまいました。題名からわかるように、この物語は祖父が妻の死を受け入れ、自分の死も受け入れていく物語であり、主人公が祖父の死を受け入れていく過程が描かれています。でも、ユーモアたっぷりの物語で、その中にスウェーデンの典型的な食べ物、ミートボール、シナモンロール、コケモモのジャム等が姿を現し、その食べ物にも一つ一つ意味があって、おいしそうで温かくて魅力的な物語となっています。アダムという頼りがいがある大人が出てきて、p131で祖父を病院から連れ出した自分を責める主人公を、おじいさんはああいう人だろうとなだめてくれるところでは、たとえ老人でも病人でも障碍者でも人権があるということを教えてくれます。嘘が嘘を呼ぶ苦い味も12章の「カンペキなうそ」でしっかり描かれていて、実に見事な物語だと思いました。キティ・クローザーの挿絵も一目見た時からあまりに魅力的で、目が離せませんでした。
ニャニャンガ:ウルフ・スタルクは好きな作家なので、刊行後まもなく読んだので再読です。スタルク最後の作品ということで読む前から胸が熱くなりました。おじいちゃんと孫、人生の悲哀をテーマにしたスタルク作品は最高です。ただ今回は、おじいちゃんがあまりに口が悪くて偏屈だったので、物語世界に入るのに少し時間がかかりました。島から帰ってきたあと、天国で妻と再会するときのために言葉遣いを直そうと努力するおじいちゃんが大好きです。ただひとつ残念なのは、キティ・クローザーの挿絵をスタルクさんが見られなかったことです。対象年齢の読者がどのように読むのかを知りたいと思い「読書メーター」を見てみたところ、勤務校の男子生徒にすすめられたという書きこみを見つけ、きちんと届いているんだなとうれしくなりました。
ネズミ:とてもおもしろく読みました。はじめから、おじいちゃんが死んじゃうんだなとわかるのですが、それでも読者を思いがけないところまで連れていってくれます。ストーリーや人物に無理がなく整合性があって、ほころびがない、完成度の高い作品だと思いました。改めていいなと思ったのは、この本に出てくる人たちが、誰ひとりとして、いい人になろうとしないところ。こうじゃなきゃいけない、というような道徳や偽善がない。看護師さんも、おじいちゃんが患者だというのに悪口を平気で言うんですね。日本の子どもの本とは、人間の描き方がずいぶん違うと感じました。
ハル:皆さんの感想を聞いていて、思い出し泣きしそうです。本を閉じてからしばらく泣いてしまったのですが、もしかしたらこんな体験は初めてかも。私は小さいころ、おじいちゃんのことがあんまり好きじゃなかったので、子どものころにこの本を読みたかったなぁと思います。子ども時代に読んでいたら、愛する人を失うという体験を、この本で初めて覚えたのかもしれませんね。登場人物、ユーモアもたっぷりの表現、イラスト、訳文……そういった全部、この本のすべてに愛があふれている感じがします。そして今度、北欧を旅することがあったら、お皿に添えられたコケモモのジャムも大事に食べようと思いました(以前に旅したときは、なんでおかずにジャムがのっているのかよくわからなくて、よけちゃったので)。
雪割草:あたたかくて素敵な作品だなと思いました。おじいちゃんは、古風で怒ってばかりですが、人間味あふれる描写で、「訳者あとがき」にもあるように、作者の、おじいちゃんのことが大好きという気持ちが伝わってきました。それから、「死」の描き方もいいなと思いました。カラスがオジロワシになって飛んでいくラストシーンへ向かって、p149にはウルフの見えないものへの気づきが書かれていますが、子どもの等身大の体験に近く感じました。ほかには、ウルフとおじいちゃん、ウルフとお父さんの関係が、p59にあるように世代の違いだけでなく、一人ひとりの違いとして描かれているのもよかったです。人生のはじめの方にいるウルフと人生の終わりの方にいるおじいちゃんの交流が、味わい深かったです。
マリンゴ:タイトルから、重い展開をイメージして、今まで敬遠していたのですが、想像とは違ってとてもハートフルで、楽しい部分もある物語でした。「嘘」が出てくるお話って、それがバレたらどうしよう、とハラハラする流れが一般的だと思いますが、この作品は、嘘を言うことを楽しむ少年が主人公で、ピンチに陥っても、仲間のアダムがすらすらと嘘をつくなど、嘘を肯定する展開がおもしろかったです。お父さんの前で、おじいちゃんとの冒険の事実を主人公がぶちまけると、お父さんがまったく信じてくれない、という場面が印象的でした。p126「合宿でなにがあったか、話してみなさい」と言われて、「……寝袋の中にゲロを吐いた子がいた」と答える場面はユーモラスで、笑ってしまいました。事実がすべて正義とは限らない、と考える作者の想いが伝わってきます。大きなことではないのですが、唯一引っかかったのは、p114からp115にかけて、アダムが卓球の試合ですぐに負けた話をしたあとの主人公のコメントです。「すぐに負けて、よかった」「ビリだっていったほうが、うけがいいでしょ」「負けた人のことは、みんな、かわいそうだと思うよね。で、ふだんよりやさしくしてくれる」などと続くのですが、これが、物語の流れのなかで若干唐突なので、後の伏線かと思ったらそうでもなく、少しとまどいました。
ハリネズミ:p114からのところは、ウルフの人となりをあらわしている表現だと思って読みました。融通のきくちょっとちゃっかりした性格の子なんじゃないかな。ウルフ・スタルクは角野さんと同じ時期に国際アンデルセン賞候補だったんですけど、選考期間の間に亡くなられたので、候補から除外ということになってしまいました。さっき、ハルさんが泣いたっておっしゃったのですが、私は、あっちこっちで笑いもしました。しみじみさせながら笑わせもする作品って、すごいです。文章にも絵にもあちこちにユーモアがちりばめられています。たとえば、汗臭い女の人に寄っていくっていうエピソード+p20の絵で、私は噴いてしまいました。子どもらしい視点も随所にあります。たとえばp10「ぼくは、まえからずっと、おじいちゃんが怒りだすときが好きだった。その場にいると、ものすごくドキドキする」とか、お父さんに「わたしの目を見ろ」と言われて、p122「ぼくは見なかった。パパの眉毛を見ていた。目でも眉毛でも、パパにはわからない」とか。p130で、パン屋の店に入って「店の中に入ると、あたたかくて、うす暗くて、いいにおいがして、ぼくはからだがふるえた」とか。スタルクには、上から目線や猫なで声がまったくない。あと、短い文章の中で、じつに的確に表現しています。たとえばp72「ぼくがジャムの瓶を持ってもどると、おじいちゃんはしばらくのあいだ、その手書きの文字をじっと見つめていた。それからふたをあけ、パラフィン紙の封をナイフでそっとはがした」というところですけど、あれだけ罵詈雑言を連発していたおじいちゃんが、おばあちゃんの作ったコケモモのジャムには万感の思いを抱いていたことが伝わってきます。それと、どのキャラクターにも奥行きがある。下手な作品だとお父さんを悪者にしてしまうところですが、お父さんも、p146のお菓子を買ってくるくだりや、そのとなりの絵を見ると、ただの堅物ではないことがわかりますよね。最後のカラスとオジロワシのところも伏線がちゃんとあるし。キティ・クローザーの絵も、ほかのにも増してすばらしいので、スタルクを敬愛していたことが伝わってきます。
カピバラ:私もスタルクは大好きな作家なんですけど、大好きなスタルクの最後の作品だというさびしさと、おじいちゃんの最後の旅という悲しさとが重なって、なんともいえないしみじみとした読後感にひたった一冊でした。スタルクの持ち味はユーモアとペーソスだと思いますが、それが十分に味わえる作品だったと思います。時代も国も違うのに、こんなに親しみを感じる人が出てくる本っていうのは少ないものですが、先ほど「登場人物がみなほかの人に自分を良く見せようとしない人たちだ」という感想がありましたが、なるほどと腑に落ちました。何度も何度も繰り返し読みたい作品です。
まめじか:登場人物が人として立ち上がってきて、この人たちはページの向こうにちゃんといると感じられました。主人公のウルフはおじいちゃんのことをよく理解していて、たとえば「死んだ人を愛しつづけることって、できる?」(p60)ときいたときに「だまれ、ガキのくせに!」なんて言われても、それは「できる」という意味だとちゃんとわかってる。わざと汚い言葉を言わせて、その罰として薬を飲ませるのも、おじいちゃんへの想いが伝わってきます。ウルフは人生がはじまったばかりの子どもで、一方おじいちゃんは人生を終えようとしている。夢と現実の境があいまいになって、おばあちゃんとかオジロワシとか、そこにはいないはずのものが見えるようになったおじいちゃんの目に映るものを、ウルフはときどき感じながら最後の時間をともに過ごして、やがておじいちゃんは船のエンジン音のようないびきをたてて向こう側の世界へと出航していく。たった2日間の冒険が、主人公の心にかけがえのないものを残したのですね。冒頭に出てくる紅葉した葉は、次の世代に命をつないでいくことを思わせるし、コケモモのジャムは生きることそのものというか、人生という大きなものを日常のささやかなものにぎゅっとこめるように描いていて、そういうのも見事だなあと。おじいちゃんが弱っていく姿を見たくなくて病院に来たがらないお父さんの描写には、リアリティがありました。あと、ウルフがバスの中で、汗のにおいがうつるようにおばさんにくっつく場面なんか、ユーモアがあっていいですね。挿絵も物語にとてもよく合っています。キティ・クローザーは現実と想像が入り混じった世界を鮮やかに描き出す画家で、私はとても好きです。死をテーマに扱った作品も多いですね。
さららん:しばらく前に読みましたが、ほんとに短いけど、どこもかしこもおかしいような切ないような、魅力的なお話でした。おばあちゃんのお葬式のときに、汚い言葉を吐いてしまったおじいちゃんは、天国でおばあちゃんと再会するときのために、これからはきれいな言葉をしゃべれるようにがんばろう、と決意します。そんなところに、おじいちゃんがおばあちゃんに伝えきれなかった、深い愛を感じました。そして、この本はあえて直訳風にした翻訳の仕方がすごくおもしろくて! p44の「かわりに息子と、とてつもなく愉快なわたしのおいがまいります」とか、下手にやったら目も当てられない表現ですが、それがものすごく笑えるんです。これは菱木さんのマジックかなあ。シナモンロールはよく食べるけれど、カルダモンロールは食べたことないので、食べてみたいです。おじいちゃんが静かにいびきをかきはじめた場面では、涙が出そうになりました。
サークルK:読書会に参加させていただくようになっていちばん涙を流した作品でした。タイトルがすでに物語るように、主人公のおじいちゃんの死に向かっていくお話ではありますが、悲壮感がなく「命がゆっくりと尽きていくときの時間」ということを作者が尊厳をもって温かい言葉で語ってくれていて、素晴らしかったです。その素晴らしさを翻訳と挿絵がさらに引き立てていました。p61のおじいちゃんと孫がまったく同じポーズで船室の椅子に座っているところはユーモラスで思わず笑みがこぼれましたし、p159の挿絵で孫の男の子がおじいちゃんの大きな手を握りながら最後の時を過ごしている様子には、胸を打たれました。ベッドサイドテーブルにおばあちゃんの写真とほんの少しだけ残ったコケモモのジャムの瓶が置かれていることが描かれていたからです。大好きな妻の作ったコケモモのジャムはおじいちゃんの生きるエネルギーそのものになっていたはずなので、挿絵に空っぽの瓶ではなく、ほんの少しジャムが残された瓶が描かれたことによって、おじいちゃんが明日もまた生きておばあちゃんのジャムを食べたいと思っていたのかもしれない、という希望のようなものが感じられました。p90で示唆されていた「オジロワシ」にp161で見事に姿を変えたおじいちゃんの最期は悲しみに満ちたものでなく誇り高いものであったのだなあ、としみじみ感じ入りました。
すあま:最後に登場人物が死んでしまうことがわかっている話は子どものころからあまり読みたくないのですが、スタルクなら絶対おもしろいだろうと思って読みました。ウルフが両親をだましておじいちゃんを連れ出すところは、途中で見つからないか、おじいちゃんは具合が悪くならないかと、ハラハラする冒険物語を読んでいるようでした。アダムがいたのも大きかった。家族じゃないけど助けてくれる大人が出てくる物語はいいですね。出てくる大人がちゃんと描かれているし、アダムも魅力的な大人で、おじいちゃんとわかりあえている感じもよかったです。日本でも、子ども向けに老いや死、認知症をテーマにした本がいっぱい出ているけれど、ウルフ・スタルクにかなう人はいません。泣かせる、感動するだけでなく、やっぱり笑えて楽しいところもあるのが良いと思います。ウルフはいい子だけど、それだけじゃなくて嘘もつくし、個性豊かで生き生きしている。おじいちゃんが亡くなってしまうのも自然に描かれていて、いいなと思いました。死を描いていると、怖かったり悲しすぎたりするものも多くて、そういう話が苦手な子にも読みやすくて受け入れやすい話だと思いました。来日されたとき講演会でお話をうかがったのですが、物語のウルフに会ったようで、とても楽しい時間でした。訳については、汚い言葉を話す人たちを、キャラクターが伝わるように訳すのは難しいのではないかと思いましたが、すばらしい翻訳でした。
シア:『うそつきの天才』(ウルフ・スタルク著 はたこうしろう絵 菱木晃子訳 小峰書店 1996)という本が大好きでしたので、ウルフ・スタルクだ! と思いながら読みました。「最後の旅」という題名を見て、また題名ネタバレをしている……とガッカリしたのですが、結果的にかなり泣かされました。日本版はこの手の題名多いので、なんとかしてください! おじいちゃんの汚い言葉がかえって生き生きしていて、本当におばあちゃんを愛していたんだなというのも伝わりましたし、変わっている人なんですがとても素敵な人だと思えました。こんな人生いいなと思いながら読みました。子どもに是非読んでほしい本です。挿絵は色鉛筆ですかね、きれいな色合いでした。小学生くらいから読むのにいいと思います。夜に読んだので、シナモンロールとかコケモモのジャムなど、誘惑にかられる1冊でした。
しじみ71個分:読んでもうとにかく感動しました。短い物語の中で、どうして人間関係がここまで書けるんだろうと驚くばかりです。詳細な説明は書いていないのに、おじいちゃんとの関係ばかりか、お父さんとウルフ少年との関係など、全部わかってしまうんですね。キティ・クローザーの絵もすばらしくて、最後のおじいちゃんとおばあちゃんの二人がよりそっている後ろ姿の絵を見て、涙腺崩壊しました……。アダムも看護師さんたちも脇役ながら、人がらがみっちりと描きこまれていて、とても魅力的です。著者はキティ・クローザーの絵を見ることなく、出来上がった本を手に取ることなく、亡くなられたとのことですが、自分が老境にあって、おじいちゃんのことをどういう心境で書かれたのかなと思うと、また泣けてきます。汚い言葉を使うけれども愛情深い人で、短い言葉や行動の中におばあちゃんへの愛情があふれていますね。病院を抜け出して島にわたる際におばあちゃんの姿を見たり、おばあちゃんの腰かけていた椅子に座って窓の外を眺めたり、と不在の人を見る、またその人の見ていたものを見ようとするという行為が、不在の人を思う深さを直接的な言葉でなく語っているところに、ウルフ・スタルクのすごさを感じました。それから、ウルフ少年の嘘も、自分の苦しまぎれの保身とか自分勝手とかではなく、おじいちゃんを楽しませるためで、自分の力で考え、アイディアで難局を切り抜けていくという、この物語に代表されるような、西欧の活力ある子ども像は大変に魅力的ですし、そういう物語が日本のお話でも描かれていくといいなと思いました。
さららん:キティ・クローザーが日本に来たとき、お話ししたことがあるんです。そのとき、日本で何をしたいですか? ときいたら、島に渡りたいと言ってました。このスタルクの本の中に出てくる多島海の風景は、ベルギーとスウェーデンの両方を行き来して育ったキティの原風景でもあるんだ、と思いました。
ニャニャンガ:原書の表紙では、おじいちゃんの足元にタイトルが入っていますが、邦訳では上に移動していますね。空の部分が原書の倍くらいになっていますが、どうやってつけ足したのかなと思いました。
ハリネズミ:日本語版には帯がついているから、タイトルを上にしたのでしょうね。原画が大きかったのかもしれないし、コンピュータ処理で空の部分を伸ばしたのかもしれません。
(2021年10月の「子どもの本で言いたい放題」より)