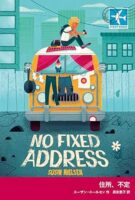
原題:NO FIXED ADDRESS by Susin Nielsen, 2018
スーザン・ニールセン/作 長友恵子/訳
岩波書店
2022.06
〈版元語録〉4か月前、ぼくとママはキャンピングカーで暮らしはじめた。アパートを追い出されホームレスになったんだ。ところが一時的なはずの車上生活は長引き、しだいに身も心も追いつめられていく。親友に噓をつくのも、もう限界! TV番組に出て賞金を獲得すれば何もかも解決する――ぼくはそう信じた。少年の涙と希望の物語。
花散里:出版されたとき、話題になったのですぐに読みました。「住所」がなく、トイレもシャワーもないキャンピングカーでの暮らし、頼る人もなく、友だちにも嘘を重ねていく主人公の姿は、今回読み直していてもつらくなりました。母親には母親の考えがあること、それをフィーリックスが理解していることも、痛々しいくらいでした。そんな中で、友だちに支えてもらっていること、万引きをした店の店長や、レストランの人など、周りの人たちの描かれ方が良いと思いました。後半、クイズ番組にエントリーするところなどは興味深く読めましたが、日本の中高生がどうやって読んでいくのでしょうね。
ANNE:精神的に弱いところがある母親と二人でキャンピングカー暮らしを続けている12歳の男の子が主人公です。さまざまな不自由を強いられる中でも、母親の万引き行為を目撃してしまう場面は、本当につらく胸が締め付けられるように感じました。ただ、自らも難民である食料品店主の夫婦や、妥協することが苦手で周囲に溶け込めない友人などが、彼に温かく手を差し伸べてくれるのが救いでした。文章の中にところどころ太字で書かれている部分がありますが、原書ではどのように表記されているのかが気になりました。久しぶりに会った(生物学上の)父親が主人公に「好きな子ができたのかい? どんな女の子? それとも男の子かな?」とさらりと尋ねるシーンも印象的でした。作者はカナダの児童文学作家だそうですが、これもお国柄なのでしょうか? 今を生きる若い読者にぜひ薦めたい一冊です。
まめじか:主人公を助ける人たちの描き方がとてもよかったです。シリアからの難民のアーマディさんなど、日本の児童文学ではなかなか描かれないような人物ですよね。物語の中に、住宅価格の高騰などの社会問題が自然に組みこまれていると感じました。物語の後半、主人公がクイズ大会に出て優勝するまでの部分は、いまひとつはいりこめませんでした。いろいろな大学で幅広く学んだアストリッドや、クイズ番組が好きだったおばあちゃんといっしょにいたことで、主人公はクイズが得意だという設定なのですが、それで歴史の年号など細かいことまでおぼえられるものなのか……。
アンヌ:キャンピングカー生活の奇妙にウキウキする感じと、芸術家気質で魅力的な母親との工夫とウソに満ちた生活がとても魅力的に描かれていくのですが、そこからどんどん悲惨な感じになっていって、読んでいてつらくなりました。作者は、読者をドキドキさせるのがとてもうまいけれど、賞金を18歳まで受け取れないと知って窓に向かうところでは、自殺するんだと思ってしまい先が読めないほど怖く、この後の落ちといい、見事ではありますがつらい場面だと思いました。最後のほうの友だちと3人で神様はいっぱいいると語り合って、何か人間には計り知れない力もこの世にはあるということを話し合う場面は好きです。そして最終的に「人間を信じる」という、母親とは違う価値観を持って終わるのもよかったと思います。あとがきに、恋人ができたというと男女どちらと聞くところがカナダらしいと書かれていましたが、図書館や車を襲う変態男たちが、少年である主人公も狙っているという性暴力の現実を描いているのも重要だと思いました。
雪割草:「ぼく」の一人称の語りは、そのキャラクターがよく感じられて、どんどん引き込まれて読みました。内容も、おばあちゃんが亡くなって、家を売って、買ったマンションにトラブルがあって、シングルマザーなのに母親が失業し、鬱で、キャンピングカー生活になり、とありうるリアルな設定だと感じました。母親が万引きの常習犯になり、ヒーターのような大きなものまで盗んでしまうのは驚きでした。「ぼく」が母親に頼れず、ハツカネズミやおばあちゃんの形見のトムテを心のよりどころにしているのは、胸が痛むけれど子どもらしく、生きものや文化的なものを大事にしていて共感できました。アーマディさんがシリアから逃れ難民キャンプで生活していたというのも今的で、だからこそ「ぼく」の力になってくれるのも、人が支え合って生きていることを描いていてよかったです。最後に、「信じられる人」に出会うことの大切さを書いているのもあたたかな気持ちになりましたし、「ぼく」は強いけれど、その強さには無理がなく、子どもらしさもあって見事だと思いました。
きなこみみ:とてもおもしろく読みました。この物語は、主人公フィーリックスのお母さんの存在がとても大きく描かれています。彼女は、子どものときに父親から虐待を受けていたり、同性愛者のお兄さんが、お父さんに追い出された挙句に、孤独のうちに死んでしまったところを見てしまったりして、深い鬱症状を抱えているんですよね。世の中も、他人も、信じられないんです。だから、誰にも頼れなくて、息子と密室状態で、引きこもっていく。そこのところがうまく描かれているなあと思いました。『ノマドランド』という映画(クロエ・ジャオ監督.2021)も、キャンピングカーで転々としながら、生きていくというお話でしたが、やっぱりそうやって転々としていくのは、非正規雇用とか生き難さと深く結びついているんだなあと、この作品を読んで改めて思ったんです。いちばんつらいなと思ったのは、二人が生活しているキャンピングカーに、トイレがないんです。p88で、「ぼくは、こんなトイレがほしかった。」とフィーリックスが泣きながら思うシーンがあって、私も泣けてしまいました。家がない、っていうことは、いちばんプライベートで人に見せたくないところが守られないんだなって。トイレとかシャワーという、体にまつわる痛みが伝わってくるところが、とてもうまいです。アストリッドにとって、息子だけが信じられる存在なんですね。だから、息子に依存していって、どんどん二人の関係が逆転していって、追い詰められていくのが真に迫ってつらい。救いは、まわりの人たちが二人に手をさしのべてくれるところで、私は特に、我が道をゆく、空気を読まない女の子ウィニーが好きでした。フィーリックスも、はじめは嫌だなと思っていたのに、その性格がまわりまわってフィーリックスの救いになっていくのが良くて。最後、クイズ番組で優勝するのは、上手くいきすぎだなあと思っていたら、賞金をもらえるのが18歳からで、ラッキーチャンスでめでたしめでたしじゃなくて、まわりの人が手を差しのべることで、未来に繋がっていく、というのが良かった。誰にも頼らないで生きることにこだわっていた「不信」が、「信頼」に塗り替わるラストに、希望を感じました。あと、小さなことなんですが、p92に「公文で落第」というところがあるんですが、これが私の知ってる公文式の教室なら、落第ってあるのかな?と不思議に思いました。
オカリナ:フィーリックスの気持ちをリアルに想像しながら読めるのがとてもいいと思いました。お母さんは、読者をいらいらさせる存在ですが、『タトゥー・ママ』(ジャクリーン・ウィルソン作 小竹由美子訳 偕成社)のお母さんと一緒で、自分なりに子どもを愛しているのは伝わるので、どこか憎めないところがありますね。母子関係や、他者の支援を受けてはいけないと思い込むところなどは、ウィルソンの作品とも共通しています。日本は一斉教育で突出した個性や特異な考えはたたかれますが、資本主義に反対だと言って万引きをするところなど、フィーリックスのお母さんだけではなく、ほかの国にはこういう人ってけっこういるような気がします。アジア系の子どもとヨーロッパ系の子どもが親しくなるのは、最近の一つの傾向かも。自分が落ち着ける安定した場所を持てない子どもたちがたくさんいることに気づかせてくれる作品です。
スズメ:ちょっと盛りこみすぎかなと思ったけれど、とにかくおもしろかった。お母さんのことを子ども時代から現在にいたるまで、実にくわしく描いていて、すぐそばにいるような感じがしました。万引きをすることや、ときどき「スランプ」になることも含めて、チャーミングですね、お母さんの主人公に抱く愛情は、自己愛に近いものだけれど本物の愛情なのですが、メンタルの病をかかえていることもあって、坂道を転がりおちるように悪いほうへ、悪いほうへ落ちていってしまう様子が、読者の納得がいくように描かれていて、見事だと思いました。
母親にくらべて、主人公は胸が痛くなるほど健気なのですが、作者は主人公を孤立させずに、ふたりの親友を配しているので、安心して読めました。クイズの場面は、まさにアメリカンドリームですが、こうでもしないと救われなかったんじゃないかな。少し話がずれるかもしれないけど、主人公に手を差しのべるのがシリア系移民の食料雑貨店の店主というところを読んで、桐野夏生さんの『砂に埋もれる犬』(朝日新聞出版 2021.10)を思いだしました。もちろん児童書ではありませんが、親にネグレクトされた子どもが主人公で、その子を救うのがコンビニの店長さん夫婦なんですね。今の時代、近所付き合いは希薄ですし、小さい子どもほど警察や交番に親のことを訴えでるのに二の足を踏むといいますから、こういう地元のお店とかコンビニに協力してもらうということができないのかなと思いました。
ハル:もう、はらはらしながら読みました。ユーモアもあって、登場人物も個性的で、立体的に描かれているので、引き込まれて読むのですが、気づけば結構過酷な状況にどんどんはまっていく展開に、人生、一寸先は闇で、明日は我が身だなぁと思わされます。母親の体験として、だれかに援助を求めたり、福祉に見つかったりしたらとんでもないことになる、というトラウマが描かれているので、大人向けの小説だったら、このまま、社会的養護体制の課題を浮き彫りにした、で終わってもいいのかもしれないけれど……と思いながら読みましたが、そこはしっかり児童文学として着地していて、ほっとしましたし、感動しました。
コアラ:とてもよかったです。主人公のフィーリックスと一緒に苦楽を共に味わうように読んできて、最後にこんな素晴らしい言葉が出てくるなんて思わなくて、p311の7行目以降、「でも今、〜それは人だ。」のところは、声をあげて泣いてしまいました。ただ、クイズで賞金獲得して貧しさから脱するという設定は、映画の「スラムドッグ$ミリオネア」(ダニー・ボイル監督.2008)を思い起こさせたし、登場人物のウィニーが、ハリーポッターシリーズのハーマイオニーを思い起こさせるところがあると思いました。設定には既視感がありました。母親のアストリッドについては、人間味があって、万引きは共感できないけれど、彼女の弱さが私は憎めませんでした。どんなに生活が落ちていっても、子どもを捨てて逃げる、ということをせずに、食べ物も息子に多く与えたりして、息子を愛しているということが伝わってきました。フィーリックスのクイズの賞金の話のところでも、p210の後ろから6行目「あなたのお金よ」とアストリッドが言います。喉から手が出るくらいほしいはずのお金なのに、どんなに落ちても清らかな心は失っていないと思いました。フィーリックスについても、世の中に対する見方や考え方が、『あした、弁当を作る。』の同い年の主人公に比べて人間味があると思いました。p40〜p43の「アストリッド流『うそのつき方』」なんて、よく分析しているし、あたたかみがありますよね。気になったのは、最初の見出し。「午前十二時五分」となっていますが、夜中の「午前零時五分」ではないでしょうか。
さららん:アストリッドと「ぼく」の親子関係はもちろん、周囲の人たちとの関係に説得力があり、脇役の使い方もうまくて、引き込まれました。たとえばアストリッドの教え子だったけれど、今は売れっ子の画家でいるソレイユ。親切な人なのですが、アストリッドは明らかに嫉妬を覚えている。そしてソレイユの留守宅に入って、お金まで盗んでしまう。アストリッドは万引きの常習犯で、なにもかも正当化してしまう非常識な人物ですが、適応障害を感じさせ、息子への愛情は深い。「ぼく」は、アストリッドへの違和感を募らせていくけれど、その行動を止められない。キャンピングカーに籠る匂いにも、空き家のガレージで暮らしていたとき、人に見つかって、延長コードをあわてて抜いて逃げるところにも、リアリティがありました。個人的に納得できなかったのは、ついに「ぼく」が出場できることになったクイズ大会に、アストリッドの盗んだコンバースをはいていくところ。ここは、別のクツを履いてほしかった……! 最後の最後まで、気を抜かずに話を回収していくのは、脚本家でもある作者の資質なのかもしれませんね。
ニャニャンガ:物語の構成が巧みで読ませる作品でした。こんなに簡単に住所不定になってしまうものなのかと怖くなるほどリアルで、主人公のフィーリックスが、家がないことを隠すようすが痛々しかったです。はじめは苦手な相手だったウィニーが、彼女なりの方法で応援してくれたのがナイスと思いました。もうひとりのナイスな登場人物は、アーマディさんで、現実では出会うことが難しいけれど物語にはぜったい必要な存在だと思いました。また、母親の行動にハラハラし通しで、フィーリックスはヤングケアラーだと思いました。
ネズミ:とてもおもしろく読みました。自分勝手な論理でまずいことをして、職場で問題を起こしてクビになり、子どもに対しても世話をできない母親というのは、日本でもいるし、嘘っぽい話ではないと思いました。よかったのは、ディランとウィニーという友だちの存在です。ずけずけとものを言いながらも、相手に面目ない思いをさせない、互いへの深く思いやりのあるあたたかな関係が見える描き方がとてもいいなあと。万引きの場面については、フィーリックスの苦しみも見えて、これを読んで、万引きをしてもいいとは誰も思わないと思うので、これを書くこと自体がいけないとは私は思いませんでした。人物の描き方が全体によく考えられていて、たとえばアーマディさんは、難民だと書かれたあとで、シリアふうの食べ物が出てシリア難民だとわかるなど、うまいなと思いました。ユーモアもあるし、中学生くらいから読んでほしいです。
すあま:はらはらしながら読み進めました。お母さんのように、プライドが高くて他人の手を借りることができず、生活保護も受けない、という人は実際に多いのではないかと思います。こういう人たちをどう支援していくのかは、難しい課題です。主人公が万引きで捕まり、それがきっかけで、難民としてつらい思いをしたアーマディさんが助けてくれるところがよかったです。そして、主人公が賞金を狙ってクイズ大会に出場したのに、その賞金を手に入れることができない、という展開も意外性があったし、ラストは明日につながる感じで読後感がよかったです。クイズ大会の様子は、ウィリーが書いた記事でわかるのもおもしろかった。最後に訳者のあとがきから、著者の『ぼくだけのぶちまけ日記』(岩波書店)の主人公たちが登場していることがわかり、そっちももう一度読み返したくなりました。
マリーナ:読み応えがありすぎて、ヒリヒリします。ページを途中で閉じたくなるけど、やめられず、ノンストップで読了しました。家のこと、お母さんのこと、少しずつお金が減っていく過程がわかりやすく描かれています。かなりシビアな状況だけれど、からっとした文体と、この主人公の強さのおかげで、ディテールの友情部分やキャンピングカーの序盤の生活など、楽しんで読める部分も多かったです。LGBTQの話が、メインではなくさらっと出てくるあたり、いいなと思いました。ひとつ気になったのは猫の体重について話す場面です。p68「うわあ。九キロくらいありそうだな」が、ちょっと不自然だなと思いました。「10キロくらい」ならわかるのですが、ネコの体重を8キロとか9キロとか、ずばり推定するのは相当なネコマニアかと思うので……。おそらく原文は「20ポンドくらい」なんですよね。翻訳が難しいところかと思いますが。
(2023年06月の「子どもの本で言いたい放題」より)