| 日付 | 2016年11月24日 |
| 参加者 | アカシア、アンヌ、クマザサ、げた、さららん、すあま、西山、ネズミ、 マリンゴ、ルパン、レジーナ、(アカザ、エーデルワイス) |
| テーマ | 子どもから大人への成長物語 |
読んだ本:
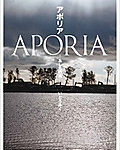
いとうみく/著 宍戸清孝/写真
童心社
2016.05
版元語録:2035年、東京湾北部を震源とするM8.6の大地震発生。沿岸部を津波が襲う。俺は母さんを見殺しにした――母を救えなかった中学生・一弥は、絶望の底から生きる希望の光を見出せるのか…。

原題:DOLL BONES by Holly Black, 2013
ホリー・ブラック/著 千葉茂樹/訳
ほるぷ出版
2016.06
版元語録:「この人形の粘土には人間の骨が使われてるの」誰も触ってはいけないはずの人形に触れたことをきっかけに、3人の冒険が始まる。

原題:PAPERBOY by Vince Vawter, 2013
ヴィンス・ヴォーター/著 原田勝/訳
岩波書店
2016.07
版元語録:1959年、メンフィス。ぼくは夏休みのあいだ、友達のラットに代わって新聞配達を引き受けることになった。すぐにどもってしまうせいで人と話すのは緊張する。でも大人の世界へ一歩踏み出したその夏は、思いもよらない個性的な人たちとの出会いと、そして事件が待っていた。2014年度ニューベリー賞オナーブック。
アポリア〜あしたの風
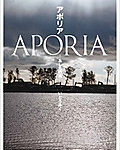
いとうみく/著 宍戸清孝/写真
童心社
2016.05
版元語録:2035年、東京湾北部を震源とするM8.6の大地震発生。沿岸部を津波が襲う。俺は母さんを見殺しにした――母を救えなかった中学生・一弥は、絶望の底から生きる希望の光を見出せるのか…。
さららん:何度か書評で紹介されていたので、読みたかった本です。過去の現実として書くと、震災の描写が読者にとって生々しすぎるので、近未来を舞台にしたんでしょうね。それでも東日本大震災のとき、テレビやネットで見た画面が次々と浮かんできて、「あのとき」に投げ込まれた感じがしました。片桐という男性に主人公は津波から救われたけれど、それは同時に母を見捨ててしまう行為だった。「生きる」意味に真正面から取り組んだところに、作者の気概を感じます。汚れた水の中をボートで行くところなど、リアリティがあり、感情が揺さぶられる場面もあるいっぽうで、よく理解できないところも残りました。そのせいか、どこか未消化のまま読み終えたんです。ひょっとしたら、自分の心をガードしていたのかも。震災を体験した人はもっとガードがかかって、この物語は読み通せないかもしれません。でも、読んでよかったなあと思ったのは、情報の伝わり方が実感としてわかったことかな。現場にいる人には切れ切れにしか伝わってこないし、避難所に行って初めて情報が固まりとしてつかめるけれど、それももちろん十分じゃない。新聞で読んだいたときには、ピンとこなかったことが、理解できました。
西山:「3.11」を書いたということには賛成。本になるのはいいことだと思ってます。それは前提として、どうして近未来にしたのか。それが腑に落ちません。未来として書くならこれからの未来をどうしたいのか、という構想が必要だと思うんです。それを決定的に感じたのは、自衛隊のヘリが助けにくるシーン(p247)で、実はがっかりしちゃった。ああ、2035年も自衛隊が救助に当たるんだって。もう海外派遣で忙しくて、国内の被災地支援なんてする余裕はないと皮肉に思ったりもするんですが・・・・・・。もともとテレビで自衛隊の救援映像の露出が増えていてとても違和感を持っていたので、がっかりしたんです。<子どもの本・九条の会>で『9ゾウくんげんきかるた』(ポプラ社)を作ったとき、これは「3.11」の前に作ったんですが、そのとき私は「人助けするならあかるい色を着て」という読み札を考えていた(使いませんでしたけど)。レスキュー隊員の蛍光オレンジとか目立つ色と比べて、迷彩色の目的は人助けではない。近未来も、結局迷彩色が活躍しているんだ、それが現状を容認しているようで・・・・・・。地震の時の様子をリアルに書くということは時間が経つに従って必要になってくると思うので、5年経ったいまこういう作品が出るのは意味があるのだとは思います。連続テレビ小説『あまちゃん』では、津波の場面をジオラマに水がかぶる様子で表していました。あの日がまだ近かった時点では、被災者でなくてもそれで十分だったと思います。でも、時間が経って、また、あの時の記憶を持たない子どもたちにとっては、はっきりと描写されることが必要になってくると思います。
マリンゴ:東日本大震災を想起させる災害を東京で、という試み、いいと思います。東京が舞台だと、震災の記憶がなくても自分に身近な物語として読める子どもたちもいるでしょうから。ストーリーに勢いがあって、一気に読めました。ただ、文章の表現に関することですが、擬声語への依存度が高く、それが気になりました。ガタガタ、ゴー、プープープーなど。小学中学年くらいの読みものだったら、擬声語で伝えるというのは効果的かもしれませんが、この本の対象年齢は高学年から中学生以降だと思うので、それにしては幼い印象を受けました。また、いろんな人物の視点で描くことによって、群像劇を立ち上がらせていますが、少しめまぐるしい気もしました。たとえば冒頭のお母さんの視点は、主人公の見ているものとあまり変わらないので、なくてもよかったのかな、と思ったり。
アンヌ:同じ作者の『二日月』(そうえん社)と違って、詩的な表現やユーモアがない作品でした。読んでいて登場人物の名前がうまく憶えられませんでした。松永と北川の口調が同じだったり、片桐と伯父さんも似たような感じだったりして、その他のわき役もあまり肉付けされていないと思います。トラウマがあってもう死んでもいいやと思っている大人が3人もいて、厚木は孫まで殺して心中するつもりでいた。そんなすごいことの告白も唐突で、なぜここで保育士に話すのか奇妙に感じました。近未来の設定のわりに、未来が描かれていません。例えば、この時代には避難所に必ずボートの設備があり、その装備はこうだとか書きこまれていないと、映像が浮かんでこないし未来の感じがしません。主人公の今後についても、方向性がないと感じました。避難所もいつかは閉鎖されるのだから、その後のことが気になります。
クマザサ:近未来に設定したのは、やはり東京で起きたらどうなるか、ということを書きたかったからではないでしょうか。でもその割に、地名が架空になっているせいか、臨場感がないんですよね。たとえば,,区ではなにが起きて、××区ではどうなって……とか、実際の地名が出てくればよかったかもしれない。東日本大震災のあとで震災を書くということは、作家としては非常に力が入ることだと思いますし、事実野心的な作品なのだと思います。ただ申し訳ないですが、やっぱり物足りなさを感じてしまいました。まずそれぞれの人物について、設定以上のことが立ち上がってこないんです。余計なことが書かれていないためか、人物像にふくらみがない。またトラウマを抱えている人が多すぎて、人名を覚えるのにもちょっと苦労しました。ざっくりまとめてしまえば、引きこもりである主人公の一弥が、震災を経験して、さまざまな人に出会い、徐々に他人に対して心を開いていく過程を描いた小説となるのでしょうか。乱暴にまとめてしまえば「震災」が主人公の成長の糧にされてしまっている。きわめて個人的な問題が、震災という大きな世界の危機に直結しているという点では、これも「セカイ系」の物語の変奏といえるのかもしれません。草太という小さな男の子が、地鳴りに似た音をきいたのがきっかけで、さけびつづけて止められなくなってしまう場面など、印象的なところもありました。この草太のおじいさんで厚木という人物がでてきますが、後半、この人は持病で長くないので、地震が起きる前は、孫を殺そうと決意していたということがわかります。非常にたいへんなことというか、この人物一人の物語だけでも、きちんと書けば一冊分の長さになるのじゃないかと思いますが、この本ではあっさりと流れていってしまいます。そういうふうに、いろいろな興味深い素材は入っているのですが、未消化であるという印象が否めません。取材もされたでしょうし、作家として大きなテーマに向き合って書かれたのだと思いますが……。千代田区の図書館では児童書棚ではなく、大人の本棚に分類されておかれていました。
アカシア:みなさんがおっしゃるような欠点もありますが、私はおもしろかった。近未来にしたのは、東京を舞台にしたかったからだと思います。被災地、とくに福島の方たちと話すと、たくさんマイナスを背負わされっぱなしで、それが悔しいとおっしゃる方もいます。なんとかこれを自分たちにとってプラスの体験にできないかと。この作品は、マイナスをプラスに変えていく部分を書いています。被災地を舞台にした柏葉幸子さんの『岬のマヨイガ』(講談社)が野間賞を受賞しましたけど、あれは被災地の人たちが読んだら気持ちの整理ができそう。こっちはそういうものではなくて、距離のあるところから書いている。他者も自分も信じられなくなっていた一弥が、否応なく人と生のつき合いをせざるをえなくなる。その過程で自分だけでなくほかの人も困難を抱えていることを知り、後ろ向きで死の方を向いていたり、人とつながれなくなっていたりするその人たちが、なんとか生きる方を向いていくのを見て、自分も生きるほうを向いていく。そこは、上手く書けていると思います。登場人物のだれがだれだかわからなくなったという声もありましたが、年齢も特徴も違うので、私は見分けがつきました。
レジーナ:近未来の東京を舞台にしたのはなぜでしょうか。意欲作だとは思いますが、東日本大震災を背景にしているのに、正面からぶつかっていない印象を受けました。東日本大震災の写真も使われていますが、生々しくならないようにしたかったのか、ほとんどの写真は見開きではなく、ページの端だけに使われています。主人公は母親を置いて逃げますが、ほかにもいろんな人が出てきて、それぞれ苦しんでいるので、全部を描くには無理があるように思いました。主人公の葛藤だけでも、非常に大きなテーマなので。
アカシア:大震災なので、重たいものを抱えてしまっている人が多いのは当然かと思います。生死を目の前にしたとき、それまでは見ないですませていた重たいものが大きく立ち現れてくるのでは? 近未来の東京にしたのは、東京の人たちの多くがもう福島を忘れているので、それなりに意味があると私は思います。それから写真は、近未来の東京が舞台だけど、東北大震災ともつながっているんだよ、ということで敢えて使っているんだと思います。
げた:不登校になった中2の野島一弥が、大地震の後の津波による大災害の避難生活のサバイバルな状況の中で、生きる方向性を見つけ出し、改めて歩き出す物語ですね。一弥の周りには震災前に既に生きる死ぬを考えていた人たちが集まってきてるんだけど、きっと作者が取材する中で、そういう人が多くいたんだろうと思う。でも、一弥が生きる力を持てたことで、ある意味、ハッピーエンドになってよかったよね。自分も被災地に10日間派遣された経験があるんだけど、毎朝の自衛隊員を含む災対本部会議の緊張した雰囲気は今でも思い出すとドキドキしますね。あの頃は余震も頻繁にあったしね。確かに、迷彩服でなくてもいいかも。この話は近未来20年後の東京湾周辺が舞台なんだけど、東京オリンピック前に地震来ないとも限らない、オリンピックが中止にならないとも限らないよね。来ないことを祈るばかりです。
ネズミ:パーッと読めて意欲的な作品だなと思ったけれど、ひっかかるところもいろいろとありました。1つは、心に何か傷を負った人ばかりがここに集まっていること。極限状態だからそれが噴きだしてくるとも考えられるけれど、人物があってその人が抱えた過去というよりも、過去を語るための人物として、みな一弥を動かすために登場しているように、不自然な感じがしてしまって。また、こういうところで小さな子から元気をもらえるのはわかるけれど、草太君が主人公を動かす1つの道具のように思えて読後感がすっきりしませんでした。回想ではなく、起きていることを描写する形で現実を描くにしては、主人公の葛藤や不安があっさりしている気もしました。
すあま:いろいろと引っかかるところがありました。まず、東日本大震災から24年後の東京、という設定でしたが、未来であることも東京であることも読んでいて忘れてしまうくらい、伝わってこなかったです。東京で24年後に大地震が起きたらどうなるのか、についてのリアリティが感じられませんでした。それから、主人公に共感できませんでした。引きこもりだった子どもが、外の世界に出ざるをえない状況に置かれたらどうなるか、ということですが、あまり主人公を応援したい気持ちになりませんでした。そして、読み終わったときに感じたのは、津波の被害を受けた人たちは読めない本なのではないかということです。ただ、東日本大震災を知らない、実感がわかない人に人たちには疑似体験できるのかもしれません。作者もそこがねらいなのでしょうか。
ルパン:災害の話、として読みました。作者がほんとうに書きたかったのは、主人公の成長物語だったのだろうと察しますが、残念ながらそちらはあまり感情移入できませんでした。一弥にはあまり共感できないまま終わりました。それよりも、初めは3.11の話だと思って読み始めたのに、近未来の東京が舞台だということに驚きました。意欲作だとは思います。大災害が実際に来たらどうしよう、と、読み終わってからそのことばかり考えてしまいました。できれば、災害は舞台というか脇役というか、モチーフとしての役割にとどまり、主人公の葛藤と、悲しみの克服をメインに感じさせてくれるような、そういう力のある物語だったらよかったと思います。
アカザ(メール参加):まず最初に「健介叔父さん」問題。お母さんの弟なら「叔父さん」ですが、兄さんなら「伯父さん」のはずですね! これは、まずい! 東北大震災のあと、私もなにか書きたいという作家の気持ちは、良くわかります。なにを、どう書いたらいいか、作家なら、みな考えたと思います。木内昇さんの『光炎の人』(角川書店)を読みましたが、木内さんは原発の事故のあと、科学者の良心について懸命に考えたそうです。ベストセラーになったとは聞きませんが、電気学について、明治から満州事変に至るまでの時代背景について入念に調べた、じつに読みごたえのある作品でした。『アポリア』の作者は、「ひきこもりの少年が、大震災のときに触れあった人たちとによって、生きる希望を取りもどした」ということを書きたかったのでしょうか。それとも、さまざまな登場人物のそれまでの人生を書くことによって「それでも生きていく」ことの大切さを書こうと思い立ったのでしょうか? 戦争や原発事故などの人災とはちがう、誰のせいでもない大惨事や、難病、障碍などを感動に結びつける物語って、あまり好きじゃないんですよね。それなら、ノンフィクションのほうが、ずっと胸に迫るものがあると思います。福島から避難していじめを受けた子どもの手記の「しんさいでたくさん死んだから、ぼくは生きていきます」という一行のほうが、この本一冊よりずっと重い。小説なら、もっと思索を深めて、物語を熟成させてほしいと思いました。それから、近未来に、東京に起きる震災という設定ですが、東京に起きることの特異性や、原発のことが書かれてないのはどうしてでしょう? おとといの地震のときも、みんなの頭をまずよぎったのは、福島の原発はどうなっているかということだったはずなのに。エーデルワイス(メール参加):読み終わって次の朝、強い地震がありまさかの津波も。東日本大震災を思い起こしました。2011年4月上旬、気仙沼のお寺の一角に設けられたSVA(シャンティ国際ボランティア会)の事務所に一泊したことを思い出しました。雪がまだ時折舞い、プレハブ住宅がそれは寒くて、布団にくるまっていてもなかなか眠ることができませんでした。仮設トイレは外の少し離れたところにあるので、行くのがおっくうでした。震災直後、濡れながら一夜を明かした方々はどんなに寒かったろうと思います。
『アポリア』の中の場面もリアル感が出ています。ただ食料のことは出て来ましたが、トイレのことには触れていません。敢えて避けたのでしょうか? 震災という中での生死を扱いながら、個人の抱える悩み、悔い、悲しみを描いて、それを乗り越えようとしている人びとや、主人公の一弥の心境がよく伝わってきます。どうして不登校、引きこもりになったかを母親や健介に説明できないのか、と思うのは大人ばかり。説明できないのが思春期。黙って見守ることの難しさを感じます。一弥が、自分を助けてくれた片桐を怨み、母親を助けられなかった自分に対して罪悪感と絶望感を抱いているところは、震災後生き残った多くの方の気持ちを代弁していると思いました。自分でも被災しているのにも関わらずボランティアをしている人をたくさん見ました。それで自分も元気になっていったのですね。再生を感じますが、5年たっていても被災地の方はまだ読めないだろうなと思いました。
(2016年11月の言いたい放題)
最後のゲーム

原題:DOLL BONES by Holly Black, 2013
ホリー・ブラック/著 千葉茂樹/訳
ほるぷ出版
2016.06
版元語録:「この人形の粘土には人間の骨が使われてるの」誰も触ってはいけないはずの人形に触れたことをきっかけに、3人の冒険が始まる。
ネズミ:こういうの私、苦手で。すみません。エンタメが悪いというわけじゃないけれど、人形の謎を追う不思議な物語ありきで、登場人物も出てくるものもすべて面白いストーリーのための小道具のようで楽しめませんでした。それと、最後に3人が図書館から電話をするところで、どの親も怒らないのに納得がいきませんでした。
げた:選書当番だったんですけど、表紙とタイトルで選びました。1回読んで、軽いけどミステリアスな部分もあるし、子どもから大人への成長物語でもあるし、おもしろいと思って、みんなで読もうと思いました。人形遊びに夢中だった、幼馴染3人が大人になることで、それを止めさせられる状況になった。不思議な夢を見たポピーがきっかけで、「最後のゲーム」となるイースト・リバプールのクイーン=エレノアの墓を探し、骨を埋めるという冒険をすることになり、結局、やり遂げたってことになるわけですね。その冒険の過程でアリスの秘密やなぜ、ザックがゲームを止めざるを得なかったのかが、3人の中で明らかになって、新たな3人の関係が始まる。また、ザックと父親との関係も新たな段階が始まる予感がします。でも、クイーン=エレノアのお墓探しが最初感じたほどは、再読後はおもしろくなかったかな。バスステーションで、必ずしも逃げる必要がなかったのに、逃げたりして、歯がゆい感じがしました。まだ子どもってことなのかな、とも思います。
レジーナ:昨年から気になっていた作品だったので期待して読みましたが、一連の不可解な出来事は人形のせいだったのか、はっきりと明かされない終わり方で納得できませんでした。
アカシア:千葉さん訳の本は、いつもすぐに引き込まれるのですが、この本は入り込めませんでした。生まれるべくして生まれてきた物語というより、苦労して作り上げた物語だからなのかな。ザックのお父さんがフィギュアを捨ててしまったことを、ザックはポピーとアリスに言えない。その言えないという点がずっと最後の方まで引っ張っていくキーなんだけど、なぜそこまで言えないのか、よくわからない。その理由が納得できるようなかたちで出ていないので、不自然に思ってしまう。ほかにも、自然に入り込める流れじゃないなと思ったところがありました。私はホラーでも、もっとひそかに怖いようなのが好きなので、この本みたいに、表紙から「どうだ、不気味だろう」みたいに迫って来るのは苦手です。
くまざさ:千葉さん、こういうのもお訳しになるんだと。『スタンド・バイ・ミー』(スティーヴン・キング著、山田順子訳、新潮文庫)みたいな子どもたちの家出とその顛末。自分の好きなこと(この本の場合は人形遊び)と、世間一般の価値観が対立した場合に、迷わず自分の好きなほうを選べっていうのは、千葉さんが選ぶ作品らしいなと思いましたが、いっぽうでホラーはあまり千葉さんっぽくないですよね。じつはとくに前半なんですが、日本語の文章をもうちょっとすっきりテンポよくできないか……ということにばかり引っかかってしまって、なかなか入り込むことができませんでした。12歳の男の子と女の子2人が主人公で、男の子は、自分もいい加減大きいのに、女の子たちと人形遊びをしていていいのか、と悩むわけですが、こういう感じの悩みって個人的にはもっと早く来たようにも思います。お父さんと電話するシーンはよかったと思いますね。最近、年のせいか、児童文学を読んでいても、子どもたちのことより、登場人物の大人のふるまいに心惹かれることが多いんです。自分が悪いと思ったことは受け入れてきちんと謝罪する、そういう大人になりたいものだと思います。
アンヌ:ダーク・ファンタジーは大好きなのですが、この作品にはそういうおもしろさが感じられませんでした。最初の人形遊びの場面にもあまり引き込まれなかったし、実際の冒険が始まってからもリアリティがなくて楽しめませんでした。ヨットを盗んで川を渡るところなど、かなりいい加減な感じです。図書館からの電話で、家出によって大人の状況が変わるという所も、ポピーについては書いていない。3人の主人公も、アリス以外はあまり描き切れていない気がします。現実との対比で際立つはずのファンタジー要素も妙に曖昧で、謎が深まったり謎が解けたりする醍醐味がありませんでした。この旅のきっかけとか、エレノアがなぜ図書館の地下にいたのかとか、すっきりしないことが多かったと思います。
すあま:表紙の絵が怖いので読まずにいた本でした。全体的に中途半端な印象です。ファンタジーならファンタジーで、人形がしゃべるとか、もう少し工夫がほしかったと思いました。最初のところで登場人物の子どもたちの関係とその空想世界がどうなっているのかを理解するのに苦労しました。最後も尻切れとんぼでよくわからないまま終わってしまいました。
マリンゴ:とてもおもしろかったです。もっとも、読み始めの冒頭の部分では、人間と人形が同時に多数出てきたので、把握できるか不安になりました。整理して覚えるのに何度も読み返したりして。で、人間が人形の世界に連れて行かれるハイファンタジーかと思ったら、そのまま人間の現実のなかで話が進むローファンタジーだったので、その意外性もあってストーリーに引き込まれ、楽しめました。ラスト、結局どうだったのか曖昧なまま終わることへの批判が先ほどありましたが、私は敢えて曖昧にしている部分も好きでした。お父さんの気持ちがジャックに伝わるシーンもいいなと思いました。
西山:今、聞きながら、私だけじゃなかったんだと安心しました。私は、この表紙とタイトルでおもしろそうだから、通勤の往復で読めると思ってたんですが、出だしでつまずいた。誰がなにやら、となっちゃっていきなり失速して結局読み終わりませんでした。家出したところあたりで、雰囲気として『スタンド・バイ・ミー』を連想したりしました。
ルパン:ひとことでいえば、「気持ち悪かった」です。表紙の不気味さもさることながら、人形に子どもの遺骨を入れるとか、死んだ子供の個人的な思いだけが生きている子どもを動かしているとか…読む前に、この作品に期待した一番の理由は、「翻訳者が千葉茂樹であること」だったのですが…。今までは、「千葉さんが訳すものにまちがいはない」という信念があったのですが、やっぱり間違えることもあるんですね。
アカザ(メール参加):ホラーは大好きなので、期待して読みました。今まで千葉さんが訳したものとは雰囲気が違うという興味も。ハラハラしながら読みすすんでいきましたが、おもしろかったです。冒険の道すじが怖いですね。難をいえば、エレノアの真実が、ポピーやザックの夢にあらわれるというのは、ちょっとどうでしょう? 夢は夢でもいいのですが、真実は3人が調べていって分かってくるというほうが、すっきりすると思うのですが。ホラー、あるいはミステリーと成長物語をからませるという狙いはいいと思うのですが、ホラーなのかミステリーなのか、はっきりしてほしい。それから、アリスとポピーの生活環境のちがいは分かるのですが、性格のちがいが、いまひとつはっきりしませんでした。
(2016年11月の言いたい放題)
ペーパーボーイ

原題:PAPERBOY by Vince Vawter, 2013
ヴィンス・ヴォーター/著 原田勝/訳
岩波書店
2016.07
版元語録:1959年、メンフィス。ぼくは夏休みのあいだ、友達のラットに代わって新聞配達を引き受けることになった。すぐにどもってしまうせいで人と話すのは緊張する。でも大人の世界へ一歩踏み出したその夏は、思いもよらない個性的な人たちとの出会いと、そして事件が待っていた。2014年度ニューベリー賞オナーブック。
ルパン:ものすごくよかったです。ゆうべ、「明日読書会だから急いで読まなきゃ」と思って開いたのですが、1ページ目からもう時間を忘れ、何もかも忘れて、最後まで読みふけりました。唯一、「四つのことば」が今ひとつ明快にわからなかったことだけが残念ですが。student, servant, seekerはなんとなくわかるのですが、“seller”には、どんな哲学的な意味が隠されているのでしょう。でも、その謎もまた余韻として心に残ります。ところで、あとがきを読むと、これは自伝的小説なのですね。途中まで、昔の話だと気づかずに読んでいました。黒人がバスの座席などで差別されているという描写で、初めて現代が舞台でないことに気が付きました。でも、こういう時代って、それほど遠い過去の話ではないんですね。だってそれを経験した人がまだたくさん生きているのですから。この物語は、すべての登場人物が実に活き活きと描かれているところが一番よかったです。まるで今、そこにいるかのように、それぞれの姿が目に浮かんできます。
西山:気持ちよく、ストレスなく読みました。いつの時代か、意識せずに読んでいて、いま言われたように、私もバスのシーンで、あれ?となって裏表紙を見て1959年と気づきました。148ページの、大人になりたい理由など、とてもおもしろく読みました。吃音という困難を抱えているからこその部分と、その特殊性を超えた、普遍的な思春期の考え方や感じ方が分裂していなくていいなと思いました。言葉そのものが中心で、英単語自体のちょっとずらした言葉遊びや、お母さんの言い間違えなど、日本語に移し替えるのはものすごく大変なことだと思うんですけど、説明が挿入されるという感じではなくて、自然に読めたので、これは、すごいと思いました。
マリンゴ:岩波書店のスタンプブックスシリーズ、大好きです。なので、今回もとても楽しく読みました。装丁もとても素敵ですね。実は、私も数カ月新聞配達をしていた経験があるので、この本の新聞配達のシーンを読んで、いろいろと思いだすことがありました。たとえば、夕刊を毎日、門の外で立って待っている人がいたなぁ、とか。そういう触れ合いがあったので、この少年が配達を通してさまざまな人と出会っていく展開はリアルだと思いました。そして、何よりも文章がすばらしい。全文を通して読点が1つもないんですよね! それでいてまったく読みづらさを感じさせない、翻訳の技がすごいと思いました。
アンヌ:読点がなかったのですね。今の今まで気づきませんでした。「人が刺されたあの事件のこと……」と始まるのに、読んでいる最中は主人公の吃音の悩みに夢中になっていて、そういう事件に向かっていることも忘れていました。スピロさんに名前を聞かれて気絶する場面では、主人公の痛みを体中で感じました。2人が詩を一緒に朗読するところは、言葉を声に出す喜びと吃音の不可思議さを同時に感じられ、本当に素晴らしい場面だと思いました。マームが動物園で写真も撮ってもらえないということに、差別が様々な形で人を支配していたことを知らされました。スピロさんの変わった話し方とか、文章全体の不思議な一本調子とか、この翻訳者にしては変だなと思い、原文を読んだ人に教えてもらおうと思って今日来たのですが、読点なしだったとは……。すごい翻訳だと思います。うまい小説という書き方ではないけれど、本当に心に残る物語だと思います。表紙のポーチのベンチ型ブランコの絵もとても魅力的で、物語のイメージがうまく伝わっていると思います。続編があるなら読んでみたいと思っています。
アカシア:本の構造自体は『アポリア』と同じで、周りとのつき合いに困難を感じている少年が、否応なく周りの人と知り合うことになり、そこから成長していくという作品です。でも、こっちの方が、主人公に寄り添って一緒に成長していくような気持ちで読めますね。まだヴィクターは吃音を持っているので、しゃべるときには必要以上に息継ぎをしてしまうことから、文章を書くときは息継ぎなしで書きたい。だから原文もカンマなしなのですが、それを日本語でも、読点なしでいてちゃんと流れる文章にしている翻訳者の原田さんの腕がすばらしい。また脇スジとして、ヴィクターが父親とは血がつながっていないとわかる場面があるのですが、そこもとてもうまく書かれていて破綻がない。周囲にいる人たちがまた個性派ぞろいで、しかも味がある。うまい作家だし、うまい翻訳者。何度も読みたい作品に仕上がっています。
レジーナ:主人公はテレビ少年との出会いで、人は見かけより複雑で、いろんなものを抱えていると気づきます。主人公もマームもスピロさんも、1人1人が生き生きしていて魅力的です。誤解されたり、想いをうまく言葉にできなかったり、人と心を通わすことの難しさは、だれもが日々感じていることです。吃音の少年が主人公ですが、多くの人に届く普遍的な成長物語だと思いました。
げた:吃音の大変さを改めて、知りました。皆さんが言うように、スピロさんは知的で、カッコいいですよね。子どもの人格を認めて、1人の人間として接する。自分も常にそうありたいと思ってます。ワージントンの奥さんについては、主人公の少年が彼女を大人の女性として憧れる気持ちがなんとなくわかるような気がします。マームは母親以上の存在ですよね。マームの存在に比べて、父母の存在が薄いのが気になりました。R・Tとの戦いの場面は手に汗握る感じで、とっても、おもしろく読めました。本の装丁もかっこいいですね。
ネズミ:ほんとうにおもしろかったです。日本人の書いた作品と、外国の作品の違いというのも考えさせられました。吃音のことなど、日本のリアルな環境で描くのはかえって難しくて、現実との違いが気になってしまうのではと思うのですが、外国だとこういうものかと、かえってすっとその世界を受けとめて読める気がします。そして視野を広げることもできる。海外文学のよさですね。作品のおもしろさについては、みなさんのおっしゃるとおりですが、特に私の心に残ったのは「言葉」と表現をめぐるくだりです。言葉を出したからと言って、それですべてを表現できるわけじゃないというのが、書かれていますよね。80ページでは、自分が言おうとしたときに、思うように相手が受け止めないもどかしさや、人が発した言葉が、文字通りの意味だとは限らないことが書かれています。また246ページでは、マームが「パチリと大きな音をたててハンドバッグの口をしめた」のが「すべて終わってけりがついたことを宣言したみたい」というふうに、行動から読み取られる意味を語っています。お母さんの言い間違いは、それでお母さんの性格を露呈したり。いろいろなことを考えさせられました。
アカザ(メール参加)今日みんなで読んだ3冊のなかで一番良かったばかりでなく、最近読んだなかでも最高でした。原田さんの訳も本当に好きな作品を訳しているという感じが、ひしひしと伝わってくる見事なものでした。子どもの友だちに吃音の男の子がいましたが、これほどの苦しみを抱えているとは気づきませんでした。吃音を克服した作家ならではの悩みが細やかに描かれていて、興味深かった。医学的に吃音を治療するのではなく、人と人とのつながりで克服し、成長していく有様が描かれていて感動しました。程度にかかわらず障碍に悩む人たちにとって、心強いエールを送っている作品だと思います。どの登場人物もしっかり描かれていて、それだけでも素晴らしい。マームが素晴らしいですね。黒人が市民権を得る前の社会で誇りたかく、しかも賢く生きている姿が、とても美しいと思いました。
エーデルワイス(メール参加):IBBY主催「バリアフリー絵本展」(盛岡巡回展)の中に展示されていた1冊で、興味を持ちました。筆者の自伝的物語というのは納得。吃音症の少年の言葉を発音する心理がよく伝わってきました。黒人のメイド、マームとのやりとりやマームがヴィクターと呼ぶところが好きです。深い愛情が伝わってきます。R.T.とのやりとりはらはらしました。解決してよかった! スピロさんとのやりとりはまるで禅問答ようです。含蓄がある言葉の数々ですね。心に残った言葉がたくさんあります。1959年のアメリカの南部の様子、特に映画に出てくるようないかにも南部のアメリカの家の様子が分かります。まだ人種差別が色濃い中、ヴィクターの家は裕福で両親も人格者のようです。出生証明書の欄に「父親不明」と書いてあった件については解決されていないので、続編に明かされるのでしょうか。このことも筆者の事実なのかと気になります。
(2016年11月の言いたい放題)