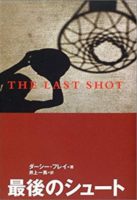
原題:THE LAST SHOT by Darcy Frey 1994
ダーシー・フレイ/著 井上一馬/訳
福音館書店
2004.06
オビ語録:1991年ニューヨーク、コニー・アイランド。バスケットボールに賭けた四人の若者の暑い夏。……その後、四人の運命は大きくわかれた。ある者は栄光の舞台へ、ある者は悲劇的な結末へ。感動のノンフィクション。
アカシア:語り手の「私」は、p26に「私は、チームに密着する地元の記者として」と出てはくるんですが、どういう立場でどうかかわろうとしているのか、後の方になるまでうまくつかめなくて、読んでいてとまどいました。それにノンフィクションなのかフィクションなのかもわからない(帯にはノンフィクションとありますが、図書館で借りたので)。雑誌に連載されていたせいか、コーチのこと、プレーヤーの争奪戦、親の期待、本人の焦り等々、流れが整理されていなくて、同じ問題が繰り返し出てくる。それに、それぞれのキャラの違いがそうそうくっきりしていなくて、イメージしにくかったですね。単行本にするときには、章ごとに一人一人とりあげるなどしたら、もっとわかりやすかったのでは? 読んで得したな、と思ったのは、コニーアイランドが遊園地だけじゃないこととか、NBAビジネスの内幕とかがわかったこと。
翻訳については、原文の文体はわからないけれども、下町の10代の少年たちの会話を、ずいぶん古典的に訳しているなあ、と思いました。たとえば6ページの just do it を「不言実行」と訳したり、ナイキのコマーシャルの口調「若者よ、一生懸命働き、一生懸命練習して、ご褒美にナイキの靴を買おう」も古典的。ひっかかったところもいくつかありました。たとえばp150に「俺は我慢して奴らの望むところへパスを出してやるのに、頭で受けやがるんだ。あいつら塊だよ、パンの塊だ」ってありますけど、パンの塊なんて日本語の会話で聞いたことないから、えっ?って思った。p151の「ずっとこれだよな?」も、どういうニュアンスなのか、よくつかめない。p268には「印象をよくするためにちょっとめかし込んで行ったほうがいいと思ってるんだ」と言ったあと「たぶんスニーカーがいだろうな」とあるんですけど、「めかし込む」と「スニーカー」が普通はつながらないから、ここも、えっ?と思ってしまう。p343ではステッフォンが「うんにゃ」と言ってますけど、そこまでの口調と違う。それと、「彼」という人称代名詞がやたらと出てくるのも気になりました。
訳者あとがきには、「これはバスケットボールについての本であると同時に、アメリカン・ドリームについての本でもある」とありますけど、本文p348には「奨学金の獲得を目指す一連の過程は、〜アメリカン・ドリームの黒人版ではなく、その残酷なパロディになってしまっている」とあって、もう少しこの2つの言い方の間の隙間を埋めておかないと読者に対して不親切です。この著者の言いたいことは、最後の最後の方に出てきて、それはおもしろいし、その後の主人公たちの生き方と照らし合わせてみるとなおさらおもしろいのですが、そこまでたどり着くのが一苦労。NBAで活躍しているステッフォン・マーベリーを知っている人なら、その周囲のことがよくわかるから、どんどん読めるでしょうが、中高生一般にお薦めできるような本だとは思いませんでした。
むう:訳については、アカシアさんのおっしゃるとおりだと思います。わたしも、あれ?と思う箇所がけっこうありました。読んでみて、これは子どもの本ではなく、大人向けのノンフィクションだと思ったし、そもそも井上さんがボブ・グリーンの訳をしているというのが頭にあったので、最初からノンフィクションのつもりで読んでいました。子どもの本という枠をはずして読んだので、さまざまなことを時系列で並べていくなかで、アメリカの社会のある一面が浮かび上がってくるのがとても、おもしろかったです。ある登場人物に沿って読み進んでいく物語というよりは、さまざまな事実を積み重ねていって全体像をあぶり出すタイプの本だと思いました。プロバスケットボールの選手を青田刈りする人々が殺到する有望高校生を集めたナイキ主催の全国大会が、黒人ばかりの選手を白人のコーチや監督が品定めして、あたかも牛の品評会のようだという形容があったりするのも、きついけれど、なるほどと思いました。ローマの拳闘士にも通じるようなプロスポーツの見せ物としての性格や、そこにしか活路を見いださざるをえず、その夢にすら手が届かずに終わってしまう貧困層の子どもたちといったアメリカの実情がかいま見えて、その意味でとてもおもしろかった。ただ、子どもを描いた本と子どもに向けた本は違っていて、これは子供に向けた本ではないように思った。訳文からも、それを感じました。どうしてこの本が福音館から出ているの?という感じですね。向こうでは子ども向けに出ているんでしょうか。
祐:大人の本、子どもの本という区分けにかかわらず、この作品は名作とは言いがたいですね。アメリカなら、このような本は掃いて捨てるほどあるんです。ナラティブの失敗でしょうか。作者が何を目的として書いているのか、意図がわからない。伝記ならば、このような設定で書くには無理がある。青春物語だとするなら、ひとりひとりの登場人物にリアリティが感じられない。おそらく、語り手の視点の問題でしょう。社会的な問題意識を描くなら、もっと主張やメッセージを明確にすべきですね。「私」の位置の不確かさが問題です。語り手になったり、登場人物になったり、255ページあたりでは解説者になっている。一貫性がないんですね。
ポロン:私は、すっごくおもしろく読みました。オドロキに満ちた物語! 3つの大きなオドロキがありました。1つめは、知らなかったスゴイ世界を知ったオドロキ。いやはや、たいへんな世界です。そんななかで、ここまでがんばる高校生がすがすがしい。4人の子は、みんなタイプがちがうし、私はそんなにこんがらがらなかったな。それぞれの登場人物を応援したくなった。
2つめのオドロキは、この作品がノンフィクションだった、ということ。これは衝撃的でした。26ページの最後の行に、「私はチームに密着する記者として、これからその一部始終を見届けることになるのである」とあるので、てっきり地方紙の記者かなにかなんだと思ってたら、新聞社で働いてるようすとか、自分で書いた記事とかでてこないし、ヘンだなーと思いながら読んでいたんです。学校にも自由に出入りしてるみたいだし、みんなの家のことも知ってるし……。「私」は、どこへでも行けて、自分がその場にいなかったときのこともわかっちゃう「神の目をもつナレーター」で、こういう設定って、フィクションっぽい。それで、フィクションだと思い込んでいたのに、エピローグの最後に「この作品はノンフィクションだが、ラッセル・トーマスと母親の名前は変えてある」という一文を発見して、もーびっくりしました。結局、「私」というのは、フリーライターで、1冊の本(つまりこの本)を書くという契約をした。このリンカーン高校バスケ部について書くための専属ライターだったということでよいのかしら。
3つめのオドロキは、この本が図書館のスポーツの分類の中のバスケットのコーナーにあったこと。こういう本を好きな人も、このコーナーにあるとは思ってないかも。と思う反面、バスケの練習法がのってる本を見たくてきた、普段ぜんぜん本を読まないような子が偶然手にとって、「いいじゃん、この本」っていうような出会いが生まれたりするのもよいなあと思いました。この本、別の図書館では、YAのコーナーにあったのですが……。
あと、文章についてなんですが、全体に一文が長くて、ときどきわかりづらかった。たとえば23ページ「リンカーン高校のチームの選手名簿は……」というところなど、まちがってはいない、正しい、正しいんだけど、入り組んだ文章で、すっと読めなかった。それから日本語では、この単語はちょっと……と思ったところがいくつかありました。たとえば、14ページの1行目、ステッフォンの髪型について「はやりのレザーカット」と出てきますが、次の行では「小さなつるつるの頭」とのことなので、たぶんスキンヘッドなんだと思うのです。だから「かみそりを使った髪型」ということだと推測するのですが、日本語で「レザーカット」といったら、別のもの。ちょっと前にカリスマ美容師という人たちが得意としていたような、長さのある髪にシャギーをいれたようなものを指しますよね。ほかにも、14ページ4行目の「キャンディ・バー」は、日本語ではたぶん「チョコレート・バー」。26ページ9行目や31ページ4行目に出てくる「ハイトップ・デザインのスポーツシューズ」は「ハイカット」のことかなと思いました。
すあま:私が借りた図書館でも、バスケットボールの分類の棚にありました。最初フィクションだと思っていたので、「私」がだれなのかが、わからなかった。装丁の感じは早川書房の本のようですね。大人で、ある程度読みなれた人じゃないとこの本は難しいと思う。作者の興味は、バスケットではなく、バスケット界の影の部分にあるわけだから、『スラムダンク』を好きな子がこれを読むとは思えない。
ケロ:全体を通して、突き放したような覚めた感じを、おもしろいな、と思って読みました。バスケットボールの専門用語や、アメリカの黒人の多く住む地区独特の空気など、わからないところを飛ばし読みしましたが。ただ、他の方も言っているように、最後の一文を読んで、初めてノンフィクションだということが分かりました。このような本の場合、ノンフィクションだということを、きちんと最初に言ってくれないといけないのでは?と思いました。これは、編集という視点での事なのかもしれませんが。それとともに、ちょっと章立てがよくわからなかったです。プロローグ、夏、一流大学による選抜、エピローグなんですけど、なんでここなのかな?という感じ。内容については、山場がなく、それぞれの学生のことが、流れでとらえられない。訳については、ボブ・グリーンの訳者だし、以前に読んだ物にもあったアメリカンコラムニストの匂いがあり、同じ世界だな、と思って読んだので、あまり違和感はありませんでした。
ハマグリ:折りを見て少しずつ読もうとしたら、前に読んだところが頭に入ってなくて、また最初から読むということを繰り返しました。わかりづらいところが多いですね。やはり、「私」が一体だれなのか、なかなかわからなかった。本分の終わりに「この作品はノンフィクションだが、ラッセル・トーマスと母親の名前は変えてある。」と書いてあるけど、これを前に持ってきたほうが、最初からはっきりノンフィクションとわかって読めてよかったのに。長年バスケットをやっている息子(20代)に読ませたら、ぱっと読んで、おもしろいと言ってました。バスケをやっている人なら、練習風景にしても、試合の詳細についても、もっと想像力が働いて、楽しめるのではないでしょうか? NBAの試合をよく見ていれば、選手の生い立ちや裏話にも関心があるので、この本はそのあたりの本当のことが書かれているということで、興味深く読めるのだと思います。バスケをやっている子ならだれでも読んでいるのはコミックの『スラムダンク』。あのときのあのセリフ、あの試合のあのシュート、というのが共通の話題になっています。本でも、そういう存在になれるものが出ればいいのに、この本はYAじゃないと読めないですよね。それから、エピローグで後日談があって、謝辞があり、訳者あとがきで後日談の後日談があるのは、ちょっとしつこい感じがした。エピローグだけで終わったほうが余韻があってよかったのではないかと思います。
カーコ:実はこの本は書評で見て、バスケットをしている息子が昨年高校に受かったときプレゼントしたのですが、読んだ形跡がありません。今回自分で読んで、バスケットやNBAがいくら好きでも、本を読みなれていない中学生には難しそうだ、と思いました。その理由の一つは、固有名詞やアメリカの生活を知らないとわからない言葉が非常に多いこと。もう一つは、この4人の高校生の描き方。彼らの内面をえぐりだすというよりも、外から見て書いている感じ。試合のシーンなども、この子たちに感情移入して読めませんでした。『スラムダンク』を読んでいる子を、それと一味違ったおもしろさでひきつけるところまで行かないのでは? みなさんの指摘している訳文の文体は、私はわざとこういうふうに訳したのか、と思いました。
げた:図書館員としては、福音館書店の本であれば、いい本だろう、と思ってしまうんですよ。あとがきには、古典とあるし。読んでみて、みなさんと同じような感想を持ちました。バスケットボールの本というよりも、ニューヨークの公営住宅街に住む子どもたちが、どうやってはいあがっていくかという社会派の本なのかと。
(「子どもの本で言いたい放題」2006年2月の記録)