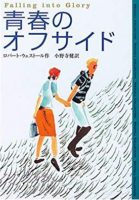
原題:FALLING INTO GLORY by Robert Westall 1993
ロバート・ウェストール/著 小野寺健/訳
徳間書店
2005.08
オビ語録:知らぬまにぼくたちは〈入ってはいけない場所〉に足を踏み入れていた…/巨匠ウェストールが描く、輝きと深い闇が交錯する十七歳の忘れがたい日々
アカシア:「エマ・ハリスをはじめて見たとき、ぼくは十歳だった。/戦争中だった」っていう書き出しがうまいですね。それに、ほかの2冊に比べて、この本は人間がちゃんと描けている。p44に「自分自身でさえ怖くなるようなさまざまな迷いを抱えたこの醜い野郎」と主人公の少年が自分のイメージを語るところがありますが、この年齢の男の子の心のあり方がよく出ています。主人公のロバート・アトキンソンとと先生のエマ・ハリスだけでなく、脇役のウィリアム・ウィルソン、ジョン・ボウズ、それにかわいそうなジョイス・アダムソンなどの描き方もうまい。こんな子いるだろうな、というリアリティがあります。文学を書きなれているウェストールのうまさなんでしょうね。スポーツ(ラグビー)を描いている部分も、先生やコーチを出し抜いて秩序をひっかきまわしてやろうという作戦があって、おもしろく読めます。訳でひっかかったのは一箇所だけで、p171の「仲間なんていうと、銀行強盗みたいだね」というところ。あとは、うまい。最近子どもの本で人間をちゃんと描き出しているものが少ないので、そういう意味でも、今日読んだ3冊の中ではこれがいちばんお薦めですね。
むう:とにかく、おもしろかったです。人間もよく描けているし、情景もすばらしい。主人公と先生とがローマン・ウォールに行くときのあたりの風景なんかも目に浮かぶようで、いいなあと思いました。思春期の男の子の、力が有り余っていたり、性のことをもてあましたりといったことがきちんと描けていて圧倒的。まわりの女性もちゃんと描けてはいるけれど、ちょっと男にとって都合のいい女性ばかりという気がしなくもなかった。でもそれは、おそらく主人公の目から見ているからなんでしょうね。ロアルド・ダールもそうだけれど、イギリスには男の子をきちんと書ける男の作家がいますね。とにかく、力のある作家だなあと思いました。
すあま:ウェストールの作品でこの本の前に読んだのが『禁じられた約束』(野沢香織訳 徳間書店)だったので、2冊が同じような印象で、私の頭の中ではセットになっています。大人になりかけ、でもやっぱり17歳、というところがちゃんと書いてありますね。最後は主人公が脅迫されていて、どう決着がつくのかと思っていましたが、納得のいく終わり方でした。読み手の年代によって、主人公の気持ちに添って読む人と、先生の気持ちに添って読む人がいるのではないでしょうか。
ポロン:おもしろくて好きです。青春の甘酸っぱいところと痛快なところが両方入っています。ラグビーにおけるがんばり方もイイ。ジョン・ボウズがとても好きで応援してました。エマが、最後は仕事に一生を捧げました、というのは、男性の願望なんでしょうか?
アカシア:そこは、男性の願望というより、エマが教師だったという部分が大きいと思ったけどな。
ケロ:のめりこんで、泣いて読みました。(「えー、泣いたのー」という声あり)。はい、だあーっと滝のように涙が出ました。何に泣いたのかというと、この切ない恋愛にですよ。こんな風な恋愛を描いて、子ども向け(ま、YAですが)というのは、日本ではないな、と思いました。主人公よりも、先生に感情移入してしまいました。自分の年のせいかな。ジョイスがかわいそうな子っていう意見があったけれど、私はそうは思いませんでした。むしろ、勝者ですよね。主人公に出会って、最初はろくに自分を表現できなかった子が、だんだん自分を確立し、輝いていく様子がえがかれていて。こういうところも、ジョイスときちんと対比されて描かれていて、すごいな、と思いました。
ハマグリ:私は先生の立場で読むというよりは、この主人公の気持ちになって読みました。最初の描き方が、とても読者をひきつける。デブ、デブと言われている子が、いじめた子をのしてしまい、体が大きいことを逆に武器にして、ラグビーで開花していく。頭がいいということにも気付いていく。この子の側から、最後まで読めました。一番好きだった場面は図書館にローマン・ウォールのことを調べにいくところ。司書が執務室にしまいこんでいる本を読ませてもらうくだり。「そこでコリンウッド・ブルースを開けたぼくは、ラグビーをはじめたときとおなじく、一気に栄光の世界へ突入したのだった。まるで、それまで知らなかった自分の家を見つけたような、それがもう何年も待ってくれていたような気持ちがした」(p27)。人類の偉大な財産に触れた喜びが伝わってきました。書き方も文学的で、「だがテニソン・テラスはちょうど未婚の叔母のように、自分の生活を固く守っていた。」(p89)というように、比喩を用いた修飾節が多く、言葉を尽くして書き込んでいます。女性では、エマよりもむしろ、ジョイスの書き方がうまいと思いました。ジョイスとつきあいながら、主人公がエマと天秤にかけて考えていくところがうまく書けています。ただ、この時代のイギリスという背景を味わえるかどうか。今の高校生が読んだとき、『ジェーン・エア』のロチェスターと『嵐が丘』のヒースクリフが引き合いに出されたり、シェイクスピアの『テンペスト』の脇役の名前が出てきてもわからないんじゃないかしら? 日本の読者にとっては限界があるのが残念です。
カーコ:私も『禁じられた約束』に続けて、印象をダブらせながら読みました。感心したのは、思春期の男の子の描き方。感情の機微や友達とのかけひきなど、このリアリティは男性作家にしか出せないのでは? また、読み終えたあとに、一人一人の人物がどういう人だったかくっきりと思い浮かべられます。これは人物がとてもよく書けているからでしょう。しかも、「子どもに書く」という姿勢が貫かれていて、どの人物に対しても目線があたたかい。日本でもこういう世界が書ける男性作家が出てくるといいですね。
げた:私も『禁じられた約束』と併せて読んでみました。。共感というよりは、気恥ずかしいような気持ちを持ちながら読んでいきました。主人公が優秀な子で、うらやましいな、というところも。ラグビーのラフプレーで、バッジをとられるのだけれど、文章の中ではラフプレーだということが読めなかった。原題は Falling into Glory ですが、日本語の書名とはかなり違いますよね?
アカシア:思春期ってつらいことがたくさんある時期だと思うんです。でもその中に、栄光の瞬間があるんですよ。さっきハマグリさんが挙げてくれたところにも『栄光の世界へ突入した」という表現がありましたけど、エマとの関係の中にも栄光があるんじゃないでしょうか?
げた:仮題のときは『栄光への堕落』となっていたのに、出版時には『青春のオフサイド』としたんですよね?
ポロン:オフサイドって、フライングみたいな意味ですか? ちょっと早かった。一瞬早く前に出てしまったということ?
アカシア:書名のオフサイドはいいと思ったんですけど、「青春の」は古くさいし、ダサい。私が中高生だったら「青春のナンタラ」という本なんて読みたくはないですね。おじさんやおばさんが懐古的に読む本かと思ってしまう。中高生に手に取ってほしい本なので、それが残念。
(「子どもの本で言いたい放題」2006年2月の記録)