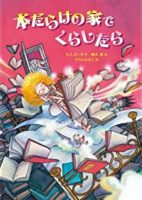
原題:THE ANYBODIES by N.E.Bode, 2004
N.E.ボード/著 柳井薫/訳 ひらいたかこ/挿絵
徳間書店
2009.12
版元語録:11歳の女の子ファーンは、ある日、自分が不思議な能力をもつ一族なのだと知らされる。そしてある特別な 本を見つけるため、父とともに素性を隠して祖母の家にのりこむことに。ところがその家は、本だらけで…? 本をふると、中から登場人物がとびだしてくる! ふしぎがいっぱい、本好きにはたまらないユニークなしかけがいっぱいの楽しい物語。
プルメリア:この本を手にするのは今回で2回目です。生まれたときから一緒に暮らしていたとってもまじめな家族が変わってしまい、おとなしかった男の子が元気になる展開がおもしろい。ときどき魔法が出てくるのも、おもしろさにつながってます。おばあちゃんに会いたい女の子が、自分の居場所を見つけるのがテーマの、成長文学なのかな。明るい挿絵がいい。最後に紹介されている作品にでてきたリストから、本を読みたくなるのではないでしょうか。
コーネリア:表紙も楽しそうだし、おもしろそうな気がするなと思って読み進めていたのですが、どうもお話の世界に入り込めなかった。このハチャメチャな感じ、荒唐無稽な感じについて行けないのかな……ファンタジーが苦手だったのか……。つかみ所のないお話でした。
ハマグリ:本を開くとコオロギが出てくるというように、冒頭から突拍子もない出来事が描かれているし、挿絵もファンキーだし、これは奇天烈な話だな、と覚悟して読んだので結構楽しめました。でも全体の雰囲気と違って、テーマはお母さんを探す、自分の居場所を見つけるという王道なんですね。中でも本だらけの家のおばあちゃんがおもしろくて、本好きかどうかのテストだといって、その本を読んでいないとわからない質問をする。本の中で本のおもしろさを伝えているのが楽しかったです。挿絵はアニメーションを見ているようなテンポの速いものだと感じました。
優李:かなりめちゃくちゃな設定と思って読み始めたので、わりと楽しく読めました。魔法の秘密の書や、自分の居場所探しなど、テーマが多すぎる感じがします。ただ、何度も出てくる「何ごともありのままではないのでは」の『ありのまま』にひっかかりました。この場合は「見た目」ということなのでしょうが、「ありのまま」と「見た目」は違うので、日本語としてはヘンです。最初、主人公の養親(?)の会計士夫婦が、あまりにも現実離れした無機質な書かれ方で、こんなので子どもはついてこれるのか?と心配になりましたが、子どもたちは意外に平気で気にしないようでした。それより「本のテスト」のところ、女子はなんとも言わなかったけれど、男子の中には「なんかいやだ」といった子が何人かいました。作者の言葉が作中何度も出てくるところは、ちょっとおせっかい過ぎの印象です。私は苦手です。
メリーさん:主人公が魔法を使えるようになるまでの前半はちょっとまどろっこしいのですが、後半、話が回り出してからおもしろくなりました。(「ここからが話が急展開します」というところあたりから)。なので、主人公にいろいろな目的はあれど、実際に魔法を使って何かするというところをもっと読みたかったなと思いました。そして、作者のコメント、ト書きのような部分ですが、先に種明かしをしてしまっているところが何か所かあって、もう少し効果的に使ったらいいのになと感じました。
チェーホフ:地の文は読みやすいのですが、途中で出てくる作者の言葉が嫌でした。物語の世界に入り込めても、作者の言葉に邪魔されて冷めてしまう。おもしろい雰囲気があるけど、最後まで読んでやっぱりつまらないかもと思ってしまいました。話が盛り上がるシーンが遅いのかもしれません。絵が可愛いなと思いました。
みっけ:とにかく、作者のセリフがうるさくて! どこかでちょっとだけ出てくるくらいならいいんだけれど、あれこれ物事を説明しすぎ。こんなふうに作者がしゃしゃり出てきてあれこれ説明するくらいだったら、地の文とか台詞とかに織り込むくらいの工夫をしろよ!と思いますね。それに、まるで物語とは関係のない、自分の大学時代の教授の話が出てくるでしょう? せっかくこっちが物語世界に浸れそう、と思ったところで、そのたびに腰を折られるものだから、ひどくイライラしました。魔法があってぶっ飛んでいる話はけっして嫌いではないけれど、この話は物語としてきっちり固まっていない感じで、おもしろそうなことがあれこれ寄せ集めてあるだけという印象。これだけいろいろなことが起こっているのに、勢いよく読み進めるという感じじゃなかったです。
あかざ:「とっちらかった本だな」というのが、まず第一に感じたことです。本当はおもしろい本なのに、自分の頭がとっちらかっているからそう思うのかと不安になりました。最初の部分の、退屈きわまる夫婦に育てられている子どもの様子を見に、魔法の世界の者たちが姿を変えてやってくるというところはハリポタとそっくりで、すでにこういう書き方がひとつのスタイルになっているのかと、ちょっとショックを受けました。語り手がときどき姿をあらわす手法は、児童劇などによくあるのでさほど気にならなかったけれど、ストーリーがとっちらかっているのを、これで立て直しているのかなと、ちょっと意地悪な見方もしてみたくなりました。とにかく、あれやこれや盛りこみすぎていて、はたしてクライマックスはどこなのかなと思いました。それから「ダレデニアン」は、誰にでもなれる術ってことですよね。それだったら、マイザーもある程度できているので、必死になって秘密の書を探さなくてもいいし、主人公たちも、世界がひっくりかえる一大事のように騒がなくてもいいのでは? 「ダレデニアン」と出てくるたびに、「なんでやねん!」と、思わずつぶやいていました。私も、この物語のキーワードのように出てくる「なにごともありのままでではないのでは……」という言葉には首をかしげました。「ありのまま」というと、「ありのままの自分でありたい」というように、いいイメージで使うのでは?これは、なにごとも見た目とは違うという意味なのでしょうか? また、訳者あとがきに、終わりの部分でドラジャー夫妻も別の顔を見せるとあったので、もう一度読みかえしましたが、結局サルになったというだけですよね?
サンザシ:あまり出来のよくない本だな、と思いました。リアルなキャラクターはひとりも出てこないわりに、筋書きがばかまじめなので、私は楽しめませんでした。はちゃめちゃなキャラならば、そういうふうに物語も進めばいいのに、そうではない。作者がたえず顔を出して何か言うのも、やたらうるさくて私は嫌でした。ハマグリさんは、本好きかどうかのテストが楽しいとおっしゃってましたが、単なる知識テストに過ぎないでしょ。知ってる子には優越感、知らない子には劣等感をあたえるだけなんじゃないかな。主人公が窮地に立ったときに、何かの本の中身を思い出して切り抜けていくという設定ならまだしもですが…。
(「子どもの本で言いたい放題」2011年1月の記録)