| 日付 | 2001年4月26日 |
| 参加者 | 愁童、ねむりねずみ、オカリナ、トチ、裕、ウェンディ、紙魚 |
| テーマ | 受賞作 |
読んだ本:

角野栄子/作 佐竹美保/画
福音館書店
2000.10
魔女のキキがコリコの町に住むようになって、4回目の春がめぐってきました。キキは16歳になりました。そのもとへケケという12歳の女の子が転がりこんできます。ケケは不思議な力をつかって、宅急便の仕事を横取りしたり、デートの邪魔をしたりして、キキをとまどわせます。自由奔放で小生意気なケケにふりまわされながらもキキは少しずつ変わっていきます。ふたりが反発しあいながらもお互いにとってたいせつなものをもとめて成長していく姿が描かれています。

原題:THE VIEW FROM SATURDAY by E.L. Konigsburg, 1996(アメリカ)
E.L.カニグズバーグ/作 小島希里/訳
岩波書店
2000-06
<版元語録>6年生のノア、ナディア、イーサン、ジュリアンは大の仲良し。複雑な家庭の事情を抱えている子どもたちの生活を描きながら、どうやって4人が親友になったか、その謎を語る。ニューベリー賞受賞作品。
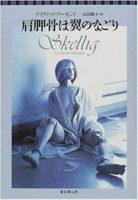
原題:SKELLIG by David Almond, 1998(イギリス)
デイヴィッド・アーモンド/作 山田順子/訳
東京創元社
2000.09
<版元語録>古びたガレージの茶箱のうしろの暗い陰に、僕は不可思議な生き物をみつけた。青蠅の死骸にまみれ、蜘蛛の巣だらけの彼は誰、…それとも、なに?夜明けの闇と光が繊細に溶けあう、どこにもない物語。カーネギー賞・ウィットブレッド賞受賞作。
魔女の宅急便その3〜キキともうひとりの魔女

角野栄子/作 佐竹美保/画
福音館書店
2000.10
魔女のキキがコリコの町に住むようになって、4回目の春がめぐってきました。キキは16歳になりました。そのもとへケケという12歳の女の子が転がりこんできます。ケケは不思議な力をつかって、宅急便の仕事を横取りしたり、デートの邪魔をしたりして、キキをとまどわせます。自由奔放で小生意気なケケにふりまわされながらもキキは少しずつ変わっていきます。ふたりが反発しあいながらもお互いにとってたいせつなものをもとめて成長していく姿が描かれています。
オカリナ:ケケという3歳年下のライバルが出現して、その子との軋轢が話の中心になっていると思うんだけど、それだけじゃなくて、エピソードを積み重ねていくのは、今までと同じ手法ね。表現はうまいし、落としどころもあるし、最後もうまくまとめているし、ところどころに泣かせる配置もしている。巧い作家だなと思いました。最近YAばかり読んでいたせいか、そんなに強烈な印象はなかったけど、それはそれでいいんでしょうね。もしかしたら、1巻目や2巻目と比べるとインパクトが少し弱いのかな。挿絵は、シリーズの3冊とも別の画家だけど、並べて比べなければ違和感はなくて、イメージは統一されてると思いました。いずれにしても、角野さんは、どの巻でも独自の世界を展開してますね。
ねむりねずみ:次回に読む本のお知らせをもらったとき、「挿絵に注目」とあったけれど、すみません、1巻目も2巻目も読んでません。 第1作の映画しか見ていないけど、映画のイメージとつながるものは感じました。なんとなく、懐かしい世界で、普通なんだけど、ちょっと魔法があるというゆとりが懐かしくて心地よいのかなって、そんな感じがしました。魔法自体は、すごい魔法とかファンタジー系の魔法じゃなくって日常的だけど、ちょっとだけ外れている程度。ほうきで飛べるくらいのことで、それを周りが「それもあり」と認めちゃうところが心地よいのかな。おもしろかったです。後に何か大きなメッセージが残るというものでないけど、魅力的だけど決して強いばかりではない人間が、つい人と競ってしまったり、そんな自分を何とかしなくちゃと思いつつ、なかなか何とかできないみたいな感じはよくわかる。エピソードが積み重なるなかで、気持ちがうーっと鬱積してしまうあたりなんかよく書けてますよね。同じような経験をしている子が、そうなんだよね!と思って読むんでしょうね。
トチ:角野さんの作品が、この読書会でよく話題になる「似非英国ファンタジー」と違うのはどうしてなのか、と考えながら読みました。けっきょく、登場人物は欧米ファンタジーのキャラクターだとしても、借り物ではない角野さんの世界がきちんとできているからなのね。だから、安心して読めるんだと思う。
裕:「ブックバード」(IBBYの機関誌)のある記事で、角野さんの作品が多くの日本の魔女ものに見られる「似非英国ファンタジー」といっしょくたにされて書かれていたことがあって、ご本人はとても傷ついていたと聞きました。
紙魚:(イラストを見ると)とんぼさんなんかは、成長しているせいなのか、画家が違うせいなのか、巻によってずいぶん印象が違いますよね。編集者としては、逆に1冊ずつ変えようという意図があったのかもしれませんけど。
ねむりねずみ:「似非英国ファンタジー」が似非だと感じられてしまうのは、書きたいことと設定がちゃんとひとつにまとまっていないからだと思うんですよね。でもこの作品は、書きたいことがあって、それが、時計台のあるような舞台設定で行われているだけのことというくらいにちゃんと書けているから、似非という感じがしないんじゃないかな。
トチ:この作品は「大人」が書いているという気がする。年齢だけは大人でも、大人になりきれていない「少女」が、ファンタジーっぽい雰囲気を楽しむために書いているんじゃなくて。だいたい、子どもの本には「大人が(あるいは、おじいさんやおばあさんが)小さい子どもたちに語りきかせる」というエレメントがあるものね。エリナー・ファージョンやルーシー・ボストンにしても。
裕:角野さんは自分の少女時代、自分の子ども時代に向かって書いている気がする。自分の子ども観といったらいいかな。彼女のノスタルジーは、今の子どもにも通じる。天性のストーリーテラーだな、そのへんがうまいなと。メッセージも、最後に上手にまとめているし。
紙魚:1巻は、学生のときに、母親に「おもしろいわよ」と薦められて読んだんです。私の母は変わった人で、私が幼い頃、自分は空が飛べると言っていたんです。大人になればみんな空を飛べるようになると。「でも、外で空を飛んでいる人なんか見たことないよ」って疑ったら、「人に見られると飛べなくなるから、みんな見られないように気をつけてるのよ」と言われたりして。それで毎日、ある決まった時間に母が家からいなくなるんですね。少したつと、「空飛んできたわ」って縁側から帰ってくる。だからすっかり信じ切っていました。ある日、縁側の戸をがらっと開けたら、雨戸に張りついている母を発見。まあ、その時分にはそういう嘘もきちんとうけとめられるようになっていたので、ひとつの「物語」として私のなかに残りました。おそらく、母は私に「物語」を伝えたかったのではないかと思います。今では、本という形ではなくても「物語」は存在するんだなあと思います。そういうこともあったせいか、母は大学生だった私に『魔女の宅急便』を渡したんでしょう。母もストーリーテリングの能力があれば、こういうものを書きたかったんじゃないかなあと思います。角野さんのこの本に対しては、自分より年下の人のために、物語を紡ぎだす目線を感じましたね。ただうまいだけではなくて、成長を重ねる自分を確認する作業をきっちりしてきた方だと思うんです。しかもそれを物語につなぎ合わせ、ひとつの世界にしていくことができる人なのでは。だから、設定はファンタジーではあれ、エピソードの中で、私にもこんなことあったなあ、と感じられるんですね。こういう確認作業というのは、誰にでもできることではないですよね。キキの中にちゃんと血がかよった成長が感じられる。そもそも、フィクションというのは、ある意味、人を騙すことだとすれば、人を騙して楽しんでもらうのが好きでないと・・・。
裕:作者は、お母さんが早く亡くなったので、悲しみを紛らすために、いろいろなお話を作って、お友だちに話して聞かせては、欠落観を補っていたそうなのね。それで、嘘つきと言われたりもしたそうなんだけれど、そういうことが、作家になることを促したのかも知れないわね。
オカリナ:お父さんからしょっちゅう講談を聞いていたとか。
ウェンディ:1巻目を読んだときのことを懐かしく思いながら、キキも思春期になったのね、と感慨深く読みました。ケケというライバルが生活に入りこんできて、虚栄心とか張りあう気持ちが芽生えて・・・というあたりは、私も昔、意固地だなあと自分でも思いながら、どうにもならなかったときの気持ちが、ふとよみがえりました。
愁童:図書館に借りに行ったら、3巻目は36冊もあるのに全部借りられてて予約待ち。結局借りられなくて、読んでいません。2巻目を借りて読んだけど・・・。ハリ・ポタも未だに予約待ちだけど、借りてるのは大人がほとんど。直接子どもに手渡しての感触がつかめないって図書館司書が嘆いていたけど、こっちは、子ども自身が借りているんで、すごいなって思った。1巻、2巻と末広がりに読者が増えてるんじゃないの? アニメなんかの影響もあるだろうけど。
裕:これが英訳されたらどうかしらと考えてみたのね。訳はあるらしいけれど、出版はされていないの。このレベルでもちょっと厳しいのかな。重厚さが不足してるところなんかが・・・。まず、日本の日常現実世界がもっている骨組みはないですよね。メッセージ性が弱いのかしら。
トチ:マーガレット・マーヒーの、魔女とか英国ファンタジーのキャラクターが出てくる作品は、最初はニュージーランド独自のものが登場しないというので、ニュージーランドの出版社では出してもらえなかったのね。それがニューヨークで出したら大評判になり、たちまちインターナショナルな作家になったのよね。まあ、同じ英語圏なので、日本の作品を海外に紹介するのとは少し事情が違うかもしれないけれど。
オカリナ:日本の児童文学で外国で紹介されているものといったら、何があるのかな。『夏の庭』(湯元香樹実、ベネッセ)、『13歳の夏』(乙骨淑子、理論社)、末吉暁子、吉本ばなな、村上春樹、マンガ・・・、と見てくると、日本独自の世界を書いたものばかりではなくて、いわば無国籍的なものも多いわよね。うちの子は1巻目で好きになって、2巻目も読んだ。で、私が3巻目を読んでいたら、それも読みたがったの。日本的とか無国籍的だとかに関係なく、やっぱりそれだけの魅力があるんだと思う。何でもおもしろがる子じゃないのに。生活臭があったほうがいいのか、ないほうがいいのかは、いちがいに言えないんじゃないかな。
愁童:ハリー・ポッター現象を思うと、この本が読まれていることに、ホッとするね。もしかしたら意識して日本の生活臭をはずしたところで展開しているのかなあ。でも、これの1巻目が出た時は、とても新鮮な感じがしたね。
紙魚:キキはたしかにとてもいい子として描かれていて、今の世の中にはいない子かもしれない。それでも今の子も読みたくなるお話だとすれば、つまり純粋に楽しむために読んでいるとすれば、それもいいことだとは思いますが。
愁童:それだけ今の子どもたちの実生活が大変なんでしょう。大変なときは、角田光代さんの『学校の青空』(河出書房新社)のような陰々滅々としたのは、読みたくないだろうしねえ。
(2001年04月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)
ティーパーティーの謎

原題:THE VIEW FROM SATURDAY by E.L. Konigsburg, 1996(アメリカ)
E.L.カニグズバーグ/作 小島希里/訳
岩波書店
2000-06
<版元語録>6年生のノア、ナディア、イーサン、ジュリアンは大の仲良し。複雑な家庭の事情を抱えている子どもたちの生活を描きながら、どうやって4人が親友になったか、その謎を語る。ニューベリー賞受賞作品。
オカリナ:この本はどうも読んでらいれなくて、途中で放り投げたくなりましたね。出版されてすぐ読みかけて放りだし、もう1度挑戦して放りだし、今回みんなで読もうということになって、やっとのことで最後まで読みました。まず、最初に「博学競技会」という言葉で、えっと思ったの。どうしてこんな訳語にするのかな? 物知りコンテストとか、物知りコンクールでいいじゃない。もともと物語の構造が複雑だから、さらっとは読めないんだとは思うんだけど、この翻訳では、おもしろさがまったく伝わってない。ニューベリー賞を獲得した作品とはとても思えなかった。原文は、もっとおもしろいのかもしれないね。
ねむりねずみ:前から気になっていた本で、原文を読みたいなとは思っていました。やっぱりカニグズバーグだし。訳に関する要素を除くと、ノアにしてもナディアにしても、出てくるキャラクターはやっぱりカニグズバーグという感じ。都会的でセンスもあって、子どものキャラクター作りはとってもおもしろいと思った。 でも、訳がいまいちなんですよね。最初のノアのところで、「実は」「実は」のくりかえしにうんざりしてしまった。ノアの口癖なんだろうけど、もうちょっとなんとかならないかなって気になってしまって。短編集『ほんとうはひとつの話』みたいなのかな、と思って読んでいくと、うねうねとつながっていくスタイルだったので、途中でへえっと思い、最後の娘さんのあとがきを読んで納得しました。やっぱりうまいなと思ったし、著者の冒険心みたいなのがおもしろかった。でも、訳には悩まされました。p233のロープの輪っかが出てくるところなんか、どういう状況なのかよくわからなかった。凝った構成なのに、ディテールがきちんと伝わってこなくて、途中でやたらとひっかかった。
オカリナ:身体障害者の先生が出てくるじゃない。この先生像がいまいち見えてこないのよね。やっぱり訳のせいなのかな。うまく訳せば、もっと人物像がうかびあがるはずだと思うんだけど。先生の人柄がうかびあがらないから、この「競技会」に関しても、ただ知識を競わせている嫌な先生のようにしか思えなくて、魅力が伝わらなかった。
ねむりねずみ:『エリコの丘から』(カニグズバーグ 岩波書店)にも似ている感じがしました。物語全体が謎めいているところなんかが。何度かあっちこっちひっくりかえして、やっと全体の話がつながったんだけど、本当は1度でつながらなくちゃいけない。シンさんが時々亡霊みたいに出てきて先生と会話しているところなんかが、よくわからなかった。それと、翻訳がなぜこのタイトルになったかもわからない。p13の、弟のジョイが「祖父母のところに・・・行かされた」っていうくだりも、きっと原書で作者はいろいろ考えて言葉を探しているだろうに、訳が荒っぽい感じ。
裕:私も、わりと何でも普段は義務感で読みとおすのに、途中で挫折しちゃった。翻訳のせいだとは思わなかったんだけど。
トチ:これって、4人の子どもの話と1人の大人の話が、それぞれ色の違う糸のようにからまって、ついには美しいタペストリーを織り上げていく・・・そういう構成の物語よね。ところが、訳のせいでそれぞれの糸の色分けができていない。だから、さっぱりタペストリーが見えてこない。本当に残念なできあがりになっている。それから、「ジャック・スプラットは脂身がだめ、奥さんは赤身がだめ・・・」というの、有名なマザーグースの唄よね。訳は「童話」となってるけど、原文でも「童話」とは書いてないんじゃないかしら。それから、マーガレットのトレーナーの色が「青緑でとても派手」というようなことを書いているんだけれど、「青緑」だったら日本ではちっとも派手な色じゃないから、「どうしてなの?」と思ってしまった。きっと原文はturquoiseとなっているのでは? ターコイズは日本の辞書では確かに「青緑」となっているけれど、けっして「青緑」ではない。トルコ石の青だから、空色や水色に近い色よね。これなら派手といってもおかしくはない。重箱の隅をつつくようだけど、そういう細かいところが気になりだすと、物語の世界に浸れなくなるのよね。
オカリナ:筋でどんどんひっぱっていく話ならともかく、こういう凝った構成になっている作品は、翻訳には特に気をつけたいわね。
トチ:物語のほうでは、カニグズバーグって、どうしてこんなに頭のいい子が好きなんだろうと思ってしまった。知力で大人と対等にわたりあえて、しかも意志がしっかりしている。こういうのも一種のアメリカン・ヒーローなのかしら。私は、黒板にいたずら書きするハムみたいな子のほうに共感をおぼえるけど。
オカリナ:ハムという子は、物語の中ではあっさり切り捨てられてるのよね。
ウェンディ:「博学競技会」で華々しい勝利をおさめつつあるところ、そろそろ終わるのかなあと思うのに、次々と7、8年生に勝ち進んでいくのは、冗長な気もしましたね。訳文が読みにくいのは私だけかと思ってました。カニグズバーグだし。構成的には興味深く読んで、読み終わってから娘さんの解説でモーツァルトの構成を取り込んだ、と知って、なるほど、と思いました。4つの短篇小説といってもいいようなプロットが、最後に一つのうねりに収束していくところが、もっとうまく描かれていれば、もっとおもしろかっただろうな。でも、これも訳の問題なのかもしれませんね。これだけあれもこれもと要素を盛り込みながら、破綻なくまとめあげられるのは、さすがにうまい人だなと思いましたね。アリスが象徴的に使われていたりする点も、親しみがわくし。ただ、訳は、英語が苦手な私でも、原語が想像できてしまうようなところがある。特に、プロットごとにあえて語り手を替えることによって、織り成す物語だと思うので、やっぱり訳でも語り口をかえてほしかった。ただ、昔だったら何とか日本語にしていただろう言葉でも、今はあえてカタカナのままでいいんだなと再確認できる部分もあって、翻訳の仕方も変わってきたんだな、と参考になりました。
愁童:ぼくも読みにくくて挫折寸前だった。カニグズバーグは大好きなんで、自分の感性を責めてたんだけど、皆さんの翻訳論を聞いてて溜飲が下がりました。最初の結婚式の模様も、どたばた調で、饒舌な割りにわかりにくい。あそこを抜け出るのにエライ苦労しちゃった。
紙魚:この本って、対象が小学5、6年以上となってますよね。その年齢ではもちろんですが、その年代より少しは読解力はがついたのではないかと思う今の私が読んでも、読みにくかったです。構成を把握しながら読むって相当の力を要すると思うんです。やっぱり自分におきかえてもそうですが、子どものときって、大局的にとらえるのって不得手でした。そのかわり細部には目を光らせてるんですけど。小学生の自分だったら、この構成が「モーツァルトの交響曲」と言われてもよくわからなかったと思います。でも、もっと読みやすくて、その組曲みたいな構成がわかれば、読書のおもしろさをもっと味わえて、読書を広げるきっかけになるだろうに。これを読んだゆえに、ほかの本へとの興味もなくなってしまうとしたら、とっても残念。これだけおしゃれな構成のおもしろさを、ぜひ子どもにも知ってもらいたかったな、とは思います。細部だけでなく、大枠の構成がおもしろいなんて感じ方をしてもらえたらいいのに。私が編集を手がけるときは、そうなってもらえるように、ぜひ気をつけたいと思います。こういうのって、わからないところがわかったときがすごくおもしろくて、新しいステージを知ったように世界が広がるから。
トチ:こういう構成の物語は、道しるべというか、キーになる言葉がとても重要だと思うの。それがうまく訳されていなかったり、間違ったりしていたら物語そのものも理解できなくなってしまうと思うわ。
紙魚:うーん、モーツァルトの曲だって、技量があって曲を理解しているピアニストが弾いてこそですよね。
ウェンディ:まず、どこにメロディラインが隠れているかがわからないと、弾きこなせませんものね。
オカリナ:翻訳者が伏線を伏線と意識していないと、読者にも伝わらないから、難しいですよね。
トチ:会話の部分でもノアとイーサンが区別できない。二人の性格の違いも見えてこないわ。
愁童:カタカナで「キョウイクシャ」と書いて、作者がこめた皮肉っぽさを、 今の子どもたちに伝えられるのかな。訳者は、本当にカニグズバーグの言葉を伝えてくれてるのかなっていう不安を感じたな。 『Tバック戦争』(カニグズバーグ)なんかは、実にいいなって思ったのに。
オカリナ:『Tバック戦争』は筋があって、わかりやすかったんじゃない。それでも翻訳はひっかかったけど。そういう意味では、『ティーパーティーの謎』はもっと翻訳が難しい作品ね。
ねむりねずみ:原文の英語はきっとこういうふうに書いてたんだろうなと思わせるところが多々あって、英語にひっぱられてる感じ。英語だと通る言い回しでも、日本語になると変だったりする。
オカリナ:岩波はせっかくカニグズバーグの秀作は全部出そうとしてくれているのだから、もっとていねいに本をつくってほしいな。お願いしますよ、ほんとに。
(2001年04月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)
肩胛骨は翼のなごり
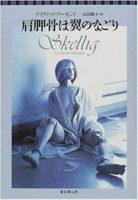
原題:SKELLIG by David Almond, 1998(イギリス)
デイヴィッド・アーモンド/作 山田順子/訳
東京創元社
2000.09
<版元語録>古びたガレージの茶箱のうしろの暗い陰に、僕は不可思議な生き物をみつけた。青蠅の死骸にまみれ、蜘蛛の巣だらけの彼は誰、…それとも、なに?夜明けの闇と光が繊細に溶けあう、どこにもない物語。カーネギー賞・ウィットブレッド賞受賞作。
オカリナ:おもしろかったけど、文句が2つあるのね。まず、表紙が内容と全然違うでしょ。どういう人に読ませたいのかわからない! もう1つは題名。売れるとも思えないし、お洒落とも思えない。それに、この本の出し方は、子どもを読者対象にはしてないわよね。原書の対象は9〜12歳なんだけど、邦訳にはルビもないし。私は、子どもにも読める形で出してもいい本じゃないかと思うんだけどな。内容的には、スケリグは、ホームレスのイメージよね。しかも、死んだ動物を食べ、嫌な臭いがする。「メルヘンチックな」童話が児童文学だと思っている人にはショックだろうし、そういうのと対極にある話。物語は、ウィリアム・ブレイクを下敷きにしてて、ブレイクの詩が好きな隣の女の子の存在がおもしろかった。学校へ行かないんだけど、堂々としていて、イギリスだったらこういう女の子いそうな気がする。主人公の男の子は、引っ越してきたばかりで、妹が死にかけていて、親もそっちに一所懸命になっているから、不安定に揺れている。それで、精神的に日常とは違うところへ行きかけているところを、この女の子が引っ張ってくれる。普段のサッカーや学校生活では見えないものをこの少年が感知していくプロセスが、うまく書けていると思いましたね。
愁童:おもしろかった、すごく。表紙と訳の最初の部分はひっかかったけどね。訳文はおもしろくないなあと思いながら読んでいった。本作りにも作品世界を正確に伝えようというような意欲は感じられないしね。でも原作の力が、そんなものふっとばして輝いていたと思う。スケリグは、子どものときは見えたけど、大人になったら見えなくなったものの象徴かな。赤ちゃんが死にそうになったとき、母親にも見えたという描き方は、イメージがふくらむね。ここまで読んできた甲斐があった、うまい! と 思っちゃた。ところが、次の日に隣の女の子と見にいくと、スケリグが戻ってきていて、それからおもむろに子どもたちの前から居なくなるってところは、ちょっとね。戻ってこないほうがよかった。その方が、 鮮やかなイメージを残してくれると思うんだよね。吐き出したものが臭いといったようなディテールが、きちんと描かれていて、雰囲気が伝わってくるので、引きずられる。そこはうまいと思った。それにしても、訳書の本作りには腹が立ったなあ。
トチ:この作家は私の大好きな作家。「スケリグ」という原題のこの作品も、テーマといい、文学的な香気といい、英国の文学史上に残る作品だと思う。日本でも外国でも、「襤褸の人」と「聖者」を結びつけて描くということが昔からあるけれど、この作品ではそれを「ホームレス」と「天使」にして描き、その汚くて清らかな、力があって無力な存在が、主人公やその妹を救うという設定になっている。特に、それが児童文学という形であらわれているのが、素晴らしい。なのに、日本の出版社は3つの点でこの素晴らしい作品を傷つけているのよね。1つめは、表紙。私の知っている若い人は、本屋の書棚からとりだして表紙を見たとたんギョッとなって、また棚に戻してしまったんですって。まるで、ポルノグラフィもどきの表紙で、内容を裏切っている。2つめは、タイトル。3つめは、カーネギー賞をとった児童文学なのに、子どもに手渡そうとしていないこと。大人の本の出版社がこうやって海外の素晴らしい本をさらっていって、大人の書棚に並べてしまうというのは、本当に残念だと思うわ。この作家の作品は、これからもこの出版社で出すという話だけど、惜しいなと思う。版権というのは買ったからといって、その出版社が煮るなり焼くなり勝手にしていいというものではない。その作品を最良の形で日本の読者に送るという義務があると思うんだけど。
ねむりねずみ:ネズミを食べたたりする汚いイメージと、聖なるもののイメージが一緒になっているところが大切なのにね。私は、訳文が完全に子どもを捨てているのがすごく嫌だった。原文はとても平易なのに、なぜこうするかなあっていう感じ。これじゃあ、子どもはわからない。地の文だって、子どもが語ってるはずなのに、こんな表現、使わないと思うところがたくさんあった。凝りすぎ。ともかく、はじめから大人だけをターゲットにした本にしないでほしい。原作者は、9〜12歳の子に送りたいと思って書いているのだから。でなければ、原書も大人向けの文体にしているはず。それに、子どもなればこその読み方ができるはずで、大人になってから読むのとは違うはずだと思う。そういう点で、ものすごく腹がたつ。原文を読んでいたので、あれ、これって誤訳じゃない?っていうところ(p3のI couldn’t have been more wrong.「それよりひどいことがあるなんて」など)が気になってしまった。訳によって、受け取る作品のイメージが原文と変わってくるから、翻訳って怖いなって思った。1章の最後だったかしら、The baby came too early.「そして赤ちゃんも早く生まれた」ってあるけれど、早く生まれすぎたという感じではないのかしら。
オカリナ:赤ちゃんは臨月で生まれないと、それだけで大変なわけだから、私は「早く生まれた」でもいいと思うけど。
愁童:だいたい、「旨し糧」なんて言わないでしょ。翻訳者のセンスが古くない?
トチ:原作者だって、子どもの本だと意識して書いたと言っているのに。
愁童:「なんでこんなところに越してきちゃったんだろう」とお母さんが思うところ。納得の上のはずだったんじゃないかと思ったけど、確かに、一生懸命そうじしたために早く生まれちゃったという前提があれば、わかるよね。読んだときは、よくわからなかった。
ねむりねずみ:スケリグが好物を中華料理のメニュー番号でいうところも巧いですよね。現代イギリスの生活の雰囲気も伝わってくるし。
オカリナ:スケリグは現代の「星の王子様」なんだなと思いましたね。きれいでもないし、かわいくもないところがすごいじゃない。
愁童:スケリグのことを汚いなと思いながらも、読者が最後までついていけちゃう筆力があるよね。フィリップ・プルマンの『黄金の羅針盤』(新潮社)にエンゼルが出てくるよね。あのイメージに通じるものがある。文化のつながり、ネイティブでないと書けないものという気がしたね。
ねむりねずみ:むこうでは、天使にもいろいろあって、羽が6枚で目がついてたりするのもある。そういう日本とは違うイメージの広がりがあるから。
オカリナ:天使にも階級があるしね。
愁童:日本だとこういう世界を書こうとすれば、廃屋で暮らす少年少女は出てこないよねえ。
オカリナ:今の日本には、スケリグがいてもおかしくないようなスペースがなかなかないけど、イギリスにはまだあるんじゃない?
ねむりねずみ:イギリスは人口が分散しているので、そういうところも残っているんじゃないかなあ。
オカリナ:日本でも、私が小さいときは近所に得体の知れない不思議な人が居たわよ。軒を借りて小屋をつくって住んでいたりするの。そういう人を見ると、いろいろ想像したものだったけど、今は「不思議を感じさせてくれる人」は隔離されちゃっているでしょ。イギリスには移民もふくめて「変わった人」はたくさんいるわよね。学校行かないで平気な人もいるし。日本のような、みんなが「並み」の画一的な社会では、日常的なファンタジーは生まれにくいのかもしれないな。
愁童:ぼくも、集団疎開先で経験してるね。得体の知れないおじさんがいて、村人がそれなりに存在を認めていて、下肥汲み専門みたいな仕事をやってるんだけど、仕事がないと、いつも共同温泉場にボーっと入ってるんだよね。顔だけがお湯の上にプカプカ浮かんでるみたいな感じでね。ぼくら子どもも、そのおじさんとよくいっしょに入ったよ。なんか不思議だったね。
ねむりねずみ:画一社会は、そこにいることで、ぞわぞわっとする部分を感じる人、っていうのを、全部排除しちゃうのよね。
紙魚:これ、表紙はもちろん悪いんだけれども、私にとってはいい経験になりました。編集者の役割というものを考えられたからです。入社したての頃、書店のお手伝いをさせていただいたことがあるんですが、毎朝、その日の新刊が届くと、店長が中身を見ずに、店に置く本と置かない本をふりわけていくんです。店長は、表紙だけをぱっと見て瞬時に判断していくんですよ。わー、待って、その本おもしろそうなのに! なんてことがよくありました。本を選ぶ理由って、いろいろあるじゃないですか。内容がいいってことはもちろん、ほかにも、手ざわりがいいとか、デザインがいいとか、気にいっている書店で薦められていたからとか。でも、やっぱり表紙って大事なんだな、本の顔なんだなって実感しました。今回、内容はいいのに、表紙がよくないこの本を見たことで、本づくりの一端を担う者として、できるだけその本のよさを伝える努力は惜しみたくないと痛烈に感じました。作品を好きになり、この世界を理解しようと努めて、できるだけいい表紙を作ろうと。こんな本になっちゃうこともあるのだったら、逆にそれだけがんばれる部分もあるんだなと思ったんです。
オカリナ:私は、とにかく目をひく表紙にして本屋に置いてもらおうとしてるのかな、とも思ったんだけど、表紙に引かれて買った人は逆に失望するでしょ。売れちゃえばいいって思ってるのかな?
トチ:そういう版元だとしたら、版権を買うのが許せないわよね。
オカリナ:表紙や書名が中身と合っていないいう意味では、今のところ今年いちばんギャップの大きい作品でしょうか?
(2001年04月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)