| 日付 | 2017年12月22日 |
| 参加者 | アカシア、コアラ、アンヌ、冬青、花散里、レジーナ、西山、しじみ 71個分 、(エーデルワイス) |
| テーマ | 動物と人間 |
読んだ本:
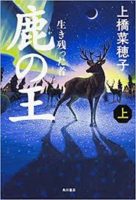
上橋菜穂子/著
角川書店
2014
版元語録:感染から生き残った父子と、命を救うため奔走する医師。過酷な運命に立ち向かう人々の〝絆〝の物語。 *本屋大賞受賞

原題:THE WOLF WILDER by Katherine Rundell & Gelrev Ongbico, 2015
キャサリン・ランデル/著 ジュルレヴ・オンビーコ/画 原田勝/訳
小峰書店
2017.09
版元語録: ロシアの森深く、母親とオオカミたちと暮らす少女フェオ。ある日、残忍なラーコフ将軍が現れ、オオカミを保護した罪で母を連れ去ってしまう。少女はオオカミを連れ、元兵士の少年と共に、母を取り戻すため旅に出る。
鹿の王(上/生き残った者 下/還って行く者)
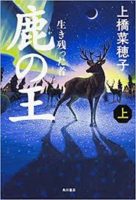
上橋菜穂子/著
角川書店
2014
版元語録:感染から生き残った父子と、命を救うため奔走する医師。過酷な運命に立ち向かう人々の〝絆〝の物語。 *本屋大賞受賞
西山:出てすぐに買って読みました。それっきりで、今回読み返す時間がなかったので、その時の印象だけでごめんなさい。もちろん、おもしろかったけど、期待ほどではなく、少しずつ冷静に読んだという感じでした。先が気になってしょうがない、というほどのめり込まず、淡々と少しずつ読み進めたという感じ。冒頭は、なにが起きるんだろうと、とてもドキドキしながら読んだんです。坑内の描写はすごいと。でも物語が進むと、説明的な世界になってしまった。下巻303ページ、真ん中あたりの「ひとりひとり、まったく違うの。どの命も」といった上橋菜穂子の基本的価値観に共感しつつ読んだけど……という感じです。アンデルセン賞受賞直後で派手な帯とか、テレビで騒いでたりとか、何を今更、上橋菜穂子はずっと前からおもしろいわい!と、拗ねていたせいかもしれませんが、上橋作品の中では、私にとっては評価はあまり高くないんです。
レジーナ:謎解きのおもしろさの中に、なぜ死ぬ者と生きのびる者がいるのか、病や死を得ながら生きるのはなぜか、という大きな問題を扱っています。民族間の対立や抑圧は、上橋さんのほかの作品に通じるテーマですね。この本の世界には、混血のトマのように、混じり合いながら血をつなげていく人がいる一方で、火馬の民のように、国を奪われた痛みを忘れられない人たちがいます。オタワルのように、自分の国を失ったあと、知識や技術を活かして国の中枢に入りこみ、したたかに生きのびる人々もいます。国や民族の複雑な関係性を、人の体に広がる宇宙に重ねているのは、ユニークでおもしろい視点ですね。自然を支配しようとする人間の傲慢さ、人知を超えた自然のしくみについても考えさせられます。本のつくりですが、いろんな種族が出てくるので、地図があるとよかったです。
花散里:出版されて、すぐに読みました。自分が大人だからかもしれませんが、主人公のヴァンがとても魅力的に描かれていると思いました。岩塩鉱で出会ったユナを助け、育てる姿は印象的で、ユナを見守る眼差しなどが目に浮かぶようでした。医術師ホッサルが懸命に治療法を探す様子や、愛する人々を救うために奔走していくヴァンの生き方など、下巻の後半がおもしろかったです。謎の病の恐ろしさなどが、とても上手に描かれていると思いながら、惹きつけられるように読みました。『ゲド戦記』(アーシュラ・K.ル=グウィン作 清水真砂子訳 岩波書店)の4巻目が出たときもそう思いましたが、これはYA以上の、むしろ大人の本ではないかと思います。「守り人」シリーズや『獣の奏者』は小学校の図書館でも、とても良く読まれていて子どもたちに人気があります。
冬青:くりかえし読んでも、その度に発見があって面白い本ですね。大人向けのエンタメ本でもエピデミックものは沢山出ていますが、わたしが読んだかぎりでは、たいてい近未来の世界や現代を舞台にしています。でも、この作品はいかにも上橋さんらしい世界を舞台にしているので、魅力があります。自然の描写も美しくて緑の空気をいっぱい吸ったような気になるし、飛鹿を柵の中に入れるところの描写など、実際に動物をどう飼いならすかを見てきた人でなければ書けないような箇所があちこちにあっておもしろかった。でも、地図を見返しにでも入れてくれれば、もっと分かりやすかったのに。病気や免疫についての記述は必要な部分だと思うけれど、ちょっと退屈でした。冒頭は衝撃的で、印象的な場面ですが、それがどういうことか分かるまでがちょっと長くて、年若い読者には辛いのでは?
ヒイラギ:ルビの振り方は、一般書ではなくYAですね。
アンヌ:人の名前が難しいので、今回は読み直しながら、登場人物のページに人物関係表を作って書き込んで行きました。1回目に読んだ時は謎解き中心で読んで行ったので、2回目の今回の方がずっと楽しめました。とにかく私はファンタジー世界を作者が戦争で壊してしまうというのが嫌いで、この作品では戦いはあるものの全面戦争はないので、世界の隅々まで楽しめたという感じです。家族を失っている主人公のヴァンが、一人の幼女を助けたことによって、すんなりと移住民の家族の中に入って行くことができ、その家族は結婚によって別の民族とつながっている。様々な形で家族が形成され、新しい世界が出来上がっていく可能性を示しています。支配層の王たちが、それぞれの妥協点を常に探っているという感じもよかった。もう一人の主人公のホッサルが中心の医学の場面も、推理小説のようにおもしろく読めました。病に抗体がある者はトナカイの乳でできた食品を食べていて、トナカイは地衣類を食べていて、その地衣類でできた薬は、超能力を得たユナの目には光って見えると描かれているところは、ファンタジーならではのとても美しい謎とき場面だと思います。気にかかるのは、後追い狩人サエです。すぐれた能力がある女性なのに、子どもができなくて婚家から身を引いていたり、「あれは寂しい女だから気を付けろ」なんてホッサルに言われたり、やたら顔を赤らめる場面があったりして、かなり女らしく描かれています。封建主義の国の物語だから仕方ないとしても、少し物足りない気がしました。
コアラ:物語の世界に浸っておもしろく読みました。下巻の438ページから440ページくらいで、〈鹿の王〉とは何かという話があるのですが、英雄的な話を否定して、残酷さや哀しみを語る父親のセリフ、仲間を救うのは出来る者がすればいい、ひよっこは生き延びるために全力を尽くせ、という話は、まさに若者たちへの大人からの言葉だなと思いました。それから、音と漢字のあてはめ方がいいですよね。「飛ぶ鹿」と書いて「ピュイカ」と読ませるのは、いかにもピュンピュン飛ぶように駆ける鹿を思わせて、うまいなと思いました。ただ、上下巻の大作のわりには少し印象の薄い物語でした。
しじみ71個分:長編で、世界も人物も複雑な構成になっているのに破綻がない。これだけの世界を構築できる筆の力がまずすごいと思います。ローズマリー・サトクリフのローマ帝国時代のブリテンの物語シリーズを思い出しました。あとがきに、上橋さんはご両親の介護や、ご自身の更年期障害といった、命、生死、病といった問題の中で向きあう中で生まれた物語だと書かれていましたが、上橋さんの思いがよく伝わる作品だと思います。柳澤桂子さんの著書にも言及しておられましたが、私も『われわれはなぜ死ぬのか : 死の生命科学』(柳澤桂子著 草思社 1997)を読んで生物の生死について考えたこともあったので、自分の関心に重なるところの多い作品でした。人の手の水かきが出来ては消えていくように、個体の中で生滅、生まれては死ぬことを繰り返しているという命の不思議さを描くことに挑んだ上橋さんの思いに強く共感します。政治的な面でも、あの国がモデルかしら、とか想像できるのもおもしろいポイントでした。いぶし銀の大人のラブストーリーとしても読めるし、医療、政治、家族等多面的な読み方ができる作品ですし、いろんな知識がもりこまれていておもしろかったです。想定する読み手は高校生以上くらいでしょうか?
ヒイラギ:最初に読んだときは、医学の部分や政治の部分は難しいなと思って、いい加減に飛ばし読みしてしまいました。登場人物がたくさんいて関係も複雑だし、政治の部分も、最初読んだときは私自身の頭の中がうまく整理できなくて、表面的なおもしろさだけを追ってしまったんです。でも今回は、自分で地図も人物関係リストも作りながら読んでいったら、前よりずっと頭に入ってきて、おもしろさも深まりました。構成もよく考えられていて、医学や政治の部分の理屈や説明が続く後にはユナのかわいい言葉や自然の描写があって、うまく調和がとれているんですね。そのあたり、すごくうまいと思います。動物と人間の結びつきもおもしろくて、そのあたりもじっくり考えて書かれているように思います。
ユナが子どもの実像と少し違う、という意見も聞いたことがありますが、この本の中ではこれでいいじゃないかな。知らない親族のところで暮らしたり、ホッサルのところに行ったり、がまんしているところはわずかしか描かれていませんが、ユナが主人公ではないからね。生物の死については「病の種を身に潜ませて生きている。身に抱いているそいつに負けなければ生きていられるが、負ければ死ぬ」というふうに書いてあったりするところで、1回目に読み飛ばしていたのが、今回はああ、なるほどと思ったりもしました。非血縁の人たちが家族をつくっていくというところもおもしろいなあ、と思って読みました。
アンヌ:文庫版には地図がついているようですよ。
しじみ71個分:私は科学的な硬い記述と、ソフトなストーリー部分が交錯することによって、読み方にリズムができるので、それがおもしろいと思いました。ユナについては、ウィルスに感染した生き残りなので、突然変異して新しい人類となってもっと活躍したりするのかと期待したけれど、そこはそうではなかったですね。
アンヌ:たしか親戚の伯母に預けられたとき、ユナは頑固に誰にもなつかないで家を抜け出してばかりいると描かれていますよね。
レジーナ:ユナの舌足らずなしゃべり方は、ところどころ幼すぎるというか、ちょっと不自然に感じるときがありました。
ヒイラギ:私はそれは引っかかりませんでした。この異世界にはいろいろな言語や方言があるのかもしれないし、様々な種族の中で育っているので、最初からすらすらとはしゃべれないんじゃないでしょうか?
冬青:ユナは、リアルな人間の子どもというより、少しばかり神性を持った存在として描かれているような気がしたけど……。
しじみ71個分:確かに、ユナのしゃべり方はその年齢の実際の子どもとはちょっと違った感じは受けました。大人が見た小さい子ども像的な印象。そういえば、私は、描写からユナの絵柄が思い浮かんでこなかったですね。
エーデルワイス(メール参加):以前読んでから読み返していません。文庫でも人気で、予約が続きました。読み応え充分で、浸りたい作品です。日本でもないヨーロッパでもない、架空の時代と世界がなんともたまりません。ただし、私はNHKで放送中の「守り人」を見る気になれません。上橋さんの世界観を出すのには、テレビドラマではむずかしいのかな? ところで、『鹿』ですが、日本中増え過ぎてこまっています。岩手でも問題になっていて、駆除されつつあります。11月下旬に処理されたシカ肉がよそから我が家に届きました。夫がシチューにしてくれましたが、山での姿が思い出されると夫は口にしませんでした。私は「鹿の王」など忘れペロリと食べました。牛肉のようで美味しかったです。
(「子どもの本で言いたい放題」2017年12月の記録)
オオカミを森へ

原題:THE WOLF WILDER by Katherine Rundell & Gelrev Ongbico, 2015
キャサリン・ランデル/著 ジュルレヴ・オンビーコ/画 原田勝/訳
小峰書店
2017.09
版元語録: ロシアの森深く、母親とオオカミたちと暮らす少女フェオ。ある日、残忍なラーコフ将軍が現れ、オオカミを保護した罪で母を連れ去ってしまう。少女はオオカミを連れ、元兵士の少年と共に、母を取り戻すため旅に出る。
コアラ:おもしろく読みました。日本とは全然違う世界で、引き込まれました。深い雪や「極みの寒さ」という吹雪など、寒さの描写が印象的でした。翻訳も読みやすくて、かなりの分量なのにすらすらと読めました。「オオカミ預かり人」というのは架空の職業だそうですが、オオカミとの触れあいはとても生き生きと描かれていたと思います。
アンヌ:とにかく表紙も挿し絵も素晴らしくて、楽しみながら読み進めました。オオカミとの生活にリアリティがあって引き込まれましたし、イリヤという兵士が突然現れてオオカミに魅了されて共に行動し、最後には彼の目指しているものもわかって行くというところも、おもしろく読みました。革命の場面で、演説に賛同するのも刑務所に一緒に行くのもまずは尼僧たち。作者はロシア革命の発端である女工たちのデモを踏まえて、この場面を書きたかったのではないかと思います。疑問に思ったのは、刑務所の中にもオオカミを連れた男たちがいるという場面。番犬替わりなのでしょうか? 少し説明がほしかったところです。ラストのエピローグはもっと民話的な語り口にするとか、違う形にしてほしかった。物語と地続きな語りのまま終わるという感じは、少しあっさりしすぎている気がしました。
西山:最後も敬体にすれば、入れ子で昔話のようになったのかな。
アカシア:一応、全体を昔話風にしているんじゃないですか。
冬青:導入部が敬体で始まっていて、最後も昔話のような語り口で終わっているので、敬体のほうが良かったかもね。
アカシア:でも、そうすると、ドラマチックな場面の緊迫感やスピード感に欠けるから、これでいいんじゃないかな。
しじみ71個分:とてもおもしろく読みました。ワイルドな女の子という設定は好物です。前半の展開はスピード感があって、とても気持ちがいいし、敵のラーコフの描き方もとてもいい。これでもか、というほどの極悪人に描かれていてメリハリが効いています。オオカミとの触れあいは胸に迫りますし、脱走少年兵のイリヤがバレエが好きで最後には願いが叶うという点も好もしいし、少年少女の革命というのも、現実味はないけれど、作者からの子どもたちへの激励として受け止めました。
冬青:こういう才能にあふれた若い作家が彗星のように現れるなんて、イギリスの児童文学会はすごいと思いました。“Rooftoppers”もおもしろそうだし。まず最初に「オオカミ預かり人」という仕事を思いついたところが素晴らしい。飼いならされたオオカミを侍らせているロシア貴族の邸宅なんて、ぞくぞくしますね。登場人物が大勢出てくるけれど、それぞれが個性豊かに描かれているので、まったくごちゃごちゃにならずに読めました。ラーコフの憎たらしさがちょっとマンガ的だけれど、これくらいに書かないとドラマチックにならないのかもね。フェオのしゃべり方が、森の中で暮らしているにしては女の子っぽいけれど、これはお母さんが貴族の出だから? 世にも美しいお母さんの背景が知りたいと思いました。
花散里:この本を手にしたとき、表紙画や装丁から絶対におもしろそうだと思って読みはじめました。「野生動物を救う」というテーマで4冊の本を取り上げて紹介(科学技術館メールマガジン)した時に、上橋菜穂子さんと獣医師、齊藤慶輔さんの『命の意味 命のしるし』(講談社)を読みました。齊藤さんは「野のものは、野に帰してやりたい」という思いで猛禽類を野生に帰すために取り組んでいて、上橋さんは「リアル『獣の奏者』」に会いに行くために北海道を訪ねています。この本では、オオカミを野生に帰すという設定にかなり無理があるのでは、と思いながら読みました。91ページのオオカミが仲良く寝ている挿画は、「これがオオカミ?」と気になりましたし、オオカミはもっと獰猛で獣っぽいのではないかと、全体を通して感じました。『鹿の王』で上橋さんは飛鹿とトナカイの違いや、狼に似た黒い犬の怖さとか、よく調べた上で書かれていると思いました。後半、革命扇動者のアレクセイが登場し、子ども達が革命を動かしていくような行動を起こしたり、フェオが演説する場面になると、「オオカミ預かり人」としての前半のストーリー展開から違ってしまったような印象で、読後感はあまり良くなかったです。
冬青:革命にしては、ちっちゃいけどね。
レジーナ:きれいな装丁の本ですね。極寒の地の静謐な美しさや自然の厳しさ、オオカミの息づかいが感じられるような本です。43ページ「家の周囲の森は命の気配にふるえ、輝いている。森を通る人たちは、どこまで行っても変わらない雪景色を嘆くが、フェオに言わせれば、そういう人たちは読み書きのできない人たちだった。森の読み方を知らないのだ。積もった雪は吹雪や鳥たちのことをうわさし、それとなく教えてくれている。朝が来るたびに新しい物語を語っている」、177ページ「雪景色は見わたすかぎり足あとひとつなく、まだ若い木々があちこちで雪に埋もれ、祈りを捧げる北極グマのように見える」など、ところどころに詩的な文章があるのもよかったです。フランスの革命では、何度も覆されてようやく民衆が力を得ます。これはハッピーエンドで終わっていますが、実際にはロシアの革命でも多くの血が流れたのでしょうね。一か所気になったのは、45ページ「今いるオオカミたちのうちの二頭は、人間で言えばちょうど自分と同い年くらいの女の子」です。同じページに「ハイイロは、フェオより数か月だけ早く生まれた雌」とあります。犬は人間の6~7倍はやく年をとるので、オオカミもだいたいそうだと思うのですが、そうだとすると、「人間で言えば同い年くらい」にはならないのでは。
ヒイラギ:「人間で言えば」の部分がちょっとちがうかもしれませんね。
西山:大変おもしろく読みました。いろんな意味ではじめての世界でした。題材も、ちょっとした描写もとても新鮮で。気に入ったポイントがいくつもあるんですが、まず、随所に笑える箇所があるのがいい。例えば、8ページ、5行目から、「オオカミのいる家には幸運がやってくる」として、列挙しているのが、「男の子は鼻水をたらさず、女の子にはニキビができない」という思いもよらない次元で、始まって2ページ足らずのこの段階で「これはおもしろい!」となりました。168ページ「オオカミのところはわからないけど、あとはわかる」とか、全体としてはシリアスで、張りつめていて、血のにおいもするけれど、クスッとさせるところがちょこちょこ出てくる。それを読む楽しさがありました。子どもたちの革命は魅力的だけど、後ろの方は急に軽くなる気はしました。ユーモアを味わいつつも、戯画的には読んでいなかったので、子どもたちが殺されても不思議はないと思っていたから、ホッとするけれど、分裂したイメージになってしまった気はします。アジテーションも浮いてるかもしれない。
カバー折り返しのところに引用された一節「世界でいちばん勇敢で賢いオオカミが死んだ。だからわたしは…」の一節は、自身を奮いたたせるための言葉だと思って、いつ出てくるかいつ出てくるかと思いながら読んでいたので、演説の一節だったことは、少々不満ではありました。軽くなったようで。それでも、演説は魅力的で音読したら気持ちよさそうと思ってしまった。あと、新鮮だった表現、48、49ページ「唇に凍りついた鼻水をかみくだいて吐き出すと」とか。182ページで感情が表れやすい「眉や鼻の穴、口や額がぴくりとも動かないから「表情が読めない」なんて、目以外で心を読もうとするのが新鮮でした。296ページの「罪を犯す覚悟を決めた美しい子どもたちの一団」なんて表現も好き。唯一引っかかったのは、307ページ、「三十分後〜」のところ。時制があれ?と。オオカミを感じさせるシルエットなど、私はイラストにも魅力を感じました。全体に厳しい寒さが感じられるのもいい。訳者おぼえがきで、どこが創作なのかが書いてあるのも親切。満足の一冊でした。
ヒイラギ:さっき花散里さんがオオカミは挿絵とはちがってもっと獰猛なイメージなのではないかとおっしゃったのですが、私はオオカミが好きなので動画や画像もいっぱい見たことがあるのですが、そんなことないです。安心している時はかわいい表情やのんびりした表情を見せるものです。それに、このオオカミたちは人間に飼われていた歴史をもつ者たちですからね。挿絵もぴったりだと思って見ていました。ただ、野鳥を自然に帰す活動をなさっている齋藤先生の本は私も何冊か読みましたが、この本の場合は、生まれてすぐに人間に飼われたオオカミだから、私もリアリティを考えれば野生にかえすのは無理なのではないかと思います。
私はおもしろい冒険物語として読んだので、そういうリアリティとの齟齬はあまり気になりませんでした。これは楽しく読ませる作品なので、これでいいじゃないか、と。原題にもなっているwolf wilderは直訳すると「オオカミを野生に返す仕事をしている人」というくらいの意味でしょうが、訳者の原田さんもそのあたりも含めて考えられたのでしょうか、「オオカミ預かり人」という訳になさっている。リアリティという点でいえば、革命家と言われるアレクセイは15歳で、そのほかの子どもたちはみんなそれより年下です。だから、この子たちが革命を起こすというところにもリアリティはあまりないかもしれない。私は、じつはリアリティにはかなりこだわる方なのですが、この作品ではあまり矛盾を感じませんでした。たぶんこの作品なりの世界がうまくできていて、訳者もうまくそれに沿って訳されているからだと思います。舞台は100年ほど前ですが、今描かれている物語なので、ジェンダー的にもきちんと配慮されていますね。主人公のフェオはおしとやかとはほど遠い嵐のような少女だし、兵士のイリヤはじつは踊るのが好きでバレエダンサーをめざしているなんて。
西山:たしかに女の子が強く描かれているのもいいですよね。
アンヌ:実は読み始めた時はもっとロシアの幻想文学的な物語だと思っていました。特にお母さんについては、とても高貴な顔をして威厳があるというので最初は魔女なのかなと思いました。お母さんについての謎解きもしてもらいたい気がします。
冬青:続編があるのかも。
西山:少年兵のイリヤが、オオカミの出産を見たがるところ。子どもにもどる様子がきゅんとするほどよかった。
アカシア:あの場面があるから、イリヤが兵士の身分を投げ捨てて将軍にたちむかうことを決意する場面も納得できるんですよね。
西山:32ページの真ん中あたり、「さげすむような目でにらんだ。少なくとも、そのつもりでにらんだ。本で読んだだけなので、どういう顔をすればいいのか、じつはよくわかっていない」という、ここもハッとさせられ、すごくおもしろく読みました。読書体験と実生活での体験にこういうベクトルがあることを端的に示してくれたことは意義深いと思います。
エーデルワイス(メール参加):好きですね、めちゃくちゃ。わくわくしました。ロシア皇帝時代オオカミをペットにしていたなんて。なんということをしていたのでしょう。マリーナとフェオの親子が魅力的で、フェオがかっこいい! 作者はまだ若い方で、アフリカジンバブエで幼少期を過ごしている。こんな物語を生み出したのですね。今後も期待したいです。訳もとても読みやすくてよかったです
(「子どもの本で言いたい放題」2017年12月の記録)