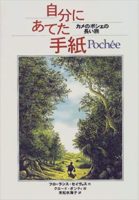風野潮/著
講談社
1999.10
<版元語録>野間児童文芸新人賞,椋鳩十児童文学賞に輝く「ビート・キッズ」続編。高校2年生になった横山英二を描く「青春ロック編」です。 *講談社児童文学新人賞も受賞
ひるね:達者な大阪弁の作品よね。登場人物のキャラクターがステレオタイプで「じゃりんこチエ」と同じ世界。とくに、お母さんは美しくてか弱くて、すぐ病気になっちゃうんだけど、女性の作家がどうしてこういう母親を描くのかしら? 七生は、養子だからっていうことで悩むんだけど、これって一種の差別だと思う。「養子である」という事実を必要以上に深刻に描くのは、どうも気にいらないのよ。それから、音楽をテーマにしてるんだけど、音楽の楽しさが伝わってこなかった。彼らが一所懸命になっている、ビートの追求のおもしろさが伝わってこないの。この作品がもしも大阪弁じゃなくて東京弁で描かれていたら、つまらなくてとても読めなかったと思うな。
オカリナ:私、前回欠席だったからバツとして、日本の作品を決めなさいっていうことになって、この本は議論を呼ぶ本だからおもしろいかなと思って選びました。『ビート・キッズⅡ』ではいろんな賞をとってて(第38回講談社児童文学新人賞、第36回野間児童文芸新人賞、第9回椋鳩十児童文学賞を受賞)賛否両論ある本だから。今回図書館で借りようとしたら、区の全館で貸出中だったの。そんなに人気があるのかとびっくりしちゃった。大阪弁がおもしろくて、ノリでわーっと読めた。『ハリー・ポッター』と同じで、登場人物はステレオタイプ。七生って、絶対いるはずないキャラクターなんだけど、そういうことを深く考えないで、決まりごとのなかにどっぷりつかって進んでいけばついていける。でもさ、この年齢の男の子がジャズバンドとブラバンとを両方好きでやるなんて、私のまわりを見てるかぎりではありっこないと思う。そこはリアリティがないような気がしたな。
ねねこ:本を読まない子に本を読ませるための1冊としては、いいと思うんだけど・・・。今、評価が、混乱をきわめる代表的な本。この本を「新しい」とか「おもしろい」っていう人は、かなり古い人だとは思う。おもしろさのかなりの部分が大阪弁に頼ってる。べつに、それが悪いことではないし、それも一つの芸だとは思うけど。ただ、生活苦のために高校をやめるなんて、今どきピンとこないし、CDも知らない中学生がいるのかなとか、ちょっと不自然な設定はあった。だけど、本を読んだことのない中学生からファンレターがびしびし届くらしいよ。
オカリナ:中学生が手にとりやすいように、装丁とか本づくりに工夫があって、定価も安いし(1100円)、『ハリー・ポッター』よりずっと良心的ね。
ねねこ:たしかに、そういう努力はしてるけど、それだけでいいのかって気持ちもある。それだけじゃなく、漫画にはできないことをやってやろうじゃないか、ぐらいの意気込みはほしいよね。こういう本が売れると、自分がおもしろいと思うものをつくっても売れないんじゃないかって、少し心配になってきちゃった。
ウォンバット:ツッコミどころが多すぎる作品! あとがきによると作者は漫画も描いてたそうで、『ビート・キッズⅡ』の扉の絵もみずから描いてるんだけど、この顔まるっきり吉田秋生のマネ。それで、主人公の名前が英二ときたら、もう『バナナフィッシュ』でしょ。とすると、七生はアッシュそのものやん。天才で美形で、冷酷なところがあって、家庭環境が複雑で、人に言いたくないダークな出生で……。初めにそう思っちゃったもんだから、もう意地悪な気持ちから挽回できなかった。この作品は、漫画のセリフからト書きから絵まで、全部を本の体裁で文章化して、物語のような形にしてるだけなんだよね。だから物語の楽しみである、「心を働かせる」スキってもんが、全然ないの。全部が全部この語り口で埋めつくされてて、空白がない。漫画だったら、きっとこの作品も嫌じゃないと思うんだけどな。文学に夢をもちすぎてるのかなあ、私。この文体だから、関東人にはなじみにくいってこともあるんだろうけど。こーゆーイントネーションで読まないと、ついていくのがたいへんだし、それがスムーズにできない私は、疎外感を感じてしまった。
モモンガ:私も、大阪弁って一字一句一所懸命読まないと入ってこないから、すごく疲れた。でも、日本の創作って最近はヒネこびたものが多い中で、明るくて元気の出る作品だと思った。変なうっとうしさがないのが、この本の特徴。でも、やっぱり登場人物はステレオタイプだし、中学生に薦めたときに、「おもしろかった!」とは言われるだろうけど、それ以上の感想は聞けないと思う。英二が語るという形式にしたことで、必要なこともむだなことも、べらべらべらべらしゃべってるって感じなんだけど、英二が憎めないキャラクターだから、「マ、いっか」と思わせられちゃうところが、成功のカギだと思う。ストーリーも、いきなり浪速節になったりするんだけど、それもすべてキャラで許せちゃう。
愁童:ケチをつけはじめればいろいろあるけど、最終的に今の子どもたちにはいい作品。標準語だったら、許せないと思うけど。ブラバンとかクラブ活動で癒されるってこともあるだろうし、一つの完結した楽しい世界を楽しめばいいんじゃない? 本好きになるためにはこういうプロセスも必要だと思って、まあ、こまかいこといわずに、楽しんでよ。
(2000年02月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)