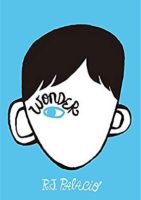高橋うらら/作
さ・え・ら書房
2024.09
フキダマリ: よかったです。自分の状況や境遇を分かり合える人がきっといるから、探して出会おう、という主張がとても伝わってきました。すごくミラクルな事例ではなくて、現実的な事例であることもよかったです。いい言葉だなぁ、と思うところもありました。たとえばp52「待っているのではなく、自らおもむくことが大事なんだよ」というところ。ただやっぱり、きょうだい児は大変で、その重苦しさも伝わってきました。
西山:親が、もちろん悪意もなくさらっと放った言葉が、言われた「きょうだい児」にはそういうふうに刻まれていたかというのは、これは、親の立場で読むとかなりきついだろうなと思いました。このノンフィクションは、ヤングケアラーにも光を当てるようになってきているフィクション作品に対する刺激にもなると思うので、児童文学作家も読んだ方がいいと思いました。
エーデルワイス:本を買うときは(注文も)なるべく地元の書店へ行きます。注文してもネット注文と変わらず1日で届くのですが、この本は出版の関係か2週間くらいかかりました。読書会に間に合ってよかったと思いました。「きょうだい児」という呼び方を初めてこの本で知りました。「ヤングケアラー」という言葉が定着したように、少しずつ生きやすい世の中になっているのだと思いました。ミュージカルの力、参加して生き生きしている姿は素敵です。作者も体験者で3例が具体的にあり共感できました。「二度とがまんしない!二度とあきらめない!」はいいですね。恋愛、結婚のことも書かれていますが、わかりやすく安心感を持ちました。
ハリネズミ:今回この本が読めてよかったとは思いました。特にp75にまとめてあるきょうだい児の抱える悩みなどは、なるほどそういうこともあるのか、と。ただあえて言えば、実名や写真を出してのノンフィクションだと、ここまでしか書けないんだろうな、とも思いました。たとえばフィクションだと、ずいぶん前に出た丘修三さんの『ぼくのお姉さん』を読んだとき、こんなふうに書ける作家がいるのだということに、私は衝撃を受けました。それに比べ、こういうノンフィクションだと、どうしても光の部分を描いていくことになるので、陰の部分、闇の部分には筆が及ばない。タイプが違う本なので、それでもいいのですが。ただ、人間を立体的に描くのが文学だとすると、やっぱりこういう本は、「こんなふうにがんばっている子どもがいるよ」「そういう子どもたちをこんなふうに支えている人たちがいるよ」「きょうだい児でも、こんなに活躍している人がいる。だからみんなも応援しよう」というメッセージを届けるだけになってしまうのでは? と思いました。
きなこみみ:障碍を持つきょうだいに、親の視線が偏ってしまったり、きょうだいに我慢や支援を求めてしまいがちだったり、親の大変さを理解するがゆえに、複雑な事情を抱えてしまったりすることを、穂乃果さんと結衣花さんという兄弟に取材しながらていねいに描いてあると思います。とくにp75 からの、きょうだい児の子どもたちがどんな悩みを抱えているのか、という一覧は、ああ、こんなにたくさんあるんだ、結婚や老後のことまで考えて、自分を縛ってしまうことがあるんだと改めて感じることでした。障碍者への社会的な援助は、まだまだ足りないのだと実感します。そのなかで、弁護士の藤木さんも、穂乃果さんも、同じ境遇の人たちと話し合ったり活動したりすることで、精神の安定や居場所を得ているんだなあと。誰かが犠牲になるのではなく、支援も含めたネットワークの広がり、安心して自分の人生を生きることを実現する社会を作ることを考えさせられます。そういう、社会のほうから、障碍を持つ子どものいる家庭をどう支援するか、という視点も、もう少しあるといいなと思いました。また、穂乃果さんが、歌と踊りにのせて自分の思いを伝えて心を解放していくのは、芸術活動が人間にとってどんなに大事なのかという証左だなと思います。
ツミ:きょうだい児にとっても、そうでない子どもにとっても、大切な本だと思いました。p121の、障碍者福祉を仕事としている方たちの国家資格が無いという事実は知らなかったので、ショックを受けました。後半に、おとなになったきょうだい児、藤木さん、志村さんの話があるのは、きょうだい児の子どもたちにとって、とても励みになると思います。ただ、ノンフィクションの文体について、ちょっと考えさせられました。主人公である穂乃果さんの話は事実として感動したけれど、「 」のなかの穂乃果さんの言葉がお利口さんすぎるというか⋯⋯。作者の言葉ではなく、実際に穂乃果さんから聞いた言葉で<穂乃果さんは「⋯⋯」と思ったといっています>というように、客観的に書くべきじゃないかな。そのほうが、取材の対象としたひとに対するリスペクトになるのでは?
雪割草:きょうだい児がどんな思いを抱えているのか知らなかったので、この作品を読むことができてよかったです。特に、演劇など芸術活動を通じて自分を表現できるようになっていくところがいいなと思いました。それから、藤木さんの話もおもしろく読みました。アメリカに研修に行った際に、ジムで障碍のある人が暗証番号を忘れてしまったとき、正しい番号をすぐに教えるのではなく、ヒントを出して自分で試すことができるようにするという「失敗する権利」の話は、ローズマリー・サトクリフの「傷つく権利」の話を思い出しました。確かにノンフィクションで描けることの限界はあるのだと思いますが、きょうだい児として穂乃果さんや作者がどんなに大変な思いしてきたのか、特に我慢してきたことなどはリアルに感じることができました。
しじみ71個分:大変、意義深い作品だと思って読みました。きょうだい児については、物語でしか触れてこなかったのですが、今回、ノンフィクションで読んでみて、いろいろ考えることがありました。高橋うららさんは視点の温かさを感じる作家さんで、ほかのノンフィクション作品でも良い印象を持っています。職場の選書でさまざまなノンフィクション作品を読みましたが、書き手の想いがないと、通り一遍の事実の羅列になったりして、のっぺらぼうな印象のままで終わってしまうこともありますが、この本は、きょうだい児の当事者に寄り添った温かな視点が感じられたので、読んでよかったと思います。p75の悩みのリストは、きょうだい児がこんなに心のうちで悩んでいるのかと思って、衝撃を受けました。リストなので、簡潔にまとめてあるけれど、その裏にはとても重い実体験があるのではないかと思わされました。そこにたくさんの事例が隠れているのでしょうけれど、個人情報の観点などから難しいのかもしれないですね。穂乃果さんの物語でも、自己犠牲を自分に強いるのではなく、自分の生きたいように生きていいんだよ、という応援メッセージに集約されているように思いました。なので、ほかのポイントについて、書き込みが薄くなってしまったのかなとも思いました。おとなになったきょうだい児の方々の紹介もあり、希望を与えるメッセージになっているように思います。また、高橋さん自身がきょうだい児ということで、学校費用の支払いが未了だった事実を伝えただけなのに、お父さんに叱られたというくだりは、胸が痛みました。これは1つの具体例ですが、この作品の後ろにはどれほどのつらいことや苦しいことがあったのかなと想像すると、ノンフィクションだとどうしても個人の生活に踏み込まないといけないと思いますし、それによって傷つく人もいるかもしれないので、もしかしたら、フィクションで描く方がやりやすいのかもしれないなと感じました。
さららん:「多様性を認めあう社会」の章のp123で、すでに出たように、アメリカでは障碍のある人が暗証番号を忘れてしまっても、周囲の人が手出しをしすぎず、「失敗する権利を、奪わなかった」という一節があります。、雪割草さん同様、私もそこで立ち止まり、障碍のある人を一人の人格として見る視点が自分にも欠けていたのではと、ハッとさせられました。きょうだい児として育った人が、作者も含めて何人か登場しますが、私は弁護士になった藤木さんの話が興味深く感じられました。「いいところは、ぜんぶお姉ちゃんがとっちゃったのね」という何気ない母親の言葉が、ナイフのように胸に突き刺さったのがよくわかり、その言葉で母親は藤木さんと弟の両方を傷つけたことに気が付いてほしいと思いました。この本の中で、「心魂プロジェクト」と出会って、舞台に立ち、自分を解放できるようになった穂乃果さんのエピソードが出てきます。個人的な話になりますが、私も舞台の立ち上げに協力したことがあり、おとなも子どもも障碍のある子もみんな参加できる舞台にしたくて募集をかけたところ、障碍のあるお姉さんが妹と一緒に参加してくれました。主催側の私たちは、ふたりなら安心、と単純に思っていたのですが、この本を読んで初めて、きょうだい児の苦労を知り、自分は何もわかっていなかったことが、今さらながら恥ずかしくなりました。
ニャニャンガ:高橋うららさんの作品は『風を切って走りたい! 夢をかなえるバリアフリー自転車』(金の星社)を読んだことがあります。本書はナイーブなテーマだと思いますが、作者自身が高度難聴のある妹さんがいる「元きょうだい児」であるから書けたのだろうと想像しました。我慢することも多かった方たちが前向きにとらえて昇華させるようすが描かれているので、きょうだい児として悩んでいる子どもたちの一助になればよいなと思いました。とくにp75にある事例に心当たりがある人が、必要なところにアクセスできればと思いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ハル(メール参加):なんというか、ちょっと語弊があるかもしれませんが、ああ、そうだったんだろうなという感じがあると言いますか、新たな発見はなかったのですけれど、共感できました。どんなときも「わかりあえるひとがいる」「ひとりじゃない」ことを知ることは、やっぱり大きな安心につながるんですね。そう考えると、このことに限らず、日本ももっと気軽にカウンセリングを受けられるように、カウンセリングの文化が根付くといいなと改めて思いました。問題が体や行動に発露する前から、誰かと話せるといいですよね。この本には登場しませんでしたが、反対に「きょうだい児」と呼ばれることに違和感を覚える人もいると思うんです。その人たちの気持ちも聞いてみたいなと思いました。
(2024年12月の「子どもの本で言いたい放題」より)





小-163x200.jpeg)