
せいのあつこ/著
PHP研究所
2017.04
まめじか:p7でカレンダーを机に置いて、「ノートだけ机に置くより、ずっとかわいい」というところでまず、「かわいい」という表現でいいのかなと思いました。宮子が大林くんの手紙にひとこと「小さい!」と書くのもそうですが、全体的に言葉足らずの印象です。p22で先生が宮子に学級委員の仕事を手伝わせるのも唐突だし、突然訪ねてきたクラスメイトを前に、大林くんのお母さんが平身低頭で謝るのも理解できなかった。人物像や行動が不自然で入りこめませんでした。「~だもの」「~よ」「~わね」というフェミニンな言葉づかいや「あの馬鹿」なんていうせりふも、小学校高学年の子どもにはそぐわない感じがします。また、小学6年生の子が友だちのことを思い描いたとき、「体は細くて胸はないけれど」(p 64)っていうふうになるでしょうか。文香のお母さんは不登校について「たくさん休むといろいろとめんどうなことになる」「なぜたくさん休んでいたのか、何度も説明しないといけなくなる」「役に立たない人間だと区別されるかもしれない」(p107)と言うのですが、あまりにも乱暴な説明にとまどいました。
シア:私も話に入りこめませんでした。テンポが全体的に緩慢で、どこか漫画的でした。そのせいで悪くするとギャグ寄りになってしまう場面もあって、私は卯沙ちゃんの言葉や態度などのちぐはぐさに失笑してしまうこともありました。どこをとってもドロドロしそうな展開なのにしていなくて、あっさりしています。これが現代的で、現代の小学生なのでしょうか? それなのに、先生はいつも役立たずのテンプレで描かれているので悲しいです。気になったのは、大林君のメールアドレスは了解を得て回しているのかというところ。このネットリテラシーはいただけません。それに、空いている席には誰が座ってもいいんですよね。単なる便宜上のもの。移動教室とかクラブ活動もありますし。すべてをていねいに使えばいいんです。マーキングしたい日本人の感覚だなと思いました。ウルフ・スタルクの本を先に読んだので、すべてが狭く感じました。日本的というべきなのでしょうか。最後にツッコミたいところがあって、p172「携帯を開き」とあるんですよね。スマホじゃないのかと。パカパカケータイなのかと。小学生だからなんですかね。
カピバラ:自分の本心を作文に書くことができない主人公の気持ちが正直につづられているから部分部分には共感する子もいるのかもしれませんが、物語としては一向に先に進まないのがもどかしかったです。結局、手紙もメールも書けないまま終わるという結末は中途半端で、大林くんが何を感じ、どうして学校へ来ないのかわからないし、物足りなさを感じました。宮子、中谷くん、卯沙の描き方ももう一つつっこんでほしかった。最初にクラス全員に大林君への手紙を書かせ、全員で家に届けるなんてこと、本当にやっている学校があるのでしょうか。私はここでまず引いてしまいました。大林君とお母さんの態度も後味が悪いです。歴史好きのお母さんとの会話は、おもしろくしようとしているのだろうけど、効果がないし、違和感がありました。
ハリネズミ:感想文や手紙でついつい思ってもいないことを書いてしまうことはあるし、文香が大林君の席にすわって考えてみるという展開はいいかもしれませんが、物語の流れから見て不自然なところが随所にあって、入り込めませんでした。たとえば、宮子がまわりを巻き込む押しの強い性格だとわかっているのに、文香が大林君のメアドを渡してしまうところとか、大林君の席にだれかが荷物をおいているのを見とがめて文香は自分が席にすわりつづけるわけですが、ほかの生徒が荷物をおくより、ほかの生徒がすわってしまうほうが大林君の存在を無視してしまうことになるような気もします。しかも文香はp129で中谷君が文香の席に座っているのを見ると、「他人(ひと)の席に平気で座るなんて」と文句のような言葉をつぶやくのは変。それと、最後の場面が唐突で、ただ情緒的な言葉でまとめたようで気持ちが悪かったです。物語世界がもう少しちゃんとつくってあれば、いい作品になったかもしれませんが。
マリンゴ:発売されて間もないころに、話題になっていたので読んだ記憶があります。そのときは、いい作品だけれどそんなに尾を引かないないなぁ、と思っていました。学校生活っていろんなことがあるけれど、物語があまりに「大林くん」と「手紙」に集約されている印象だったからです。今回、再読したときのほうが、おもしろく読めました。主人公は、ちょっとADD(注意欠陥障害)気味なのか、部屋の整理整頓ができない子で、周りの人はどうなのかあまり気にしていません。でも終盤、人の部屋はどうなのだろう、と関心を持つようになるなど、視野がゆっくり広がっていく感じがいいと思いました。ただ、これは好みの問題かもしれませんが、最終章の六章がまるごとなくていいのではないでしょうか。五章から、時がほとんど進んでないので、そこで終わっている方が、余韻を残したのではないかと思います。あるいは、六章を入れるなら、何カ月かあとに飛ぶとか、そのくらい話が展開したほうがいいような気がしました。
しじみ71個分:読んでなんだかイライラしてしまいました。学校のクラスのとらえ方が古くさいなぁと思いまして……。不登校の子に対してみんなで手紙を書くことを強制して、みんなで届けにいくなんて、ひと昔まえの教室運営ではないかなと……自分の子どものときの話を思い出してしまいました。先生に大林君へ手紙を書くことを強制されるのも不快でしたし、リーダー格の女子の宮子に強制させられるのも、読んでいて本当に嫌でした。宮子から「小さい」とか言われて、一方的に、こうあってほしい大林くん像を押しつけられるというのもいい迷惑だなと感じてしまい、物語の後半で宮子が少しいい子に見えてきた、という表現もあったのですが、ぜんぜんそのように寄り添った気持ちにはなれませんでした。唯一、共感できるとすれば、主人公の子が思ってないことを書けないというのは正直だと思ったことですが、その先の展開がなく、大林君の席に座って、大林君の椅子の傾きを感じ、彼が見ていたものを見る努力をするというのは、わかるような、わからないようなで……。断絶も含め、不在の人への思いや働きかけがあってこそ、読者の心が動く何かが生まれるのではないかと思いました。主人公の中で、不在の人への気持ちや思いがどう深まっていったのか、まったくわからなかったんです。大林くんが禁じられた屋上に上がって、しかられたけれど、なぜ一人だけ反省文を書けなかったのか、という点をきっかけにもっと大林君の物語を深められたのではないかと思うし、彼のお母さんが必要以上に自己肯定感が低いことにも背景があるはずなのに、それがまったく描かれていなくて、もやもやしたままです。結局、椅子に座ることも、手紙を書くことも、彼の気持ちには迫らず、自分たちの自己満足でしかないのではないかと思えてしまいました。『12歳で死んだあの子は』(西田俊也著 徳間書店 2019)にも感じたのですが、亡くなった子のお墓参りをすることに終始して、その人の不在が訴えかけてこなかった点に共通したものを感じ、思い出してしまいました。人の不在に対する心の動きがないと、物語が成立しないんじゃないのかなぁ……。
すあま:主人公は、感想文や反省文と同じように、手紙も嘘を書いていいと思って、きれいな文章の手紙を書く。先生がいいって言ったので正解だと思ったけれど、そのあとでほかの人の手紙を見て、ハッとする。手紙は相手に気持ちを伝えるものだから嘘ではだめだ、ということに気づいたことから物語が展開していくのだと思ったのですが、うまくいっていないように思いました。共感できる登場人物がいないことや細かい描写がちょっとうるさく感じられることなどで、読みづらく感じました。会話の間に頭の中で考えていることが入っているのもわかりにくかったです。登場する大人である先生や親がきちんと描かれていない大人不在の物語で、今回読んだスタルクの本とは対照的でした。あまりおもしろさが感じられませんでした。
サークルK:p47で「いつかちゃんとした手紙」を書く、と書いた文香の「最後の手紙」がp170で「板、ぴったりでした!」で落ちがつく、という展開に肩すかしをくった、というか愕然としてしまいました。もうちょっと、何か言葉はないのかな。ショートメールなどのやり取りになれているイマドキの子どもたちは、短ければ短い方が心に響くと思っているのかしら、ととまどいました。そしてこの物語が今を生きる小学校高学年の子どもたちに「あるある、だよね」という形で受け入れられているのだとしたら、小学校の現場の寒々しさというか、子どもたちがとても気を使って毎日を送っている息苦しさを思ってつらくなりました。これからを生きる子どもたちがもっと言葉を豊かに紡ぐことができるようになってほしいなあ、と願いながら読みつづけるしかありませんでした。
ハル:今、サークルKさんの意見を聞いて、ハッとしたのですが、確かに私はこの本を、今の子がどう読むかという視点では読めていなかったです。それに、2017年の刊行から少し時間が経っていますので、もしかしたら当時は画期的なテーマだったのかも知れず、あくまで2021年11月現在の感想になってしまうことも、考慮しなければいけないとも思います。そう先に断りつつも、これはいったい、いつの時代の、誰の話なんだと思うような、アップデートされていない感じが、私は受け入れられませんでした。仮にこれがノンフィクションだったとして、すべてが実際にあったことだったとしても、それを描き出して「大人ってほんといやよね」「先生って全然わかってないよね」「同調圧力、ほんといやね」で終わるのではなく、じゃあどう変えていこう、どうしたら未来が変わるだろう、というところまで感じさせてほしかったです。ただ、不登校になる理由が明確でないというのは、現実の世界でも往々にしてあることだとは思います。
ネズミ:正直な気持ちを書けない主人公というテーマはいいなあと思いましたが、物語は残念ながらあまり楽しめませんでした。p15で大林くんのお母さんが、パート先で自分の息子が学校であったことを話すところで、こんなことあるのかなと思ってしまって。不登校のことが、p108で「学校に行かないのはとんでもないことらしいのはわかった」と書かれたあと、それ以上に深まらないのも、物足りませんでした。閉塞的な息苦しさを超える、新たな気づきや共感がもっとあったらと思いました。
ニャニャンガ:主人公の文香が嘘を書きたくないという点には共感しましたが、全体的にどうかといえば共感できませんでした。気になったのは、大林くんが不登校になった本当の理由が明かされない点です。また、担任の先生の行動が怖かったです。立ち入り禁止のところに入ったくらいで反省文を書かされ、学校に行かなくなった大林くんの心の傷を理解しているのだろうかと思うほど、子どもたちに無言の圧力をかけ、無神経な行動をとるなど既視感がありました。クラスのみんなで不登校の生徒に手紙を書くとか、宮子を教師の「使える子」として学級運営をしているのは、わが子が小学生だったときと重なったのでリアルだと思います。でも、大林くんのお母さんは謝りすぎ、文香のお母さんはマイペース、友だちの卯沙はふわっとしているようでしっかりしているなど、マンガのようにキャラ立てしようとしているのかなと感じました。
さららん:この作者は言葉にすると壊れてしまう感覚を、書こうとしたのかなあと思いました。主人公は、最後まで手紙を書かず、読者としてはもどかしい感じ。そして大林くんの気持ちが主人公に少し伝わるのは、親友を通しての伝言と間接的なメールの画面だけ。主人公は大林君の席にすわって、その気持ちを想像する毎日なのですが、そんな主人公を大林くんはちょっと意識していて、最後のほうで「板」をくれます。椅子の傾きを調整するために。関係性に踏みこまないで人物を描いているから劇的な展開もなく、開けられた容器に、読者が「大林君はどう感じているんだろう」「どんな子なんだろう」「なぜ学校を休んでいるんだろう?」と自分の想像で埋めるほかない物語でした。そこには空白があって、書きこみが足りないといえばそれまでなんだけれど、今の子どもたちの感覚に通じる部分があるのかも……そういう意味では現代的なんでしょうか? 友だち同士のコミュニケーションが取れているような、いないような関係は理解できませんが、代わりに物の手触りをていねいに書いている点がおもしろかったです。
アンヌ:読みながら、事件と事件との間に物語としてのつながりがなく、読者が詩や和歌を読むときのように、間を埋めながら読んでいく作品のような気がしていました。実に繊細な感じで。だから、具体的なイメージがうまくわいてこない部分も多く、ハンカチが選べなくて2枚差し出す意味とかは、うまく読み取れませんでした。手紙を書き直すというのはわかるのですが、やっと本当の手紙が書けたのに、それを出す前に中谷君と大林君とのメールのやり取りが始まってしまうという第六章は、先ほどマリンゴさんからもご指摘があったのですが、時間の経過が速すぎる気がして奇妙な感じがしました。歴史おたくの文香の母親は、ユーモアとして描かれているのでしょうが、p107で不登校について「何度も説明しなければいけなくなる」は親の立場の説明だとしても、「役に立たない人間として区別される」という発言をするのには疑問を持ちました。
ルパン:私は今回の選書係だったのですが、この本はある意味傑作だと思って選びました。たしかに小学生としてはおとなびた感があり、中学が舞台のほうがよかったなと思いますが、ものすごくリアリティを感じます。みんな、もやもやしていて、方向性なんてないんですよ。定着して方向がつけられた学校制度の中に閉じこめられた子どもたちの現実です。そして大人たちの現実でもある。子どもが不登校になって、どうしたらいいかわからない自信のない親。自分がどうして学校に行かれなく(行かなく)なったのか自分でもわからない子ども。感想文や手紙を書けと言われてどうしたらいいかわからない友だち。旧態依然の価値観をもち、マニュアルに頼る自信のない(あるいはありすぎる)先生たち。この中の登場人物に似た人たち、私のまわりにはたくさんいます。物語の中で不登校の理由がはっきりしたり、それを解決できる大人がいたりしたら、そっちのほうがよっぽど非現実的です。「個人の自由」や「個性の大切さ」を声高に言いながら、足並みをそろえることを強いる「学校」という社会の中でみんな困っている、という現実をあぶり出した作品だと思っています。みんなが先生に言われて書いた手紙の中で、大林君は主人公の手紙だけに反応した。それを知った主人公は何か自分ができることはないかと模索した。ここで二人はちゃんと繋がりました。答えがなくてもいいじゃないですか。りっぱな大人が出てきて解決しなくてもいいじゃないですか。現実ではむしろそんな大人が都合よく出てきてくれることのほうが少ない。この主人公は何もしなかったわけでも何もできなかったわけでもない。私は「理想の大人や理想の子どもが描けていない」と思う人こそ「大人目線」なのだと思います。もやもやして困っている子どもたちはきっと共感し、「こんな自分でも、できることをさがしていいのかもしれない」と一歩、いや、半歩でも踏み出せるかな、と背中を押されるはず。文章の細かいところで課題はあるかもしれませんが、今回はそういう理由で選びました。
(2021年10月の「子どもの本で言いたい放題」より)











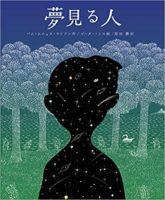




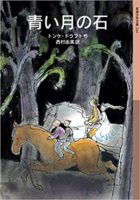
-147x200.jpg)













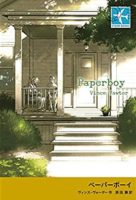
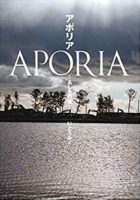
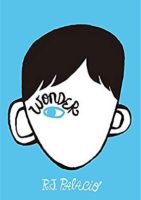


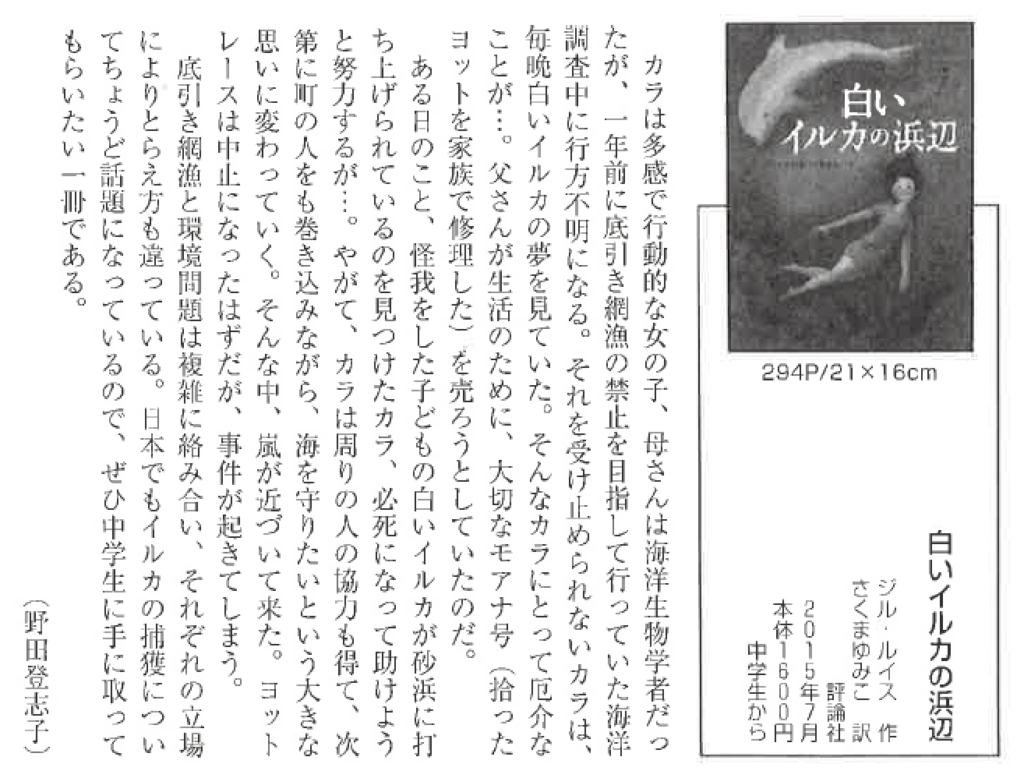



















-147x200.jpg)