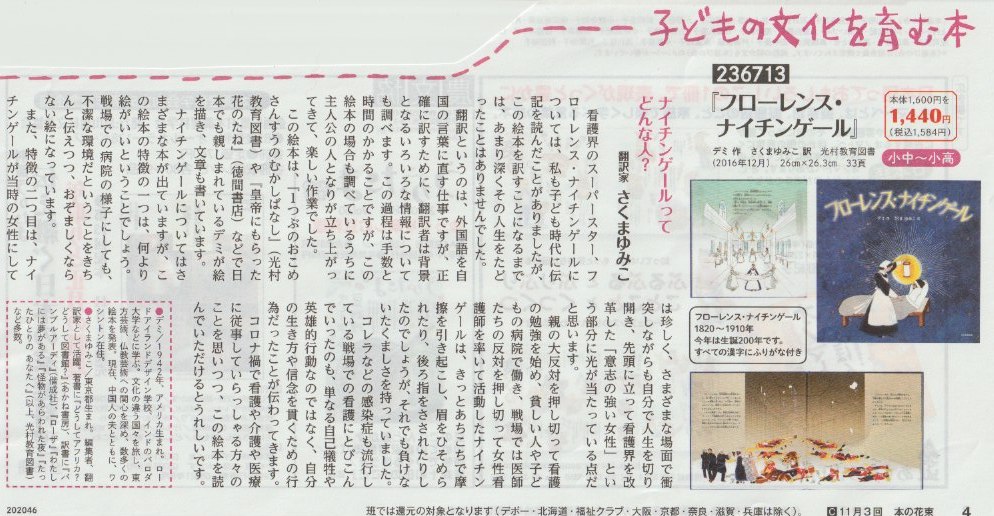中脇初枝/作
講談社
2023.08
(『伝言』を課題本とする際に、子どもの本を前提としたこの読書会で取り上げるかどうか、同じ中脇さんの著書である『世界の果てのこどもたち』とどこが違うのか、という議論がありました。そのことについての発言があります)
オカピ:主人公のひろみは戦後、生まれ育ってふるさとだと思って暮らしていた満州が、実は自分の国ではなかったと知って愕然とします。李太々の愛情を無自覚にうけていたことの重みを感じるところなども、強く胸にせまりました。現代の日本の組織的な暴力の構造まで描いているのも、すばらしいと思います。こういう力のある作品が、YAでも描かれるといいですね。
wind24 : 戦争の前後に、満州国で何が行われていたのか詳しく知らないままでしたが、この本を読んで衝撃を受けました。満州事変も七三一部隊も言葉では知っていたのですが、日本が戦争加害国として何を行っていたか、何を行おうとしていたかに今更ながら恐ろしさを覚えます。子どもの視点で描かれてはいるんですが、おとなも含め登場人物たちがうまく絡みあい話が構成されているので、一気にひきつけられるように読めました。満州国に渡った人には2種類あって、満州で仕事も地位もあって使用人も使えるような人と、貧しい農村から開拓を目的に入った人たちがいます。長野県からは後者の貧しい農村からの人たちが多く渡り、その厳しい生活を伝える満蒙開拓団の資料館があります。戦争が激しくなり日本が劣勢になるにつれ、子どもたちが秘密の軍事兵器を作らされる様子は生々しいものでした。戦争が子どもたちの日常をいとも簡単に奪ってしまうのを改めて思いました。そして現地の中国人たちが日本人にどれだけ搾取され苦しい生活を強いられたかを日本人はもっと知らないといけないと思いました。
ANNE:中脇初枝さんは『きみはいい子』(ポプラ社)以来とても気になっている作家さんです。この物語は、満州国で女学生となった主人公の生活を中心に、当時の日本人の心情がありありと描かれていますが、風船爆弾や七三一部隊のエピソードもあって、大変苦しい気持ちで読みました。図書館には、戦争関連のレファレンスも多く寄せられますが、負の歴史の資料は多くなく、苦慮するところです。歴史は歴史として、きちんと後世に残していくことが必要だと改めて感じました。
雪割草:私の祖母は満州から引き揚げてきたのですが、だれにもその体験を話そうとせず、満州を思い出すからニンニクの匂いが嫌いで、料理するときに使おうとしなかったというのはおぼえています。満州の本を読むと、いつもそんな祖母のことを思い出します。この作品はとても切なかったけれども、とてもよかったです。ひろみは終戦を迎え、満人と立場が逆転し、同じことをされてはじめて気がつきます。いろんな人の視点で語られることで、戦争を記憶するときに、相手の立場に立って考えることの大切さを伝えていると思います。それから、ひろみたちがいったん満州から逃げようとしたけど失敗して、再びもどってきたときに、李さん家族がよく帰ってきたと喜ぶ場面に、とても胸を打たれました。ひろみは、日本人と満人という違いを超えて、同じ人間同士としてのあたたかな交わりを経験していたからこそ、日本が満州でしていたことを知ったときに、深い深い心の傷となったのだと思います。戦争がつくり出す無知の怖さにも気付かされました。子どもの本かどうかはさておき、子どもにも伝えたい、読んでもらいたい作品だと思いました。
ハル:これを小説として書き上げる勇気を感じ、憧れるというか、すごいなぁと思いました。ラストが今も胸に迫ります。はるみが40年後に長春を訪れたときに、自分が満州で使っていた言葉が、侵略者としての中国語だったと気づいてしまって、「それからずっと、わたしは中国語を口にしていない」(p295)というところ。無邪気で、何も知らなくて、あたたかく幸せなはずの思い出さえも、「なつかしいなんて、日本人のわたしが思ってはいけないのに」(p295)というところが、切ないを通り越して苦しかったです。結局戦争は、人と人が心を通いあわせても、国と国とで断絶されてしまうものなんだということを感じました。
ところで、この本が「子どもの本じゃないからどう」ということではないですが、「子どもの本」であるかどうかは、ひとつには、作者が子ども向けに書いているかどうかという点によるんじゃないかと思います。この『伝言』は子ども向けに書いた本ではないでしょうし、出版されている本にもルビはありません。また、ルビがあるから子どもの本だということではなくて、表現や内容も、どの年代のひとに向けるのかというのは、それ相応の違いがあるということかなと思います。
オカピ:同じ作者による『世界の果てのこどもたち』(講談社)も一般書として出ていますが、子ども時代の記憶が、物語の中で大きな意味をもっています。「子どもの視点で描かれているもの」「子どもに向けて書かれているもの」が、児童文学だと思いますが、線を引いて大人の本と分けることはできるのでしょうか。
きなこみみ:子どもの本とおとなの本の間に明確に線を引けるのかという問題もありますね。
オカピ:出版社が一般書として出しても、図書館などで、児童書に分類されることもあります。
ハリネズミ:おとなの本を中学生が読むとか、受け取る側はそれぞれで構わないけど、出版する側は、年齢対象をきちんと考えたうえで出していると思います。そう考えるとこの本は児童書とは言えないですね。内容的にも中学生でも読むのは難しいと思います。
ルパン:私は完全に一般書だと思って読みました。けれども、この内容を子どもたちや若い人に伝えたいということは強く思います。このことを子ども向けに書いたものがあったらいいなと思います。
西山:今日は、この作品が『世界の果てのこどもたち』とどう違うのか、違わないのか、テキストに名前が挙がったときの賛否の闘い(笑)を高みの見物しようと思って、以前読んだきりで再読もせず参加しています。子どもの読書力もそれぞれですから、子どもが読むかどうかで分類することはできませんよね。結局、作り手がどっち向きに出しているかということで。『世界の果てのこどもたち』と『伝言』の違いは、いま具体的に語られたので、そうだなと納得しています。この読書会の選書の約束事として、どうするかという問題ですね。ところで、私の父は満州生まれで、母方のおばたちも満州で働いていました。繰り返し聞いた話もありますが、なかなか突っこんで聞けなくて、高齢のおばたちに戦中の話をしてもらうのは、どうしても及び腰になってしまって反省しています。101歳になるおばに、最近満州が舞台の小説を読んだと話を向けたとき、「ターチョ」とか「マーチョ」とか食べものなど、『伝言』の中の名詞や、風景が出てきて、中脇さんがこういう風に書いてくれることで、当時の満州の様子を生き生きと知ることができるのはありがたいと思います。
ハリネズミ:私は読んでよかった作品だと思ったし、風船爆弾を満州でも作ろうとしていたのを知ってびっくりしました。また上に従う風潮が強いなかで、じんちゃんという存在を出してきたところに作者の意志を感じました。でも、この本は明らかにおとな向けの本ですよね。『世界の果ての子どもたち』とこの本の違いは、『世界〜』の方は主人公たちが最初に登場するのが子ども時代で、それが徐々に歳を重ねていく。でもこの本では主人公の﨑山ひろみが最初に登場する時点ですでに敷島高女の女学生になっていて、ほかの主な登場人物もみんなおとなです。それから『世界の果ての子どもたち』は、どの子も数奇な運命をたどるのでそのドラマを追っていくのも子どもにはおもしろいのですが、『伝言』は風船爆弾を作っても役に立たなかったという話なので、おもしろさが少ない。ルビも少ない(「世界〜」の方は満州にもルビが振ってありましたが、こちらは当用漢字でも振ってないのがあります)。物語にアクションが少ない、という点も言えると思います。
風船爆弾については、『ぼくは風船爆弾』(高橋光子著 潮出版社)という、実際に少女時代に作製に携わった方が書いた児童書がありますし、小林エリカさんも『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋)という本を書いています。
きなこみみ:満州で、あのときに何が行われていたのか、その暗部に切り込んでいく中脇さんのまなざしに打たれました。女学生のひろみを軸に、複数の視点があることで、当時の満州が浮かび上がってきます。YAとして読むなら、ひろみを主人公にした部分に反応するべきなんですが、私はそう読めませんでした。この物語の中で私がいちばん惹かれたのはひろみをかわいがった、中国人の李太太(リータイタイ)であり、この物語を貫く鍵になる人は、やはり彼女だったと思うのです。地に足をつけて生き抜く力を持つ体のなかに、実はとても繊細な憧れや、熱い愛情の炎を持っていた人で、その愛情ゆえに、日本と中国の板挟みになって、生きるのがつらくなって、アヘンにおぼれてしまった人だったんですよね。そして、そのアヘンは日本が戦略として流布させていたものだということを考えると、まさに構造的な暴力が弱者を踏みつぶしていくということを、彼女は体現していると思うんです。
第七章で、老いたひろみが再び語る過去と今が、非常に読み応えがあるんですけれど、孫のあかりが受ける現代の日本でのパワハラが、ひろみの経験した満州での過去と対比になっているんですね。満州へ、アジアへ侵略していったことの加害責任を直視せずにごまかし続けている限り、日本社会の芯のようなものが、本質的に変わらない、変われないのだということがよくわかる、そういう構成で書かれていることに、深く頷きました。児童文学で、満州のことを書くのは非常に難しいと思うのですが、あまんきみこさんが、幼い頃に満州に住んでいたことを、加害責任を含めて忘れられずにいて作品を書かれたこと、三木卓さんが、満州に生きたことを原体験にして『ほろびた国の旅』(盛光社)という、これからも読み継ぎたい作品を書かれたことを思うと、これは何とかして子どもたちに伝えていかなければならない、非常に大切なこと、難しいけれど重要なことだと思います。『ほろびた国の旅』は、2009年に新装版が出ているのですが、今、図書館以外では手に入りにくくなっています。残念です。
エーデルワイス:重いテーマですが、読む機会をいただいて感謝しています。満州から戦争を経て日本の高知に至るまでの構成、登場人物の心象が見事です。李太太がとても印象に残っています。当時としては大柄な女性、纏足をせずに一生懸命に働いて、日本に組したと中国社会で石を投げられ、病んで阿片中毒になってしまいます。かわいがっていた、洋子とひろみ姉妹のために靴を作りますが完成することがなかった。鮮やかな色の花の刺繍が目に浮かびます。その作りかけの靴はどうなったのでしょう? 李太太は無事に生き延びたのでしょうか? 満州国建国13年、1945年のその街や生活は近代的で豊かだったことに驚きです。人間描写、心理描写はすばらしくて読み応えがありました。児童書か一般書かと考えると、様々な登場人物の心理を読み取らなければならないこの本は一般書と思いました。
コガモ:私は選書係だったので、すんなりと決まった『紫禁城の秘密のともだち』のほかのもう1冊と思いましたが、悩んだあげく雪割草さんとオカピさんに相談したところ、この本を推薦されて読みました。最初は児童書とばかり思っていました。私の義母は満州で生まれ育ち、主人公と同じように有名な女学校に通い、のちに結婚し、敗戦後は夫婦と子ども3人の一家で過酷な体験をしながら引き揚げてきましたが、生前、毎日のように聞かされてきた義母の話を思いだしながら読みました。作品では、敗戦後、関東軍と満鉄の社員がいち早く逃げてしまったと書いてありますが、夫が満鉄の社員だった義母の話によると、部下を置いて安全なうちに逃げ出したのは学閥で結ばれたお偉方ばかりで、中間管理職だった義父は、自分の家族だけでなく部下の心配もしなければならなかったとか。そういう細かい点では気になるところがありましたが。ちなみに義父は満州のことを決して話そうとはしませんでした。児童書ではないと気づいたのは、途中から七三一部隊の兵隊の視点に変わったときです。これは中高生が読むには難しいのではと思い、あわてて巻末の記述を読んで「小説現代」に連載されていたものだとわかりました。それで、「怯む」などの難しい漢字にルビがなかったのも合点がいきました。それでも、課題本にしたいと思ったのには、2つ理由があります。
1つ目の理由は、児童書でなくても読解力のある中高生には薦めてもいいのではないかと思ったから。2つ目は、加害としての戦争というか、戦争の加害性を児童書にどう書いていけばよいか考えたいと思ったからです。子どもは加害者になりえないと考えれば児童書で描けるのは、被害としての戦争だけ。じっさい、小学校の教科書であまんきみこさんの『ちいちゃんのかげおくり』(あかね書房)や今西祐行さんの『一つの花』(ポプラ社)を読んだ方はとても多いと思います。どちらも優れた作品なので、長いあいだ取りあげられてきたのでしょうし、それを否定している訳ではありませんが……。
わたしは戦争中に生まれ、物心ついたときには戦争が終わっていたギリギリの戦中派ですが、当時の小学校の教科書には戦争に関する物語は載っていなかったと記憶しています。子どもたちは実際に体験していたし、体験しないまでも周囲のおとなたちに聞いて知っていましたからね。1年生か2年生の国語の教科書に載っていたのは、今でも出版されている浜田廣介作『むくどりのゆめ』でした。栗の木の巣穴に暮らすムクドリの父子の話で、子どもは母鳥が亡くなっているのを知らされておらず、巣穴の外の栗の枯葉がカサコソというたびに、お母さんが帰ってきたかと思う、それは悲しいお話で、クラスの女の子たちは「悲しいね」といいながら、大好きだといっていました。その「悲しいね」と、「ちいちゃん」や「ひとつだけ」を読んだ子どもたちが感じるであろう「悲しいね」は、どこが違うのだろうと、ついつい考えてしまいます。そのまま、あまり本を読まなくなっておとなになったら、戦争の加害性を考えないままになってしまう……。もっと悪ければ、そういうのは自虐史観だと思うようになったりして……。
戦争の加害性を考えさせる作品としては、中国と日本の両面から戦争を描いた乙骨淑子さんの『ぴいちゃあしゃん』(理論社)や、自分自身の体験から満州を描いた三木卓さんの『ほろびた国の旅』がありますが、いずれもかなり昔に書かれたものですよね。海外の作品にはウェストールの『弟の戦争』(徳間書店)とか、モーパーゴの短編「カルロスへ」(『だれも寝てはならぬ』所収 ダイヤモンド社)とか……。今の日本の作家は、そういった作品を書いているのでしょうか?
西山:日本の加害を書いた作品といえば、七三一部隊を取り上げた松谷みよ子『屋根裏部屋の秘密』(偕成社)がいちばんに思い浮かびます。日本児童文学者協会で作った「文学のピースウォーク」シリーズ中の、今関信子『大久野島からのバトン』(新日本出版)は広島の毒ガス兵器作りに携わった人の被害者でもあり、加害者でもある面を書いています。同シリーズの高橋うらら『幽霊少年シャン』(新日本出版社)は、おっちょこちょいな幽霊少年を出すコミカルな作りながら、個人として親切な振るまいと植民地支配している構造的な暴力を書き出しています。あと岡崎ひでたかの『トンヤンクイがやってきた』(新日本出版)、森越智子のノンフィクション『生きる〜劉連仁の物語』(童心社)とか。
あと、ついでに言っちゃっていいですか? この夏神戸で開かれたアジア児童文学大会で発表された中国の作家湯湯(タンタン)さんのお話がとても興味深くて、遅まきながら「トゥートゥルとふしぎな友だち」(髙野素子訳 平澤朋子絵 あかね書房)シリーズの3冊を読んだんです。中国の少し昔風の村の少女が主人公の切なさや怖さのある不思議の世界で、とてもおもしろかったので、お薦めしておきます。
ハリネズミ:無意識の加害ということでいうと、『ぼくの心は炎に焼かれる』(ビヴァリー・ナイドゥ著 野沢佳織訳 徳間書店)もおもしろかったです。
(2024年09月の「子どもの本で言いたい放題」より)














-138x200.jpeg)