
| 日付 | 2002年7月25日 |
| 参加者 | ペガサス、アカシア、トチ、すあま、紙魚、羊、アサギ、ねむりねずみ |
| テーマ | ノンフィクション |
読んだ本:

原題:FREMTIDEN by Eirik Newth,1999
アイリック・ニュート/作 猪苗代英徳/訳
NHK出版
2001
ソデ語録:人口爆発、環境汚染、食糧不足によって、人間は近い将来絶滅する。そんな予測もいまや無謀な考えではない。現代人は、地球の未来に責任がある。科学は未来を救うことができるだろうか? 大きな可能性を秘めた科学の力を正しく発展させて、環境を保護し、美しい地球を未来に残すことが、現代人の使命だ。その使い方を誤れば、一挙に地球滅亡へと進むことも考えられる。ミクロの科学技術から宇宙開発まで、現代の最先端科学をわかりやすく解説し、これからの人間の生活がどうなるのか、あらゆる可能性を探ってみる。子どもが読んでも、おとなが読んでも、楽しくためになる科学読みもの。

千石正一/文・写真
集英社
2000
著者のはじめの言葉:爬虫類だの両生類は無表情で何を考えているんだかわからない、とよくいわれる。しかし無口だがこれらの動物もしゃべらないわけではない。ずっとじっくりつき合っているとときおり話している現場に出くわすことがある。これはそういう現場を集めてみて、人間のことばに翻訳してみたものである。

原題:LE LIVRE DE NEMO by Nicole Bacharan & Dominique Simonnet,1997
ニコル・バシャラン&ドミニク・シモネ/作 永田千奈/訳
角川春樹事務所
2000
ソデ語録:ネモは、あなたたちの兄弟のような存在です。この不思議な星で、少しでも人間らしく生きるために大切なことを、あなたたちに伝えたくてこの本を書きました。——ニコル&ドミニク
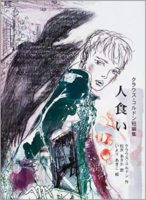


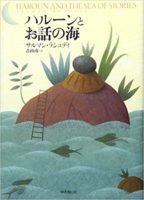






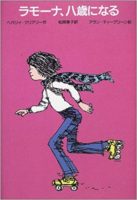
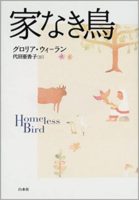

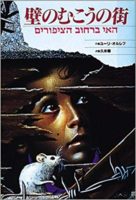
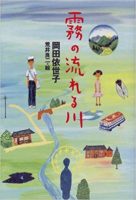


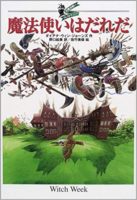
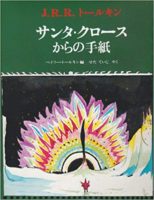
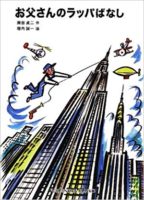
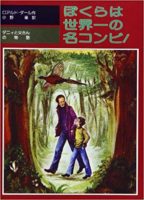

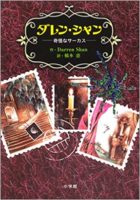
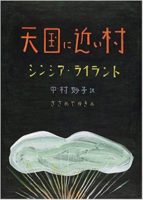
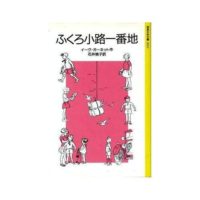
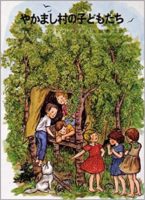
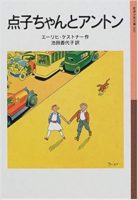
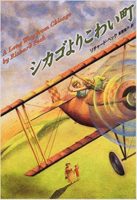
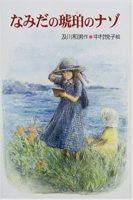

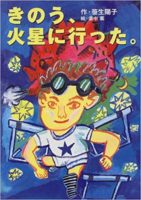

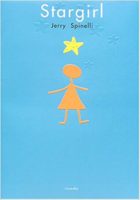
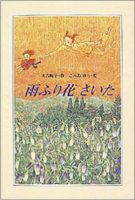

-142x200.jpg)