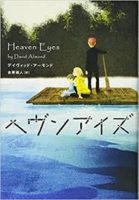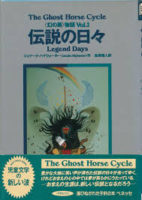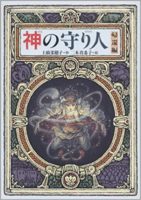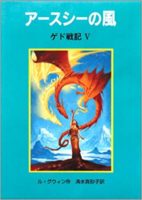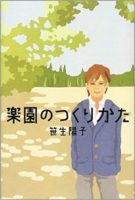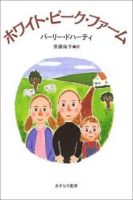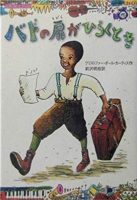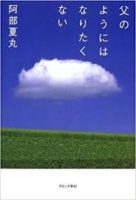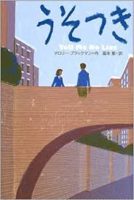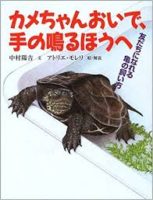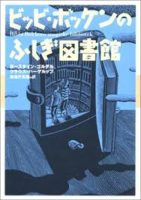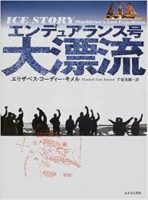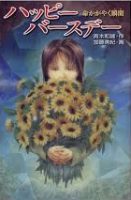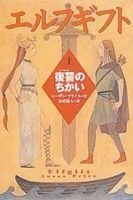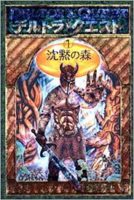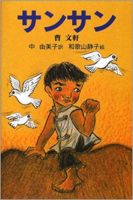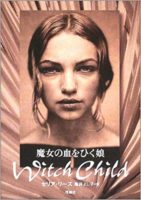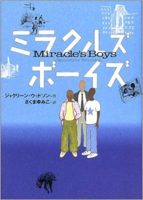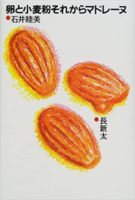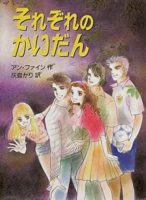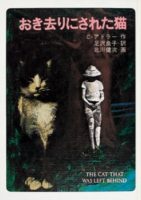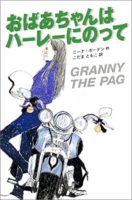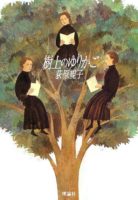金城一紀/作
講談社
むう:おもしろかったです。すごい勢いで読んでしまったので、うまく感想がまとまらないけれど。この作家がコリアン・ジャパニーズだからこそ書けたと言うか、読み終わってまず、まいったなあと思いました。同じようなことでも、日本人が書いたら違っちゃうだろうし。差別される側に生まれついた人の作品だからこそ、存在自体で差別されるということが実感として読み手に迫ってくる。私はわりと社会問題には関心があるつもりなのだけれど、英語の本を読む関係もあって、黒人の差別のほうが目配りしやすく、在日の問題などは逆に知らないんですよね。でもその差別の重たさをぐいっとはねかえしていく力強さが気持ちよくて、そこが他の作品と違うように思いました。ドラマというのはどうしても矛盾のあるところに発生しやすいわけだけれど、そのドラマを、怨念とかによりかからず書いているところが、とても気持ちよかった。主人公が桜井と知り合ってから後は、「在日」であることをどうするんだろうというのに引っぱられて一気に読めたというのもあります。在日の人って韓国人としても認められない部分があるんですよね。アイデンティティの問題はほんとうに大変なんだろうなと思うけれど、この本にはそういう安易な同情をスカッとはね返すパワーがある。後味のいい作品だからこそ、逆に読者も読んだ後でそういう社会的なことまで考える気持ちになれそうな気がする。ともかく、「国家権力」という言葉が浮かずに日常におさまってしまう状況というのはすごいと思った。
羊:私は、この作品が直木賞とる前に、なんかのきっかけで読んだのね。これは情景描写がなくて、この男の子の感情のうねりだけで進んでいくのに、重くない。濃い内容なのに気分よく読めた作品。だから、直木賞をとったときはうれしかった。
トチ:本を読む前に映画の批評をどっさり読んでいたので、いまさら読んでも新鮮味がないかなと思ったのですが、どうしてどうしてとても面白かった。第一に主人公の両親をはじめ、登場人物のキャラが立ってるっていうのかしら、おもしろかった。実際に「在日」の友だちもいるし、「在日」の人と結婚した友だちもいるので、なんとなくわかったつもりになっていたけれど、知らないことがどっさりあってショックでした。ただ、私の好みとしては、最後に桜井とまた仲良くならなくてもよかったのに、と思いました。なんとなく、ここらへんが直木賞的。よりをもどさないほうが、すがすがしかったのでは?
紙魚:もうずいぶん前に出た本だし、映画化されたりして、読んでいなくてもあらすじをご存知の方もいると思うのですが、今回わざわざこの本を選んだのは、「これがカッコいい」という新しいイメージを強烈に打ち出した作品だからです。刊行時読んだとき、おもしろかったし衝撃的でしたが、今回読み直してみても、やっぱりよかったです。差別について考えましょうという姿勢じゃなくて、がつんと若者に伝わる文体、物語だったことが、よかったんだと思います。今、何をしたいのかとか、どういう大人になりたいのかっていう像が見えにくいと思うのですが、こういう新しい感じ方とか考え方が「カッコいい」んだというのが伝わってくるのって、すばらしい。若者には重要なポイントだと思う。なんだか小説に世界を変える力があるんじゃないかと感じられる。
むう:この主人公のように「在日朝鮮人」として民族学校で育つと、ときには20歳くらいでも日本語が拙いままといった人も出てくるんですよね。実際知り合いにそういう人がいたんですが。それってすごく堅い殻に閉じこもっている姿勢にも取れるけれど、そうさせるだけの差別が日本にはある。ところがこの本では厳しく差別されているという被害者意識をふりかざしてない。あくまでポジティブだから、在日ではない人、それほど社会問題に対する意識の強くない人の心にも迫ってくるんだと思う。
ペガサス:装丁の感じや映画の宣伝などから、もっとずっと熱い話だと思ってたのね。でも、ものすごく真面目で、第一印象とは違った。おもしろかったんだけど、青春小説としては、もっとユーモアがあってもいいかなと思った。リアルなところとしては、はじめて会った人と、会話をかわすわけでもないのに、空気感を感じる様子がうまく伝わってくると思った。どのシーンも印象に残るので、映画になるのもわかる。ジョンイルが死んでしまうところなんかも、三人称を使ってうまい書き方だと思った。
アカシア:私は、おもしろかった。何年か前に、アフリカ人や韓国人の文学者と「在日」の文学者が集まってシンポジウムがあったのを聞きにいったんです。アフリカの作家たちは、多くの場合母語で作品を発表することができなくて、英語やフランス語など旧宗主国の言葉で書いてるんですね。だから不自由は不自由なんだけど、自分たちの英語、自分たちのフランス語で書けば、そこら辺のへなちょこイギリス人作家やフランス人作家が書いたものよりもっと面白いものができるっていう、いわば開き直りの誇りみたいなのがある。でも「在日」の人はなかなかそういうふうに思い切ることはできないらしいし、そこに来ていた韓国の作家たちも、まず「怨」を語っていた。差別されてきた歴史を初めに言う。日本人があまりにも無知だから、そこを言わないと共通の基盤で理解しあえないからなんでしょうけど。学校で昭和史をちゃんと教えないと、日本人は国際人になんてなれっこないな、と思いましたね。でも、今の日本の若い人たちが「怨」の文学をつきつけられても、何のことやらわからないでしょうから、『GO』のような作品はありがたいな、と思いました。でも、もしかしたら、そのシンポジウムに出てた作家たちからは、金城さんも「差別への闘い」がないって批判されたりするんでしょうか?
気がついたんですけど、金城さんは、〈在日〉〈韓国人〉〈在日朝鮮人〉〈在日韓国人〉〈韓国系アメリカ人〉っていうふうに、全部カッコをつけてますね。普通の言い方では人間の本質は語れないっていう意識があるんでしょうね。日本人の女の子である桜井は、「在日」だろうとなんだろうと杉原の「その目」に惹かれているっていう設定がリアル。それから、今の日本の男の子って、どう生きたらいいかわからなくて大変だと思うんですけど、『池袋ウエスト・ゲートパーク』(石田衣良著 文芸春秋)や『GO』は、一つのロール・モデルを提供してるような気がします。ただね、どちらもちょっとマッチョ系のかっこよさだけど。
もう一つ、私は文章にユーモアがあると思いましたね。タワケ先輩のあだ名の由来とか、「ノルウェイ人になることにした」とか、「マルクスの悪口は言うな。あいつはいい奴なんだよ」とか、フフフって笑っちゃった。
ペガサス:まじめに書いてるところが逆におもしろいという感じはあったけど、私は表現におもしろいところが少ないと思ったの。お父さんのおもしろさが、映画の山崎努とは全然ちがうと思った。
トチ:窪塚もこの本の主人公とはイメージが違うわね。
アカシア:どうして『GO』という書名なんだろうと最初は思ったんですけど、読んでいるうちにわかってきました。作品のなかに「行く」という言葉が大きな意味をもつ箇所が4つくらいあった。最初は暴走族とにらみ合ったとき、タワケ先輩に「行け」と言われて独りでつっこみ、ボコボコにされるところ。そしたらタワケ先輩には「本当に行く奴があるかよ。おまえ、クルパーだな」って言われるんだけどね。二つ目はタワケ先輩との別れの場面で、タワケ先輩が姿を消す前に僕の背中に向かって「行け」と言う。三つ目は元秀(ウォンス)が「行けよ。ぶん殴るぞ。俺はおまえの生き方が気に入らねえんだ」と言うので見ると、元秀は泣き笑いのような顔をしてた、というところ。そして最後は、桜井がこれまで見たこともないような微笑みを浮かべて、僕に「行きましょう」というところ。"GO"っていうのは、作者が自分にも仲間にも向けた言葉なのかもしれませんね。
トチ:私の「在日」の友だちとか、その子どもたちはけっこう海外へ行って暮らしたりしているけど・・・・・・
アカシア:でも国籍変えれば違うんでしょうけど、日本の法律にはいろいろ制約があって入国出国ともに大変みたいですよ。
ケロ:この本は、出たころに一度読んでいたのですが、主人公と「桜井」とのことだけがイメージに残っていて、今回読んで、それ以外のところが結構重かったので、ちょっとびっくりしました。この小説が、「差別」ということを大上段に振りかざした小説でなく、若者のドラマとして読めたからでしょう。読み返してみて、あらためて私は、桜井がきらいだなと思いました。自分の名前を言わないとか、思わせぶりな態度がハナにつくし、あげく、「名前が椿? えっ、だからー?」という感じでした。こんなに桜井を嫌わなくても良いようなものだけれど、もしかしたら、杉原がカッコよすぎて、嫉妬していたのかも…(とかいって、よく考えたらわたしゃ、杉原の母親と同じくらいの年齢だぞ〜)。そのくらい、杉原はカッコよかった。カッコよすぎてこんなやついるか!というくらい。この小説の全体に流れる「カッコよく生きる」というか、「カッコいいもんさがし」っていうのは、いいですね。
ペガサス:男の子って、とにかくカッコいい男になりたい、っていうことしか考えてないのよね。
ケロ:若いときにいくつカッコいいものに触れられるかって、とても大きいですね。自分がどう生きていくかを考えるとき、とても大事なことだと思う。
ペガサス:あと、携帯電話がない恋愛小説っていいわね。新聞とペンを買って電話番号を交換するじゃない。
アカシア:連絡したくても、しないで我慢してるなんて、今はないものね。
羊:直接言いたくないことは携帯メールで伝えればいいしね。
アカシア:手軽にメールですませてると、結晶する恋愛なんてできないと思うけどな。
紙魚:会えない時間が愛を育てるというのに……
(「子どもの本で言いたい放題」2003年10月の記録)