| 日付 | 2004年12月3日 |
| 参加者 | アサギ、トチ、羊、紙魚、ケロ、ハマグリ、むう、愁童、アカシア、カーコ |
| テーマ | 母親の不在(非在)と娘の自立 |
読んだ本:

原題:MAMA IST GEGANGEN by Christoph Hein, 2003
クリストフ・ハイン/著 松沢あさか訳
さ・え・ら書房
2004
版元語録:まぶたにうかぶママの顔は、いつも笑っています。笑うことしか知らないみたいに。もう一度、生きているママにあえたら! でも、ママも、ママの笑顔も、この世にはもどってきません。
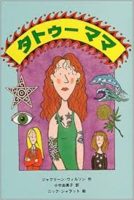
原題:THE ILLUSTRATED MUM by Jacqueline Wilson, 1999
ジャクリーン・ウィルソン/著 小竹由美子/訳
偕成社
2004
版元語録:頭からつま先までタトゥーを入れた、気まぐれで世界一すてきな母親への愛情。著者自身が最も気に入っているという作品。 *ガーディアン賞受賞作品

中脇初枝/著
福音館書店
2004.09
版元語録:祈祷師の母、そして父にも、妹の和花にもお祓いの能力がある。でも、春永にはその力が全くない。そんな彼女が、初恋、友情、家族愛の中で自分をつかむまでを描く。
ママは行ってしまった

原題:MAMA IST GEGANGEN by Christoph Hein, 2003
クリストフ・ハイン/著 松沢あさか訳
さ・え・ら書房
2004
版元語録:まぶたにうかぶママの顔は、いつも笑っています。笑うことしか知らないみたいに。もう一度、生きているママにあえたら! でも、ママも、ママの笑顔も、この世にはもどってきません。
アサギ:この作家はドイツでは純文学で有名で、ふだん児童書は書いていないのね。原作も最初は大人の本として出されて、そのあと子どもの本として出しなおしたみたい。作品自体はおもしろく読んだんだけど、ものすごく古い感じがするのは、この作家が東独出身ということと関係があると思う。西側世界からみると、数十年昔の感じがするわね。上の兄のカレルは15歳でガールフレンドができて、弟や妹が「あの二人はキスするのかどうか」を話題にしてるけど、西独では、十数年前から、生理が来たらコンドームをもたせるよう学校で女の子の親に指導しているくらいですからね。
ところどころ好きな文章がありました。たとえば、大司教がピエタを見にきて、彫刻については一言も発しなくても、はじめからおわりまでその話をしていた気がするというところなんか、印象に残りました。文学性を感じましたね。それから、作品の中でくりかえされる「悲しめることの幸せ」って真理よね。訳は、気になるところが、ちょこちょことありました。パパは大司教のことを「あんた」と呼んでるんですけど、これはduを「あんた」と訳してるんだと思うんですね。だけど、二人称のduとSieについて言うと、これは間柄の距離が近いか遠いかをを表すものなので、duを機械的に「あんた」と訳すとおかしなことになります。それから、ママもパパも10歳の主人公の女の子に対して「わたし」という一人称を使ってますけど、これも、どうなのかしら? 145ページの「宿屋兼食堂」っていうのは「旅館」のことでしょうね。
トチ:いかにもベテランらしい、手馴れた書き方で、死をどう受容していくかを書いた作品ね。幸せな仲の良い家族で、父親は腕のいい職人だし兄たちは成績優秀。世間的にも認められていて経済的にも安定していれば、こういう理想的なかたちで死を乗り越えていけるわよねと、ちょっと意地の悪い見方をしてしまったけど。安心して読めるし、子どもたちもしみじみと読むのではと思ったけれど、新鮮な驚きはない。今の世界とか、今の児童文学と少し離れたところにある作品ね。おもしろかったのは、父親が、亡くなった母親に子どもたちを会わせないところ。日本では考えられない場面で、こういう文化の違いとか、考え方の違いを知るというのも、翻訳ものを読む楽しさよね。ですます調のやさしい語り口で書いてあるけれど、ところどころ難しい言葉や、難しい考え方も出てきて、主人公の女の子の年齢や、対象とする読者の年齢をどの辺に置いているのか分からなくて、とまどってしまった。兄のパウルが主人公のウラに対して「そんなことないはずだがな」(p.45)と言ったり、ウラの友だちが「わたし、泣けてきちゃうの」(p.34)なんていうところは、子どもの会話らしくないなと思いました。
羊:1月にお母さんが死んでから11月くらいまでの話になっていますけど、お母さんを失った喪失感みたいなのがあまり感じられませんでした。『ミラクルズ・ボーイズ』(ジャクリーン・ウッドソン著 理論社)では、子どもたちが母親を亡くした悲しみが切ないくらい伝わってきたけど、この作品からは、ひとりひとりの悲しみが迫ってきませんでした。台詞が長くて、教会で牧師さんのお説教を聞いてるみたいに感じました。大司教のキャラクターはおもしろいとは思ったけれど、全体に淡々とした日記を読んでいる感じ。「お相伴する」とか「お対のデザイン」なんていう言葉が出てくるので、よけい古い感じがするのかもしれませんね。
紙魚:確かにリアルな生活や家族が描かれている作品ではないけれど、死をどうとらえるか、どう乗りこえていくかという問題をわかりやすく書いているという点では、作家の志のようなものを感じました。死と芸術、家族と再生の物語が、この子たちの時間を追って生活の中で描かれています。生活を読むというよりは、生活に意味をあたえるという作品だと思います。ひとつひとつの実際の死を細かに書いていくと、リアルな悲しみを感じすぎてしまい、死について思索する間をあたえてもらえない場合もありますが、ゆっくり読むことができ、それが、この家族たちのゆっくりとした一歩ととらえることもできました。それから、芸術についての記述はうなずける箇所が多かったです。ただ、本文中のカットと表紙の絵が合ってないような気がしたんですが。
アサギ:これ、カットも表紙の絵もズザンネ・ベルナーっていう、アンデルセン賞の最終候補になった人が描いてるのよね。絵本作品とは、また違う趣だけど。
ケロ:私は、このカットは父親の作る彫刻をイメージさせていると思って、しっくりきました。『タトゥーママ』とは、リアリティという点でまったくちがうけど、現実感のなさに、いやな感じは持たなかったです。それは、家族が意見交換するひと言ひと言が、じっくり読め、心に響いたからだと思います。この作品は、そのひと言ひと言を言いたいがために書かれているようで、ある意味、哲学的な本ですね。とくに、司教さんの言葉で、「あんたたちは、ママがいなくなって不しあわせだとおもっている。だが、かんがえてごらん。それはあんたたちが以前にとてもしあわせだったからだよ。わたしは妻や子をうしなうかなしみをあじわうことはない。しかし、そのかなしみを手に入れることができるものなら、わたしはあるいは、どんなに高い代償でもはらうかもしれない」と言いますけど、この言葉はこの家族にとって大きな励ましになっていると思うし、読者の心にも響くと思います。気になったのは、登場人物の年齢設定。ウラは、まだ人形遊びをしているなど、ちょっと10歳とは思えない。どういうことなんでしょう?
ハマグリ:出たばかりのときに読んだんだけど、ものすごく印象がうすい本でした。作家に言いたいことがあって物語にしたのだろうというのはわかるし、悪い感じはしないんだけど、あまりおもしろみが感じられなかったし、子どもたちににすすめたいという気も起こりませんでした。主人公はたしかに10歳の女の子にしては、幼く描かれていますね。一文一文が短い文章は原文に忠実に訳されているんでしょうが、そのせいか文章全体も幼い感じを受けました。お父さんがピエタという芸術作品をすばらしい出来に仕上げるということが最後のキーポイントになっているんだけど、芸術作品の良さを文章に表わすというのは難しいことなので、どんなにいい作品なのかがよく伝わってこなくて、残念でした。
むう:なんか古めかしいなあという印象でした。温かい家庭が悪いわけじゃないし、身近な人の死の悲しみをどう乗り越えるのかを書くのも結構だと思う。ピエタ像に微笑みを入れることで最後に宗教的なイメージに昇華していくのもなるほどなあと思うんだけれど、なにしろ心に迫ってこない。ふうん、そうなんだ、という感じ。すてきだなと思う台詞があるにはあるけれど、人間が悲しみを乗り越えるときというのは、そういう言葉のすばらしさで乗り越えるんじゃないと思う。もっとデリケートな細かいことの積み重ねがあって、やっとコトリと落ちるようなものでしょう。なんだか、さらっと読めてしまって後に残らない本だった。
愁童:ぼくもあんまりおもしろいとは思わなかった。数学の公式集を読んでいるような、ごくあたりまえのメッセージ。オリジナリティが感じられない。筆力でキャラクターを描ききると言うより、ストーリーの枠組設定で読者の中に誘発される喪失感や同情心に寄りかかって勝負しているような感じを受けた。作者の関心が、母親を失った女の子にあるのか、妻を失った職人の方にあるのか、どっちなんだ、なんて思った。どうでもいいような部分で、説明しすぎだったりして、訳文の影響もあるかもしれないけど、あまりぴんとこなかったな。
アカシア:さっきトチさんが出来すぎの家族って言ってたけど、実はそうでもない。上のお兄さんは買い物にいっても何を買うべきか忘れちゃうし、下のお兄さんもオリジナリティがありすぎて社会に適応できなさそう。お父さんのところにも、ガールフレンドがたくさんくる。どうも、そんなにパーフェクトな家族でもない。
日常の出来事が淡々と描かれているのは確かだけど、けっこう味わいが深いな、と私は思いました。お父さんが妻の死を乗り越えていく姿を見て、ウラが自分も乗り越えていこうと思うのも、ちゃんと伝わってきた。私もウラは幼いとは思ったけど、作家が東独の人だと聞いて納得しました。統合後はどうなのかわかりませんけど、以前の東独の人ってとっても純粋で、すれてなかったから。今出ている作品の多くはもっと刺激が強いから、これを読むと淡々としすぎて印象が薄いという感想につながるのかも。でも、ママの墓石には名前と生没年しか書いてないけど、「パパも子どもたちも、そういう気持ちは大きな字で書いてみんなに知らせることではない、とおもったのでした。だって、墓石はメガホンではないのですから」という表現とか、お兄さんたちの性格の描写とか、パパがウラに「おまえがなにを見つけだすか、おまえ自身とおなじように、どきどきしながら待っているよ。でも今からもうわかっていることがある。ウラはきれいで、かしこくて、勇気のあるおとなになるんだ。ママとそっくりにね。それをママは、ちゃんとおまえにプレゼントしてくれたのだから」と言うところとか、なかなか味わいがあります。大傑作とはいえなくても、ちゃんと文学を書いている作家ならではの作品だと思いました。
トチ:最初は大人向けの作品として書かれたと聞いて、なるほどと納得したわ。淡々とした日常を綴っていくうちに人生の奥底が見えてくる・・・・・・日本で言えば庄野潤三のような味わいのある作家なのかも。
愁童:司教をフレンドリーな性格として描こうというのは理解できるけど、キルスト教文化の中では、司教様と普通の職人とじゃ身分がちがうんじゃないの。そのあたりの微妙な上下感覚が感じられる訳になってないのが残念。
紙魚:お兄さんたちがそれぞれユニークなのに、会話にそのおもしろさが出ていない。
羊:葉巻がよく出るのには何か意味があるの?
アサギ:ドイツでは昔おみやげというと、その家のお父さんには葉巻、お母さんにはバラの花束、子どもにはチョコレートっていうのが定番だったの。いちいち考えなくていいから、楽だったのよ。
カーコ:私ははじめつまらなくて、読み進むのがすごくつらかった。でも、全体としては、女の子の心理描写が今回の3冊の中ではいちばん細かく書かれていて、いい本だと思いました。じゃあ、なんで読みづらかったのかなと考えると、それは主人公に視点が定まっていないからじゃないかと思うんですね。だから、トチさんが言ったように、誰に向けに書かれているかわからないという印象にもなってしまうのでは? 家族が言葉でお互いの気持ちを説明しあうところは、あいまいな表現を好む日本人と対照的ですよね。お母さんが亡くなったあと、だれもかれもが同情してくるのに違和感を覚えるとか、バカンスの初めにお兄さんがお母さんの決まり文句を言ってしまって気まずくなるなんていうところは、一家の心情を浮き彫りにしているエピソードですね。最近はストーリー展開ばかりで読ませる本が多くて、こういう作品は少なくなっているような気がします。
(「子どもの本で言いたい放題」2004年12月の記録)
タトゥーママ
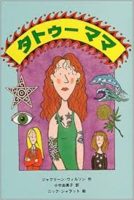
原題:THE ILLUSTRATED MUM by Jacqueline Wilson, 1999
ジャクリーン・ウィルソン/著 小竹由美子/訳
偕成社
2004
版元語録:頭からつま先までタトゥーを入れた、気まぐれで世界一すてきな母親への愛情。著者自身が最も気に入っているという作品。 *ガーディアン賞受賞作品
ケロ:壊れていく母親を見ているドルの気持ちがつらいなあと思いながら読みました。子どもは親を選べないのに、こんな母親でも好きでいるという現実がきちんと書かれているだけに、つらい。こういう状況にある子どもが読んだとき、果たして助けになるのかなあと、疑問を持ちながら読んでいきました。でも、最後にカタルシスがありましたねー。客観的に母親を抱きしめるというところが、主人公本人の救いにもなっていて、これなら「子ども向け」の作品としてオッケーだ、と納得できました。全体の中では、ドルとスターの父親が両方とも見つかるのは話として出来すぎという感じがしましたが、自分の中にもお父さんはどんな人なんだろう、という興味があったので、ご都合主義な感じを受けずに楽しんで読めました。お母さんのマリゴールドは、精神的にも不安定で、かなり特殊な存在。でも、お母さんがひとりの人間として満たされず特別な存在になりたいと思っている、というのはよくあることだと思うと、ひいてしまわずに感情移入しながら読めたかな。
ハマグリ:ジャクリーン・ウィルソンの作品は、今までもたくさん読んでいますが、どれも困難な状況におかれた子どもを書いている。結末は安易なハッピーエンドではないけれども、必ずどこかに未来への道がついているのがいいですね。それからどんなにすごい状況でも、ハハハと笑える部分が必ずあって、楽しませてくれるところもすごい。この明るさは、イラストによるところも大きいでしょうね。ドルとスターという姉妹は、大好きでお互いをとっても必要としているんだけど、それゆえに許せない部分があって、ぶんなぐりたいくらいの反感ももっている。そうした関係もよく描かれています。リアリスティックな作品のなかでは、この作者のものは子どもに勧めたいわね。
むう:うまい人だなと思いました。出だしからこっちを引き込んでぐいぐい引っぱっていくあたりも、この家族のある種のチープさもよく出ていて面白かった。ただ、わたしの視点がどうしてもふりまわされる側の子どもたちに寄ってしまって、「このお母さん、なんだかなあー」と思うところもありました。だめ母さんでも好きで好きでしょうがないという子どもの気持ちはとてもよく描けているし、それが切ないんだけれど。ミッキーが見つかったり、主人公のお父さんが見つかったりで、どうなっちゃうんだろうと最後まで引っぱられたし、この子たちがそれぞれに家族とは別の世界に触れたうえでふたたびママを抱きしめるというのもいいと思ったけれど、最後の338ページのお母さんの台詞にはすごく引っかかった。病院のカウンセリングの時間の話で、「しつこくしつこく、小さなころのことをきかれたわ。で、しまいに、ひどい話をぜんぶぶちまけちゃった。お母さんのこと、お母さんがあたしにしたこと、どれだけお母さんをにくんだか。そしたら、気がついたの。あたしもおなじだって。あたしも、おなじようなことをあんたたちにしてきた。ふたりとも、きっとあたしのこと、にくんでるわよね」って言うんだけど、こんなふうに説明しちゃうのはお手軽だなあ、と思って。この台詞、いらないですよね。ここまでで、このお母さんはまるで信用できなくて、それでも子どもたちはこの人が好きでということがわかるんだから、それでいいじゃない。
アカシア:私は、この台詞がすごくきいてると思うんです。お母さんは初めて精神科病棟で治療を受けてるわけだから、この台詞がないと、これからはまともな母子関係になるのかな、と読者は思ってしまう。でも、このお母さんは、これまでも時には「自分はだめな母親だ」って言ってきたけど、状況はちっとも変わらなかったんですね。ここも、この台詞があることによって、読者に「また言ってるけど、これからも変わらないんだろうな」と思わせる。だから、娘たちは、ここで心底悔い改めたお母さんを選び取ったんじゃなくて、お母さんは変わらなくてもそれでも好きなんだ、という設定がより強く浮かび上がってくる。
むう:つまり、だめ押しみたいなものということかな。でも、そこまでする必要があるかなあ。この本を読み終わって、まず、力があるなあ、うまいなあと感じたんだけれど、同時に、「でもなんかざらざらしてる。なんだこの違和感は」と思ってその原因を考えるうちに、このお母さんの台詞に行き当たったんです。自分のなかでここだけが消化しきれない感じで。
ケロ:でも、キルトづくりをさせられて、パーツが合ってないと娘に言われ、「どんなキルトになると思う? 信じられる? クレイジー・キルトっていうのよ」って台詞、やっぱりこのお母さんならではって感じですよね。状況的な大変さは変わらないけれど、あきらかにこの子たちの心境は変わっている。
愁童:ぼくも、むうさんといっしょ。心理学ブームだからって、セラピストの定番みたいなところによっかかるのはどうかな。こういう子どもを幸せといえるのかなとは思うんだけど、原題のThe Illustrated Mumには、作者のメッセージがうまく込められているように思った。Illustrateされちゃったママで、それに振り回されるけど、それでもママはかけがえがないという、のっぴきならない母子関係。その中で、主体的に生きざるを得ない子の、母が居てこその幸せみたいなことについて考えさせられちゃった。
アカシア:この作家は、本当に子どもに寄りそって書いてますよね。現実にこういう子どもはいっぱいいるんでしょうけど、その子たちが気持ちの出口をさがしていくところが書かれている。ハマグリさんはリアリスティックな作品として子どもに勧めたいと言ってたけど、私は純粋にリアルなんじゃなくて、エンタテインメント的な要素がとても強いと思う。娘たちのお父さんがそれぞれ都合よく見つかるなんて、リアルじゃないですよ。ただ心理的な動きはリアルで、読者の気をそらさない。うまいです。子どもたちに大人気なのも、当然ですね。
これだけひどいお母さんだったら家出するのがふつうで、なかなかお母さんを受け入れるところへは行き着けない。でも、家出したスターのことが心配なあまり、スターがきらいだったタトゥーを消そうとして、お母さんは体中に白ペンキをぬりたくってしまう。その異常な行動から、最後に娘たちがお母さんを抱きしめるところまでは、下手な人が書いたら嘘臭くてとても読めない。でも、この人が書くと、ついていけるんですよね。うーん、すごい。
あとね、さっきのお母さんの台詞について、もう一言。マリゴールド自身の母親との関係がここで初めて出てくるんですよね。文学好きな読者にとっては、なくもがなと思う気持ちもわかるけど、これがないと、マリゴールド=クレイジーですませてしまう子どもの読者もいるような気がします。
カーコ:お話としてはおもしろくて読ませられたんですけど、いったい誰が読むのかなと思いました。実際にこういう状況にいる子の力になるのでしょうか。どんなに悲惨な状況に置かれていても、子どもがお母さんを好きなのは当然のこと。10歳の子がこんな目にあって、健気に母親を支え、精神的に自立していなければならないというのが、あまりにもかわいそう。わざわざ子どもに読ませたいとは思えませんでした。大人に対する理解を子どもに強制しているように感じました。
アカシア:渦中にいる子は読むだけの余裕がないかもしれないけど、まわりの子がそういう子を理解するのにはとても役立つ。それに、オリヴァーとか、ドルのお父さんとか、里親のジェインおばさんとか、味方になって支えてくれそうな人物も登場し、ドルの世界も広がって孤立無援ではなくなっている。10歳の子に「健気」を押しつけることにはなってないと思うけど。
ケロ:これほどスゴイ状況まではいかなくても、今のお母さんって少なからずこういう部分があるので、子どもとしては、少しシンクロできるのではないでしょうか? 映画『誰も知らない』(是枝裕和監督)は、救いがまったくないけれど、これはユーモアがあり救いがあると思うので、母の「こういう部分」を理解するなり判断するなりする材料になるのではないでしょうか。
愁童:下の階のおばあさんの描き方がうまいね。批判的な世間の目の代表みたいな存在なんだけど、文句を言いながら電話を取り次いだりと、結構助けたりしちゃう。このおばあさんの存在感で、主人公一家のハチャメチャな生活に立体感が出てくるよね。
アサギ:私は時間切れで、まだ半分しか読んでないんです。イギリスならともかく、翻訳して日本の子どもにこういう物語を読ませる必然性がわからない。せつない感じがしちゃってね。
トチ:それはまだ読んでる途中だからじゃない?
アサギ:日本の状況とは、ずれていると思いません?
アカシア:日本も、もうすぐこうなるんじゃない? お金もうけのために自分の子どもに売春させる親だって出てきたくらいだから。
アサギ:まあ、このお母さんの場合、憎めないところもあるけれど。
トチ:子どもには、なにがあっても親についていくという生物的な本能もあるし、親から離れられないってこともあるしね。
愁童:姉妹の母親への思いの、それぞれの年齢による微妙な差が、うまく書かれているよね。
トチ:まず、これほど暗くて悲惨な状況を、これほど明るく、ユーモアもまじえて書ける作者の力量に感心しました。書きようによっては限りなくいやらしくなる母親も、切なく、かわいらしく描けていることに、またまた感心。昔の児童文学って、『小公女』のように不幸な主人公が状況が変わることによって幸せになるというのが典型だったけど、この作者は環境が変わらなくても、主人公の内面的な変化や成長で救われるということを一貫して書きつづけている。このほうが読者である子どもにとってずっと現実的だし、救いにもなるわよね。それから、作家であれば誰でも一度は「狂気」を書いてみたいのでは、と思うんだけど、ウィルソンもそうだったのでは?そんな作家魂が垣間見えるような気がして、おもしろかった。
羊:はらはらしながら読みました。でも、お母さんの幼さが、わりに魅力的に書かれていて、学校にショートパンツ姿で迎えにいくシーンなんかもおもしろかった。みんなから鼻つまみにされている母親でも、娘である当人だけにわかる愛情を抱いているのは伝わってきましたよ。スターに父親が見つかり行き場が出来た時から、お母さんが崩れていくという流れはすごかったですね。そのスターが距離をおいて離れて暮らしたことで、また優しくなれるというのもわかります。このままの暮らしを続けていたら破滅するしかないですよね。
紙魚:主人公の環境があまりにもひどいので、読むのがつらかったです。アルコール依存症の親とかに読んでもらうと、子どものつらさがわかっていいかもしれないと思ったくらいです。作中ときどき顔をのぞかせる、オリヴァーのやさしさとドルフィンという美しい名前には、かなり励まされました。スターとドルの姉妹って、年齢の差や性格のちがいから、母親への接し方が全くちがうのですが、その時々どちらの気持ちにも共感できて、どちらの方によって読んでいっていいのか、かなり振りまわされました。だから最後までお母さんへの好き嫌いが決められなかったのですが、それもやっぱり、この作家のうまさなんだと思います。家族ならではの、ひとつのところにとどまらず常にぐるぐるとスパイラルして動いている感じが、とてもうまく表現されていたと思います。
トチ:大人は怖いもの見たさで悲惨な物語を読みたいということがあるけれど、子どもはどうなのかしら?
アカシア:極端な設定を使うと、はっきり見えるてくるものもあるんだけど、それをどう描くかというところが大切よね。
(「子どもの本で言いたい放題」2004年12月の記録)
祈祷師の娘

中脇初枝/著
福音館書店
2004.09
版元語録:祈祷師の母、そして父にも、妹の和花にもお祓いの能力がある。でも、春永にはその力が全くない。そんな彼女が、初恋、友情、家族愛の中で自分をつかむまでを描く。
羊:タイトルから判断して、古い時代の話かと勘違いしました。祈祷師の世界を描いた児童文学は、はじめて読みました。私は九州生まれですが、小さい頃、肌が弱くて祈祷師のところにいったことがあるんですよ。治らない病気や相談事があると、みんな自然にに行ってました。
愁童:今でも、こういうことを日常生活の中に自然に織り込んでいる所ってあるよ。
トチ:文学作品としてよく書けていて、おもしろかったです。縁日で買った金魚が自分では向きが変えられないので、水槽に手をいれて変えてやるところとか、死んだ金魚に、つつんだ新聞紙の字がうつっているところとか。周りの友達の描写も実にうまい。宮部みゆきやスティーヴン・キングは超能力を持つものがこの世界で生きていくことの苦しみや悲しみを描いているけれど、この作品は家族のなかで自分だけが超能力を持たない者の悲しみを書いているところがおもしろかった。最後に超能力がなくても人を救えるということが分かって、主人公も救われるのよね。いま玄侑宗久の『リーラ:神の庭の遊戯』(新潮社)という本を読み終えたところなんだけど、ここでも同じような世界が描かれているのよね。こういう文学がいま流行なのかしら。私はあんまり子どもたちを霊的なものにのめりこませたくないほうなので、この作品を児童文学として子どもに手渡すことに一抹の不安がよぎったことも確か。こういう世界もある、ああいう世界もあると子どもたちに伝えるのはとてもいいことだと思うんだけど・・・・・・
アサギ:超能力を授かったものの悲しみといっても、私には違和感バリバリですね。『黄泉がえり』(梶尾真治著 新潮社)とか『秘密』(東野圭吾著 文春文庫)とか、このところ、こういうのって流行っているんでしょうね。この人は、こういう力を肯定して書いているんでしょうが、どれだけ信じて書いているのかしら?
カーコ:私もどうとらえていいかわからない感じでした。主人公の春永は最後に、超能力も血のつながりもないけれども、この家族の中で生きていこうと決心するわけですよね。学校での、一見仲の良い友だちとの確執とか、男の子が祈祷に興味を持ってくるところとか、うまいなと思いましたが、なぜ祈祷師という設定にしたのか、わかりませんでした。時代的にはいつごろが舞台なんでしょうね?
アカシア:ひかるちゃんが小学校で留年しているという記述があったので、昔のことだと思ったんだけど。
アサギ:でも、アンパンマンが出てくるし、義務教育の留年は今でも希望すればできるのよ。
アカシア:挿絵(卯月みゆき)が、昔なつかしい感じじゃない? 超能力に違和感を感じる人が多いみたいだけど、日本でもたとえば沖縄のユタは日常生活に浸透してますよね。アフリカのノーベル賞作家が書いた自伝なんかにも、霊能師はごく自然に出てくる。今はよくも悪くも日本の都会は近代合理主義におおいつくされてしまって、「気」のようなものを迷信と決めつけてしまう。さっき霊的なものに惹かれる危険性という話が出ましたけど、この作家はちゃんとコックリさんの危険性も書いてるし、きちんと修業しないと祈祷師にはなれないと書いて、ふわふわととびつくことに警鐘も鳴らしている。
アサギ:でも、スタンスがわからないのよ。私は、肯定するってところがそもそもわからない。それとね、総ルビはやりすぎよね。読みにくい。
アカシア:合理的な考えからはずれて切り捨てられたものを拾い上げてみるっていうスタンスなんじゃないの? それから、昔の子どものほうが漢字が読めたのは、総ルビの本が多かったからだという説もありますよ。
愁童:ぼくはおもしろかったですね。こういう力を信じているってわけではないけど、会社の優秀な技術系の同僚に、生活の中に、こういう「おがみ屋さん」との接点を大事に持ってる奴が居たんですよね。この作者は、そういうものを取り込んだ近隣の人達の日常にきちんと目配りをしていると思う。ひかるちゃんがなんでこうなっているか、なんてことも、きちんと書いている。奇異な題材を用いて、日常の中にある影の部分に光を当てているように思いましたね。
むう:冒頭で、「おかあさん」と「母親」と「お母さん」と三種ずらりと出てきたのにはちょっと戸惑いました。でも、それも後になると納得できて、今回の三冊のなかではいちばん自然にひきこまれて読むことができました。ちょっと前に理科系の顔をした超常現象がブームになって、そういうものにはアレルギーがあるのだけれど、この本には、まともらしく見せようとする嘘臭さがない。おしつけがましさがなくて、生活に溶け込んでいる様子が書かれているので、こちらもすうっと入れてしまう。それに感心しました。それと、読んでいて主人公の心のひだが手に取るようにわかる。この本の主人公は、超能力者という世間からはぐれた人々の中でさらにはぐれた普通の子なわけです。かなり特異な設定なのだけれど、人間の持っている普遍的なところがしっかり書けているなあと思いました。最後のほうで、超能力を持っていなくても人を助ける力はあるというところに収めるのもうまいですね。あと、この主人公が母親に置いていかれたにもかかわらず安定しているのは、周りの人にちゃんと尊重されて育ってきたからだと思うんですが、そういう子が主人公だからこそ読後感がいいんでしょうね。
ハマグリ:ディテールの書き方がうまいわね。主人公の目に映った情景をくっきりと切り取って描くのがうまい人だな、と思った。会話もいきいきとしている。でもこの四人の家族のつながりって、とても不自然なので理解できない。自分だけが祈祷師の力を備えていないということで主人公が悩むのはわかるけれど、そんなことに悩む前に、この家族がこうやって成り立っているというところに来るまでの悩みがあったはずじゃないの? この主人公が、このおかあさんという人をおかあさんとして受け入れなきゃならないというのがそもそもよくわからなかった。変則的な家族だけど、このような家族として成り立つまでの過程が全く書けていないので、違和感が非常にある。最後の駅の場面でも、このおかあさんをそこまで思う気持ちがよくわからない。
トチ:その部分はディテールで書けてると思うけど。『タトゥー・ママ』で主人公が終わりのほうで里親の家に行って、すぐに好きになるでしょ? あれと同じじゃない?
アカシア:現代の児童文学には、血のつながりのない者たちが血縁に頼らずに家族の関係を構築するっていう物語が多いわよね。それに、昔だって戦争とかいろんな事情で、血のつながりがない人と暮らしている人って日本にもいっぱいいたんじゃない。
ハマグリ:血のつながりにこだわっているわけではないの。
愁童:おとうさんといっしょに水をかぶったりする行為とかで、その辺は書けていると思うけど。
ハマグリ:どうしてこんな変則的な家族ができたのかってところをもっと納得させてほしいの。だって、おかあさんとおとうさんは兄妹なわけだし。こんな家族の形になぜここまで固執するのかがわからない。
愁童:冒頭の部分で、自分の母親の顔を知らない記憶の原点みたいな描写が出てくるけど、ここは文章が妙に持って回った表現で、頂けないと思ったな。
ハマグリ:結局、四人の家族ができちゃってからの話になっているので、どうしても不可解な感じがある。
ケロ:テーマが「母親」だったこともあって、そっちの切り口で読み進めました。そのせいか、超能力などの設定には違和感をもたなかったです。だから、祈祷師の血=家族の血ってこととしてすんなり入りました。主人公は、自分の出生の事から、血縁を含めて、誰かとつながりたい、といつも感じているんですね。主人公がふらふらと山中君のことを好きになっちゃうのも、結構自分勝手な友だちといつまでもつきあっちゃうのも、だからかな、と思います。春永は、いつもどこかでその答えを求めている。それが切ないですね。それにしても、「今、つきものをはらったから」という会話が出てくる家族ってすごいですよね。余計リアルに感じました。ひとつぶっとんだ設定をおくと、他が光って見えてくるんですね。おもしろかったです。
羊:『祈祷師の娘』というタイトルと「自立の物語」という帯の文言が、あまりにも相反していて、読む前はなんだかしっくりきませんでした。でも読んでみると、まさに自立の物語が描かれていました。どこにでもいるようなふつうの少女の生活を単純に書いたのでは、なかなか自立という部分は浮かびあがってきません。でも、「祈祷師」という普段垣間見ることのできない設定を加えたことで、逆にもっと切実なリアリティがうまれていると思います。もともと私は、非科学的なものにはクールなので、占いなんかにも全然興味がないのですが、こういった不思議な力が生活に入りこんでいるというのは、人間として余裕があって、じつは生き方の幅が広いのではないかとも思うことがあります。そんなことをも感じさせてくれる本でした。
(「子どもの本で言いたい放題」2004年12月の記録)