
| 日付 | 2023年10月24日 |
| 参加者 | エーデルワイス、ネズミ、オカリナ、wind24、ANNE、きなこみみ、アンヌ、ニャニャンガ、雪割草、西山、ハル、ルパン、しじみ71個分 |
| テーマ | 図書館から広がる物語 |
読んだ本:

こまつあやこ/著
講談社
2023.04
〈版元語録〉憧れの高校に合格し、書道部に入った真歩。しかし、父の療養のために引っ越しをすることに。高校を辞め、図書館の宅配ボランティアを始めた真歩は、本を届けに行った家でアラビア書道というアートに出会い…。
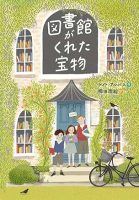
原題:A PLACE TO HANG THE MOON by Kate Albus, 2021
ケイト・アルバス/作 櫛田理絵/訳
徳間書店
2023.07
〈版元語録〉親代わりになってくれる人を探すために疎開した両親のいないきょうだい。疎開先の厳しい日々、3人にとって、村の図書館だけが救いだった-。第二次大戦下、ロンドンから疎開したきょうだいの心あたたまる物語。
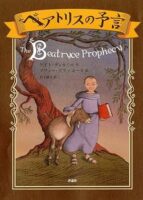

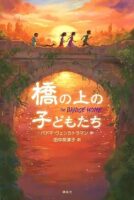
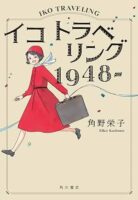
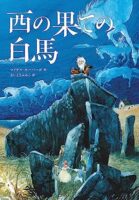
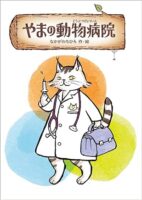
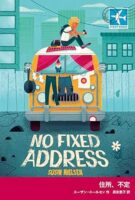
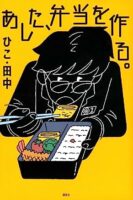
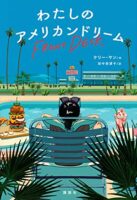
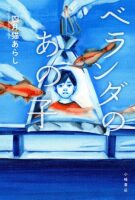
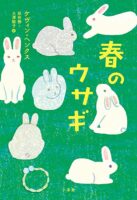


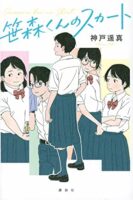
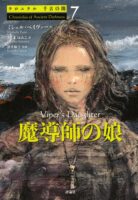

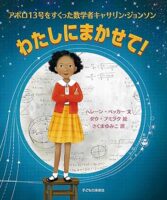
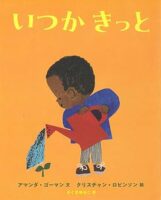
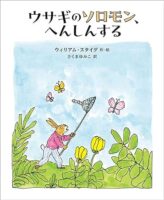




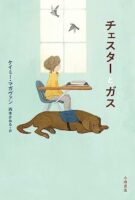
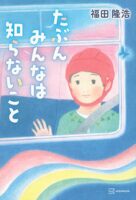
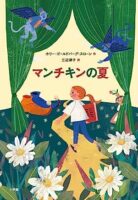
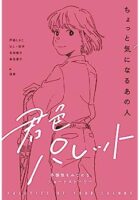

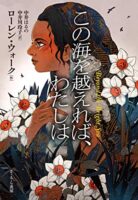


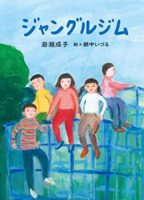
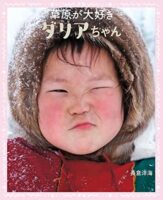

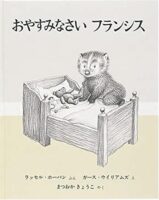


平和な世界を願って 子どもの本にできること
「こどもの本」2023年3月号(日本児童図書出版協会)に「平和な世界を願って 子どもの本にできること」というエッセイを書きました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
本さえ読めば平和が来るとは思わないが、平和につながる道を少しずつ作っていくことは、本にもできるのではないだろうか。私が訳した『子どもの本で平和をつくる』(キャシー・スティンソン文 マリー・ラフランス絵 小学館)には、イエラ・レップマンという女性が登場する。彼女はドイツ生まれのユダヤ人ジャーナリストで、ヒトラーが政権を握ると命の危険を感じて、子どもたちと一緒にイギリスに避難していた。
戦後故郷に戻ったレップマンは、ドイツの子どもたちの窮状を目の当たりにして二〇の国に手紙を出した。それぞれの国のすぐれた子どもの本を送ってもらえないか、と依頼したのである。周囲からは、「戦争でドイツと戦った国々が本を送ってくれるはずがない」と批判されもしたが、幸い一九の国からは、すぐに児童書が送られてきた。でも、一か国からは、「私たちは二度もドイツに侵略されているので、残念ながらご希望にそうことはできません」という手紙が届いただけだった。
レップマンはそこであきらめずに、もう一度手紙を出した。「ドイツの子どもたちに新たな出発をさせてやりたいのです。他の国々から届いた本を見ることによって、子どもたちはお互いにつながっていると感じるでしょう。戦争がまた始まらないようにするには、それが一番ではないでしょうか」と書いて。
すると、その手紙を読んでレップマンの意図を理解したその国ベルギーからも、素晴らしい児童書のセットが届いたのだ。レップマンは、届いた本を国内巡回して子どもたちに見せ、ドイツ語に訳して読んでやり、それをもとにしてミュンヘンに国際児童図書館をつくった。そして、一九五三年には様々な国が子どもの本について話し合うための国際組織IBBY(国際児童図書評議会)も設立した。
私が今会長を務めているJBBYも、一九七四年にIBBYの支部として発足し、「本、子ども、平和」をキーワードにし、ボランティアベースで多様な活動を行っている。詳しくはウェブサイトをご覧いただきたい。https://jbby.org
一九九八年に国際アンデルセン賞を受賞したアメリカの児童文学作家キャサリン・パターソンは、受賞スピーチの中で、「アメリカの図書館には自国で出版された本がすでにたくさん並んでいるせいか、外国からの翻訳作品も必要だということを忘れてしまいがちです。でも、私たちはアメリカの子どもたちに、イランや韓国・北朝鮮や南アフリカやセルビアやコロンビアやチリやイラクに暮らす友だちをあたえていかなければなりません。つまりどの国の子どもたちとも仲良くなってもらわなくてはなりません。人は、自分の友だちが暮らしている国に害をあたえようとは思わなくなるからです」と語っている。
こうした人たちの言葉は、子どもの本が平和につながりうることを示唆している。
子どもの本にかかわる人の中には、子どもがおもしろがればそれでいい、と考える人もいる。楽しい、おもしろいというのは、子どもの本にとって不可欠な要素だと私も思う。立派なテーマを掲げた本でもおもしろく読めなければ、子どもの本としては失格だ。でも、「おもしろい」というのは、表面的なおもしろさだけではないだろう。読んですぐは、ゲラゲラ笑ったりするようなおもしろさを感じなくても、子どもの心の中に種として残り、その種が芽を出し花を咲かせることもある。そういう種を持ったような本をつくっていければ、と私は思う。種には、平和の種もあれば、好奇心の種もあり、生きるエネルギーを生み出したり、ちょっと一休みするすべを学んだりするための種もあるだろう。
また平和を生み出すためには、偉い人に言われればそのまま従うような人ではなく、自分の頭で考え、自分の心で感じ、しかも客観的に判断できる人を育てていくことが必要だ。そのための種をまくには、本をつくる側の私たちも、これからはどんな社会が望ましいのかを、考えておく必要があるだろう。
本が売れるというのはうれしいことだし、出版を続けるためには重要な要素でもある。でも、それだけを考えていると、どんどん子どもの本は種なしの、中身も味も薄い消耗品になってしまう。つくり手の側が利益だけではなく、子どもの中で育つ種があるかどうかの質を見分けられる「目きき」になることも、とても大事なことだと思う。
それともう一つ。「理想的なことばかり言っていても始まらない。現実は違うのだよ」と言う人がいるが、子どもの本にたずさわる者としては、あえて理想を口にすることも必要だと私は思っている。(さくまゆみこ)