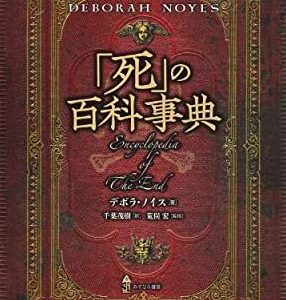げた:初版(理論社)からはかなり表現を削って、分量が少なくなって新しく出されたようですね。
ルパン:おもしろかったです。亡くなった人と会う、というのはすごく難しい設定だと思うのですが、前に読んだ『母ちゃんのもと』(福明子 そうえん社)と比べたら、こちらのほうがずっとまともです。親に死なれるって、若い人にとっては大変なことだと思いますが、その気持ちも書けていて。死んだ家族と会っているけど、こんなに仲いい家族だったっけ、とか家族のリアリティにも踏み込んでるし。無条件にいいことばかりではなかったことを冷静に思い出すんですが、わざとらしくなくて。あと、「走る」っていうことで、知らない世界を知っていくわけですが、ゼロから知っていくパターンって、説明調で鼻につくストーリー運びもあるけれど、これはそんなにいやらしくなく、読んでいて、疲れなかった。あと、醤油飲んで自殺はかるおばさんがおもしろかったです。YAものの脇役としてはずいぶん年上ですよね。そのうえ最初から敵対関係なんだけど、何となく距離が縮まっていくあたり、主人公に感情移入できました。それに対して、ドコロさんは、よくわからなかったです。その罪悪感も、罪ほろぼしの論理も。
ハリネズミ:ペースメーカーをしてもらった後輩が心不全で亡くなって「ひでえ罪悪感にとりつかれてさ。そいつへの罪滅ぼしのつもりで走るのをやめた」って、書いてありますよ。
ルパン:ラビットが死んでしまったからといって、自分まで走るのをやめちゃったのは、どうしてでしょう。やめたら、その人の死を無駄にしたような気がするんですが。
ハリネズミ:天才ランナーとか言われるレベルの人だと、ペースメーカーがつくことも多いんでしょうから、また同じことになっちゃまずいと思ったんじゃないかな。
トトキ:最後まで、すらすら読めたのは覚えています。あの世とこの世を行ったり来たりするという点は、同じ森さんの『カラフル』に似ていますね。エンターテインメントとしては、おもしろく書いてあると思うけれど、どういったらいいのか「死ぬ」ということに対する切実な感じがないのがひっかかるんですよね。一緒に読んだ『ロス、きみを送る旅』(キース・グレイ作 野沢佳織訳 徳間書店)は、「死」が身を切られるほど切実なものとして迫ってくるんだけど。なんていったらいいか分からないけれど、物語がすべて作家の掌の中にあるっていう感じ。心を揺さぶられる作品って、登場人物が作家の手に余るというか、勝手に掌から飛び出していくような感じがあるんだけれど、みんなお行儀がよすぎるというか……。
ハリネズミ:『カラフル』は、死んだ人が生き返ってきますね。
トトキ:『カラフル』は設定がうまかった。出たときは、こっちとあっちを行き来する作品もそんなになかったし。
ハリネズミ:でも、この作品では行ったり来たりを肯定してるんじゃなくて、無駄ですよって言ってます。
ajian:うーん、私にはあまりおもしろくありませんでした。突拍子もない設定や展開など、お話をつくるのはうまいと思うんですが……。この作者の『カラフル』もあまり私好みではなかったので、合わないのかもしれません。登場人物も好きになれないというか、みんな書き割りのようにパターンで分けられていて、今ひとつ物足りなさを感じます。「キリストもブッダもアッラーも一休さんも言ってなかったんだよね」とか、作者は冗談のつもりで書いているんだろうけれど、とくに笑えないってところもいっぱいある。「生きていかなきゃ」というテーマにつなげた、全部がオハナシな感じがする。
ハリネズミ:大人が読むとそうかもしれないけど、中学生くらいの子どもはおもしろいんじゃないかな。深く考えることはできないかもしれないけど、考えるきっかけにはなるように思うな。
ajian:長いので読むのもたいへんだけど、読み終えたあとは呆然とするというか、徒労感があって。最近日本の作品はあまり読んでいないから、感覚が違ってしまっているのかもしれないですが。
レジーナ:作者はきっとこの作品で、それぞれ悩みを抱えたり、傷つけたり傷つけられてりしながら、生きている人は生きている人たちで、何とかやっているということを伝えたかったのでしょうね。生者も死者も、お互いに気がかりだけど、心配しなくてもいいというのは、子どもというより大人の視点ではないかと思いました。桜並木を走る場面では、新しいことを始め、止まっていた時間が動き出す様子、家族のことを少しずつ忘れていくことへの恐れが伝わってきました。おもしろく読みましたが、生者の世界と死者の世界がもう少し絡み合っていれば……。二つの世界があまりにもかけ離れているんですよね。最初は重要人物に見えた紺野さんも、途中から存在が薄くなります。家族が亡くなり、紺野さんも引っ越してしまい、紺野さんのくれた自転車のおかげで、死んだ家族に会える。理屈は通っているんですが、頭で書いているのかもしれません。家族に会うためにマラソンを始めた主人公を非難し、自分の考えを一方的に押しつける大島君には、腹が立ちました。後から反省はしますが。同居を始め、「タマ」と呼んだおばさんに、「猫を飼うような気分なんじゃ……」と思ったり、おばさんを「装甲車」と表現しているのはおもしろかったです。文章はちょっとくどいですが、高校生くらいの読者には読みやすいのかな。
ajian:いや、「生者は生者で生きていきましょう」とか、浅いと思ったんですよね。そんなに簡単な人間観とか死生観でいいの? と思ってしまいました。私にとって小説が魅力的なのは、そこに描かれている人物に、どうしようもない人間味を感じてしまうときで、正直に言って、ここに出てくる人物たちが死のうが生きようがどうでもいいと思ってしまいました。一言でいって、心に迫ってくるものがなかったんです。
ヤマネ:森さんの作品は好きなんですが、『カラフル』と『ラン』はあまり好きではありません。『リズム』『宇宙のみなしご』などは、きらきらした少女の気持ちがよく描かれていて大好きなんです。軽さが受け入れやすいのか、小学校高学年の女の子たちからも人気がありました。ただ生と死の話になると、設定から受け入れるのが難しくて。また、タイトルが『ラン』なのでもっと走ることが描かれた話かと思ったら、そうでもなく期待外れでした。読む人の好みにもよるかもしれませんが、苦しいことをもっと深く描いてそこから立ち上がる主人公の姿を読みたかったな。主人公の置かれている状況は、すごく辛い状況なのに、それがあまり伝わってこないから。一方で、生と死の世界をつなぐレーンの説明はつじつまが合うようにうまくできているとは思いました。
すあま:子どもの本ではなく、大人の小説だと思って読みました。自転車があの世に連れて行く、という設定や描写をうまく頭の中に描けず、話に乗り切れませんでした。天涯孤独の主人公があるきっかけで走り始める話、ではだめだったのか、新しい人間関係ができていくところを丁寧に書けばよかったのではないかと思いました。はたして死んだ家族のところを行き来する必要があったのか、と考えてしまいました。1冊にいろいろなことを盛り込みすぎのような。おもしろいキャラクターも出てくるので、ちょっともったいない感じがしました。
げた:今回は私が選書係だったんですが、最初の2冊が決まっても、あと1冊、日本の本がなかなか見つけられなくて、本屋さんの棚で見つけたんです。最初の部分で、紺野さんと主人公の出会いと別れの箇所を見て、テーマにつながるかと思って読み始めました。ストーリーとしてはありえないこだし、言ってみれば荒唐無稽ですよね。ありえないけど、ランニング仲間とのやりとりは現実的な、ありそうなストーリー展開でリアルなファンタジーですね。エンターテイメントとしては、おもしろかった。死んだ人がファーストステージにいる段階で溶けていき、次のステージに行って、生まれ変わるというのもなるほどと思いましたね。人間年をとると、死ななくても、実際既に溶けているんじゃないかなって。
プルメリア:『ラン』なので『DIVE!!』(森 絵都 講談社)のようなスポーツ青春ものなのかなと思ったら、そうではなかったです。真知栄子さんとのバトル、どちらも譲らない強い女の人ですね。猫が死んだときに猫と椅子をうめ、庭を掘り返したときに作業着姿の男に「猫がいませんでしたか」って尋ねると、「わからない方がいい」と答えられ意味深な感じでしたが、何故かネコは紺野さんがお骨として持っていました。奈々美さんと真知栄子さんは意思も口調も強くおばさんパワー?がたくましい感じ。「穴熊(アナグマ)さん」名前の設定もおもしろい。
ハリネズミ:私、ユーモアは大事だと思うんですけど、おやじギャグみたいなレベルでも中・高生に受け入れられるのかどうか、ちょっと疑問でした。あと、ネコは紺野さんの飼い猫だから、息子のところにまず行くんじゃないかな、なんていう疑問もありました。
げた:ちなみに、醤油は、戦前、徴兵逃れのために体の具合をわざと悪くするために飲んだ人がいたということを聞いたことがあるんですが、死ぬためじゃなくてね。
トトキ:江戸時代に醤油飲み競争をして亡くなった人がいるって話は聞いたような……。
ハリネズミ:エンタメだと仕方ないんだけど、マチエイコを除くと、人物像がステレオタイプかな。
げた:エンタメとして書いたんじゃないですか。
ajian:マチエイコが主人公のほうがおもしろいんじゃないかな。
(「子どもの本で言いたい放題」2014年6月の記録)