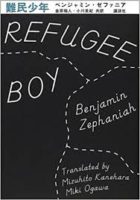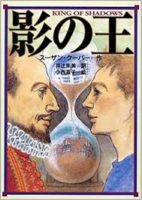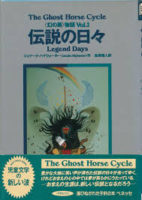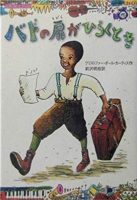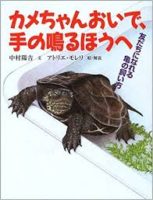花形みつる/著
講談社
2001
版元語録:独りぼっちの私。伝説の巨大女と呼ばれているシノちゃんとボンバーというあだ名のアリサ、なんでこんな人達の仲間に…? 怖いけれど楽しい日々が始まった。
愁童:今回の課題本では一番おもしろく読みました。子どもの「今」が書かれてるって思う。教室から疎外されているような子どもをうまく書いている。現実には、こういう関係って、たじろぐ子が多いと思うけど、主人公に感情移入することで、いろんな人間関係に子どもらしく素朴に踏みこんでいくきっかけになるといいなって思いました。
トチ:イマドキの子どもがこの作品をどれくらい身近に感じるかはわからないけれど、私はとてもおもしろく読みました。シノちゃんとアリサがが漫画的だけど生き生きと描けているし、それぞれの背景も深刻にならない程度にさらっと書いてある。人生の奥深さを感じさせる作品とまではいかないけれど軽い読み物として気持ちよく読めるんじゃないかしら。ただ、「〜なの」「〜なの」という文章が続くところ、語り手のちょっとうじうじしている性格をあらわしているのかもしれないけれど、ちょっとうるさかった。
カーコ:私は、入りこめませんでした。普段見ている小4と小6の子と比べると、この子たちは、確かに今の子が使うような言葉づかいをしているんだけど、想像しづらかったんです。暴力に訴えてくるような子って、家庭的なこととか、何かがあって乱暴するようなことがあるんだけど、この二人は素直でハチャメチャなんですよね。家では安定していて、教室に入るとむちゃくちゃなことを通しているというところに、リアリティを感じられなかった。実際に子どもが読んだら、どのくらい身近に感じられるだろうと思いました。
紙魚:子どものときって、言葉がうまく使えないから、取っ組み合いしたり、体でぶつかってコミュニケーションすることが多いんだけど、だんだん言葉を使えるようになると、言葉でなんとかしようとするじゃないですか。その中間にいる年齢の子どもたちの、体と言葉のギャップをうまく書いていると思いました。シノちゃんやアリサには、体や勢いで人とぶつかっていく力がある。それに影響されて、コタニは、自分が本来持っている力に気づくという過程が、しぜんに伝わってきました。
ハマグリ:今の子どもたちの友だちづくりの難しさ、今の子どものかかえる問題を書きたい人なんだな、ということはわかるんだけど、今の子どもたちを描いている物語って、居場所がなくて浮いている主人公という設定が多すぎて、またかという感じがしましたね。この作家は、文を書くのが好きで、思った通りに手が動いちゃう人なんでしょうけど、この文体はいかがなものかと思いましたね。26ページ「あたしってつまんないやつなの。動きはトロいしギャグもつうじないし、知らない相手だとアセッちゃってなにをしゃべっていいのか、よくわかんないし。云々」っていうけど、自分でそういう割には、この一人称の饒舌なしゃべり方は、「つまんない、トロい」子だという感じがしなくて、違和感がある。この子はこういう子なんですって書くんじゃなくて、どういう子なのかは、行動を通して読者が自然に理解していくものだと思う。
トチ:具体的なところは万引きのところだけね。
ハマグリ:会話文だけでなく、地の文にも今の子のしゃべりことばを多用して、「こーゆー」「トートツ」などと音引きで入るのは気になりますね。しゃべっている言葉と、文章として読む言葉はちがうんじゃないかな。
紙魚:この作品だけでなくて、最近、大人の文芸でも、地の文に、自分でボケて自分でツッコミを入れるという文体が目出つように思います。あと、今の子どもたちって、ふだんの会話でもしぜんとそういうことをやってる。
ハマグリ:一人称の小説って、読者が主人公に心を寄せやすいものだと思うけど、自分ひとりでどんどんしゃべっていく感じと、実際のこの子というものにギャップを感じてあまりくっついていけなかったの。
アカシア:私は、コタニノリコみたいな子っているだろうなと思ってリアルに感じましたね。実際には力を持っているのに、まわりとのつき合い方がわからなくて自分ではトロいと思ってる子って、この年頃にはたくさんいると思う。だから違和感なく入っていけて、とってもおもしろく読めました。子ども同士の会話が、テンポよく進んでいくのがいい。「こーゆー」とか「トートツ」は漫画なんかだとしょっちゅう使われているし古くなるとは思わないけど、「鈴木その子」なんていう固有名詞は古くなりそう。何年かたつともう知らない子が出てきますよね。最後、いなくなったコタニを、シノちゃんとアリサは捜しに捜しているんだろうと思ったら、実際は授業サボって遊んでただけだったというのも、この二人の特徴がくっきり浮かび上がるし、リアリティがあっていいですね。それに対してコタニが「もー、シノちゃんもアリサも、自分勝手でメチャクチャなんだからー」と、最後の最後に大声でどなります。これまでは言いたくても言えなかったのが、最後にふっきれて言えた。三人のこれからを予感させる終わり方で、すごくうまいと思いました。
流:それぞれの人物がありがちではありながら、結局ふつうの子どもはありがちなわけだから、テンポよく読めました。そんなにわざとらしくなくて、しぜんに読めました。
(「子どもの本で言いたい放題」2004年10月の記録)