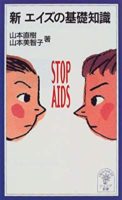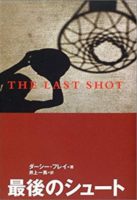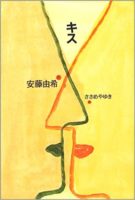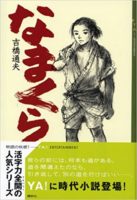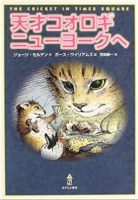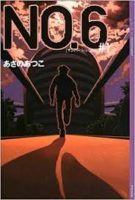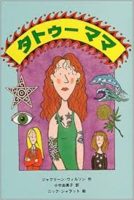原題:SUNNANANG by Astrid Lindgren(スウェーデン)
アストリッド・リンドグレーン/著 マリット・テルンクヴィスト/絵 石井登志子/訳
徳間書店
2005
版元語録:ずっとむかし、身よりをなくした小さな兄と妹が、雪の森で、まっ赤な鳥を見つけました。鳥をおいかけて、二人がたどりついたのは、光あふれる春の草原でした…。「子どもの本の女王」リンドグレーンが、貧しい時代の子どもたちを優しいまなざしで見つめた、珠玉の幼年童話。
トチ:今回選書係のたんぽぽさんによると「いつまでも頭から離れない話」ということでしたが、本当にいつまでも心に残る話でした。語り方も絵もさすがにうまいと思ったし、虐げられている子どもたちへの時代を超えた作者の愛情や、怒りも感じました。特に41ページの「ミナミノハラがなかったら……」という台詞など、こんなに悲しい言葉があっていいの?とまで思いました。『マッチ売りの少女』の世界だわね。ただ、訳者の後書きに「(この物語は)悲しいまま終わっていません」とあったけれど、「??」と思ってしまった。日本の子どもたちは、この物語は死で終わっていると理解するでしょうし、キリスト教の世界ではいざ知らず、日本の読者にとっては「死=悲しいこと」のでは? たとえ天国に行けたって早死にしちゃいけない、そう考えるほうが「まっとうな」気がするんだけど。
たんぽぽ:悲しすぎて、自分の学校の図書館には置いていません。絵本でも、文字量が多いと子どもは手にとりにくいのだけれど、このように幼年読み物にすると、子どもが手にとれるかなとは思いました。
げた:扉を閉めることで兄弟は天国に行ってしまったという、悲しい結末。悲しいから、私の区では全館には置かなかった。絵もいいし、子どもの心に入ってくると思うが。せっかく学校に行ったのに、ひどい目にあうし。
カーコ:何度も何度も同じ言葉でたたみかけられて、イメージが心に焼きついてくるようでした。最初の灰色の世界と、赤い鳥の対比のあざやかさが見事でした。個人的には、『エーミルと小さなイーダ』(さんぺいけいこ訳 岩波書店)のような明るい作品のほうが好きですが。
ハマグリ:リンドグレンの中では、悲しいお話なんだけれど、子どもはたまに悲しーいお話を読みたいと思うときがありますよね。貧しくて、みなしご……それだけで、子どもをひきつける。リンドグレンの作品集(岩波書店)の中でも、とくに『小さいきょうだい』や『ミオよわたしのミオ』が好きだという子どもも時々いるんですよ。赤い鳥の国とは、キリスト教でいう天国を表していて、現世では救われないんだけれど、最後に救いがあるということでしょうか。『小さいきょうだい』には全部で4話の短編がはいっていますが、その中の1編をこのような形で1冊の本として出してくれると、読みやすいし、読者が広がるのがいいですね。岩波版の訳者大塚勇三の独特の口調は捨てがたいですが、石井登志子訳はくせがなく平易だと思いました。挿絵画家も違い、こちらは、村の中でも森の中でも、兄弟の姿をことさら小さく描いていて、読者が心を寄せざるをえないんですね。前後の見返しの絵もいい。
アカシア:新しい作品だと思って読み始めて、途中から「ああ、これは『小さいきょうだい』で読んだ話だな」と思い出しました。リンドグレンは多才な作家ですよね。楽しい作品もあれば、悲しい作品もあるし、子どもの日常を描いた作品もあれば、ファンタジーもある。年齢対象もいろいろです。扉を閉めるというのは、自殺することなんでしょうか? リンドグレンは、本当に辛いとき、そういう道を選ぶことも認めているんでしょうか?
アサギ:私は悲しいお話はあまり好きじゃないけど、悲しい話を読みたいというのは、確かにあるわよね。
トチ:読者である自分を安全なところに置いたままカタルシスを味わうというのは、ちょっと後ろめたい気がするけどね。特に子どもの本の場合は。
アサギ:最後に死んでしまうのだから、悲しくてやっぱりわたしはだめ。『人魚姫』(アンデルセン作)とか『フランダースの犬』(ウィーダ作)とか、子どものときは読んでいたけど。これはたぶん年齢とも関係あると思うんだけど、だんだん悲しいものは辛くなってきた。
トチ:わたしはハマグリさんの意見と同じで、こういう本があってもいいんじゃないと思うけど。
アカシア:子どもの読者は、最後死んだとは思わないんじゃない?
トチ:いや、子どもはもっと読書力があると思う。
アカシア:そうじゃなくて、今の子はファンタジーも読んでいるから、アナザーワールドに行ったと思うかも。リンドグレンは、天国を信じているんでしょうから、現世では辛い体験しかあたえられない子どもたちに、ここで救いを与えているのだと思いますね。
愁童:僕はこれを読んで、これまであったリンドグレーンへの好感度を自分の中から削除しちゃった。悲しいお話が好きな子は確かにいるけど、何かこの作品、そんな読者を意識したショーバイ・ショーバイって感じがして好きになれない。こんな本読んで育つから、練炭持っていって一緒に死のうみたいな若者にが増えるんじゃないの? せめて、『青い鳥』(メーテルリンク)じゃないけど、どこかに青い鳥がいるから自分でさがしに行ってごらん程度のメッセージがあってもいいんじゃないかな。苦しかったら死んじゃいな、みたいなことを、自分は安全な所にいる大人から言われたんじゃ、子どもはたまらないぜ!
トチ:たしかに作者は善意で書いているし、こういう子どもたちへの愛情や大人たちへの怒りも感じるけれど、愁童さんに言われてみると、これは愛情ではなく哀れみなのかも、って気もしてきたわ。
げた:子どもに向けて、手渡すのに抵抗を感じたのは、これでは子どもが救われない、悲惨すぎると思ったからなんです。
アカシア:でも、物語の舞台は今の日本じゃないですよね。日本にいると見えないけど、今だってこの子たちみたいな子はいっぱいいる。その子たちに向かって、「おまえたち死んじゃだめだ」っていうだけで、現実には何もしなかったら、もっと救いがないのでは?
(このあと、リンドグレーンの姿勢について熱い議論が続く)
(「子どもの本で言いたい放題」2006年4月の記録)