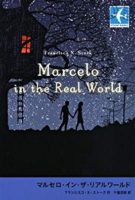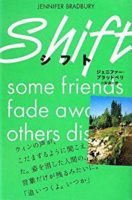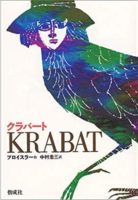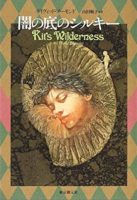原題:CLOSE TO FAMOUS by Joan Bauer, 1996
ジョーン・バウアー/著 灰島かり/訳
小学館
2013
版元語録:主人公フォスターは、毎日必ずケーキを焼くことにしている。なぜって、そうすれば、いつでもどこでもおいしいものが食べられるから。そう、フォスターは、カップケーキ作りの天才なのだ。ある日、ママと二人で家を出て、新しい人生を送ることになる。フォスターを待ち受けているのは…? カップケーキのようにあまくはないサクセスストーリー。
さらら:外に飛び出していくことで、だれも認めてくれない自分の才能を発見するという設定が、子どものころから大好きなんです。しかも、お菓子作り、という要素が、食いしん坊の私にはたまらない。主人公が得意なのはカップケーキを焼くことだったり、プレスリー好きのハック(ママの元恋人)が登場したりと、なにもかもとてもアメリカ的な背景で、私もアメリカの女の子になった気分で読みました。下宿先のレスターが、釣りをたとえに、人生ってこんなもんじゃないかと、いいことを言うんですよね。そういうのが非常にうまくからみあっている。いろんな意味で楽しませてもらった一冊でした。
プルメリア:読みやすい。チャリーナさんとの関わりを通じて、言葉を習得していく過程がとってもわかりやすかったです。話せても言葉を理解することは難しいんだなって改めて思いました。子ども(小学校5年生女子)から感想を聞くと「ハックはいやな人」「チャリーナから読むのを教えてもらうかわりに、チャリーナにお料理を教えてあげるのがおもしろかった」「チャリーナが賞状をあげるところに感動した」でした。読書が好きな女子は2時間ぐらいで読み終えていました。
レジーナ:バウアーの『靴を売るシンデレラ』(灰島かり/訳 小学館)の主人公は16歳でしたが、この本では6年生です。しかしその年齢の子どもが経験するには、非常に辛い状況です。シャワーを浴びながら泣いている母親の声を聞く場面など……。ケーキという、人生に喜びを与えるもので、家庭の暴力やディスレクシアなどの問題に立ち向かうというテーマが、とても明確に打ち出されています。チャリーナ夫人からもらった小切手を、自分のために使うのではなく、罪を犯した家族を支える場「手をつなぐ人の家」のために使うのも、好感がもてました。誇り高く、過去の栄光にしがみついている有名人のチャリーナは、E・L・カニングズバーグの『ムーン・レディの記憶』(金原瑞人/訳 岩波書店)を思い出させます。周囲の雑音に惑わされるのではなく、心の中の静けさや平安を守り、自分を大切にするよう語るレスターやチャリーナをはじめ、信念を貫くパーシーや、けちなウェイン店長、プレスリーに憧れ、自分に酔っているハックなど、味のある個性的な人物が登場するので、あまり盛りこみすぎず、人物を減らし、何人かに焦点を当てて、深く描いてもよかったのかもしれませんね。
たんぽぽ:おもしろかったです。6年生が、感動したといっています。お菓子というのも、まず惹かれるようです。チャリーナが登場する場面も、ドキドキしました。母親が、いつも自分を、認めてくれているのがいいです。私自身もそういう子どもに、やさしく、気長にせっしたいと、思いました。
ジラフ:アメリカのアクチュアリティが、すごくよく出ていると思いました。アメリカではいま、カップケーキがとっても流行っているし、イラク戦争でお父さんが亡くなっているとか、DVの問題とか、大人と子ども、それぞれの矜持が描かれているところとか。人生に対してつねにポジティブなアメリカを感じました。それと、食べ物が大きな力になっているところも魅力的でした。以前、研究生活からドロップアウトしてしまった友人が、パンを焼くことでまた生きる元気を取り戻したことがあって、食べ物や料理の持つ力をあらためて感じました。裏表紙にレシピが載っているのもいいですね。この作品についてではないですが、「前向きに生きのびる」というのはしんどい場合もあって、逆に、内向きに閉じることで生きのびられる時もあるかも、ということを、一方で考えました。
アカザ:同じ作者の『靴を売るシンデレラ』も良かったけれど、この作品もすばらしかった。主人公と母親のところにDV男のハックがいつ現れるかと、読んでいるあいだじゅうハラハラさせられて、最後まで一気に読んでしまいました。ディスレクシアの主人公の口惜しさや悲しさも胸に迫るものがあったし、それをカップケーキ作りにかける夢と才能で乗り越えていくというところも良かった。登場人物の描き方が、大人も子どももくっきりしていて、読んでいるあいだはもちろん、読んだ後もしっかりと心に残っています。主人公の身の回りだけではなく、刑務所のある田舎町の様子や出来事も描いているところに社会的な広がりを感じさせますが、良くも悪くもとてもアメリカ的。カニグズバーグに似ているなと思ったのですが、カニグズバーグの作品のほうが、もっともっと世界が広いのでは?
カボス:最初からずっと緊迫感や謎があって、それに引っ張られながらどんどん読めました。おもしろかった。コンプレックスが拭えなくてさんざん苦労したフォスターの複雑な心理が、うまく読者にも伝わるように書けていますね。またSNSやメールではなくて、人間と人間が実際に出会ってお互いに変わっていくというのが、とてもいいですよね。出てくるケーキはどれもおいしそうなのですが、日本の家庭ではもうあまり使わなくなった着色料などが平気で出てくるのは、アメリカ的ということなのでしょうか? p250でレスターがフォスターの父親をほめているところにも、弱さを克服することがすばらしいことなのだというアメリカ的な価値観が出ているように思いました。戦場で勇気をもつということがどういう意味をもつのか、そのこと自体の是非については疑ってもいない。丸木俊さんが近所の子どもたちに「戦争が始まったら、勇気なんか出さなくていいから、とにかく逃げなさい」と言っていたことを思い出しました。
コーネリア:この作品は、物語がものすごく都合よく進んでいくのですが、それが許せるおもしろさがあると思います。文中に、ジョン・バウアー格言が矢継ぎ早に、次から次へと出てきます。私もこの言葉にぐっと惹かれましたが、子どもだったら、大人よりもストレートに入ってくるのではないでしょうか。勇気づけられる作品。
夏子:主人公が12歳にしては大人ですよね。小学生向けの本なのか、ヤングアダルトなのか、ちょっととまどうところがありました。この作家は『靴を売るシンデレラ』にしても『希望(ホープ)のいる町』(金原瑞人・中田香/訳 作品社)にしても、いつも大きな問題を抱えた主人公を描きますよね。今回も、ディスレクシアや、お母さんのつきあっていた男性のDVやら、問題が山盛り。ちょっと教訓っぽいところがあるけど、主人公が自分はどうしたら幸せになれるか、一生懸命考えて、手探りしながら生きていくところがいいですよね。この本では子どもも大人も、奥行きのある人間としてしっかり描かれている。印象的な女優のチャリーナさんが、こちらもディスレクシアとちょっと都合のいいところはあるけれど、それが許せるのは陰影と味わいのある人物だからなんでしょうね。ちょっとカニグズバーグを思い出しました。
(「子どもの本で言いたい放題」2014年1月の記録)