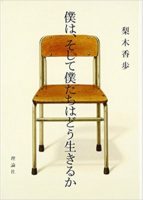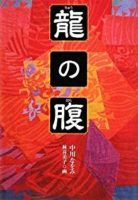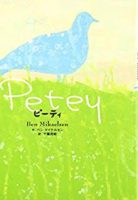原題:CHOCKY by John Wyndham, 1968
ジョン・ウィンダム/著 金利光/訳
あすなろ書房
2011.02
版元語録:11歳の少年マシューの様子がおかしい。その裏には「チョッキー」という名の不可思議なモノが……。未知との遭遇を描いた傑作SF。
きゃべつ:私は、SFをあまり読んだことありませんが、初心者でもわりと読みやすかったです。ただ、直訳っぽいところや、1文が長いところがあって、子どもにとっては、少し読みにくいかなと思うところがありました。ずっと大人目線ですが、子どもはどう読むんでしょうね。もう少し、子ども目線のほうが、読みやすかったんじゃないでしょうか。
紙魚:私もSFを読みなれていないのですが、これはとてもオーソドックスな筋運びで、異星人が未知の世界からやってくるという典型的な物語。こうした設定は、小説でもドラマでも映画でも、もう何度も何度も描かれてると思うんですが、この本がおもしろく読めたのは、そうした未知のものに出会ったときに、人間はどう反応するのかということがていねいに書かれていたからなのではと思い至りました。さまざま風変わりなSFが出てきても、結局、奇天烈なものを見たいというわけではなく、そうしたときの人間の反応を見たいのだと。
レンゲ:ファンタジーもSFも苦手なのですが、この本は論理的にわかって、問題なく読み進められました。『チョッキー』も『ジェンナ』も構成がきちんとしていて読みやすかったです。でも、自分では手にとらない本だと思う。読み始めたときに、まず語り手が誰なのかなと思って、どうやらそれが大人だとわかってきて、大人が主人公でもいいわけですけど、誰に向けて出した本なのかなと思いました。つくりも大人っぽいし、ルビもちょっとしかない。中学生に読ませようというルビのふり方ではないですよね。得体の知れないものとの出会いと、それに対する反応は興味深く読めますが、とびぬけておもしろいとまでは思わなかったので、わざわざ新訳で出し直したのはどうしてかと思いました。確かに1968年の本なのに、マスコミとかお母さんの反応が今と変わらないのはおもしろかったし、夫婦の2人の子どものうち、片方は自分の子で、片方は養子にした子だけど、わけへだてなくかわいがってところは感じよく読めました。
トム:宇宙人に会えたらドキドキしてもっと嬉しくなってしまいそうだけれど、マシューは苦しそう。それは、p268にあるように“ホストとしての精神的資質を持ち”“あれこれ疑問を持たずに受け入れようとする”、それができる子どもとしてチョッキーが見つけたのがマシューで、その出会い方にもあるのでしょうけど。ただ、時にはチョキーとマシューの楽しい交信も垣間見られたらと思いました。マシューはチョッキーに真っ向から向き合っている……、そこにマシューがどういう心をもった少年なのか感じられます。最終場面で表彰メダルが自分宛でなく、チョッキーの名になっていることを本当に喜ぶ様子は、マシューの人柄を伝えているし、チョキーとの信頼も伝えていて、とても温かい余韻を残りました。お父さんと息子の物語として読んでも読みごたえがあって、いつの間にかそちらにひっぱられてもゆきました。その中で、お母さんは安心を得ることに気持ちが逸ってかなり混乱した様子が描かれているけれど、お父さんが時々立派すぎるかも……。
p261でお父さんが「わたしたちは、原子力を手にしているのですよ」と言ったことに対してチョッキーが「認めましょう。だがきわめて粗雑な水準にありますね」と言っていますが、新たな翻訳としての初版発行が2011年2月28日で、この11日後に福島原発の事故が起きています。偶然とはいえ物語が一歩先を歩いているよう。p265“宇宙の隅々にまで存在する放射”とか、私には具体的なイメージが描けないけれど、SF好きな中高生ならきっとワクワクする世界なのでしょうね。p268 “老いた精神はありうることとありえないこととの区別をかたくなに守る”という件は、個人的にズシッと胸に響きました。
みっけ:著者の最後の作品というのだと、子ども向けに書かれたわけではないのかな、という気もするのですが、どうなのでしょう。はるかかなたからやってきた、いわば異星人のようなものが、普段の生活に入ってきたという設定はSFなんだけれど、やってきたものの外見や行動などではなく、それが来たことで、普段の生活がどうなり、家族の中がどうなっていったかに焦点が当たっているので、あまりSFという感じはなく、両親や本人の行動がていねいに書かれていたので、人間の物語としておもしろく読めました。日本にはない英国男文化の伝統というのかな、父と息子の関係がとても強いんだけれど、そのあたりがよく書けていました。チョッキーの姿を最後まで書かず(息子の声を借りていて)、声も聞かせないのも、うまいなあと思いました。おそらくそのあたりを書いたとたんに、私なんかは嘘くさく感じてしまいそうだけれど、あくまでもそれをせずに,読者の想像力にゆだねている。これってどう着地するんだろう、と思いながら読み進んでいったら、10章でマシューがいなくなりますよね。それが実は権威筋による誘拐だったというのには、あっと思ったし、感心しました。しかも、権威筋の誘拐が今後起きないようにとチョッキーがマシューの前からいなくなる。というのもいいですね。とにかく、SFはわりと苦手なのですが、親と子の関係に焦点がおかれていたので、とてもおもしろく読めました。マシューの失踪についての説明がいっさいされずに事態が進み、最後の最後にチョッキーがお父さんにさよならするところでその一件が種明かしされるあたりも、なるほどと思いました。
サンシャイン:非常に気に入りました。早い段階で人間が開発した車が非効率でという話が出てくるので、未来の存在という予想は立ちましたが、実の子ではなく養子なので、実の子ではないことで展開されるのかと思いきや、そうではありませんでした。妹の方の、見えない存在にとりつかれているというのはよくあることなのですか? お医者さんの友達が診て、「憑きもの」とか「お告げ」という話を母親が受け入れないという反応をしますが、父親の方はそれを受け入れようとする、その心情の差もよく書けていると思いました。「原子力」が出てきますが、さらに「放射」のあたり、子どもの語彙にないということでぼかされていて、私たちにはわかりません。作家の頭のなかには、そういう、人類がまだ手に入れていない存在が見つかるというのがあるのかもしれません。宇宙にはそういうものがあるかもしれないと思わせる文章力。最後は、子どもの口を借りて、乗り移ったかたちで真相が明らかになるのは、こういう方法でしか種明かしすることはできないかなと思いました。いずれにせよ、非常におもしろく読めました。
フルフル:児童書か、一般書かという点ですが、コードが一般書で、出版社としては一般書として出しています。でも、いってみれば、YAだと思います。文体も自然で、読んでいて、とても読みやすかったです。でも、1968年に出されたもののリバイバルとは気付かなかった。感覚的に受け入れやすかったのは、昔に書かれたものだからなのかな〜、それもちょっとショックですが……。たぶん今、最先端で書かれていたものではなくて、SFといっても読みやすかったのかなと思います。現代っ子が好む読み物だと、話の展開が早くて、次々といろいろな事件が巻き起こるというものが流行りますが、この作品は、前半のテンポがゆっくりめ。マシューが目に見えないチョッキーとつきあっていく過程は、とてもおもしろく読めたのだけど、なかなか話が動かないので、いつまで続くのかなと思っている自分に愕然としました。自分も毒されちゃったのかしらと……。水に溺れるところから急展開しますが、それまでは中だるみしているように感じていまいました。現代っ子同様に、せっかちになってしまっているのかもしれません。溺れたところからはラストまでは引っ張って読ませてくれました。
ただ、印象として、この内容のものだったら、前半のテンポを上げて、もう少しコンパクトになるかもしれないとも思いました。今の子どもたちには、300ページを超えるとちょっと長い(?)印象があるかもしれませんし、壮大な物語が展開するのではないので、もう少しコンパクトに読めたら読者も広がるかもしれないと感じました。最後、チョッキーが語っているところで、「現代人は燃料の無駄遣いをしている」という語るところにドキッとさせられました。原発事故があっただけに感慨深かったです。また、50年以上前にこういう作品が描けた作者に敬意を表したいです。
すあま:私は大人の本として読みました。語り手がお父さんであるからかもしれませんが、マシューの気持ちになって読み進めるというよりは、お父さんの気持ちに寄り添って読みました。かなり大変な状況なのに、このお父さんは冷静で、奥さんが半狂乱になっているのにも落ち着いて対応している。語り手が落ち着いているので、パニック小説のようにならず、読み手も落ち着いて読めたように思います。怖い話として書ける話なのに、怖くなく、読後感もよかった。妹にも同じように見えない女の子と会話する時期があり、『弟の戦争』(ロバート・ウェストール著 原田勝訳 徳間書店)や『まぼろしの小さい犬』(フィリパ・ピアス著 猪熊葉子訳 岩波書店)などを思い出しました。途中からチョッキーが宇宙人だと気づいてからは、どう種明かしするのかと思っていたら、当の宇宙人が全部説明してくれた。宇宙人が地球を見つけて偵察にきて人間の生活に入り込む、という話は、なぜ今頃出たのかと不思議に思ったけれど、刊行年を見て、60年代に出たなら古くないかと納得しました。むしろ今読んでも違和感がない。パソコンが出てこないなど、「今」ではないことに気づいたものの、古さは感じずにおもしろく読めました。ただ、誘拐事件はチョッキーの仕業で宇宙人にさらわれたと思っていたのに、普通の誘拐だったのでちょっとがっかりしました。
プルメリア:少年に霊がついているのかと内心ドキドキしましたが、あとがきに宇宙人と書いてあったのでホッとしました。少年に寄り添うお父さんの心情が全体に出ており、妹が時々話す馬の話はユーモアがあり、重たい雰囲気を和らげていたように思いました。最後に、もらったメダルにチョッキーの名前が刻まれていたこと、なんとなくぎくしゃくしていた少年と父親の心がつながったように読みました。
ハリネズミ:おもしろく読みました。科学知識の部分も、まだ古びていないのでは? 今は、昔の映画に出てきたような宇宙船とか宇宙人像は違うとわかっています。でも、広い宇宙のどこかには知的生命体ってきっといると信じて、その人たちと交信しようといろいろな試みをやっている科学者がいます。それから今SFで近未来を書こうとすると、どうしてもディストピアになってしまうんじゃないかな。この作品はちょっと前に書かれたということもあって、希望のある明るい終わり方。チョッキ—もいい人じゃないですか。だから、暗くならないんですね。
みっけ:この本で二進法の話を出しているのは、十進法というのが、人の指が10本だという解剖学的な事実から採用されてるのに対して、異星人が必ずしも十進法を採用しているとは限らない、という相対化のためだと思うんです。さらに、この作品が発表された頃は、コンピューターが出てきて二進法がクローズアップされた頃だったので、三進法やなにかにするよりも二進法のほうが最先端でもあり、多少のなじみもありという感じだったからではないかな、と思います。それに原子力に関する話は、天文関係の科学史を見てみると、原子力の発見は今の私たちには想像できないくらいポジティブにとらえられていて、それがチェッキーに対する語り手の発言にも反映しているんだと思います。もう一つ、チョッキーが、原子力など使わなくても、どこからでもいくらでもエネルギーを取り出せる、と言っているのは、おそらく宇宙の始まりであるビッグバンと呼ばれる大爆発の余熱の「宇宙マイクロ波背景放射」を取り出すという話で、こういった話が出てくるところからも、この作品は科学の最先端の結果や理論を取り入れているという点で、ちゃんとしたSFなんだなあと思います。
(「子どもの本で言いたい放題」2012年6月の記録)