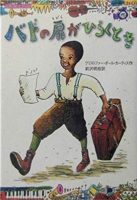
原題:BUD, NOT BUDDY by Christopher Paul Curtis, 1999
クリストファー・ポール・カーティス/作 前沢明枝/訳
徳間書店
2003.03
<版元語録>ニューベリー賞受賞 バドが六つの時にママが死んだ。10歳になったある日、バドはひとりで、まだ見ぬお父さんを捜しにでかけることにした。ママが遺してくれたジャズバンドのチラシを手がかりにして。一九三〇年代の大恐慌のまっただなか、もちまえの明るさと知恵で困難を乗りこえていく黒人少年の姿を、ユーモア溢れる語り口で描いた感動的な物語。
トチ:ニューベリー賞をとったときから、おもしろそうな本だなと思っていました。『穴』(ルイス・サッカー作 幸田敦子訳 講談社)や『シカゴより怖い町』(リチャード・ペック作 斎藤倫子訳 東京創元社)と同じような、ストーリーと歯切れのよい文章で読ませる本。トム・ソーヤーやハックルベリー・フィンのころから脈々と続いている、アメリカ文学の伝統のようなものを感じました。深刻な内容なのに、ほら話のノリで、読者をじめじめさせない。いまのアメリカの児童文学は元気がいいと思います。「バドというのは、つぼみという意味なのよ」と主人公の母親が語るところで、ジーンときました。
カーコ:とても楽しく読みました。まず、どこまでも子どもの視点で書かれていることが目をひきました。「バドの知恵」で、大人の世界のたてまえと本音をユーモラスに指摘しているのもおもしろかった。それから、大人の人物がとても魅力的ですよね。バドを車に乗せてくれるおじさんもすてきだし、ジャズバンドの人たちもいい。訳も、歯切れがよくてよかった。作品のおもしろさを、よく引き出していると思いました。
ケロ:『穴』に似てたんですね。鉛筆を鼻につっこまれたり、蜂にさされたり、辛い状況にいるのだけれど、運を自分の味方につけちゃう。励ましてもらえる。どんどん辛いまま落ちこんでいく作品もあるけれど、こういうふうに元気づけられるのもいい。
羊:施設からいろんな家に送られたりすると、「バドの知恵」というようなのが身に付くようになるんですね。おもしろかった。
ブラックペッパー:私はあまりのれなかった。10歳というのはどういう年齢なんだろうとか思ってしまった。自分突っ込み型の一人よがり。『はいけい女王様 弟を助けてください』(モーリス・グライツマン作 唐沢則幸訳 徳間書店)のときと同じように、のれなかった。6歳で母親は死んでしまったのに、こんなにおぼえているのも不思議でした。
きょん:私はすっきりとおもしろく読めた。「バドの楽しく生きる知恵」は、サイコーだと思う。うまくごまかしながら、適当に合わせて、でも自分の価値観やプライドを失わずに、自分なりにユーモアで大波をのりこえていく。マーク・トウェインの『ハックルベリーフィン』と似てるといわれて、そうだな、と思った。そういうのがアメリカンスタイルなのですか? また、バドが、純粋に誠実に生きている姿は好感が持てます。全体に流れる「臨機応変に困難を乗り越え、まわりの人々ともうまくやりながら、大波を乗り越えて生きる」という思想にとてもひかれました。今の子どもたちには、いいメッセージだなあと思って。どこにいても、「潔癖にいい子」を求められて、過剰に干渉され、管理されているのが今の子どもたち。そんな子どもたちも、「適当に」「臨機応変に」でも「誠実に」生きていってほしいというメッセージが感じられますね。でも、「ママの持っていたチラシから、バンドマンがおとうさんだと確信して、遠路旅に出る」ところとか「バンドマンがおじいちゃんだったところ」「家出した娘を思って悲嘆にくれるおじいちゃん」などは、ちょっと安易だなあと思いました。その後、ハーマンがどうなったのかもちょっと気になりました。
ねむりねずみ:魚の頭と出くわすところなんか、かなり大げさに書いているんだけれど、それがいかにも子どもの早とちりのドタバタらしくていい。いろいろ苦労していて、それなりに抜け目がなかったりたくましかったりするのに、それでいて純情だったり言葉づかいがていねいだったりと、この主人公の作り方がおもしろいですね。ぎっちょさんとのやりとりで、労働組合のことを知って危ないところに近寄るまいとなんとか逃げようとがんばるあたりも、リアリティがあります。人がよくしてくれると、うまくそれに乗っていつもその場に居場所を確保する。とてもじょうずにその場にとけこむのに、その一方で決してかばんを手放さずいつも放り出されることを覚悟しているあたりも、主人公の苦労がしのばれます。だから、最後にかばんの中身を広げるところで、ぐっと胸に迫るものがあるんですね。同じ作家の『ワトソン一家に天使がやってくるとき』(唐沢則幸訳 くもん出版)も読んだけれど、たいへんなことをおもしろく書いてしまう人だなあと、好感を持ちました。作者のあとがきでモデルがあると知ってびっくり。大変な時代のリアルなモデルを土台にして、明るい雰囲気のフィクションを作り上げたところにひたすら感心しました。
アカシア:『ワトソン一家〜』は英語で読んで、新しい作家だと感じました。文体がとても軽快でユーモアたっぷりなのだけど、歴史とか家族とか人種などのこともまじめに考えているのがわかる。アフリカ系アメリカ人の作家ですけど、差別とか抑圧を声高に言ったりはしない。『ワトソン一家〜』では、黒人の教会が爆破される事件が登場しますけど、エピソードとして出していて、糾弾したりはしない。この作家は、むしろ誰もがかかえる日常を書いていくのだけれど、文体のリズムだとか、生活の描写に、アフリカンアメリカンらしさが強く出ています。それに、この作家は、しかつめらしい顔をして書くのじゃなくて、自分も笑いながら書いているんじゃないかってところがありますね。こういう作品は、ユーモアにしても文体のリズムにしても、翻訳でその雰囲気を出すのは難しいですよね。この日本語訳も、最初だけ重いなあと思いましたが、だんだんに軽くなって読みやすくなりました。
ペガサス:久しぶりに、子どもらしい楽しい本を読んだなあと感じました。子どもらしい感覚をもとにした記述が随所にあるところがいいですね。p102の4行目、ママが持っていたチラシが気になってどうしようもなくなるというのを、カエデの大木にたとえているが、どのくらい高い大木になっていくかを子どもらしい表現で書いています。p154の後ろから4行目、お父さんに会いに行って、いよいよ扉をあけたと思ったら、「なんだ、中にまた扉がある」なんて、とてもユーモラス。そういうところも楽しかった。最後は、単におじいちゃんとバドの感動の対面という形で終わるらせるのではなく、素敵なバンドの仲間たちに一人前に扱ってもらって、仲間にしてもらうという形にしたのがよかったです。このように扱われるのは子どもにとってとても満足のいくことだし、読者には、ここで終わりではなく、この子のこれからの人生までが目の前にぱーっと見えてくる感じがします。訳は、名前で「ネボスケ・ラ・ホーネ」とか、うまく日本語にしているなと思いました。
愁童:すごく微妙な感じ。いいお話だなと思う反面、「ユーモア」って感じはぜんぜんしなかった。苛酷な環境を生きてきたということが、どんな場面でもきちんと読者に感じられるように書かれているのは、すごいなって思った。最後、いい大人ばかり出てきて、調子いいなって感じもあるけど、そこに到るまでのパドの描写に説得力があるので、素直にほっとしちゃうね。ほっとして読み終われる本て、今、必要なのかもな、って思いました。
トチ:孤児院にいても、プライドを失わない主人公の生き方とか、歴史的な背景は知らなくても、日本の子どもにじゅうぶん伝わるところがあるのでは?
愁童:一人称で書かれているのに、客観描写のようにジャズマンや運転手の人物像がはっきりとイメージ出来る。うまいなって思いました。
アカシア:アフリカ系の作家だと、ミルドレッド・テーラーが『とどろく雷よ、私の叫びをきけ』(小野和子訳 評論社)のシリーズで、同じ時代を舞台にしてますよね。そっちは深刻な差別を、まなじりを決してえぐり出すように書いています。でも、カーティスは若い世代ということもあって、差別は随所の記述から推し量れるけど、それを正面から糾弾するわけではない。原文はもっとユーモアがあるのかも。でも、同じ質のユーモアを日本語で表現するのは無理ですよね。
すあま:気持ちよく読めたし、読んでいて楽しかった。安心して終わるしね。「何かが閉じても新しい扉が開く」と信じて進んでいくから、ロードムービーのように、どこに行きつくかなと思いながら読み進めていきました。現代の本だと、大人も不安定で自信がなく描かれていますが、時代が前のものだと、大人がしっかりしていて、子どもたちにきちっと接しています。バンドの人たちの子どもとの距離感がいいですね。最後は、うまくいきすぎかもしれないけれど、謎解きのようになっていて、すっきりとして読み終えられました。装丁の絵もいいな。
(2003年05月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)