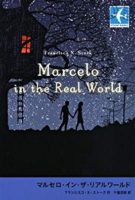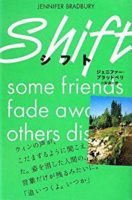井上林子/著 宮尾和孝/挿絵
講談社
2013.07
コーネリア:こういう男の子いるだろうなって、楽しく読みましたけど、マンガチックな構成で、読み飛ばしてしまって、心に残らなかった。小学生くらいの男の子だとが読みやすいのかもしれません。
レジーナ:タイトルを初めて聞いたときは、ゲイのカップルの物語かと思いました。「やっと日本の児童文学でも、そうしたテーマを扱うようになったか!」と思ったのに、ふたを開けてみたら、シングルファザー同士で暮らしている設定でした。小学6年生が、おぼれている子どもを助けるのは、そう簡単にはできないので、リアリティーが感じられませんでした。また、家出していることに気がつかず、主人公の持っているパンを見て、「朝食を持参しているなんて、用意がいい」と言ったり、「ぐるぐる」という呼び名を本名だと思ったり、夜パパがあまりにもとんでいて浮世離れしているので、ファンタジーの世界に迷いこんだように感じました。主人公は、自ら状況を変えようとはしていない。いわば逃避ですね。リアルな設定なのに、異質な空間が唐突に現れ、主人公はそこに逃げこみ、しばらくの間、現実とは別の時間を過ごす。しかし児童文学では、家出や旅を通じて、それまでと異なる自分になって帰ってくることが大切なのではないでしょうか。たとえば、E・L・カニングズバーグの『クローディアの秘密』(松永ふみ子/訳 岩波書店)では、家出をした主人公は、自分だけの秘密を持って、家に戻ります。でもこの物語では、主人公の中のなにかが決定的に変わったり、成長したりはしない。挿絵の宮尾和孝さんは、ジェラルディン・マコックランの『ティムール国のゾウ使い』(こだまともこ/訳 小学館)や中村航文の『恋するスイッチ』(実業之日本社)の表紙も描いていらっしゃる、今人気のイラストレーターですね。
さらら:ストーリーラインは単純で、言葉も台詞のやりとりで続いていく。映画みたいで、ラノベに似ていますね。目で見える情景が続いていて読みやすいけれど、軽い。家事をやらないお父さんに対する、子どもからの反撃というのは、私が好きなテーマですけど、文体についていけなかった。ちょっと文章のつくり方が粗いのかなあ……。
夏子:状況の設定が秀逸だと思いました。父子家庭の集合体っていうのは、母子家庭の集合体と比べると、今ひとつリアリティーがないでしょ? だから、理想化できるのでは? ほら、ひまわり畑の真ん中にあるという「夢の家」にいるのがオッサンなわけだから、イメージが新鮮になるじゃない。とはいえ「ひまわりの家」のポイントは、朝パパの超楽天的な個性ですよね。「テキトー、ずぼら、いいかげん。でも超ハッピー」で、これはまあ、パターンかな。この個性を、夜パパが讃仰していて、それで共同体ができあがっている。めぐる君も影響を受けて、やがて「うちのお父さんのようなテキトーなやり方もありかも」と受け入れるようになる。よくあると言えばよくある展開ですが、私は楽しく読みました。女の子はペアの天使というキャラですよね。ジャラジャラとアクセサリーをつけているのは、フラワーチルドレンというか、ヒッピー風。深読みすると、お母さんがいないという欠落を、なんとかして埋めたい衝動があるとか? ただイラストが、髪型やらリボンやら正確でなくて、残念です。こういうふうに、登場人物をパターンやキャラで描くところが、ラノベとかマンガっぽいんでしょうね。でも主人公は家出をすることで前に進んだからこそ、「他者を受け入れる」という課題を成し遂げたわけで、なかなか良い本だと思います。
たんぽぽ:どうかなって、思ったのですが、読んでみたらおもしろかったです。3年生ぐらいから高学年まで、よく読んでいます。家出という設定も好きで、主人公の気持ちが自分たちと重なるようです。最後に父親がわかってくれたというのも嬉しいようです。これも食べ物を囲むシーンが度々出てきますがあたたかい気持ちにさせてくれます。
ジラフ:私もうまく乗れなかったくちで。やっぱり、ゲイのカップルかなあ、と思いました(笑)。シチュエーションがちょっと“おとぎ話”みたいで、吉本ばななの『キッチン』(福武書店、角川書店)を思い出しました。『キッチン』は性転換したお父さん(というかお母さん)でしたが、日常の中で、そういうおとぎ話的な場所を持つことでやっていける、生きていかれるということはあるなあ、と思いました。
アカザ:ノリが良くて、最初からすらすら読めました。キラキラした女の子たちが出てきたところで「あれ、これはファンタジーなのかな? ふたりともこの世ならぬ存在で、キングズリーの『水の子』(阿部知二/訳 岩波書店ほか)みたいな展開になっていくのかな?」と思いましたが、そうはならず最後までリアルな作品なんですね。でも、なんだかリアルではない……。登場人物の書き方が記号的で、あまり体温が感じられないからなのか。たしかに主人公も主人公のパパも、家出事件の前と後では心境も変化しているし、成長もしているだろうし、ある意味、児童文学のお手本ともいうべき書き方をしているんだけど……最後まで嫌な感じはしないですらすら読めるんだけど……なにか薄っぺらいというか、心にずしんと訴えかけてくるようなものがなかった。これは、無いものねだりなのでしょうか?
夏子:すらすら読める、というのもポイントだけれど、それだけでいいと思ったわけではなくて、家出という問題解決の方法を、私は評価したいです。
たんぽぽ:4年生ぐらいで読めない子がおもしろいなーって、他の本にも広がるきっかけになれば良いなと思います。
ジラフ:作者のプロフィールを見ると、梅花女子大の児童文学科を卒業して、日本児童教育専門学校の夜間コースで勉強していたそうなので、ひょっとしたら、いい子どもの本の書き方のお作法みたいなものが、知らず識らずのうちに身についてしまっているのかも、とふっと思いました。
カボス:お父さんへの不満ですけど、子どもから見れば大きいんでしょうね。大人から見れば些細なことでも、そう簡単に許すことはできないから。女の子二人が溺れたのを助ける場面は、ちょっとご都合主義的だと私も思いました。私は朝パパのキャラが好きだったんですけど、いつも飛ばしているはずの親父ギャグが途中から出なくなるので、残念でした。なかなかおもしろいシチュエーションで、父子家庭が助け合って暮らすというのは現実にはあまりないでしょうけど、こういう作品が出ると現実でもアリかなと思えてきて、そこがいいですね。
コーネリア:家出とか、お料理ものとか、子どもが喜びそうなものがちりばめられていて、読む間は子どもも楽しめるのですけれど、印象に残らなかったんですよね。
(「子どもの本で言いたい放題」2014年1月の記録)