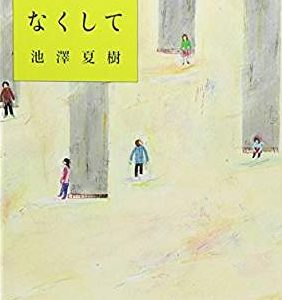うさこ:作者の、命をみる眼差しのあたたかさを感じた作品です。生きていることだけがすべてではない、魂の温もりというか、魂どうしの結びつきというか、そういうものを作品の中に感じました。キップをなくした子は駅から出られないという、一瞬ギョッとするような設定でうまく物語を展開させている。食事は駅の職員の食堂で、必要なものはキヨスクでただでもらえ、衣類は遺失物取扱から着替えを選ぶ。なんと、ここには子供用のパジャマもあり……と、一見突拍子もないことも、ついつい納得させられて物語を読み進めました。ステーション・キッズの仕事もなかなかユニークで、時に時間を止めるなどの魔法も使える。駅での集団生活も、社会的仕事をこなしながら夜はみんなで勉強と、すっかり「駅の子」社会を作り上げていましたね。そのなかにミンちゃんがいて、死んだら何も食べなくていいとか、なんで自分ばっかりと悔やんで向こうの世界へ旅立てないでいる……ミンちゃんの語ることばが実にリアルでした。ミンちゃんが旅立つために、と、おばあちゃんのお墓がある北海道までみんなで旅をして思い出を作ったあと、向こうの世界へ送る子どもたちの姿がすごく自然に描かれていました。
ウグイス:「キップはなくしてはいけないよ。なくしたら出られなくなるからね」という言葉は、子どもならだれでも親に言われたことがあると思います。本当になくしてしまったらどうなるんだろう? というところから始まるので、子どもはもちろん、そう言われた記憶のある大人も引き込まれてしまう。毎日大勢の人が駅に着いて、改札を出ていくけれど、それは皆キップを持っているから出られるわけですよね。駅というのは、どこか他の場所へ行くための通過点にすぎないのに、そこにとどまったらどういうことになるか、という話ですね。ところが、そこで生活するのは全く問題ない。食堂やトイレがあるし、仮眠室にはシャワーもあるし、着るものや日用品は期限切れの遺失物で間に合う。キオスクでは、お菓子を買おうと駅弁を買おうと全部タダ! 散髪も、本屋で本を買うのもタダ! 駅で働く人々はみな駅の子のことを知っていて、とてもやさしく接してくれる。子どもにとって、なんだか楽しい場所なんですね。しかも子どもだけの生活。絶対的な存在である駅長さんという人物が背後にいるけれど、子どもだけで考え、ルールを決めながら集団生活をする。年功序列的な構造ができていて、一つの社会が構成されている。しかも、大切な任務があり、きちんと自分のするべき仕事をこなしていく。うまくいかないときは、何と時間を止められる! 一人一人に責任もあり、子どもがいっぱしの大人のように暮らせるのは、子どもにとってとてもうれしいと思う。駅の子になれば、少し問題ありそうな子でもそれなりにきちんと受け入れられ、ちゃんと一人一人に居場所がある。そうやって、なんだか楽しい物語が進んでいくんだけど、あまり食べないミンちゃんが、「わたし死んでるの」という場面で、読者はドキッとさせられますね。ここから読者の読み方もがらっと変わり、なんとなくそうなのかなーと思っていたことが、「やっぱりそうだったんだ、この子たちは!」と思わせられる。
そのあとは、ミンちゃんがぐっと表に出てきて、死後の世界の話という色が濃くなってくる。それからさらに局面が変わるのは、新入りの中学生が「キップをなくしても、清算券を買えば出られる」という、考えてみればあたりまえのことを言うとき。閉じ込められてるわけじゃない、出たければ出られる。そこで、自分はどうしたいのか、という問題をつきつけられる。そのあたりから、前半と雰囲気が変わってきますね。最初は、東京駅構内の細部の描写にリアリティがあり、ぐんぐん読み進んでいくんだけど、だんだんにちょっとした小さい疑問が積み重なってくる感じがしました。この子たちはどうして駅の子として選ばれたのか? 何らかの理由があって駅の子になるのでしょうが、何なのかはっきりしない。自分からキップを捨てる子もいるけど、どうしてなのかよくわからなかった。一生いるのではなくて、いつか出られるのだけど、出るきっかけも不明。親たちにはちゃんと連絡がいっているから心配していない、というけど、どういう連絡がいってるのか、疑問に思いました。
カーコ:私はこの作者が好きでいろいろ読んできたんだけど、この作品は全体に今ひとつ楽しんで読めなかったんですよね。自立した子どもの共同体という設定は、最初おもしろいと思ったんだけど。なぜおもしろくなかったのかな、と考えてみると、一つには、出てくる子どもたちが、全体にもののよくわかったいい子ばかり。みんな自分の役割を悟って、とても素直に行動するでしょう? 実際の子どもというのは、もっとハチャメチャなものだと思うんですよね。大人の見た子ども、という感じがしてしまって。また、最後に駅長さんが具体的な人として出てくるあたりでなんだかがっかりして、そのあと物語についていけなくなりました。グランマの語る死後の世界を、なるほどと読めるかどうかで、読後感が違ってくるんじゃないかしら。
たんぽぽ:キップをなくして出られなかったらどうしよう、家では心配してるだろうな、と思ったけれど、子どもたちはそんなことを考えずに暮らしているし、みんな、死んだ子かと思ったら、それも違っていた。後半は斜め読みになってしまいました。
ミラボー:作者は相当な鉄道ファンですね。設定も、青函連絡船があった時代ということが途中でわかります。鉄道好きな子に勧めてみたい。最後に子どもたちは家に帰りますが、そのあとどうなったんでしょう? 終わりが完結していないところが気になります。死生観や輪廻のことが出てきますが、p80に「生きているものが死ななければ、赤ん坊が生まれることもできなくなる」と書いてあるのを読んでドキッとさせられました。そうなのでしょうか?
アカシア:この作品は、まず設定がおもしろいですね。大人のいないところで子どもだけで段取りをして暮らしていくというのがおもしろい。カニグズバーグの『クローディアの秘密』(岩波書店)では子どもたちが美術館で暮らしますが、ここでは東京駅。そんなところでも暮らしていける、という発想がユニークです。駅のディテールもしっかりとらえて書いているところがいいですね。作者はインタビューで、イギリスの児童文学にあるような「行って帰る話」を書いた、と語っていますが、イギリスの児童文学は、帰ってからどうなったかも書かれているのに、この作品は、どうなったかが読者の想像にまかされています。大人の読者にはいいですが、小学生くらいだと大人よりもっと物語に入り込んで読みますから、疑問もあれこれ生まれてくるでしょうね。
宇宙全体の大きな大きな心の中にいるコロッコたちが集まって新しい次の命をつくる、そしてコロッコは永遠に転生する、という考え方には、ひかれましたね。駅で暮らす子どもたちという意外性から物語が始まり、途中からミンちゃんの話になっていきます。ミンちゃんに関しては、読者も素直についていけて最後も安心しますが、他の子のことは書いてないのは、どうなんでしょう?
げた(メール参加):『キップをなくして』は身近なところに、非日常の世界を作り出して子どもたちを一時その中に引っ張りこむ話です。発想はおもしろいと思いましたが、読み終わって、子どもにとって「駅の子」になるということにどういう意味があるのか、と思いました。駅長さんや「死んだ子」を取り上げる中で「死」について作者の意見表明をしていますが、子どもはどういうふうに捉えるのでしょうか。なお、図書館ではこの本は一般書扱いになっています。
カーコ:一つわからなかったのは、この子たちが駅の子でいつづけた理由が釈然としないのに、最後に主人公は夏休み後、駅に戻るというでしょ? どれほどの動機があったんでしょうね。
アカシア:自分たちが果たしてきた役割を誰かが次の子たちに伝えなきゃいけないから、と書いてありましたよ。
カーコ:一人残らなければならないというのはわかるけど、なぜこの子がその一人になろうと思うのかしら?
アカシア:日常のリアルな世界との関連を考えていくと、なかなか難しいわね。
カーコ:ミンちゃん以外は、家族のことは全く書いていないし。
うさこ:キップをなくしたところで、もう魔法がかかっていると思ったので、私はあまり違和感はなかったけど。
アカシア:行って帰る話だと、帰ってみると現実の時間はストップしていたのがわかるとか、あるいは浦島太郎みたいに現実の世界でははるかに時間が進んでいたとか、とにかくファンタジー界と現実界では時間の流れ方が違うのが普通だけど、これは現実に学校に行く子どもたちを助けるところが出てくるので、現実世界と接点があり、そういう処理ができませんよね。子どもが読んだら、その間親たちや学校の仲間たちはどう納得していたんだろうか、とか、捜索願は出てなかったんだろうかとか、ひっかかるんじゃないかな?
(「子どもの本で言いたい放題」2006年9月の記録)