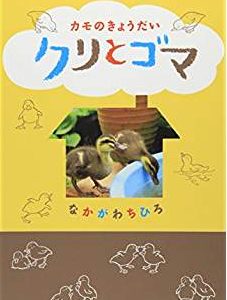メリーさん:楽しく読みました。構成もうまく、わくわくしておもしろかったです。この本はカルガモの観察記録ですが、それを見つめる人間の記録でもありますね。そういう意味で、観察者のなかがわさんの視点がとてもいい。動物を扱う子ども本で難しいのは、対象をどこまで擬人化するかということ。今回のこの本では、そのバランスをうまくとっていると思いました。写真、ビジュアルについても、本文を読みながら実物を見たいなと思うところに、いいタイミングで入っていました(たとえば、カモの足は大きいというところなど。写真を見ると、普段は水の下にあって見えない部分の写真がきちんとある)。呼ぶとカモが答える最後の場面も感動的で、ノンフィクションとして、本当にバランスがいいなと思いました。
みっけ:とてもおもしろかったです。正直言って、かわいいかわいいという感じのウェットなものは苦手というか、かまえてしまうのですが、これはちょっと違いました。文章そのものが上手だし、語りかけるようでとっても優しく、親しみを持てるように書いてある。それでいて、カモとの間にある種の距離感を保ちながら生活しているので、決してウェットになっていない。これはすごいことだと思います。作者が葛藤を抱えながら流されていないというか。いずれ野生に返すという意識を持ち、つねに考えて動いていることがいいなあと思いました。そもそもかわいい生き物だから、それとみっちりつきあって世話をしたりすれば、メロメロになっても不思議ではないのだけれど、そこをきちんと押し戻して、最後まで別れを前提に動いている。戻ってきたカモを棒ではたいた男の子に感謝するというのも、なかなかできないことだと思います。そういう姿勢を保っていれば、当然抑えめというか、引いて書くことになるわけですが、だからこそ、という感じで、最後の別れの部分はうるうるしてしまいました。最後に姿を見て、その後も何回か声を交わして、それもなくなるという流れの余韻が残って、とてもよかったです。
なたね:あの中川千尋さんが、カルガモの子を育てて記録しているとなったら、もうおもしろい本にならないはずがないですよね。なんでうちに話してくれなかったのかと、いろんな出版社が思ったのでは? みなさんがおっしゃるように、なにより野生の命を育てているという姿勢がずっと貫かれているところが素晴らしい。いままでいろんな動物を育ててきた蓄積があり、ローレンツ博士の本をはじめ沢山の本を読んでたくわえた知識があったから、ここまで素晴らしい記録になったのだと思うけれど、そういうところを微塵も感じさせず、教えてあげようという姿勢が一切ないところがいいですね。絵も文章もユーモアたっぷりで、笑わせたり、ほろりとさせたり。子どもたちにも一生忘れられない本になるのではないかしら。近所の公園の池で、毎年カルガモの親子が泳いでいるのを見るけれど、来年は今までと少しばかりちがって見えるのでは……と思ってます。
ハリネズミ:カルガモは留鳥だから、うちの近くの公園にも1年じゅういますよ。
プルメリア:写真やイラストがたくさん入っているので、かわいいなと思いました。子どものころにスズメのヒナを拾い、押し入れに入れて飼おうとしたことがあります。でも次の日にヒナは死んでしまい「自然の生き物は飼ってはいけない」と母親に強く言われたことを思い出しました。なかがわさんが自然の生き物を育てることは大変だったと思います。げんちゃんが卵に番号をつけるところが子どもらしい。日常生活の中でのカモの具体的な描写がかわいくわかりやすく、この作品が小学校中学年の課題図書になったと知ったときは、とてもうれしかったです。本を楽しんで読んでいる子どもたちの姿はよく見ましたが、課題図書で読書感想文を書いている子どもたちは、『チョコレートの青い空』(堀米薫作 そうえん社)が多かったです。そちらのほうが内容的に書きやすい作品だったのかも。
ヒーラ:この本には驚きました。びっくりです。ちょっとできすぎなくらい。げんちゃんと著者との親子関係もとてもよい。作家が、自分の家で育ててそれを文章にしているというのがすごい。カモさんたちととしっかり交流ができているんですね。文章表現も素晴らしい。p136などは、そのまま詩として読めます(朗読する)。
シア:私も驚きました。成長記録系の本かなと思っていましたが、語り口もよく、話に引き込まれました。図鑑だけでは気づかないような細かいことが描かれています。成鳥への羽の生え変わりのことや、寝る前にくちばしまであたたかくなるということなど、目からウロコです。幼い頃から都心に住んでいるので、こういう生活に憧れますね。育てた生き物を野生に返すという作品はいつも最後がつらいものですが、これもそうでした。『あらいぐまラスカル』(スターリング・ノース著)もそうですね。距離感を保ってクールに書かれていますが、感動的に締めているのがさすがです。鳥ってここまで人になつくのか、と思いました。読んだ子はみんな、カルガモを育ててみたいと思うかもしれないですね。
クモッチ:大きく使える写真があまりなかったんだろうと思うなか、かわいらしく作っているので、内容もさることながら、デザイナーさんの努力もあると思いました。フンがくさい、など、五感に訴えるところなどがすごい。羽が生えかわっていくところ、青緑の羽など、細かく追いかけているところがすごい。クリの背中に栗みたいな丸があるというくだりは、ぜひ写真で見たかったです。
ハリネズミ:私は中川さんの本はほとんど読んでいるのですが、その中でもこの本がいちばんといっていいくらい好きです。クリとゴマは単なるペットではなく、野生の鳥。それでも放っておいては死んでしまうというので卵からかえしていくのですが、こんなことをしていいのかどうか、というとまどいが著者の中にはある。カルガモのヒナは本当にかわいいという描写もありながら、もう一方では育てるのは本当に大変だとか、いろいろな動物を飼ってみたけれど「カルガモの緑フンのくささときたら、ぜったいに一位です」、「庭じゅうが、ものすごいにおいになりました」など別の面もちゃんと書いている。自分が育てて感じていること、考えていることを自分の文章と絵と写真で表現しているので、リアリティが半端じゃない。それに、カルガモに焦点を当てながらほかの生き物へと向かっていく視点もある。佐藤多佳子さんの『イグアナくんのおじゃまな毎日』(偕成社)も同じような視点があって私は好きなのですが、この本もいろいろな目配りのバランスが絶妙です。観察も行き届いているし、文章もポイントがきちんとおさえられているし、ユーモアもちゃんとある(たとえばp46)。クリとゴマがどんどん成長して力をつけていく様子(たとえば最初の雷雨の時の反応と、二番目の時との違いなど)からは、伸びていく命の力強さを感じます。教えをたれるいやらしさもないし、感動させようとするあざとさもないから、よけいに響いてくるものがあります。おまけに、この本を読んで、カルガモのひなを育ててみたいとついつい思ってしまう子どもたちのためには、奥付ページに「鳥のひなをみつけても、ひろわないでね。たぶん親鳥がそばにいて、勉強中だから。けがをしてたら動物病院にそうだんしてね」とあって、ちゃんと釘をさしている。たくさんの子どもに読んでもらいたい素晴らしい本です。
(「子どもの本で言いたい放題」2012年11月の記録)