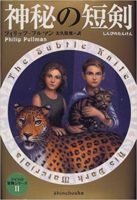
原題:THE SUBTLE KNIFE by Philip Pullman, 1997(イギリス)
フィリップ・プルマン/著 大久保寛/訳
新潮社
2000.04
<版元語録>オーロラの中に現われた「もうひとつの世界」に渡ったライラは、“スペクター”と呼ばれる化け物に襲われ、大人のいなくなった街で、別の世界からやって来た少年ウィルと出会う。父親を探しているウィルはこの街で、不思議な力を持つ“短剣”の守り手となる。空間を切りさき別世界への扉を開くことのできるこの短剣を手に入れた少年と、羅針盤を持つライラに課せられた使命とは…。気球乗りのリーや魔女たち、そして天使までも巻き込んで、物語はさらに大きく広がっていく―。世界中で大ベストセラー、カーネギー賞受賞の壮大で胸躍る冒険ファンタジーの傑作。
ウォンバット:今回、私はたいへん苦しい闘いでして。毎晩、おふとんの中で読もうとしたんだけど、もう眠れて眠れて……。結局p170で時間切れとなってしまいました。このシリーズの1巻目『黄金の羅針盤』(新潮社)も、以前この会でとりあげたけど、私はどうも好きになれなかったのね。寒々しくて。今回も、最初にウィルが人を殺してしまうでしょ。それで彼は、罪の意識にさいなまれるわけだけど、こんなに簡単に人が死ぬっていうのも、どうもなじめないのよねぇ。なんだか、全体におぞましい雰囲気だし。
オカリナ:私は、読むには読んだけど、ぐんぐん引き込まれたというより読書会のために最後まで読んだって感じ。読んでて、気持ちが引っぱられるということはなかった。『黄金の羅針盤』のときも思ったことだけど、頭には響くけど、心には響かないのかな。それで、どうもすわりが悪いというか、おちつきが悪いの。このシリーズは2冊読んでも、全体の構造がまだよくわからない。だから頭ではいろいろ考えるんだけどね。こんな、とてつもない話、この先どういうふうにまとめるつもりなんだろうね、なんていう興味はすごくある。
ひるね:アマゾン・コムに、Margot Liveseyという人が「プルマンをいいという友だちは、しつこくて雄弁だった」って、書いていたんだけど、なるほどと思ったわ。
一同:ふーん、なるほど!
モモンガ:私は、p98までしか読めなかった。『黄金の羅針盤』がとても気に入っていたから、これも楽しみにしてたんだけど、今回は時間がなかったの。ここはun poco読みか?! とも思ったんだけど、この作品はちゃんと味わいたかったから、いいかげんには読めなかった。今回は、世界が3つになるのよね。
ひるね:そうそう。現実世界、ライラたちの世界、ダイモンのいる世界の3つね。
ねむりねずみ:私は、1巻も2巻も原書で読んだのね。まず1巻を読んで、大きなショックをうけたの。うっわー、これはすごい!! って。それで、2巻が出版されたとき、うれしくって、大事に読もうと思ったのに、読みはじめたらおもしろくて、一晩で一気に読んじゃった。今回、翻訳を読んでみたけど、原書どおりのおもしろさだった。プルマンは、すごい世界を作ったわね! やっぱり「ハリー・ポッター」シリーズ(J.K.ローリング著 松岡祐子訳 静山社)とは、根本的に違う。この本は「ライラの冒険シリーズ」の2なんだけど、1巻めに完全におんぶにだっこというんじゃなくて、これはこれで、またすばらしい世界になってる。こうなってくると、3巻目は、もっとすばらしくなるか、おもいっきり破綻するか、のどっちかしかないでしょ。どうなっちゃうんだろうね。私は、1か所、泣けるところがあったの。それは、気球乗りのリー・スコーズビーが死ぬ
ところなんだけど。この物語の登場人物って、基本的にみんな強いでしょ。ライラもウィルも、ものすごく強い。それで唯一、弱いというか、ふつうの人であるリーさんは死んでしまう、と。登場人物があんまりにも強くて、日本人がふだんなじんでいる心象風景とは、ずいぶん違うでしょ。だから、日本の読者の中には、そういうところでなじめないというか、ついていけないって思っちゃう人もいるかもしれないね。登場する子どもたち、ライラにしてもウィルにしても、従来の子ども像とは全然違うのよ。1巻目で、ライラは、父にも母にも裏切られる。2巻目では、ウィルは子どもなのに、保護されるのではなく、逆に母を守らなくてはいけない保護者のような立場に立たされてる。ふたりとも“今”を反映した存在。それから、天使が善悪を越えた存在として登場するのも、オリジナリティがあるよね。
ウンポコ:ぼくは、p47まで。
ウォンバット:さすが、元祖ウンポコ!
ウンポコ:1巻目は読んでなくて、だいじょうぶかなと思いながら読みはじめたんだけど、やっぱりわかんないところがあってね。『黄金の羅針盤』を読んでないとだめなのか・・・と、ちょっと疎外された感じがして、落ちこんじゃったね。物語世界に惹きこまれていけば、すいすい読めるんだろうなーとは思うけどさ。1章は、おもしろかったんだよね。でも2章以降は、もうロッククライミング状態。
愁童:今回のテーマは、ぼくとひるねさんが決めたの。どうしてこれを選んだかというと、裕さんに言われたことが気になっててね。ぼくは、『黄金の羅針盤』を読んだとき「ハリー・ポッター」と同工異曲のご都合主義だと思っちゃったんだよね。ライラが窮地に陥ると、すぐだれかが助けてくれるだろ、というようなことを発言したら、裕さんに「プルマンの世界は、英国では非常に高く評価されてる。これが理解できないのはオカシイ!」というようなことを言われたんだな。そのときは、そんなこと言われてもという感じだったんだけど、どうも、その言葉がひっかかっててね。2巻目を読めば、プルマンの世界のすばらしさが理解できるかなと思ったんだ。そして、読んでみたわけだけど、おもしろかったな。「ハリ・ポタ」と違って独創性もあるし。天使にしても、キューピーみたいな顔をしていて羽がついててっていう既成のイメージとは全然違う、プルマン独自の新しいものになっていて、読み手の中にはっきりしたイメージを残してくれる。力のある頭のいい作家だよね。とてもよく練られていて、よくできてる。だけど、できすぎというのかな、スキがなくて、物語世界に没入できるような作家の体温みたいなものが、あまり感じられない。
モモンガ&ひるね:クールよねー。
ひるね:私は、おもしろくて好きでしたね、この作品。オリジナリティの魅力ね。天使にしても、剣にしても。だけど、こんなものすごい大風呂敷をひろげて、これから先、ストーリーテラーとして、どうまとめるのかしらね。登場人物にしてもなんにしても、ひとことでいえば「おもしろくて、わかりにくい」のよ。おもしろいのは原作のおかげ、わかりにくいのは翻訳のせいかな、と思った。だって、えーっと、ほらここ、p296の「塔の灰色の、胸壁の上には、死肉を食うハシボソガラスが旋回していた。ウィルは、なにが自分たちをそこへひきよせたのかを知って、吐き気をもよおした」っていうところ。読んでて、私は、何が自分たちをそこへ引き寄せたのか、全然わからなかったのね。雑な読み方をして、読み飛ばしてしまったかなと思ったの。これはウィルが指を切断したあとの場面なんだけど、よくよく考えてみたら、指から流れおちる血が、カラスを引き寄せたのかなと、思い当たってね。もしかしたら、これは3人称で書かれているから、themをカラスなのに自分たちと誤訳してこういうわかりにくいことになっちゃったのかもしれないと気づいた。これって編集者が気づかないとね。
オカリナ:これ、もったりした文章だけど、原文は、短く、切り付けるような、すぱすぱっとした文章なんじゃないの?
ひるね:アメリカの友人たちに聞いたら、この作品の文体を好きとか嫌いとかいった人はいたけど、難解だといった人はひとりもいなかった。だから、難解なのは、日本語の問題だと思うわ。
オカリナ:今までの冒険物って、仲間と力をあわせて進んでいくっていうパターンが多かったでしょ。その点、この作品は新しいと思うのね。ライラもウィルも孤独。ひとりでがんばってる。ふたりが協力するところも出てくるけど、一心同体の仲間というふうにはならなくて、お互いに完全に心を許しはいない。こういう世界を描くには、もっと簡潔な、きびきびした文章でないと、雰囲気があわないんじゃない? なんだか人物像がはっきりしなくて、感情移入しにくいのよね。
ひるね:私は、とくに会話が気になったわ。魔女の話し方もピンとこないし、リー・スコーズビーもグラマン博士もまったく同じ口調になってる。原書はどうなのかしら。
オカリナ:それにしても、いったい、どういうふうに終わらせるつもりなんだろうね。まるで見当がつかないわね。3巻目を読んでみないことには、わからない。
愁童:『黄金の羅針盤』で残された謎が、『神秘の短剣』でずいぶん解明された。そこんとこは評価したいね。それはいいんだけど、今回解明されたのと同じくらい2巻目自体の謎があるからなあ。
ねむりねずみ:明らかになった分を埋め合わせるように、また新たな謎が・・・。次の巻へもちこされる謎の数は、結局減ってない。私にとって、ライラはとても魅力的なキャラクターだった。この巻では、彼女の成長もみられるでしょ。わがまま者で、他人を思いやることなんて、『黄金の羅針盤』では皆無だったけど、『神秘の短剣』の途中から、ライラはウィルのことを思いやることができるようになる。それにしても、この話、弱い人はみんな死んじゃうんだよね。リー・スコーズビーも、恋をした魔女も。
ウンポコ:冷徹なのかな。
オカリナ:ウェットではないよ。
ウンポコ:この顔は、絶対ウェットではないね。(後袖のプルマンの顔写真をみて、うなずく)
ひるね:プルマンは、お父さんが軍人だったから、小さい頃から引っ越しが多くて、いろんな国での生活を体験しながら大きくなったのよ。そんな体験が、彼を「ひとりで生きる」ってタイプの人にしたんじゃない?
ウンポコ:この本、子ども向けではないよね。
ひるね:読者として子どもを意識してるのなら、子ども向けの翻訳者を選ぶはず。だから、子ども向けには作ってないわね。子ども向けと限定しないで、大人にも読めるような本にするのはいいことのように思うかもしれないけれど、外国で子ども向けに出版された本を出すのなら、まず第一に子どもが読めるような本作りをして、子どもの手に渡してもらいたいと私は思うの。エミリー・ロッダの『ローワンと魔法の地図』や、『ザ・ギバー』(ロイス・ローリー著 掛川恭子訳 講談社)が大人の本棚に並んでいるのはとてもうれしいことだけれど、もともと子どもに向けて書かれた本が書店の子どもの本の本棚にないのは悲しい。本というのはお金を出して版権を買った出版社だけのものではなくて、ある意味でみんなの財産なんじゃないかな
(2000年10月の「子どもの本で言いたい放題」の記録)