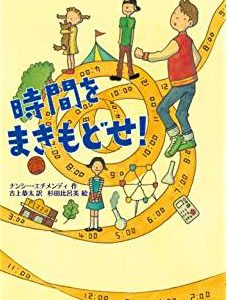ショコラ:最後はハッピーエンドになるんだろうなと思って読んでいました。ハラハラドキドキしながら読みましたが、タイムマシンってこんなに簡単につくれるのかな、というのが疑問。課題図書は、字が細かいしあんまりおもしろくなくて「うん?」っていうのが多かったけど、中学生も手に取りやすいおもしろい内容の作品が今年は課題図書になってよかったなって思いました。
たんぽぽ:これを読んだ子が、今度は『テレビのむこうの謎の国』(エミリー・ロッダ著 さくまゆみこ訳 あすなろ書房)を読みたいと言います。どちらも表紙が黄色で、同じ画家が絵をつけているからでしょうか。両方とも子どもたちにはとても人気です。違う場所に行くというのが、子どもを強くひきつけるようです。私は最後、足に障害が残らなければよかったのになぁと思いました。
メリーさん:読みごたえがあって、とてもおもしろかったです。タイムマシンものは、それこそ数え切れないほどあって、過去のどこかをいじってしまうと、それが現実の何かに影響を与えてしまう、というのは永遠のテーマです。今回は、最後にその運命を自分の身に引き受ける主人公が、とてもよかったです。失ってみて、はじめてわかること。過去に戻るたびに、自分ではないだれかが不幸にあってしまうこと。単純に正義のヒーローではなくて、試行錯誤をしながら、何とか未来を変えようとするうちに、自分も変化していく。SFはタイムスリップの仕掛けに目がいきがちですが、この物語では、主人公の成長の過程がおもしろかったです。一点、「パワーオブアン」の「アン」は最初、人の名前かと思って読んでいたので、訳語は要検討かなと思います。
ハリネズミ:私はおもしろくて、ぐいぐい引き込まれて読みました。ただ、大人のSFものって、過去をいじれないっていうのが法則としてあるじゃないですか。これは、その辺が甘いんですね。それに、おじいさんが機械を渡しにきたっていうのが、何のためだったのか、考えてもわからなくて、そのあたりをちゃんと書いてくれないと、子どもの読者に失礼なんじゃないかと思いました。この作家は、大人向けを書くときと子ども向けを書くときで、心構えが違うのかしら。私も「パワー・オブ・アン」は、やっぱりちゃんとした日本語にしてほしかったなって思いましたね。
たんぽぽ:おじいさんが渡しにくるところは、なんだろうって、考えちゃいますよね。小学生だと、そこまで考えないかも。中学生だと考えるのかな。
ハリネズミ:小学生でも、すごく読んでる子なら考えるんじゃないかしら。それに、小さい子向けだから、そこはあいまいでもいいや、と作者が万一思っているとしたら、悲しいな。
カワセミ:起こってしまったことをリセットできたらいいっていのは、だれでも1度は考えることでしょう。どこにでもいるような男の子のありきたりな日常生活のなかに起こった不思議なできごととしておもしろく読めるんだけど、結構シビアな内容も含まれている。私はこの本って、本来はもっとホラー的なおもしろさのある本なんじゃないかって思うんですよね。杉田さんの挿絵は明るくて好きだけど、この作品に本当に合っているのかな? 明るく楽しい話にしてしまってよかったのかな? もっと大人っぽい、しゃれたつくりにしたほうが、合っていたんじゃないかな。
メリーさん:97ページに機械の絵があるんだけど、モードに対応してなんかあるって言っているから、ちょっと違うんじゃないかって思いました。絵はぱっと見、イメージ違いますよね。
ハリネズミ:こわいところは、ありませんね。
カワセミ:エンデの『モモ』みたいに、ちょっとこわいところ、不気味な感じがあるじゃないですか。それを出したほうがいいのにね。
(「子どもの本で言いたい放題」2009年7月の記録)