日本児童図書出版協会で出している月刊誌「こどもの本」に、2017年の5月号から2018年の4月号まで「子どもの本に見る新しい家族」というタイトルで、従来型ではない多様な家族を描いた子どもの本について連載していました。もう一度手を入れてから自分のウェブサイトに掲載しようと思ったのですが、コロナ禍で資料が置いてある東京にも戻れず、手を入れる時間もないので、とりあえず誤植や舌足らずのところだけを訂正し、基本的にはそのままこちらに転載します。
子どもの本に見る新しい家族⑫
もっと多様性を!
これまで11回にわたって、子どもの本に新しい家族がどう描かれてきたかをみてきた。子どもにとって最も身近な環境である家族・家庭を通して、子どもの本をとらえ直してみたいと思ったからである。日本ではまだ家族というと血のつながりが前提だと思い込んでいる人が多い。そして父親はたくましく外で働き、母親はパートくらいはするにせよ家で家事や育児にいそしみ、子どもは思春期には多少の揺れがあったとしても最終的にはしかるべき企業に職を得る─それが安泰な暮らしの基盤であり、家族の理想像だと考えている人もたくさんいる。そこからは、親の離婚再婚は身勝手だと責める目や、単親家庭や里子や養子は特殊な、かわいそうな存在だという視点も生まれる。
子どもの本の編集者の中にも、そうした従来型の家族の理想像を提示することが肝要だと考えたり、日本の平均的な家庭・家族の有り様を描くのが大事だと考えている人が少なからずいる。そこからはずれた状況やマイノリティの人々を描いた本は読んでもらえないし売れないと思っていたりもする。
先日ある若い絵本作家から、子どもがたくさんいる絵を描いたとき、左利きの子どもを一人混ぜておいたら、左利きは描かないでほしいと編集者から言われたという話を聞いた。これは極瑞な例だとしても、そういう風土の中では、ただ今現在自分がいる小さな(いじましい)社会の中でのマジョリティに沿った価値観しか提示されない。女性の役割にしても、一時は編集者たちが討議を重ねて、ジェンダー的にずいぶん考慮された絵本も出版されていたが、最近はそれも少ない。
◆ マイノリティの提示にも意味がある
しかし私は、子どもの本がマイノリティを提示していったり、読者がマイノリティの視点を学んでいったりすることも大事だと考えている。そうしないと、子ども社会のなかでも同調圧力がさらに強くなり、なんらかの点で自分は多数とはちょっと違うと思っている子どもたちが「自分は自分のままでもいい」と思えなくなってしまうだろう。ひいては、他者が何を考え、何を感じているのかを想像する力も弱くなってしまうだろう。
日本の子どもの自己肯定感は、諸外国と比べてきわめて低いという。(古荘純一著『日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか』光文社新書)。平昌オリンピックに出場した選手たちからは「自分を信じて」という言葉がよく出たが、自分を信じることができない子どもたちが日本にはたくさんいる。日本ではまた、場の「空気を読んで」、「みんなと合わせる」ことも奨励される。そういう考え方に沿えば、左利きや、LCBTQや、単親家庭をはじめとするマイノリティは特殊なのであって、「みんなと合わせる」ことができない人たちだということになってしまう。
でも、実際は子どもたちの多くが、自分はマジョリティとは違うところがある、とか、どこかで無理をしないとみんなに合わせられない、と感じているのではないだろうか。それなのに、マジョリティに合わせることをよしとする画一的な考え方を親や教師が事あるごとに提示し、本でも見せていたら、子どもの自尊感情が低いままになってしまうのも当然ではないだろうか。
◆日本と欧米の作品を比べてみると
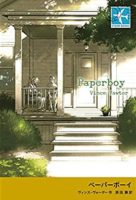 家族や家庭にしても、これまで見てきたようにアメリカやイギリスでは、ずいぶん前から多様な家庭が作品の中に登場していたのに対して、日本の作品の多くは、ごく最近までマジョリティを取り上げることを当然と考え、いわゆる問題小説の中にしかマイノリティは登場してこなかった。
家族や家庭にしても、これまで見てきたようにアメリカやイギリスでは、ずいぶん前から多様な家庭が作品の中に登場していたのに対して、日本の作品の多くは、ごく最近までマジョリティを取り上げることを当然と考え、いわゆる問題小説の中にしかマイノリティは登場してこなかった。
ついでに言うと、それは家族像ばかりではない。ほかのマイノリティにしても同じである。
一例をあげると、アメリカの作家ヴィンス・ヴォーターの『ペーパーボーイ』(原著 2013/原田勝訳 岩波書店 2016)と、椎野直弥著『僕は上手にしゃべれない』は、どちらも吃音をもつ少年を主人公にした中学生向きのフィクション で、どちらの著者も自分が吃音で悩んだ体験をもっている。しかし、『ペーパーボーイ』においては、吃音は作品を構成するいくつかの要素の一つにすぎない。一方『僕は上手にしゃべれない』の方は、主人公の吃音の克服が最大のテーマとなっている。日本のこの作品では主人公が「他者と違う」点が前面に出ているが、アメリカの『ベーパーボーイ』では、他者と違っているのは主人公だけではない。じつに個性的で多様な人物たちが主人公を取り巻いている。
で、どちらの著者も自分が吃音で悩んだ体験をもっている。しかし、『ペーパーボーイ』においては、吃音は作品を構成するいくつかの要素の一つにすぎない。一方『僕は上手にしゃべれない』の方は、主人公の吃音の克服が最大のテーマとなっている。日本のこの作品では主人公が「他者と違う」点が前面に出ているが、アメリカの『ベーパーボーイ』では、他者と違っているのは主人公だけではない。じつに個性的で多様な人物たちが主人公を取り巻いている。
日本の児童文学作家は、マイノリティを取り上げるときはそれなりの覚悟をして、それをメインテーマにして作品を書くことが多いのに対し、欧米では、マイノリティは多様な登場人物の一人として、さりげなく登場してくることも多い。
 たとえばアメリカの件家アリ・ベンジャミンが書いた『ジェリーフィッシュ・ノート』(原著 2015/田中奈津子訳 講談社 2017)の主人公スージーの兄アーロンはゲイだが、「兄さんのボーイフレンドのロッコ」という言葉がちらっと出てくるだけなので、気づかずにスルーしてしまう読者もいるだろう。また、スウェーデンの作家アンナレーナ・ヘードマンが書いた『のんびり村は大きわぎ!』(原著 2010/菱木晃子訳 徳間書店 2010)の主人公アッベ(10歳)は、生後3か月のときスリランカからスウェーデンに養女としてやってきた。その後養親が離婚してアッベは養母と暮らしているのだが、この物語がメインに描いているのはそこではなく、子どもたちが村の人たちをまきこんでギネス世界記録に挑戦する様子である。養女であったり、親が離婚していたりする部分は、物語の背景として登場するだけだ。
たとえばアメリカの件家アリ・ベンジャミンが書いた『ジェリーフィッシュ・ノート』(原著 2015/田中奈津子訳 講談社 2017)の主人公スージーの兄アーロンはゲイだが、「兄さんのボーイフレンドのロッコ」という言葉がちらっと出てくるだけなので、気づかずにスルーしてしまう読者もいるだろう。また、スウェーデンの作家アンナレーナ・ヘードマンが書いた『のんびり村は大きわぎ!』(原著 2010/菱木晃子訳 徳間書店 2010)の主人公アッベ(10歳)は、生後3か月のときスリランカからスウェーデンに養女としてやってきた。その後養親が離婚してアッベは養母と暮らしているのだが、この物語がメインに描いているのはそこではなく、子どもたちが村の人たちをまきこんでギネス世界記録に挑戦する様子である。養女であったり、親が離婚していたりする部分は、物語の背景として登場するだけだ。
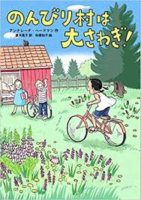 といってもスウェーデンの子どもの本が、すべてそのようなあっけらかんとしたトーンで描かれているわけではない。この連載の3回目でも触れた絵本『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R.ホルムベルイ文 エヴァ・エリクソン絵 菱木晃子訳 BL出版 2004)は、親が離婚して母と二人暮らしの少年が久しぶりに父親と会う話だが、一緒に暮らせない父と息子のやるせなさを漂わせていた。
といってもスウェーデンの子どもの本が、すべてそのようなあっけらかんとしたトーンで描かれているわけではない。この連載の3回目でも触れた絵本『パパはジョニーっていうんだ』(原著 2002/ボー・R.ホルムベルイ文 エヴァ・エリクソン絵 菱木晃子訳 BL出版 2004)は、親が離婚して母と二人暮らしの少年が久しぶりに父親と会う話だが、一緒に暮らせない父と息子のやるせなさを漂わせていた。
またスウェーデンの第一線で活躍していた作家ウルフ・スタルク(昨年6月に72歳で死去)の『シロクマたちのダンス』(原著 1986/菱木晃子訳 佑学社 1994、偕成社 1996)は、かなリシリアスなトーンで、別居した両親の間で揺れ動きながら自分を見いだしていく少年の気持ちを描いていた。スタルクが、少し前の作品(たとえばアメリカのジュディ・ブルームが書いた『カレンの日記』や、ドイツのベーター・ヘルトリングが書いた『屋根にのるレーナ』)と違って、離婚する親に非難がましい目を向けていないことにも注目しておきたい。
◆それぞれのお国事情はあるけれど
もちろん子どもの本も、それぞれの国の事情を反映している。英米にしろスウェーデンにしろ、親の離婚や再婚、単親家庭、養子、里子などは日本と比べてずっと多い。だからそうした多様な家庭が作品に描かれるという側面ももちろんある。しかし 英米や北欧の絵本や児童文学が「多様性」を重視するのは、それだけが理由だとも思えない。多数派からの距離や違和感を感じている子どもたちに、多様な価値観や多様な存在のあり方を提示することによって「少数派でもだいじょうぶだよ。どんな状況のどんな子どもだって生きていてほしい」というメッセージを送っているのではないだろうか。
私の孫の一人が通っている幼稚園では、母の日にはお母さんの絵を、父の日にはお父さんの絵を子どもに描かせる。「お母さんのいない子は、おばあさんの絵でもおばさんの絵でもいい」などの配慮もあるらしいのだが、配慮があったとしても、単親家庭や養護施設で幕らしている子は疎外感を持つことだろう。といっても、今は保育国、幼稚園、小学校の多くは、家庭の多様化をかんがみて、母の日や父の日の行事をしなくなっているらしいが、差し障りがあるからやらない、というだけでいいのか、という疑問も感じる。
先日目にしたBBCニュースでは、母の日、父の日ではなく「家族ウィーク」を設けたイギリスのある幼稚園が紹介されていた。子どもたちがそれぞれ固有の自分の家族を絵に描き、どんな時に家族といて楽しいと思うか、うれしいと思うかを話すというものらしい。先生たちは、最初から多様な家族像をしっかり認めたうえで、子どもたちが「これも家族」「あれも家族」「それも家族」と自然に思えてくるように指導していた。
◆子どもは新たな未来をつくる存在
子どもは新たな未来をつくる存在だ。教師や親や権力者の言いなりになるより、自分の心で感じ、自分の頭で考えて、今よりいい未来をつくっていってほしい。
どんな子どもの本を書くか、出すかは、そこにつながっている。子どもの本にかかわる人たちは、世界は動いていることを認識し、どんな社会に子どもをおいたらいいのか、ということも考えてみてほしい。
家族ひとつを考えても、血のつながりとか、従来型の家族像にばかりとらわれてしまうと、新たな未来にはつながらない。昨年厚生労働省は「新しい社会的養育ビジョン」を打ち出して、里親や養親の数を増やそうとしている。それについても、子どもの本の作り手は考えてみてほしい。そして、子どもたちが未来を考えるときに参照できるような多様な価値観や多様な選択肢を、子どもの本でも示しておいてほしい。
(日本児童図書出版協会「こどもの本」2018年4月号掲載)