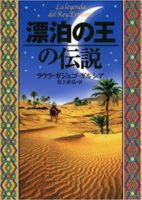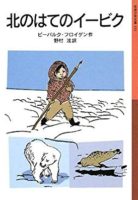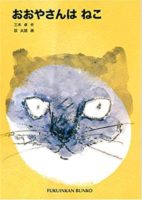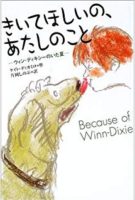原題:LOVE THAT DOG by Sharon Creech, 2001
シャロン・クリーチ/著 金原瑞人/訳
偕成社
2008-1
版元語録:「詩なんて書けない」と思っていたジャックが、すぐれた詩に出会い、書くことで、抱えていた悲しみから解きはなたれていきます。
げた:この作品は、1人の少年が詩に出会って、詩人の言葉を借りつつ、だんだんと自分の言葉を獲得して成長していく話ですよね。図書館でも、なかなか子どもって詩の本を手に取ってくれないんですが、こういった形で、読み物として1冊の本にまとまっているものを子どもたちに伝えるのもいいのかなと思いました。文字を使って絵を描く、というのは日本語だとあんまりしっくりこないかな。どうなんでしょうね。
ウグイス:見た目も、内容も、すごくしゃれた本だと思いました。詩で書かれていることが大きな意味をもっているんだけど、詩を訳すというのはとても難しい。詩というより、主人公の独白のように訳されていますよね。詩という感じがしなかったけど、気持ちはとてもよく伝わった。アメリカでは詩を暗唱させるという授業があるので、ここに出てくる詩はたぶん皆が知っているんでしょう。それに則って自分の詩を書くというところが、1つのおもしろさになっているんだけど、そのあたりが日本の読者にはよく伝わらないのが残念。有名な詩であっても、日本だといろいろな訳があるので、皆が共通に持っている日本語訳がない場合が多いからね。文章は短くてすぐ読める本だけれど、内容は実はすごく難しいのでは?
メリーさん:とてもおもしろかったです。物語の展開に、現実の詩人が書いた詩がかかわっているのはおもしろいなと思いました。主人公は、詩なんて書けないと言っているけれど、つぶやきそのものが詩になっている。子どもが発する言葉は何でも詩になりうるのだな、と改めて思いました。主人公の気持ちがよくわかるのは、作家にあてたお便りのところ。読者からの手紙を彷彿させました。それから、自分の詩をワープロで打つくだり。手書きの文字が活字になると、とたんにそれらしく見える、という感覚はよくわかります。子どもが自分で読むのには、ちょっと難しいかなと思いますが、好きな1冊です。
サンシャイン:最初読んだとき、原文で読みたいなと思いました。日本語だとなかなか詩的に訳せないと思ったので。この子の成長物語として読めるところがとてもよかった。「あの男の子が好きだ」という詩の一部を変えて自分の詩を書くというくだりがありますが、日本語の詩の教育でもこういうことはやってるんでしょうか。短歌の本歌取りというのもありますが、もちろん子どもには無理だし、自由詩の場合もどうでしょうか、難しいのではと思います。ところで、オバマさんの就任式がありましたが、言葉の重み、演説の重みが日本とずいぶん違いますね。詩的に感じるところもありました。言葉に強い力もあったし。(原書を見て)詩集ではなく、novelとなってますね。お話として読む作品なんですね。
ヨカ:とてもいい話でした。最初は、あちらの言語で書かれた詩を日本語に訳すのって、どうなのかな、とちょっと身構えて読み始めたんです。でも、一番強く感じたのは、この子の成長物語なんだということでした。その意味で、とにかくうまい。最初はすっかり心を閉ざしていた子どもが、たぶん教員がいい詩を提示しながら上手につんつんと刺激を与えたことによって、卵からかえる雛のように、自分でも殻を破って心を開いていく。その様子が実に自然に感じられて、すばらしいなあと思いました。だれでも身に覚えのある迷いやこだわりといったことが、過不足なく書いてあって、ああ、こういう子っているよなあ、私もそう感じたことがあるよなあ、と実感できる。これは、子どもと教師と詩という教材の幸福な出会い、なんだろうけれど。日本でも、詩の授業はいろいろと実践されていますが、そういう取り組みをしてきた教師があらまほしく思っているのは、こういう出会いなんでしょうね。『フリーダム・ライターズ』(エリンとフリーダムライターズ/著 講談社)も、文学と子どもの関わりを書いた本だったけど、この作品も、そういう意味ですてき。しかもそのうえ、終盤にさしかかると、なんとウォルター・ディーン・マイヤーがこの子の学校に来てしまう! もうびっくりでした。ただし、詩とのかかわりという点でいうと、日本の子どもがこれを読むのは、かなりのハンディがあるのではないかな? だって、おそらくここに登場している詩は、向こうの子どもたちが学校で教わっていて暗唱できるくらい、あるいはどこかで読んだことがあるという程度に、親しんでいる作品のはずで、だから向こうの子がこの作品を読むときは、その知識に乗っかって、イメージをふくらませられる。でも、日本の子どもは、というよりも、日本の大人だって、全部の詩を知っているわけではないので、イメージがふくらみにくい。それに、1つの言語で書かれた詩を他の言語にすると、まったく違うものになってしまうので、その点でも、難しいところがあるなあ。その意味で、ぜひ原書を読んでみたいと思いました。
エクレア:この作品は、シャロン・クリーチのほかの作品と違うテイストで驚きました。「あの男の子が好き」という詩がとてもおもしろく、それを真似している男の子もおもしろい。リンゴと犬の形が文字でできている詩を拡大コピーして、クラスの5年生の子どもたちに見せたところ、とてもおもしろいと大喜びをしていました。タイガーの詩は虎の字が出ていて、たまたまこの本を薦めた虎太朗君はとてもうれしがっていました。「なんでも詩にしていいんだよ」というメッセージは、文章を書くことが苦手な子どもたちをホッとさせるでしょう。しかし児童詩とこの詩は違うので、ちょっとその辺は気になります。外国の詩を渡す機会がないので、これを機会に渡してみたいと思います。
ハリネズミ:この本は、詩の本ではなくて、子どもの成長の本だと思いました。『ぼくの羊をさがして』の続編のような。最初にこの子ジャックが書いたのは「問題なの/は/青い車。/どこだらけで/道をびゅんと走ってきた。」という詩です。そして、「なぜ青い車が問題なのか」ときかれても、言おうとしない。心がぴたっと閉じているんです。ここで、ストレッチベリ先生が「それがないと意味がわからないでしょ」なんて言ってたとしたら、この子の心は開いていかなかった。でも、この先生が無理強いしないで励ましていくうちに、ジャックはしだいに心を開いていき、やがて青い車とスカイという犬が出てくる長い詩を書くんですね。それを読むと、この子にとっては青い車が大問題だったということがよくわかる。自分の大好きな犬をその青い車がはねたんですから。その悲しさがこの子の心に中で大きな固まりになっていて、この子は心を閉ざしていたってことがわかるんです。ジャックが、詩を書くことによって気持ちをだんだんに解放していく課程は、とてもよく書かれています。私は最初に原書で読んだんですけど、やっぱり詩って翻訳が難しいだろうな、と思ってました。でも、別に韻を踏んでいるわけではないから、素直に子どもの気持ちによりそって訳せばよかったんだな、と、この日本語版を見て思いました。ウォルター・ディーン・マイヤーズはアフリカ系アメリカ人で、とてもやさしそうな、いい人そうな、作家です。
ウグイス:103ページで、「開かなかった」を「開か」「なかった」で改行してあるのはなぜ? 原書ではどうなっているのかな?
ハリネズミ:原書は、1単語ずつ改行してますね。he/never/opened/them/again/ever. 英語だと、胸がいっぱいになって、言葉がぽつぽつとしか出てこなくなっているというニュアンスを感じます。
(みんなで、原書をしみじみ読む)
うさこ:「詩」の本ということで読み始めましたが、最初はなかなか入っていきにくかったです。でも、読み終わったときにとても感動しました。詩という形をとっているけど、日記風な感じでもありますね。私も犬が大好きだから、自分の家の犬がいなくなったら、死んじゃったら、私どうなるんだろういう気持ちをいつも持っています。だから、この男の子の喪失感にとても共感できました。ものすごく悲しいときは、悲しい気持ちを何かの言葉に置き換えて胸の奥から出したいのに、なかなか言葉にできない。この作品は、そういう過程を上手に表現してあるし、言葉にすることによって、男の子の心が開放されていく様子がとてもよく描かれていたと思います。
セシ:詩の本だと思って読んでいくと、韻とか倒置法もなくて、つなげたらそのまま文章になるような言葉で書かれているので「あれっ」と思いました。なら、どうして詩の本なのって。子どもにとっては、文字が少なくて、読む進めやすい面もあるんでしょうけど、やっぱり翻訳は難しいですね。全体のストーリーはいいけれど、先生が読んでくれた詩の魅力が今ひとつ伝わってきません。最後に授業で使った詩をまとめて載せているけど、日本版では体裁を工夫して途中に詩を入れていくようにしたらよかったのでは? ネタばれでだめかな? 私たちが詩を聞いたとき、これは宮沢賢治だとか白秋だとかわかることがあるみたいに、ここにある詩は、英語圏の読者なら思いあたるものなのかしら。日本の読者にはそういう勘がまったく働かないので、ギャップがあって残念だと思いました。
クモッチ:年をとったせいか涙もろくなって(笑)、この本は泣きながら読みました。何に感動したのかというと、やはり1人の男の子が、だんだんに言葉を獲得していく流れが、とてもよく描かれていたからです。この男の子が、飼っている犬を事故で亡くして、それについての状況を詩に表現していくのですが、詩を書いた時点でその死を乗り越えていることがとてもよくわかりました。この詩をみんなの前に掲示したら、みんなが悲しい気持ちにならないだろうかと他の子のことまで心配している。言葉で何かを表現するということは、その事柄を乗り越えるということなのかも知れないなと思いました。さらに、この男の子は、乗り越えるだけでなく、この物語の最後に、「すきだった」という詩を書いてますよね。詩人の詩の言葉を借りてではあるけれど、死んでしまった自分の犬に対する気持ちをしみじみと書いているところに、さらなる感動を覚えました。
(「子どもの本で言いたい放題」2009年1月の記録)