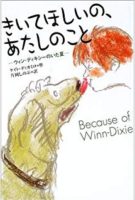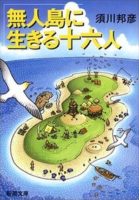梨屋アリエ/著
講談社
2007.09
クモッチ:前半部分は、3人の女の子たちの状況説明みたいな感じでそれが長いので、読むのがしんどかったです。すごく極端で(これってファンタジー?と思うような極端さ)嫌な感じだったから。でも、真ん中あたりから、話の展開が早くなって、どうなって行くんだろう?と引っ張られてどんどん読みました。このあたりから、登場人物、特に女の子たちが、等身大の中学生になってきたのね。たとえば、弥生が Marchの綴りを間違えるところとか、水晶の結構おっちょこちょいの部分とか、ユーモアもあって。作者は、勢いで書いている感じがあって、後半は地の文が、誰が言っているのかわからないところもありましたけど。よく言えば勢いがある。悪くいえばちょっと雑かな。ストーリーのおさめかたも、同じ事が言えてると思いました。水晶が、だんだんと生きていく方向に目が向いていく過程はとてもよく書けているけれど、弥生の闇は深すぎて水晶が「弥生を助けたい」と思ったりしても、ちょっと無理だよなと思いますよね。読者対象の中学生は、どんな風に感じるのか、ほんと聞いてみたいな。自分の状況も辛いけど、これほどじゃないな、ということでほっとしたり、突き放しておもしろく読んだりできるんでしょうか? あと、愛弓がほれっぽいという部分ですが、前半でたくさんの子とつきあったり、後半エッチなおじさんのところに愛弓が行ってしまう、それもそんなに嫌そうじゃない部分などは、性的な描写を書かないと、なぜ行ってしまうかという気持ちの揺れが伝わらないのでは?と思いましたね。
ハリネズミ:愛弓は、性的な衝動というより、最初は食べ物をもらいたいからおじさんのところへ行くんじゃないの?
フェリシア:父性の変わりに受け入れてもらえる安心感があるのだと読み取れると思います。ありのままの自分を受け入れてくれる存在(そこには、大きな代償を払っているだけれど、本人はそうとは気づいていない)として、あらがえない気持ちがあるのでしょう。
メリーさん:今の子どもたちが読むと、リアルだというのかもしれないですが、正直言って、半分まで読むのがつらかったです。世の中は、砂糖菓子みたいに甘くなく、不条理だということはわかるのですが…。中盤を過ぎて、自殺に失敗するあたりから、おもしろくなりました。最初の予想は、性格も境遇も全くことなる3人が仲良くなって終わる、というものだったのですが、見事に裏切られました。水晶と愛弓は携帯電話で意志の疎通をはかるのだけれど、弥生とは最後までそうはならない。着地点を見つけられないまま終わったので、逆の意味でリアルでした。
とくに強烈だったのが「嘘をつく」ということ。弥生は状況に応じて嘘をつき、使いわけ(!)、論理が破綻すれば、「死ね」で断絶して終わり。これまでの子どもだったら、嘘のほころびで、状況は多少変わるのだけれど、弥生の場合はどこまでいっても本音がない。それぞれの物語もやはり自分なので、自己同一性に悩むこともない。弥生はすごいなと思いました。
実は、ケータイ小説を買って読み比べてみたのですが、この本が深いなと思ったのは、最後の場面。著者が3人と対等に向き合って、お前はどうするんだ?と問いかけている気がした点です。3人は今の子どもの類型で、大人の言葉は通じるけれど、心はまだ大人ではない(水晶)、大人の言葉も通じないし、心も子ども(愛弓)、大人の言葉も通じないし、心も子どもを卒業している(弥生)の3つ。信頼できる大人がいないこの世界で、君たちはどう生きるのか?それを問い続けながら、終わっているような気がして、いろいろなことを考えてしまいました。
小麦:いい大人はひとりも出てこないですよね。
フェリシア:この読書会の課題として適当かどうか迷ったのですが、私は、とても衝撃的で、おもしろかったし、現代の話としてちょっと注目したかったので選びました。読み始めは、ただのエンタメかもしれないと思いました。出てくる子が、かなり典型的な子どもたち。そして子どもと保護者との関係も、それぞれのパターンが典型的に設定されていて、極端すぎるけれど、なさそうでありそうなところが怖い。お金持ちだけれど愛情に飢えた子、ネグレクトされていて寂しがり屋の子、賢くて親の期待を一身に集めているけど自我の目覚めと共に「いい子」の枠からはみ出しはじめた子。極端だけれど、絶対にどこにでもいる子だと思いました。ブログで知り合った子どもたちが、なんとなく共謀して寄り添っていくのも、今っぽい関係なのかなと思いました。今の子どもたちって、ケータイ依存症なので、だからこそ怖いですよね。そして、親が見たらびっくりするくらい子どもくさくて、ばかげているところも、リアリティを感じました。
「世直しテロをしよう」と考えるようになる経緯など、子どもの身勝手さもよく描けているように思いました。それでも、最後に、死ぬのはやめて生きていこうと思う、自分で生きていくしかないということをわかる、この「自力で生きていくこと」を勝ち取るところが、この話のすごいところだと思います。誰も助けてくれないというのは極端だけど、今の世の中、だれも助けてくれるわけじゃないから、自分で生きていこうというメッセージがこの本にはあるので、子どもたちはそこに何かを感じるのではないかなと思います。最後に、ちゃんと着地してほっとしました。
小麦:読み終えて最初に思った感想は「この時代に中学生じゃなくてよかった……」です。中学生の話し言葉や、メールの気持ち悪い文体なんかはとてもリアル。大人が取材して頑張って書いたという感じが一切ないですよね。文章もスピード感があって、ぐんぐん読めます。全体的に極端な設定も多いんだけど、あえて味付けを濃くして、読者を引っぱっているんだなと思いました。ただ、いまいちどこに向けて書いているのかがわかりませんでした。ラストで水晶が、生きて行く希望らしきものを見いだします。弥生を助けたいというような事も書かれているけど、この年頃の子どもの気まぐれのようにも思えて、ラストに据える希望としては、あまりに心もとない。多分、弥生が変わることはないだろうと予測できてしまいます。今の中学生をリアルに写し取って、その先に作者の思いなり、答えが提示されるべきだと思うけど、その先がすっぽりないように思いました。文学の醍醐味って、自分の想像しえない世界に連れていってくれるとか、とにかく変でおもしろいとか、色々あると思うんですが、私はこの本に関しては、そうした何かしらの魅力を見つけられませんでした。
ハリネズミ:最初のうちは、「えー、こんなやついるわけないじゃない」と思ったり、言葉とか行動で人物をあらわすのでなくて説明しちゃってるところにひっかっていたんですが、途中からこれは寓話みたいなものだと思いはじめたんですね。中学生って、自分自身をうまく扱えないし、いかようにも揺れるし、みんなで自殺やテロをやりましょうと言いかねない。親にしても、ここまで極端ではなくても、近い親はいっぱいいる。それぞれの典型を提示して、ありうるぎりぎりのところを書いている。そこが、おもしろくなったんですね。弥生は救いがたい世界にいるわけですよね。何かしたって救えないんだけど、それでも全然タイプの違う少女が手をのばそうとしている。
今の英米の児童文学だと、いい大人が出てくる物語が少なくなってます。時代がそうだからでしょうけど、大人はまったく頼りにならなくて、子どもどうしで支え合っていかなければならない。創作児童文学では、そういう設定をあまり見かけなかったのですが、これを読んで、ああ、日本でも出てきたんだと思いました。最初は読んでも時間のむだかな、なんて思ってたんですけど、読んでよかった本です。
フェリシア:私も最初、エンタメかなと思ったのですが、途中から、この関係性がリアルだと感じました。この関係性の危うさが怖いと。誰が読むのって言われると困るんだけど、「自分はこの子たちと違って幸せだわ」って読むんじゃなくて、「自分も一歩まちがえたらここに行く」という感じ? または、自分の中にある、“この子たち要素”を感じながら読むのでしょうか? どちらにしても、息苦しい気持ちで毎日生きている中学生くらいの子どもたちに、この著者の「自分が自分の力で生きていく」というメッセージは、伝わると思いますし、その力強さを感じる作品です。
小麦:解決はしませんっていう終わり方ですか。
メリーさん:爆弾3つあるので、このまま進んだら、生き延びようとしてた弥生がいちばん最初に死んじゃいますよね。
小麦:死んじゃわないんですよ。火花が散るくらいで。でも、解決はしないですよね。
ハリネズミ:読者はそれぞれの少女のどこかの部分に強く共感して読むんじゃないでしょうか。
小麦:私が中学生だったころは、本によって別の世界に行けるというのがあったんですよね。
ハリネズミ:そういう読書は、今だってあると思う。
紙魚:たとえば、尾崎豊の歌って、大人がきくと、まあ、それなりにわかるかなという感じなのだけれど、ある年代や、ある層には、絶大な信頼を持たれていましたよね。まさに若者の教祖というように。歌と自分の状況がぴったり同じでなくても、その歌に描かれている世界が、一部でも自分と重なることで、力をあたえられることはあると思う。
みっけ:第一章の「みさきと弥生」を読み終えた段階で、あれ?と思いました。なんだこれ、今時の子どもの描写かい。描写は上手だけれど、それでどうするんだろう、とちょっと意地悪く見てしまったのです。その次に、今度はあゆの話が出てきて、さらに水晶の話が出てきたところで、これは今時の子どものサンプル集だろうか?と思っていたら、その次の章で、登場人物が携帯を通してつながり始めた。このあたりから、これはかなりすごい構成なのかもしれないと思い始めて、それからは、いったいこの子たちどうなってしまうんだろう、と引っ張られて、かなりのスピードで読みました。携帯とは無縁な生活をしている人間からすれば、ふうん、こうなんだ、へえ、といろいろと目新しいことばかり。でも、そういうディテールも話の終わり方も、実にリアルだなあと思いました。
弥生がなあ……と思ったのは事実ですが、これでお手軽に救済されたら、とたんにリアリティーがなくなるし。こういう本って、読者が、登場人物と自分を完全には重ねられなくても、自分の一部が重なることでほっとするというか、けっこうきつい毎日を送っている自分と重なる人間をこんなにリアルに書いてくれる人がいる、ちゃんと見ていてすくいとってくれる人間がいるということにほっとする、という読み方をするのかもしれませんね。ここまで極端でなくても、登場人物が自分と地続きだと感じる子はたくさんいるはずだから。今時の風俗のオンパレードなんだけれど、それが展覧会で終わらずに、ちゃんと読者を引っ張っていく仕掛けになっている。練炭自殺実行のあたりからは、もうどうなっちゃうのかと先が気になってしかたがない。練炭自殺をしようとして、弥生が外から目張りしているのにほかの2人が気づくあたりには、感心しました。この作品を読んで、ついに日本でも、現実に即して子どもに直接エールを送るタイプの作品が出てきたんだなあ、と思いました。
ハリネズミ:生きていてもいいかと思うようになるまでの過程も、それなりに書かれています。
みっけ:水晶とあゆなんかは、おそらく今の学校だと、学校内では接点がなさそう。あゆは水晶をお高くとまった優等生だと決め込むだろうし、水晶はあゆを馬鹿にして鼻も引っかけないだろうし。その2人が接点を持てたのは、携帯で一緒に自殺をという異様な状況になったからです。ところが、そうやって接点を持ってみると、お互いに相手のことをそれなりに観察し、自分のことも相手のことも肯定できるようになっていく。この2人はそうやって救われていっている気がするんです。あゆにすれば、水晶に髪の毛をほめられれば嬉しいし、水晶にすれば、自分には考えられないような状況でけろりとしたところを失わないあゆをすごいと思う。そうやってお互いにちょっと視野が広がり、それがある意味で成長にもなり、生きていってもいいかな、という感じにもなる。でも、この作品では弥生は最後まで他の人と出会わないんですよね。それが弥生の救いのなさにつながっているんじゃないかな。この先弥生が他者と出会えるかどうか……出会えるといいですけれど。
ユトリロ:私は教師なんで、個人的には、好きになれない人がいっぱい出てきます。例えば愛弓の両親も嫌だし、水晶の親も嫌だし。だけど、作品としてよく書けているなと思います。愛弓、水晶、弥生3人とも私の今まで出会った人で、よく似た人物が頭に浮かんできました。「さがしたら殺す」と書く愛弓の母のような親も20何年前だっていましたから。水晶みたいに、5分に1度とはいわなくても、親に徹底的に管理されている子もいますしね。GPSで居場所を知らされるとか。作品としては、弥生だけ描写が足りないような気がします。親との関係やら。その分、作品の最後でも救いもない感じだし。だからこそ、最後の最後で弥生に疑いをもつ2人が、離れていくようになるんでしょう。私の身近にも、お金持ちだけどニヒルという子はいますよ。どうしてなんでしょうかね。
フェリシア:まわりの大人たちが真剣にその子にかかわっていないと、どうしても子どもはニヒルになってしまうのではないかしら。愛情のない両親、当たり障りのない先生、無関心な近所の人……。小さいころから、関心を持たれない子どもは、どうやって自己表現したらよいのかわからなくなってしまう。だから、友だちともうまく関係を作れない。
ユトリロ:お金がある分ハートがない親は確実にいて、高校生になってから、ものすごい悪いことをするというような子もいる。この本は、そういう意味でも、よく書けている。もしかしたら、すごい作品なのかもしれないですね。
紙魚:中学時代のある短い時期、何に怒りを抱いているのかうまく説明できないけれど、親や学校や社会に強い怒りを抱いているという、本当に特殊な瞬間というのがあると思います。大人になると、その、自分をコントロールできなかった厳しいつらさを忘れてしまうのだけれど、梨屋アリエさんは、それを忘れずにじっと持ち続けているのかな。私は、この女の子たちは、さほど極端だとは思えません。この物語と同じ状況にはないかもしれないけれど、同じような方向性の気持ちを持った子が読んで、救われる気にはなると思う。そういう意味では、すごい作品だと思います。それから、ゲームの登場が子どもの遊びの文法を変えたように、やはり携帯電話の登場というのは、人間関係の文法を変えましたね。これはどうしようもないことなのだけど、携帯以前と携帯以後では、人とのつながり方がちがう。梨屋さんは、今の子どもたちの現状を、批判することなく、そのまま書いているように感じられました。それから、弥生の「リスペクトしなさい。」という言葉は、この物語と、今の子どもたちの心を、象徴しているように思います。それにしても、『空色の地図』(金の星社)や『ツー・ステップス!』(岩崎書店)を書いている人と同じだなんて、作家というのはすごいですね。
フェリシア:『空色の地図』よりも、『スリースターズ』の方が、ずっとよかった。
ハリネズミ:『チューリップタッチ』(アン・ファイン/著 灰島かり/訳 評論社)のチューリップの場合は、父親に猫を殺すよう言いつけられるという部分が強烈で、そこを読んだだけで、チューリップの闇がわかりますよね。弥生の闇も、短くてもいいからもう少し具体的に書かれていればもう少しくっきりしてきたかもしれません。警察につかまっても親が迎えに来ないというだけでは弱いと思います。
みっけ:でも、チューリップの闇が多少は他の人との関わりがあって生まれた闇なのに対して、弥生の闇というのはもっととらえどころのないものだと思います。つまり、周りに人がひとりもいない、人とのやりとりがまるでない、自分をぶつける相手が見えない、みたいな。だからチューリップよりももっとがらんとしていて、そういう状況を、書いて伝えるのは難しそうだなあ。特に、本人に沿った形で書いていく場合は難しいと思う。弥生の心情については、第1章で語られているみさきとの家出の話の中でも、「こいつもあたしみたいに寂しいのかと思ったら、なんだ全然甘いじゃん。絶望したふりなんかすんなよ」みたいな、ひりひりする感じが書かれていて、そのみさきが火事で死んだときの弥生のリアクションのなんともねじれた感じからも、本人がとてもしんどい状況だということが伝わるんだけれど、徹底的な精神的ネグレクトというのは、接触や衝突がないだけにとても書きにくいんだと思います。なんか、大きくて真っ暗な穴ぼこのような感じなんでしょうけれど。
フェリシア:長くなって、だらだらしているのも、エンタメとして読める秘訣かもしれない。
小麦:自分が共感して読むんだったら、だらだらしていた方が感情移入しやすいですよね。メールの文体はうまいですよね。
メリーさん:ケータイ小説よりも、ずっとうまいです。
(「子どもの本で言いたい放題」2008年5月の記録)