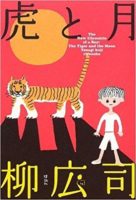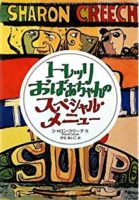フレート・ロドリアン/著 たかはしふみこ/訳 ヴェルナー・クレムケ/絵
徳間書店
2010.03
プルメリア:ストーリー全体がほのぼのとした感じ。登場人物や、子どもたちが大好きな乗り物(消防自動車など)が出てきたり、帽子をかぶせてもらうところなどは、1、2年生には楽しめる作品だと思います。金魚が物語の場面ごとに出てきて、何気ない表現ですが、ストーリーを動かしているのかなとも思いました。羊のもこもことしたやわらかい感じが、癒しになります。幼年文学として、お薦めの作品ではないでしょうか。
ダンテス:ごめんなさい。あまりピンときませんでした。ほんわかはしてますけれど。絵の色彩はきれいだと思います。
三酉:私もピンとこなかったけど、いろいろ考えました。1958年の東ドイツ。ベルリン封鎖の1960年。東西関係が緊張している中で書かれた本なので、いろいろ読み方があるのではないかと思います。だから金魚やインコは何かを意味しているのではないでしょうか。羊が突然降りてきて、生きるの死ぬのというのは、東ベルリンから西ベルリンへの救出劇を表しているのか? クリスチアーヌと主人公の名前は、ソ連を意識しつつ、キリスト教国の西側を暗示しているのか? わからないですけど。
ゆーご:対象年齢は何歳なんでしょう。読んでいる途中で意味がわからないところがあって、小学生の中学年でもむずかしいと思います。犬とザワークラウトとの関係、鳥の役割などは現在進行形で気になっています。挿絵の羊の表情が実にさびしそうですね。それもあってか、全体的にしっとりとした物語という印象です。最近の絵は細めの女の子が多いですが、主人公の女の子のふくよかさが好きです。羊のような繊細な心への理解が、この話を読むことで深まるといいと思います。
優李:さっと読んでしまいましたが、途中出てきた金魚と小鳥が活躍せず、その背景が語られないまま最後までわかりませんでした。羊は、羊雲の連想でしょうが、いいと思います。挿絵もとてもいいと思います。繊細な物語ですね。元は絵本で出ていたということですが、それをこの幼年童話の形にして、読者層に受け入れてもらえるように読んであげたり紹介したりするのは、私には大変かもしれないです。
ジラフ:純粋に、いいお話だと思いました。色や手ざわりなど、細部の“質感”がていねいに描かれていて、物語が生き生きとしています。この本がなぜ、いま出たのかと考えると(原書は1958年刊)、やっぱり、絵の魅力が大きいと思います。ヴェルナー・クレムケのリトグラフは、いま見ても非常にモダンです。ヨーロッパの言葉から日本語への翻訳は、読み物の場合、横のものを縦にすることが多いですが、挿し絵のふんだんな子どもの本では、その処理に工夫が必要です。この翻訳書は、縦書きの幼年童話のかたちになっていますが、絵の配置や、ズームと引きの緩急のつけ方なんか、絵の入れ方もとてもいいです。羊雲がモチーフということから、いつだったか、夕暮れどきに、西日を背にした雲が、クマのプーさんそっくりのかたちをしていて、金色にふちどられていて、道ゆく人がいっせいに携帯をかまえて、写真を撮っていた光景を思い出しました。雲というのは、何か連想が広がるんですよね。
メリーさん:羊を何とか助けようと、男の子たちをさっさと手配して、自分も走り回る……主人公のクリスチーネが何ともたのもしい物語でした。(対照的に、歯医者さんで歯をみがこうねと言われ、消防士の帽子をかぶってご機嫌な男の子たちは、あまり役に立っていませんが……)ヨーロッパでは、警察より消防士を信頼できる職業だと思っている人が多い、という話を聞いたことがあります。いろいろな人に出会いながらも、最後に頼りになるのは消防士さん。消防車のはしごで羊を空に返すというアイデアが、素朴だけれど味があっていいなと思いました。
すあま:幼年童話を評価するのは、むずかしくて、読み手である子どもがどう読むかを考えながら読むことが必要だと思います。私が子ども時代に好きだった幼年童話を、他の大人の人が読んで、おもしろさがわからなかったと言われたことがあり、小さい人向けの本の評価はむずかしいと実感しました。この本は、絵本だと文章が多すぎて読みにくい。だからこの形にするのはとてもいいのかなと思いました。羊を空に返すという問題を、主人公の女の子がどう解決するのか、わくわくしながら読めました。助けを求めに行った男の子が失敗したり、頼りになるかと思った羊飼いが毛を刈ることしか考えていなかったり、最後ははしご車が出てきたりと、次はどうなるのかを期待させる展開が、とてもよくできていると思います。
たんぽぽ:絵がとてもきれいだと思いました。幼稚園で男の子の一番人気の職業は消防士らしいです。安心して渡せる本かなと思いました。前は絵本の形で出ていました。これは復刊ではなく、あくまで新刊だと聞きました。最近、昔の作品を形を変えて出していることがとても多いですね。
シア:さらっと読めましたが、中身はあまり印象に残りませんでした。他の本にくらべて値段が高いですね。水の循環の話が載っており、理科的なおさえはされているので、最後には羊は消えちゃうのかと思っていたのですが、結局はしご車で解決してしまう、というファンタジーに面食らいました。それに、絵本のせいか、不自然なシーンも多く、少し落ち着きませんでした。例えば、主人公の家のインコなのだから、犬とザワークラウトの関係は知らないはずなのに「ザワークラウト!」と鳴いたり、動物と話すのが夢である主人公なのに、羊がしゃべってもとくに驚かなかったりなど。学校に通うクリスチーネですが、出てくる男の子たちは幼稚園で、年が違うんですね。とはいえ、外国の文化や風土にふれることができました。夏休みには学校に先生がいないことや、町はずれに羊飼いがいるというところ、結婚式に馬車に乗るということ(道路に馬車が走っています!)、おやつ代わりに草の茎をかじる子どもたち、消防士の服も違う、そんなところですね。それから、サーカスの車が文章には出てくるんですが、それが挿絵として出てこないなど、細かいところばかりが気になってしまいました。
オカリナ:たんぽぽさんに読んでいただければ、ゆったりとした味わいがおもしろいと思えるでしょうが、自分でさっと読んでもあまりおもしろいとは思いませんでした。絵はとてもいいのですが、物語世界の中でのリアリティが気になりました。チリは、羊は「雨になっておちてくる」と言っているのに、チリ自身は羊のまま。子どもは変だと思わないでしょうか? また消防車のはしごで空に帰るという設定は、牧歌的すぎて今の子どもには無理なのでは? 今の子どもの絵本には、たとえば「月をとりたいけどはしごでは届かない」なんていうシチュエーションが、たくさん出てきますからね。最後の、クリスチーネに対して羊がお礼を言うのではなく、金魚が「お礼をいった(かもしれない)」というのは逆に大人っぽい書き方で、この本の年齢対象の子どもたちにはわかりにくいと思います。
タビラコ:昔は、日本の絵本でも、女の子はぽちゃっとしていたんじゃないかしら。男の子も女の子も、まるまるぽちゃっとしている子どもがかわいいと思われていたのが、今ではずいぶん変わってしまいましたね。絵はとても明るくて、のんびりしていていいし、物語も「好ましい」物語なんだと思います。でも、幼年童話にしては、文章の分量が多いのでは? なんだか、内容と文章の分量のバランスが悪いなと思いました。
(「子どもの本で言いたい放題」2010年9月の記録)