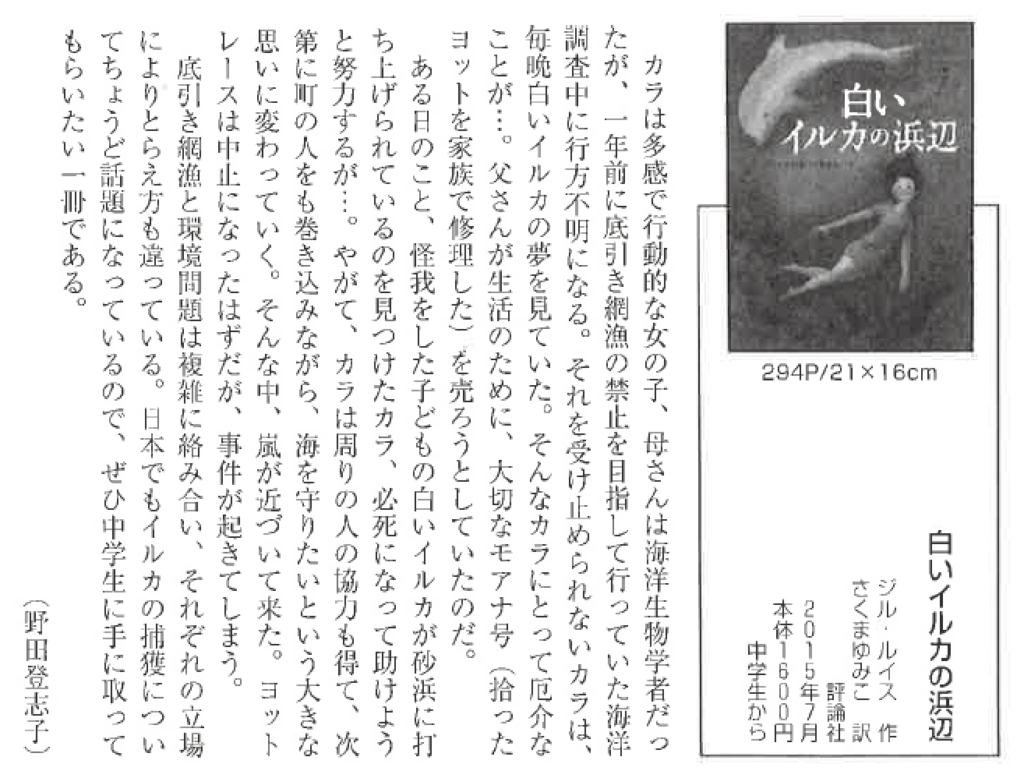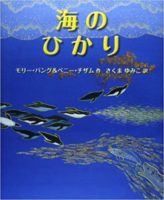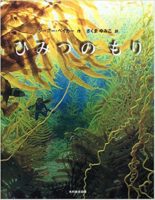レベッカ・ヤング/文 マット・オットリー/絵 さくまゆみこ/訳
化学同人
2023.09
オーストラリアの絵本で、移民・難民をテーマにしています。最後の文がないところがいちばん大事なところなので、そこをちゃんと見てもらえるとうれしいです。移民・難民の人たちは自分が生まれ育った場所の文化をもって新たな天地にやってくるということが象徴的に表現されています。移民が多く多様な文化を受容してきたオーストラリアならではの絵本でもあり、今の世界が直面している問題についても語っていると思います。
IBBYのオナーリストにオーストラリアから推薦されて掲載されていた絵本で、絵がとてもいいのです。ただ原著はマットコート紙なのに、日本語版は上質紙なので、ちょっとそこがもったいなかったかな。
(編集:田村由記子さん 装丁:神波みさとさん)