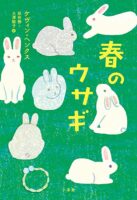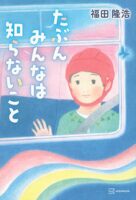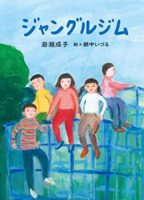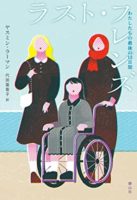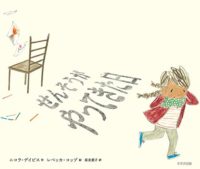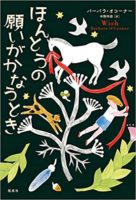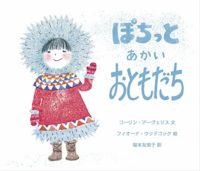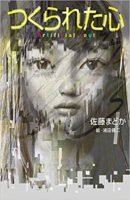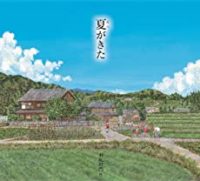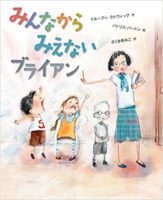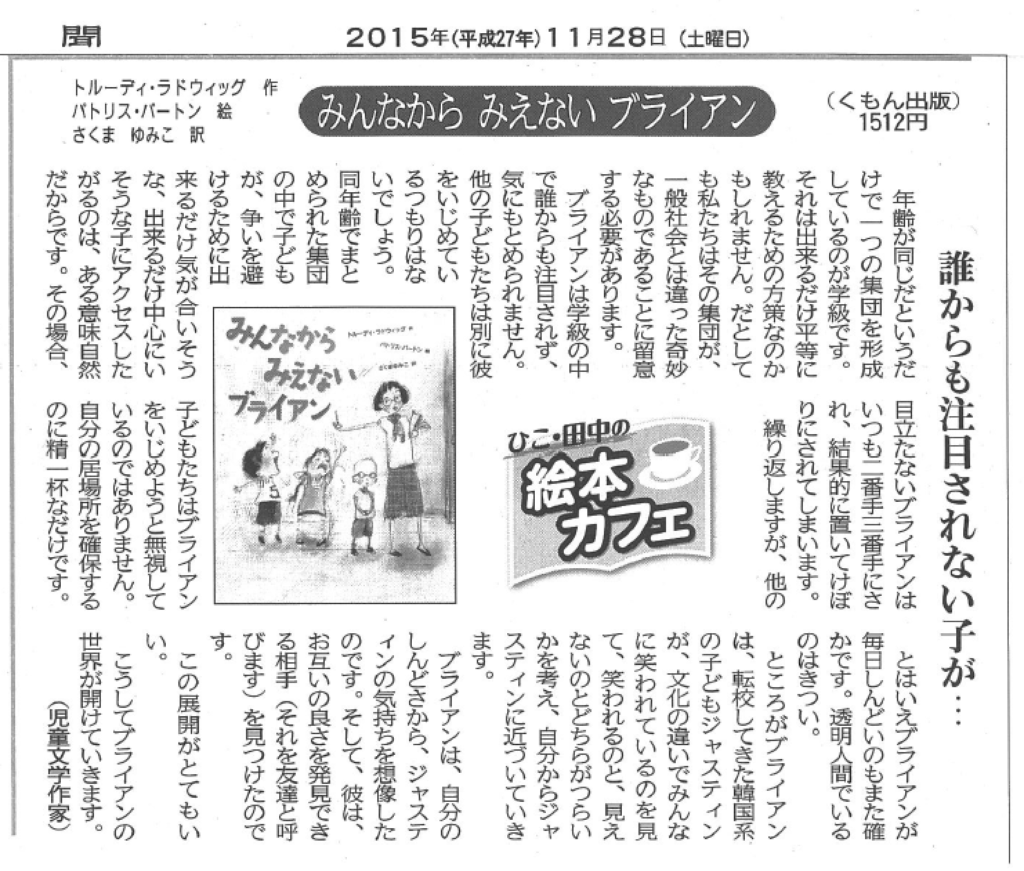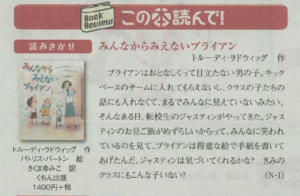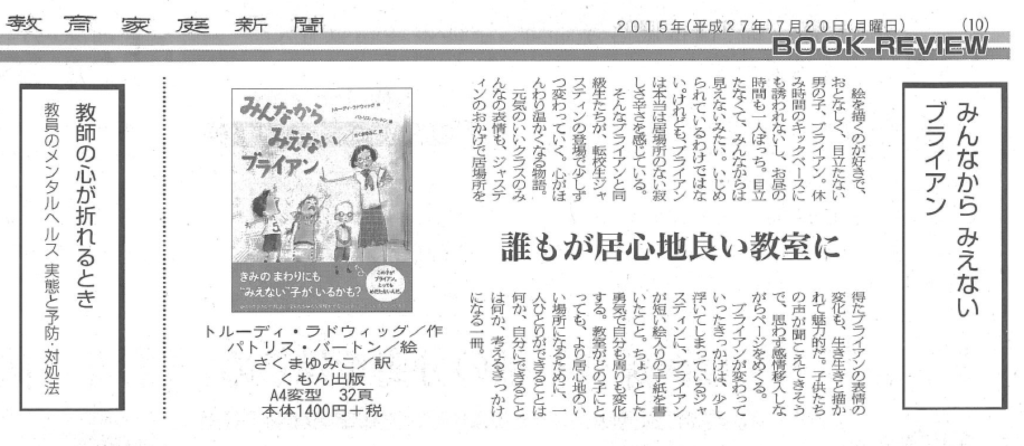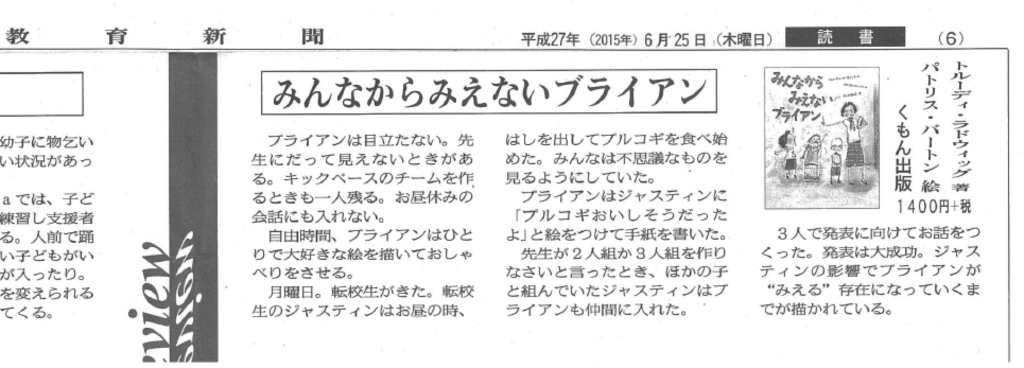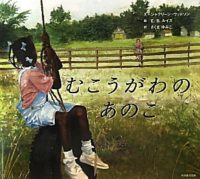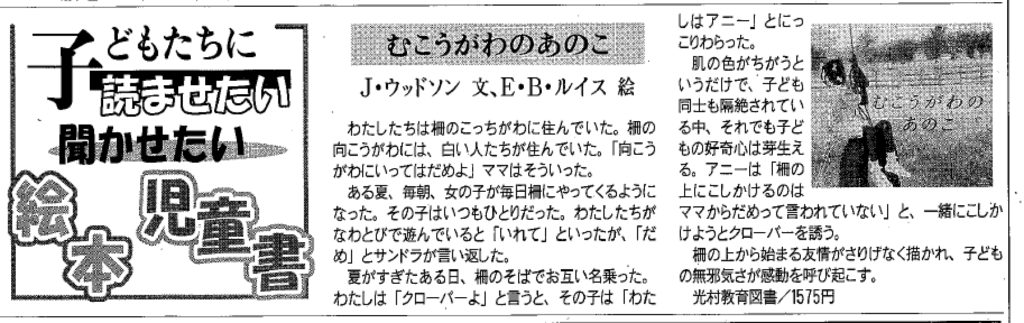志津栄子/作 くまおり純/絵
講談社
2023.01
きなこみみ:大阪が舞台の物語で、大阪者としては非常に親近感がわく物語でした。「居場所」ってなんだろう、というのがテーマですね。唯人という主人公の民族的なルーツである中国残留邦人の問題、金沢から転校してきて、大阪にも学校になじめなくて「ひとりぼっちで外国にいるみたい」というアズという女の子の心情、唯人の母が捨ててしまった故郷の人との繋がりなど、さまざまな奥行で「居場所をさがす」ということが語られるのがいいなと思いました。ふたりで天王寺動物園のライオンを見に行くシーンが、とくに好きなところ。天王寺動物園は、新世界のすぐ横にあって、独特な空気感のあるところです。雑踏のなかに、いきなり動物園があって、そこにいるライオンというのは、確かに場違いな感じがするなあと思いました。大阪は、在日の方たちがたくさん集まっておられる町もあり、様々なルーツの人たちが集まりやすいところだと思います。一方で、関西弁がキツい印象を与えたり、ニュアンスが通じにくかったりして、疎外感を与える一面もあるよなあと、この物語を読んで改めて感じたりもしました。この物語も、やはり言葉の力について考えさせられました。集団のなかでひとりぼっちだと思う唯人は、何をするにも自信がなくて、黙りがちになってしまう。自分たちを捨てた父親へのもやもやも胸にたまって、余計に重い。でも、同じような疎外感を抱えるアズと言葉を重ねるうちに、少しずつ自分が好きになるのが、いいなと。p165で、唯人が、母と本音で話しながら「なんやこれ、気持ちええ!」と思うところが、とてもよかった。自分の思いを言葉にしてみる。誰かと共有する。それが「胸のおくにチカっとあかりが灯る」場所をつくることにつながって、人との繋がりが、ふるさとで、居場所なんだというメッセージが温かいです。ふたりの担任のみのり先生が、距離をとって見守りつつ、要所要所でぴしっというべきことを押さえていい役割を果たしているのが印象的。唯人の背景は非常に深く書けていて、それが唯人という人物のなかで有機的に繋がっているのに対して、アズのこだわっている、母との関係が、もう少しリアルに見えていたら良かったなとも思いました。
花散里:表紙とタイトルを見た時に、私は読んでみたいとは思えませんでした。「ちゅうでん児童文学賞受賞作品」であるということからかもしれませんが、日本の児童文学作品を読んでいて常に感じることは、外国の作品と比べて、内容が軽いというか浅いように思っています。外国の作品は、海外の良い作品を選んで翻訳者、編集者の方々が日本に紹介してくださっているということもあるのかもしれませんが、子どもたちに手渡したいと思う作品が多いと感じています。
本作でもひとりひとりの登場人物の描かれ方に魅力が感じられないこと、ビリケンや通天閣、あべのハルカスなど、大阪の土地勘がないと分かりにくいということも含めて、設定もよくないと思いました。祖父が残留孤児という設定にも無理があり、唯人の父親の描かれ方も明確ではないと思います。母親が淡路島の家族と、どういう形で決別したのか、その母親が、「家族に見せびらかしに行くんや」という展開にも、どうして唯人と行ってみようかと思ったのかが安易すぎるように感じました。アズの存在、中国語、なわとび大会など、いろいろなことを盛り込みすぎていて、物語の展開の仕方も軽すぎて、不満に思いました。新しい作家たちの作品を紹介していくという点では、文学賞受賞作品の刊行ということもあるのかもしれませんが、文学的に、子どもたちに手渡せる作品であるのかどうかという考察はしてほしいと思います。
ルパン:私はすっと読んでしまって、まあまあおもしろいと思いました。全体の構成としてどうかというよりは、一個一個の場面に共感する子はけっこういるんじゃないかと思います。共感できないとしたら、アズが、まわりがせっかく仲良くしようとしているのにまったくこたえようとしないところ。それでも仲間に入れようとするこのクラスは、なかなかいいクラスですよね。ふつうだったら、イジメとか、少なくとも仲間外れにされたりすると思います。
施設に行ったときに、アズがおばあさんに話を合わせたことをからかう文香を、唯人がやっとの思いでたしなめたシーンは印象に残りました。あと、私は大阪に住んでいたことがあるんですが、いろんなルーツの人が今も肩を寄せ合って生きている感じがしました。東京やほかの地方にはない大阪のふところの深さとともに、そこで生きる人の苦しさを垣間見た気がしているので、ここに書かれている人たちの、自分たちのルーツを守りつつも、それでもやっぱり、日本で生まれて日本で育って、自分たちは何人なんだろうという感情は、ていねいに描けているのではないかと思いました。
シア:まずこの題名なんですが、雪の日にライオンを見に行ったのって、ほんのワンシーンなんですよね。ライオンが絡んでくるわけでもないのに、なんでこんな印象的な題名にしたんでしょう? どちらかというとビリケンの方にスポットが当たっていますよね。それでライオンはどうしたの? と読後に気になってしまいました。信じられないほどクラスのみんながやさしいのも気になりましたが、前の担任の先生のクラス運営がよほどよかったんでしょう。それに最近は少子化なのでクラスの人数も少なくて、子どもたちにゆとりがあるのかもしれません。とはいえ、なんだか老成していますよね。アズが登校しなくなったりしているのに、保護者が絡んでこないのもなんだかリアリティがありません。先生の描き方もなんだかしっくりこなくて、学級崩壊ポイントもいくつかあったのに何事もなく通り過ぎているので、どうにも上っ面だなあと思いながら読んでいました。最近の日本の児童文学はこういうほわっとした作品が多いように思います。ほわほわと上がり下がりもなく平坦に終わり、人間関係の解決や掘り下げなどもあまりしません。とにかく無難なんですよね。毒にも薬にもなりません。ティーンエイジャーなら、漫画の方がよほどおもしろいと思います。文体の関西弁は、おもしろいはおもしろいんですが、ほぼセリフなんですよね。なんだかなあという感じです。それに大人なら中国との関わりなどわかりますが、子どもが読んで理解できるのか疑問です。大阪のいじりといじめについての感覚の差は感じることができました。ちゅうでん児童文学賞で大賞を受賞していますが、どの辺が受賞ポイントなのか知りたいですね。
ニャニャンガ:中国残留法人の祖父を持つ唯人と転校生の女子アズとの交流を通した成長物語で、コンパクトで後味のいい作品だと私は思いました。関西弁で書かれているおかげで標準語よりきつくなく、読みやすく感じましたが、全体的にほわほわとした印象は否めません。深くはないのかもしれないけれど、ひとりぼっち同士のふたりが近づいていくの、よかったです。
コゲラ:中国残留邦人の家族という設定は、いままで児童文学で無かったような気がして(私が読んでいないだけかも!)、とても新鮮で、いいなと思いました大阪弁で書かれていることにも好感が持てました。ただ、私は関西で暮らしたことがないので、大阪弁=饒舌という感じがあって、唯人の内面とちょっと合わないような気もしました。おそらく偏見だろうと、反省してますけどね。タイトルは魅力的だと思って読みはじめ、なにかクライマックスのいいところで、効果的にライオンを見にいく場面が出てくるかなと期待していましたけど、途中でちょこっと出てきただけで、肩透かしをくらったような気分になりました。作者のなかでは、故郷を離れて大阪のど真ん中にいるライオンと主人公たちがリンクしているのだろうけど。
また、おじいちゃんが孤児になって、中国の親に引きとられたことを書いてある箇所を何度も読みかえしたけど、ここもずいぶんあっさり書いてありますね。どうして赤ちゃんだったおじいちゃんに名前を書いた手ぬぐいが結びつけられていたのかとか、戦争を知っている世代には胸に迫る場面だけど、今の子どもにはわかるかな? 作者が意識的に避けているのかな? あとがきの「この物語に登場する先生や子どもたちは、もはやおとぎ話の住人? いえいえ、子どもたちは今も昔も変わりません。どこまでもやさしく、大きな包容力を持っています」という断定的な言い方にも違和感を持ちました。ひょっとして深刻なことは書くまいというこだわりを、この作者は持っているんでしょうか?
wind24:5年生の1年間の出来事ですね。引っ込み思案の唯人と、心をひらかない転校生のアズを中心に子どもたちが成長していく姿が描かれています。小さないざこざはありますが、クラスの子たちが概ね素直でやさしく描かれています。現実はもっとシビアだろうと思います。子どもたちの世界はもっと冷たく時には残酷なのでは? そこは、作者のこうあってしいという願いなんでしょうか。
唯人の父親は早くに蒸発していますが、それでもなお、母親は父親の家族のなかで暮らし、蒸発した父親の悪口を全く言いません。人間が出来過ぎているのでは?と思いました。と同時に、大家族で子どもがそこに自分の居場所があり、安心して生活できることには好感を覚えました。クラスが大繩跳びで次第に団結していきますが、大繩のモチーフはありきたりなので新しさは感じませんでした。また唯人が5年の終わりでは180度変わり、好少年に描かれ過ぎではないかとも思いました。話の終盤で、アズと唯人に淡い初恋の気持ちが芽生えるのは、ほほえましいと思います。
エーデルワイス;図書館から借りたこの本は「ちゅうでん教育振興財団」の寄贈になっています。(他にも地域によって何件かの図書館で寄贈図書になっていました。)私は、好きな作品です。主人公唯人の心の軌跡をたどって読んでいるようで、唯人の心は苦しいなと思いました。いとこを頼りに生きていたけれど、いとことその家族がうらやましかったと気づくところには唯人の成長を感じました。p47の9行目「…唯人が感じているのはやさしさの孤独…」いじめもないクラスだけれどその中の孤独はよくわかります。唯人とアズ、結末は安心するような書き方でしたが、想像するにこの先二人はまだまだ大変でしょう。唯人はお父さんを中国で探し対峙しなくてはならないし、アズは淡路島のお母さんの実家を訪ねたら、そこで新たな問題が発生するでしょう。金沢のお父さんに残りたいと主張しても無理やり大阪まで連れてきて、自分の忘れられない初恋の話をするようなお母さんとも長く向き合わなければならないですし。『中国残留邦人』を扱っていますが、それ自体の問題より背景としている気がします。雪の日に動物園へ唯人と梓がライオンを見に行くシーンは心に残り、私はタイトルについてもなるほどと思いました。
サンザシ:自分に自身が持てない二人の子ども──父親が中国に帰ってしまい母と二人で暮らしている唯人と、周囲にとけこもうとしないアズ──が、おたがいだけは警戒せずに友だちになり、次の一歩を踏み出せるようになる姿が、ていねいに描かれていました。悪い人物は一人も出てこないし、悪意あるいじめっ子も一人も出てきません。それはいいのですが、アズがイマイチくっきり浮かび上がってきませんでした。こういう子がいてもいいのですが、もう少し内面を描いてほしかったし、唯人のおじいちゃんにも大きな葛藤があったはずですよね。先日、来日したシドニー・スミスさんが、「子どもの本は様々な感情を安心して体験できる場。それが将来実際に困難にぶつかったときに役に立つ」とおっしゃっていました。だとすれば、ほわほわの物語でも少しは役に立つのかな、と思いましたが、これならマンガのほうがいいという意見にも一理あると思います。
アンヌ:私も題名と内容が合わない気がしました。唯人については知らない世界が描かれていて物語もていねいに彼を追っている気がしますが、もう少し、アズについて書かれてもよかったのではないかと思います。ライオンももう少し、活躍してもよかったんじゃないかと。大阪独特のノリとツッコミの会話が描かれていますが、悪気のないものであるとしても、転校生にはつらいだろうと思います。同じ立場の子がこれを読んでホッとするかは疑問です。現実の小学校生活はこんなに忙しいのかもしれませんが、行事3つは多すぎる気がしました。
ハル:「そういうやつがおってもええ」っていうメッセージには、読者としてはだいぶ救われる思いもあるけれど、アズ本人が自分の性格を持て余しているので、「そういうやつがおってもええ」が、救いになるのかなぁ、どうかなぁ。著者は、現在は岐阜県にお住まいのようで、舞台とあった大阪とはどういうつながりがあるのかわからないけれど、金沢からきたアズがとても気取った話し方をしているような印象があり、そのあたりに大阪至上主義的なものも感じます。金沢の言葉遣いがこういうものなのか、関西の言葉以外はいわゆる標準語で書かれたのか、ちょっとよくわかりませんでした。
西山:私は好感を持てませんでした。ということでネガティブなコメントばかりになりますが……。タイトルはムード優先で思わせぶりに感じます。全体的に、設定の大渋滞。元号ばかりで、いつ、だれが何歳の時、それから何年というのもすんなり分からないし。大縄跳びは、地域により学校により違うと思いますが、男女別にする必要がわかりません。へなちょこ男子が、ちょっと生きづらさをかかえている女の子の前では急に立派になって、上から目線で振る舞うのは、それが唯人の成長として読めるのでしょうけれど、私は抵抗を感じました。アズのほうがよっぽどしっかりしているのに。バスの中のいじりのしつこさが耐え難く、それで唯人が立ちあがったのは展開としてはわかりますけれど、最終的に、悪気はないのだからこの大阪ノリを受け入れようよというベクトルを作品が持っている気がして、そこも抵抗を感じます。長縄跳びというところから、梨屋アリエさんの『ツー・ステップス!』(岩崎書店)の深さを思いだしたことでした。
コアラ:今回の選書係だったのですが、書店で見てよさそうだなと手に取って、読んでみてなかなかよかったので、選びました。今まで何度か読み返したのですが、どうしても一言でまとめられないという気がしています。作者は、やさしい世界を描きたかったのだと思います。現実というより、やさしさのほうに振った世界です。クラスを仕切る女の子がいて誰も逆らえないけれど、陰湿ないじめがあるわけではなく、クラスに馴染めない転校生のアズも除け者にしない、という「受け入れる」風土のあるクラス。やさしい環境だけれど、やさしさの中の孤独を唯人が自覚する場面があって、そのやさしさの中の孤独が、この作品の空気感になっていると思いました。登場人物の心情がよく描かれていて、どの人の思いもよくわかるなあと、私は共感しながら読みました。中国残留邦人だった祖父の思いや言葉が、唯人の中に根付いていくのも、世代を超えて受け継がれていくのがいいなと思いました。みなさんのお話を聞いていて、私は気づかなかったけれど、ああ、なるほどなと思えるものあったりして、いろいろな意見が聞けてよかったです。
コゲラ:お正月におじいちゃんの家で開口笑というお菓子を初めて食べた……という場面ですが、そんなにおいしいお菓子なら、どうして唯人はいままでごちそうしてもらえなかったんだろうと、ちょっとばかりひっかかりました!
(2023年09月の「子どもの本で言いたい放題」より)