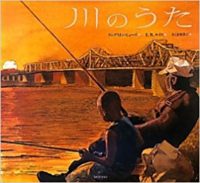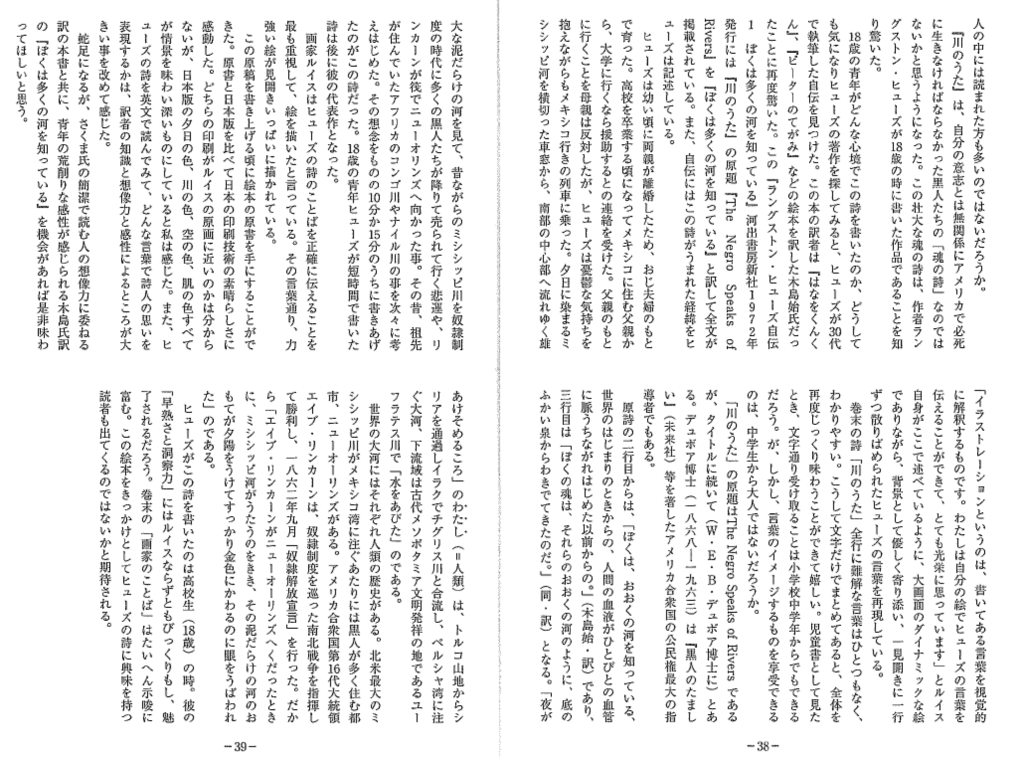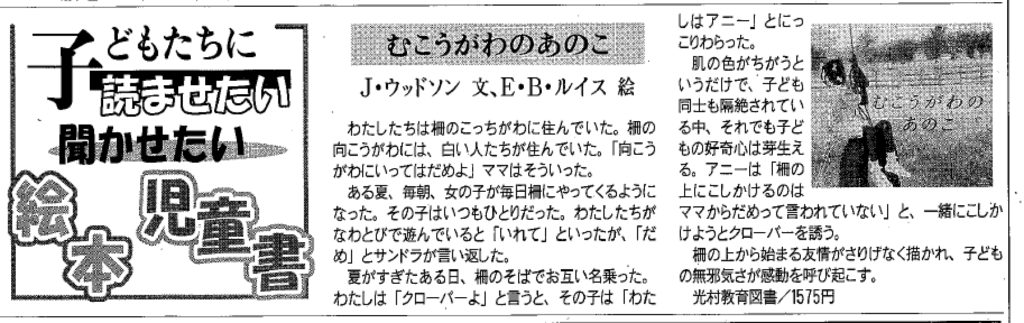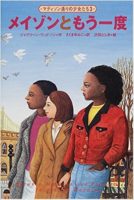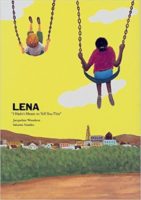ジュエル・パーカー・ローズ/作 武富博子/訳
評論社
2021.04
ハル:胸の痛くなる事件で、読んでいて心臓がばくばくしましたし、つらかったです。おばあちゃんがカルロスを憎まなかったところが、とても大きいと思います。もちろん、「お前がそんなものを渡さなければ!」と一瞬憎んだとしても、責められないですが、そこを乗り越えていけたところに希望を感じました。「最後の言葉」の「証人となれ」は、作者あとがきを読むまでは、わかるような、わからないような……? あと、大事なことだというのはわかるのですが、巻末の「参考となる質問」は、言葉は悪いですが正直、だいぶ圧が強いというか、疲労感がわいてしまったというか、若い読者にとってもかえって読後の気勢を削がれてしまうように思いました。
アカシア:最初に読んだときは、誰のセリフかな、と頭をひねる箇所があったり、ニュアンスが良くわからない箇所があったりして、そこが気になったし、巻末に質問があるのも気になって、これは結局文学ではなく、教育的な意味の強い啓蒙の書だなあと思ってしまいました。
誰のセリフがよくわからない箇所については、おそらく編集方針のせいで、会話のサンドイッチ方式のところが(たとえば[「A 」と、トムは言った。「B」]となっている外国語ではよくある書き方では、AもBもトムのセリフなのですが、本書の日本語ではこれが3つに改行されている)ネックになっていると思いました。改行を多くするのはいいのですが、だとすると訳でもわかるように言葉を足さないとまずいのではないかと思います。ニュアンスがよくわからなかったのは、p82の「やっちゃだめ」p92の「それ以上言うな」p117の5−6行目、p142の「真実が感情だった場合、どっちも真実になるんだろうか」などです。p93の「緊急支援もしてる」は「緊急支援も受けてる」かなあ、と思ったり、p172の「それではまにあわなかった」は文脈的には「それでもまにあわなかった」かなあと思ったりもしました。
ただ、今回もう一度読んでみると、最後の「参考となる質問」さえなければ、BLM(ブラック・ライブズ・マター)の問題を、生きている側と死んでいる側の両方から見た骨太の文学とも言えると思いました。著者もアフリカ系の女性で、やむにやまれぬ思いで書かれたのかもしれませんね。
wind24:BLMの問題を正面から取り上げ、その中から生まれた物語ですね。友人から借りたおもちゃの拳銃を手にして遊んでいたジェロームが白人の警官にいきなり発砲され殺されてしまいます。その後ゴーストになった彼がこれまで殺されてきた黒人のゴースト少年たちと一緒にさまよいながら、人種差別の現状を変えようと、彼らが見える人たちに働きかける設定が面白いと思いました。ジェロームに発砲した白人警官は善良な人だと思います。それは彼の娘セアラが繊細で気持ちの優しい子に育っていることや親子関係からも推測できます。しかし同時に根強い黒人への偏見を持っていることも分かります。倒れたジェーロムに対して人命救助をせず、その場へ置き去りにしたのは黒人の命を軽んじているからだろうかと思いました。また人種差別からくる発砲の後ろめたさがあったのでしょうか。
p202、p205、p207に「怖い」という言葉が連発して出てきますが、これは白人が黒人を怖がっていると取れるところが興味深いことでした。p195でジェロームの友人におばあちゃんがかけた言葉「…おこってしまった間違いは、とりかえしがつかない。正しくやりなおせるように、がんばるしかないんだよ。だれもがね」に救われる思いがしました。
アンヌ:見事な出来の本だと思うのですが、私も読み進めるのがつらくて。おばあさんが、無事学校から帰ってきてほしいと言う言葉とこれから起こることを思うと。でも、セアラが出てからは、ちょっとホッとして読んでいけました。この話では幽霊の言葉を聞ける人がそれぞれの時代にいたという設定ですが、どの時代にも死者の声なき声を聞いて異議を唱える人がいたということを、セアラを通して書いているのだと思います。ただ先ほど、アカシアさんがおっしゃったように、最後の問答集のせいで、教育者が教育目的で書いている感じがしてしまいました。ここまで著者の意図が書かれているものは、ない方がいいと思います。幽霊たちの世界という物語としての面白さが、興ざめになってしまう感じです。
きなこみみ:とてもつらかったけれど、目をそむけてはいけない物語だとも思いました。『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ〜あなたがくれた憎しみ』(アンジー・トーマス 作, 服部理佳 訳 岩崎書店)『キャラメル色のわたし』(シャロン・M・ドレイパー 作 横山和江 訳 鈴木出版)など、警官による黒人の若者への発砲事件をテーマにした物語はいろいろあるけれども、まさに真正面からこのテーマに取り組んだ作品だと思います。子どもたちとテキストとして読むのにいいと思います。主人公のジェロームをゴーストにしたのは、この問題が長い長い黒人差別の歴史の上にあること、いまだにそのレイシズムを克服できない怒りからだと思うのですけれど、p178の、ゴースト少年たちが皆で、「不公平だ。まだ死にたくなかった。はやすぎた」と叫ぶシーンに胸が詰まります。しかし、この物語は告発だけではなくって、警官の娘・セアラの視点を入れてあるんですね。ひとつの事件を多角的にとらえることで、どんな立場にいる人も、自分の問題として考えるっていうことができるように構成してあるのも、よく考え抜かれているなあと思うんです。
この作品は、現在と過去が入れ子になっていて、昔の南部の差別の実話も描かれているんですが、エメット・ティルが、白人の女性の手に直接硬貨を乗せた、あれだけのことで、あんなに酷い殺され方をするところが非常にショッキングでした。怖すぎます。ただ、『キャラメル色の私』は、主人公の少女がとっても魅力的で、物語として作品に引き込まれたんですけど、まあ、始めに主人公が死んでしまうのもあるんですが、物語にうまく入り込めない部分もありました。結末とテーマが最初に与えられてしまうことに、子どもたちがどこまで耐え抜けるかな?という気もしたり。最後の問答集が、みなさんもおっしゃるように圧が高いこともあって、物語のテーマが、物語を読む面白さを上回る感じを与えてしまう気もします。でも、レイシズムは他人事では決してない、まさに、今考えるべき自分たちの問題で、そう言う意味ではとても大切な作品だと思います。
雪割草:いくら読み進めても、作品に入りこめませんでした。会話が多く描写は現在形で、ひとつの文が短く、つながっていなくて、台本を読んでいるように感じました。訳も気になるところ、わかりにくいところが多々ありました。例えば、p89では「人種バイアス」という言葉を使っていますが、あとがきのp232で「人種的偏見とは何でしょうか(八九ページ)」と別の言葉で同じ箇所を指摘しているのは、わかりにくいと思いました。p93の「冬の暖房代の緊急支援もしてる」は「支援を受けている」の間違いだと思うので、重版があれば直した方がよいと思います。p91の「ふたりとも」の使い方やp211の「どっちの家族も」はどの家族か明確でなく、他にも主語が抜けすぎているように感じました。それから、セアラは優等生すぎるのでは? アイディアは面白いと思いましたが。
しじみ71個分:BLMを扱った本としては、本当にド直球で、胸をえぐるような内容でしたが、私は非常に重要な本だと思って受け止めました。構成も練られていて、読みごたえがありました。12歳の少年ジェロームが殺されて幽霊になったところから始まる物語なので、重たくて、非常につらかったです。私は、この本を読むまでエメット・ティルの事件を知りませんでしたが、少しネットで調べてみただけでも、エメットがむごたらしく惨殺された事件が大きく全米を揺るがし、公民権運動を推進する原動力にもなったということが分かりました。この物語の中でも、幽霊のエメットは黒人差別、黒人への暴力の象徴として描かれていて、重要なポイントになっていると思います。また、白人の女の子セアラが、警官の父が、ジェロームを殺害した事実に向き合い、父の心を変えていくところは、本当にそうあってほしいと思わされました。
作者の書いた「生きている人しか世の中を変えられない。」というメッセージは大変に重要だと思います。また、そもそも学校でのいじめがなければ、ジェロームは死なないですんだ訳で、憎しみの連鎖の芽を小さなうちに摘むということも大事なんではないかと感じました。私も、短い会話の言葉が続くところはちょっと良く分からなくなってしまって、所々誰が何を言っているのか混乱してしまいました。そのために読みが妨げられてしまったので、もう少し翻訳の工夫で分かりやすくできたのではないかなと思いました。ですが、本から伝わるメッセージはとてもパンチが効いていて、ド直球なので、若い人が読んでも分かると思いますし、ぜひ読んでもらいたいと思いました。あと、巻末に付された16の質問は、けっこう難しくて、これを授業で質問されたらすごく困るなと思ってしまったので、なくてもよかったなと思いました。
ネズミ:知らなくてもよいとは思わないのですが、アメリカの読者にはよくても、日本の読者には理解しにくい作品だと思いました。物語のいちばんの鍵になる、おもちゃの銃を持っていたことがこのような事故につながるというのが、銃社会ではない日本の読者にはピンとこないのでは? 死んだ僕と生きている僕が、交互に出てくるというつくりは、おもしろいと思いましたが。読者を選ぶ作品だと思い、誰にでもすすめるのは難しいかなと。
さららん:BLMに関する本を読んだり、情報を得たりしてきた大人には、この本を読み始める基礎知識があります。さほど長くない文章量の中で巧みに構成された、読み応えのある物語でした。ただ最初の1冊として、アメリカの問題をあまり知らない日本の子どもたちに広く薦めるのは、やはり少し難しいように思えます。物語を読みこなす前に、複雑な現実がつらくなってしまうかもしれません。死んでしまったジェローム(ぼく)を主人公に、歴史的にも知られたエメット・ティルを始め、これまで差別や偏見により殺された少年たちを「ゴースト・ボーイズ」というひとつのグループにして、これから生きる人たちのより良い未来につなげようとした点が面白く、ありそうでなかったストーリーだと思いました。p67で、加害者の警官の娘セアラが、死んでしまったジェロームに「きのどくに」と声をかける部分は、ほかに訳しようがなかったのかもしれませんが、少し軽く感じられました。学校でいじめられていたジェロームが、死んだあとセアラに対して少しいじめっこのような態度を取ってしまい、それを自分でも意識しているところになどに、人間関係を固定的なものでなく、相対化しようとする作者の視点を感じます。そのことは、最後にセアラが父親と和解する場面(p210)を用意し、そして「これが見たかった。聞きたかった。セアラと父親の両方から」とゴーストのジェロームに言わせる場面にもつながり、単純な善悪に終結させず、憎悪や怒りを越えたところまで考えさせる作者の姿勢が読み取れました。
ルパン:この作品には、みなさんおっしゃるとおりツッコミどころはたくさんあるんですが(わたしも、「ゴースト」になった主人公が「消え」ているときはどうしているんだろう、とか不思議に思いましたが)、こういう物語を日本の子どもたちに紹介するのはとても意義のあることだと思います。日本にいては書けないことであり、このような物語を通しででないとなかなか知る機会もないことだからです。それが翻訳児童文学の使命だとも言えます。登場する犠牲者たちが、主人公ジェロームを除いてみな実在の黒人の子どもであったことが本当につらく、重いことだと思いました。
この作品は、ただの「横暴な白人警官と虐げられた黒人の犠牲者」というステレオタイプに終わらず、白人警官も玩具の銃を持った子どもを体格のいいおとなのギャングと見間違えるほど恐れていたこと、差別されている黒人同士の中にもまた差別やいじめがあること、などが立体的に描かれていて、いろいろ考えさせられました。
ニャニャンガ:日本で刊行する意義のある本だと思いました。残念ながら物語に入り込みにくかった理由は、みなさんの感想をうかがっているうちにわかってきました。本文後にある「質問」は原書にはあったのかもしれませんが、教育的に感じてしまうので邦訳では入れないほうが作品としてよかったと思います。
エーデルワイス:今回の本はサークルKさんと選びました。今回の2冊はあまりにも違いますが、サークルKさんがとてもよいテーマを考えてくださり感謝しています。
「ゴーストボーイ」の表紙を見た瞬間に内容が分かりましたから、本当に読み進めるのがつらかったです。きちんと読み進め、現実の問題として作品と向き合えました。冒頭でおばあさんが毎朝学校に行く前のジェロームに「無事に帰って…」と言うところは、本当に命がけの毎日が伝わってきて心が震えました。最後の質問コーナーは興ざめでしたが、読書感想文のためかもと思ったりしました。この本の中でゴーストボーイとして出てくる1955年白人にリンチされ殺害された14歳の黒人少年エネット・ティルの映画「ティル」が公開中です。観るのには覚悟がいりますが、見ようと思っています。
サークルK:今回は選書の担当でしたが、この本を選ぶのはとても心が重くなり勇気が必要でした。それでも、現実の世界で起こっているBLM問題を児童文学作品として提起しているこの本は重要な1冊になるだろうと思われました。テキストの形式として、最後に国語の教科書のように設問が付いているのは、このような題材の本の場合、クラスで話し合ったりするときに有益だろうと思います。読んですぐはなかなか考えがまとめにくい作品だろうと思うので、このような設問をきっかけに(もちろん全部答える必要はないし、正解を求めるというより、どんなことを感じるかを共有できる場を提供する材料として)素直に感想を話し合えればよいと思いました。教育者でもある作家ということで、物語の展開が道徳的になりすぎるのではないかと心配しましたが、私にはあまりそれは感じられなかったです。
作品そのもので特に心に残ったのは、「黒人が怖い」というセアラの父親と「学校へ行くのが怖い」と言ったカルロスのそれぞれの思いです。白人で警官というアメリカ社会で権力を握っている立場の大人が、犯人を「大人だと思った」(p139)とか「(背中から撃ったにもかかわらず、ジェロームが前から)襲撃してくるようだった」(p140)といった虚偽の証言をして保身に走るところは、「怖い」という原初的な感覚がこんなにも人を縛り、先制的な攻撃を仕掛ける口実となってしまうのだとあらためて身が震えました。亡くなったジェロームの友人カルロスも「学校へ行く(=白人にいじめられに行く)のが怖かった」(p187)と胸中を父親に吐露します。お互いのことを「怖い」存在だと思っているうちは、頭ではいけないことだとわかっていても拒絶反応は止められない、怖さを乗り越えられないとしてもそこからどういう一歩を踏み出すのか、ということを突き付けてくる重たさがありました。
シマリス: 黒人が白人に撃たれて亡くなる事件は後を絶たないですし、非常に大事な重いテーマを取り上げていると思います。ただ、他にもこういう作品は今、いくつも出てきているなかで、この本は、イチオシしたいものにはならないというか……ちょっとどうなんだろう、と思う部分がありました。まず、幽霊がどういうふうに見えるのか、ルールがはっきりしていないですよね。セアラは幽霊が見える、おばあちゃんは見えないけど感じる、というように、ルールがばらばらでごちゃついている気がします。あと、先輩幽霊のエメットの他は「ゴースト・ボーイズ」とくくられて、肌の色の問題にかかわる幽霊ばかり。他の幽霊は? 世界観全体がよくわかりませんでした。生きているぼくと死んでいるぼくが交互に語るのはいいと思うのですが、一番最後、p220の「生きているぼく」の章はまったく必要ないのではないでしょうか。既にそれ以前に語られていることを、改めて書かなくても、と。それからp106「悲しみにはにおいがあることにも気づいてしまう。かびたクローゼットのなかで、食べ物が腐ってウジ虫がわいてるようなにおい」という表現には共感できなかったです。悲しみって、つらいものだけれど、そんなに拒絶するような悪い感情ではないという気がして……。
さららん:p226の締めくくりとして、「平和を」の一言があり、その言葉に「ピースアウト」とルビが振ってあります。古いスラングで「あばよ」「じゃあね」のような意味なので、英語圏の読者はそのダブルミーニングにニヤッとし、苦いユーモアを感じるところでしょう。日本人の私たちは、ひたすらまじめに重く読んでしまいがちですが、向こうのティーンエージャーには、違う受け止められ方をしているのかもしれません。
アカシア:ジェロームより前に死んだ少年のゴーストの中のひとりは、読んでいるうちにエメット・ティルだとわかります。14歳の時に白人のリンチによって無惨な殺され方をしたエメット・ティルは、アメリカでは多くの人が知る存在で、彼のお母さんはあえて棺を開いて、めちゃめちゃにされた息子の遺体を葬儀の参列者に見せたといいます。ボブ・ディランもこの非道な事件を取り上げて「ザ・デス・オブ・エメット・ティル」という歌を作って歌っています。
しじみ71個分:私も一言、いいたいです。たった14歳の少年に、白人の大人の男性がよってたかって、暴力をふるい、信じられないほどのむごたらしい方法で惨殺した事件が本当にあったということがとにかく衝撃でした。エメットは吃音のせいでうまく言葉が出ないこともあり、白人女性に口笛を吹いてちょっかいを出したというのは全くの濡れ衣だったとあります。なのに、子どもを複数の人間で徹底的に痛めつけ、体を無残に損壊し、殺害するなどということがどうしてできるのか。それは人間性を失っていないとできないことではないでしょうか。そういうことが、本当にあったと伝えていくことは必要だと強く思いました。そしていまだに差別は社会に生きていて、変わってはいないということ、人がこんなにも残酷になれるということを私たちは知っておくべきだと今、思っています。
きなこみみ:エメット・ティルの言葉の発音の仕方が暴力の引き金になったことが書かれているんですけど、関東大震災の朝鮮人虐殺のときも、「アイウエオ」とかいろんな単語を言わせて、うまく発音できない人を虐殺したりしてますよね。他にも、レバノン内戦の際に、マロン派の民兵がパレスチナ人を区別するために使うのは「パンドゥーラ(トマト)」という言葉だ、ということを、岡真理さんが『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房)で書いておられました。暴力って、違う場所で行われていても、どこか似通っているんですよね。世界中のどこを切り取っても、構造的な暴力がある。そこのところを、考えてみるきっかけにもなりますね。
(2023年12月の「子どもの本で言いたい放題」より)