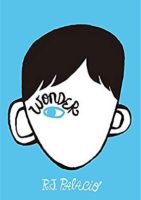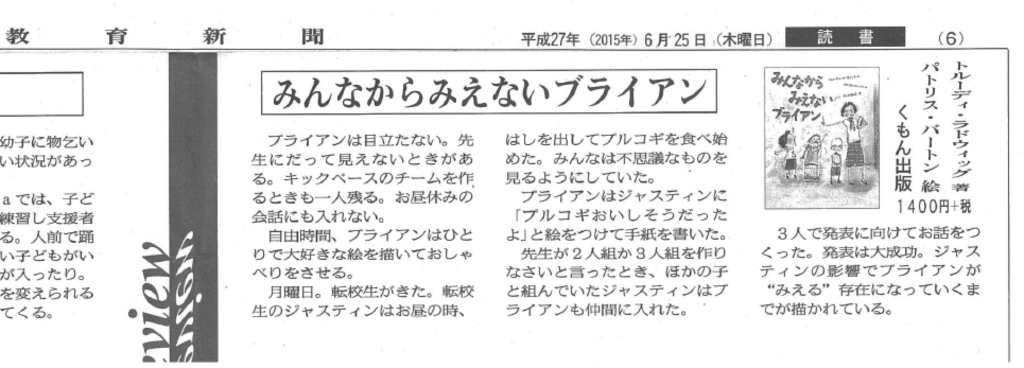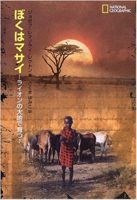村中李衣/作 長野ヒデ子/絵
文研出版
2021
花散里:まず、タイトルがおもしろいと感じました。 主人公の気持ち、母親の描かれ方など、村中李衣さんの文章がうまいし、どのページにも長野ヒデ子さんの絵があるのがとてもいいですね。私自身、運動神経が鈍くて、小学生の時の跳び箱、鉄棒、徒競走など、いつも苦手だったので共感しながら読みました。自分のことを思い返しながら、弟が、運動神経が良いということに対しての主人公の気持ちなどにも、きっと共感して読む子がいるのではと思いました。給食が食べられなくてポケットに入れて、母親に怒られるという場面なども印象的で、低学年の子どもたちが、どんどん読み進らめる作品ではないかと感じました。
アリグモ:とてもユーモラスな本で楽しく読みました。主人公はいろいろ大変なんだけれども、後半、少しずつ光が見えてきているのがよかったです。お母さんが、主人公にとっての一つの大きな“壁”になっています。悪気はないけれど熱心過ぎて圧力をかけてしまう親。この部分には共感する子どもも多いのではないかと。だから、そういう子どもの読者は、主人公がそれを解決できるのか、できるとしたらどうやって解決するのか、というところに注目すると思うのですが、この本では「おばあちゃんのおかげ」になっています。結局、お母さんよりもさらに目上の大人しか解決できないのか、というふうに子どもが読み取りかねないですよね。そういう意味でちょっと閉塞感が残るかなとも思いました。
西山:跳び箱も鉄棒も走るのも、もう、ほんとに体育がつらかったのを生々しく思い出しました。この作品は、できないことのつらさ、恥ずかしさを書いているけれど、最終的には、がんばるのかぁとちょっとがっかりするような気持ちにもなりました。でも、できなくてもいいんだよ、がんばらなくてもいいんだよ、と寄り添うより、現在進行形の子どもにとっては、こちらの方が希望で励ましなのかもしれませんね。
みなさんおっしゃるように長野ヒデ子さんの絵も楽しくてどんどん読めるのだけど、相当ネガティブなものを孕んでいる作品ですよね。「こいつ勉強ばっかして体育はできないんだぞって、みんなかげで笑ってるにきまってるし……」(p14)と思ったり、久しぶりにやってきたばあばが「どうだい? かあちゃんは、ヒステリー出しよらんか?」(p100)と言うことから、ママのあまりのバイタリティーが単純に笑えるものではないこともはっきりします。明るくテンポよく展開して、子ども読者に負担をかけないけれど、複雑でやっかいなものを抱えていて、一筋縄ではいかない作品だな、ちゃんと読み込まねば、と思っています。
アカシア:長野さんの絵がいいですね。私は長野さんの絵の中でも、これは出色の出来栄えなんじゃないかと思います。これがあるから、シリアスにならずに読むことができます。体育が苦手な子の心情が、とてもうまく描かれています。でも、p38では、[「むちゃくちゃおそいよ。わたし、体育ぜえんぶだめだもん」って笑いながら答えた。/わたし、なんで笑ってるんだろ。口の横をふにゃふにゃさせて笑うなんて、ばっかじゃないの。こういうときの自分が、いやでいやでたまらない。]とあって、この子が自分の内面もちゃんと見つめることのできる子だということがわかります。作者の村中さんも、こういうお子さんだったのでしょうか? このお母さんについては、私もウザいなあと思いながら読んでいたのですが、今どきのお母さんの中には、こういう場合、スポーツ家庭教師を雇ったりしそうです。そう考えると、この人は自分で時間と労力を使って教えているし、おばあちゃんに叱られたらすぐ態度をあらためるわけですから、勘違いしていただけで、本当はいいお母さんなんですね。
ハル:ああ、いい本読んだなぁと思って。わたしも体育が苦手な子だったので(どうでもいいでしょうけど、走るのは早かったです!)、体育の時間のこのなんとも言えない寂しい気持ち、わかるなーと深く共感しながらも、読んでいて決していやな気持ちにはならない。ママがせっせと練習させてくるのも、あこにとったらつらかったと思いますが、読み手の私は、共感こそすれ「ママはひどい」とはならず、むしろ、ママのたくましさにほれぼれするし(ジャングルジムからもジャンプできるし、海水浴も教えられる!)、ああ、体育って、生きてく上で必要な授業だよなぁとまで思えてきました。あこが「わたし、だれにもバカにされてなんかいないよ」(p117)とはっきり言うところも、いいなぁと思います。体育って本来そういうもので、苦手な子がかわいそうとか、恥ずかしいとか、そういう次元じゃないんだなーと気づかされました。物語全体に愛があるし、表現も豊かで読んでいて楽しい。ばあばのメッセージも心にしみました。親にだって、言いたいことは言わなくちゃって、小さい読者の心にも届いてほしいです。
雪割草:楽しく読みました。タイトルもおもしろいですが、それぞれの章の小見出しも良くて、目次を眺めているだけで、主人公あこがどんなふうに成長していったのかが感じられました。
それから、長野さんの絵がとても味があって見入ってしまいました。挿絵ではなく、長野さんが語られることを自分の中に入れて、ご自身として表現されているのがよく分かりました。たとえば、p29の主人公あこのウォンウォン泣く姿や、p31の怪獣になったお母さん、それからp146から147の見開きで、あこがひよこから成長していく様子など、挙げればたくさんあります。p141の「息を吸ったり吐いたりするたびに、からだが新しくなる」という表現も、少しずつ前向きになるあこがよく描けていると思いました。「ぽいたろう」という名前もおもしろいですね。でも、あえて言えば、マット運動や跳び箱など、あこが不得意なことができない子はほかにもいるだろうと思うので、気持ちは分かりますが、ひとりぼっちでもないのではないかとは思いました。
きなこみみ:私も体育が嫌いで、跳び箱も、マット運動も、鉄棒も、水泳も、ダメでした。あこがママに言われてジャングルジムに登って泣くシーンがありますが、私もジャングルジムが怖くて怖くてしょうがなかった、その気持ちが生々しくよみがえって胸が苦しくなりました。村中さんの文章は独特のリズムがあって、切ないあこの内面が伝わってくるのに、同時に俯瞰して自分を見ているユーモアがあって、どんどん読めます。p29のそのジャングルジムのシーンで「できません、できません、できません。/ジャングルのどまんなかで泣いてみた/うぉ~、うぉ~。/ほえつづけるしかない。もう永久にこのジャングルで」とあこが泣くんですが、ジャングルジムの「ジャングル」という言葉から動物が連想されてのおもしろさと、ひとり恐怖で立ちすくんでいる感じが、長野さんの挿絵と一緒にとっても伝わってきます。文章が視覚的なんですよね。p41の走っても走ってもうまく進めないシーンで「そのうちもっともっと苦しくなって、からだがずんと重くなって、あぁこれ以上はムリ、と心がむこう側をあきらめちゃう」というところ、単に諦める、じゃなくて、「むこう側」という具体的な場所を表す言葉が入って、体で感じる実感がぐっと身近になります。この一言があるから、最後に、あこが毎朝走るようになって、絵美ちゃんに「空を見る」という秘訣も教えてもらって、「ようこそ、ようこそ、と雲といっしょに広がってる」(p147)世界に、むこう側に、ちょっと近づくというのが、素直に胸に入ってきます。とてもよく考え抜かれた文章だなと思いました。
それにしても、日本の体育の授業って楽しくないですねえ。子どもの頃はあんなに苦手だった体育も、大人になったら楽しさが分かるようになったんですが、子どもの頃はほんとに苦痛でしかなかったです。懲罰的というか、できる、できない、がみんなに分かってしまう。あこを追い込んでしまうママが、ばあばに怒られて、p115で「わたしがしっかりして、子どもたちをだれにもバカにされない子にちゃんと育てなきゃ」と心情を話すんですけど、この思いってママだけじゃなくって、私たちの社会全体に、遍く、広く、深く浸透して、多くの人を縛っている気がします。子どもたちにも、とても共感できる物語なので読んでほしいですけど、いろんな価値観に縛られてる大人にも読んでほしいなと思いました。
エーデルワイス:感想をお聞きしていると、本に関係のある人は体育が苦手なのかしら。うれしくなってきます。
私も体育が苦手です。跳び箱が跳べない。ドッジボールの球を受け取れない。ゴム跳びができない……。暗い小学生時代でした。体育も勉強もできる子がいて、スーパーな子と仰ぎ見たものです。長野ヒデ子さんのイラストがとてもいいです。わざと子どものような絵に崩しています。ところどころページ数が書いていないのはわざとでしょうか。p116の10行目、ばあばに言われてママが自分の思いを吐露して泣くところがいいです。あこちゃんをありのままに受け入れてくれるばあばの存在は嬉しいです。小学生だった頃の自分を思い出しながら、あこちゃんは賢い!と、楽しく読めました。
アカシア:あ、一般化されるとまずいのであえていいますが、私は体育苦手じゃなかったです。体を動かすのは好きでしたよー。それに、小学校の時、鉄棒でクラスでただ一人大車輪ができた同級生は、後に哲学を学んで、某大学の学長になりました。本が好き=スポーツが苦手とは言えないと思うけど。
しじみ71個分:私の小学校時代を追体験するような物語でした。私も体育が大の苦手で、本当に苦痛でした。なので、あこの体育がつらいという気持ちが本当にリアルに伝わってきました。自分も逆上がりもできなかったし、跳び箱もマット運動も、走るのも全部だめで、体育の時間はとても恥ずかしい、情けない気持ちがしたもので、その気持ち、よくわかるよーと、ずっとあこに寄り添って読み進めました。村中さんが子どもの気持ちを丹念に描いているので、あこの心の動きが手に取るようにわかります。あこの体育に対する葛藤には、お母さんとの関係も大きく影響しているのがつらいところですが、日頃から人の心をよくよく観察されている村中さんだからこその物語だと思いました。子どもの気持ちを受け止めないで強引に引っ張っていこうとするお母さんの姿には、自分にもこういうところがあったなぁと反省されられましたが、お母さんもがんばらなきゃいけない、子どもにもがんばらせないといけないと思っていたのは、考えると気の毒な、切ないことですよね。ばあばの登場によってお母さんがばあばの子どもに返って泣く場面では、大人も未熟な人間なんだ、子どもと一緒に成長途中だというメッセージが聞こえるようでぐっと来ました。「大人もだめじゃん」と公然と子どもに示すのはとても公平なことで、本当に村中さん、すごいと思います。
うちの母も体操部だかなんかで、小学生の頃は布団を敷いて、逆立ちやらでんぐり返しやら練習したこともあって、うわぁ、本当に自分のことみたいとずっと思って読んでいましたが、最後にあこちゃんが走るのが好きと分かって、「なんだ、走れるんじゃん」と置いてけぼりを食らった気がして少し寂しくなりましたが(笑)、新しい考え方ややり方を見つけることで、自分の苦手なこと、苦しいこと、つらいことを乗り越えていく可能性を示した終わりは本当に清々しく、開放感がありました。走ることではないけれど誰にも、違う何かの転換ポイントがあって、少しずつ成長していくのだろうと思えました。50m走ることそのものより、苦手意識のせいで走ることの手前で向こう側への到達を諦めてしまうという、あこの心の分析がありましたが、それを乗り越えていけるだろうという期待を、明るく自然に提示してくれています。本当に児童文学はすてきだと思える本でした。読めてよかったです!
アンヌ:久々に小説を読んだという気がして、見事な構成だと思いました。私も体育は不得意な上に、スポーツ万能な若い叔父や叔母に囲まれて育ったせいで、できないことがわかってもらえない状況が主人公とかぶりました。スポーツマンの人には、お母さんがジャングルジムから飛ぶように、怖いがスリルに変わる成功体験があり、できない子どもの恐怖が理解できないんだろうなと思いました。読んでいて、失敗して跳び箱に乗っかってしまった瞬間の感覚とか、鉄棒の匂いとかまざまざとよみがえってきました。物語の中の時間がゆっくりしていて、転校生の主人公がだんだんと周りの子と話すようになって、その中で疑問を持っていくという展開もいいなと思います。唐揚げを入れるポケットとか、犬に追いかけさせて50メートル走のタイムをあげるとか、笑ってしまう場面もあり、挿絵も楽しくて、読者が主人公と一緒にひたすら悲しくならないのもいい感じでした。海の場面での水に浮く感覚が違うとか、遠泳の後の疲労感とかの描かれかたも見事で、だからこそ家族に主人公の話を聞いてやってよと叫びたくなりました。
怪我の場面はつい親の気分で読んでしまっておばあさんの言葉が響きました。弟も役目としてうまく機能していると思います。自分はできる、だからできない人のことはわからない、わかってあげる必要もない、と思っていいのは幼い子どもだけなんだというのがよくわかります。主人公は走るようにはなるけれど、この物語の中ではまだ跳び箱も鉄棒もできないままで、問題を解決したとは書かれていません。だからこそ、今体育でつらい思いをしている子供たちにも手渡せるいい物語だと思います。
(2024年07月の「子どもの本で言いたい放題」より)