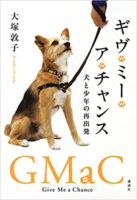アンソニー・マゴーワン/作 尾崎愛子/訳
岩波書店
2024.03
ANNE:装丁を見て少し前の翻訳書のようなイメージを持ったのですが、2024年3月出版の作品でした。時代がどんどん流れていくドラマチックなストーリーに引き込まれましたが、犬たちの過酷な戦いのシーンなどは少し苦手でした。冒頭に理由は説明されていますが、地名を敢えてキエフと訳していることにやはり違和感が拭えませんでした。子どもたちに手渡す際は、ロシアのウクライナ侵攻についても触れるべきかと思いました。カテリーナをミーシャがアルファと認識する場面、もっと読んでいくとアルファが何を意味するかわかりますが、ちょっととまどいました。
ハル:カテリーナをアルファと呼ぶことについては、p249の少し前、p247に「あの生き物は、おれのアルファだ」と認識する場面がありましたね。
シマリス:非常に引き込まれて、読みました。チェルノブイリ周辺の森だという特殊性、そして犬とオオカミの習性の違いなど、読みどころはたくさんありました。ただ、終盤、怪物が出てきたところで、ここから突然ファンタジーになるのか?と、とまどいを覚えました。結局、怪物とは巨大なウナギのことだったのですが、このあたりから物語の構造がこれでいいのか、とちょっと引いた感じで読んでしまいました。特に納得がいかなかったのは、ミーシャをキエフに連れてくる場面です。ミーシャは、おじさんに面倒を見てもらって、過ごしています。そこでナターリヤが現れて、主人公の特権で犬を奪ってキエフに連れて行ってしまいます。かわいがっていたおじさんの気持ちとかまったく無視の展開に、ちょっと心が冷えました。チェルノブイリに翻弄されて、それでも生きてきた女の子と犬が最後に再び出会うという構造にしているのはわかるんですが。人間と動物の視点を交互に描いた物語は難しいなと思います。
ニャニャンガ:チェルノブイリ原発事故のあと、生きものたちがどのように暮らしていたかにとても興味を惹かれて読みました。別れ別れになった子犬のゾーヤと飼い主のナターシャが中心の物語と思いきや、犬たちの話が8割ほどだったのは予想外ではあったものの、原発の影響など知る由もない生きものたちの生存競争を興味深く読みました。ただ、こちらも五感に訴えてくるつらさがありました。そして人間の物語とちがい、動物たちがたくさん死んでしまうのが仕方ないとはいえかわいそうでした。それでもオオカミ犬ミーシャとブラタンの兄弟愛に強く心を動かされました。
作者から日本の読者へのメッセージで、「純粋な冒険物語」とあり、原発事故は
創作のきっかけではあってもテーマではないと知り、エンタメなのかなと少し残
念に思いました。
きなこみみ:生と死、出会いと別れ、冒険、闘い。物語の渦に巻き込まれ、気持ちよく引きずり込まれてしまいました。実は1度、冒頭のところだけ読んで、ナターシャとゾーヤの別れのシーンで挫折しかけたんです。チェルノブイリ原発の事故が起こったとき、ほぼ何が待っているのかわかってしまって、つらすぎて。チェルノブイリやフクシマの事故のとき、人間が避難したあとに置き去りにされた犬や猫たちのことが蘇りました。どうも、犬や猫がつらい思いをする物語が怖いんです。ナターシャの悲しみ、いつまでも埋まらない喪失の痛みが、まるで自分のもののように伝わってきました。
でも、ミーシャの物語がはじまってからは、読むのがやめられずに一気読みです。まず、構成がすばらしい。ナターシャ、ミーシャ、そしてカテリーナという3つの世界があるんですが、時系列をいきつ戻りつして語ることによって、少しずつ謎が解かれて、物語のドラマチックさが増しています。それぞれの、原発事故から始まった生きる闘いの記録なんですが、なかでも、ミーシャたち動物のたくましさ、生き抜こうとする強さ。オオカミと暮らした哲学者が、オオカミと人とは、生きている時間軸が違うと書いていました。(『哲学者とオオカミ : 愛・死・幸福についてのレッスン』(マーク・ローランズ 著 今泉みね子 訳 白水社)私たち人間は未来にとらわれ、いつも未来の準備に今を費やしてしまう。でも、動物たちは違って、どんな一瞬でも「生きる」ことに全力で、生き抜く闘いの一瞬にも喜びが爆発しているようで、ほれぼれします。数ある闘いのなかでも、コーカシアンシェパードといっしょに、父親オオカミの群れと戦うシーンには、かたずをのみました。
印象的なのは、強く賢いミーシャの横に、いつもブラタンという足の悪い弟がいること。犬という生き物が持つ愛情の強さを象徴するようなことだと思います。闘いから逃げたように見えたブラタンが、熊をみつけて戻ってきたとき、彼が真の意味でミーシャの分身だったのだと思いました。その得難い、犬一族の強い愛情を、ナターシャとゾーヤ、そしてカテリーナという、人間と束の間でも育んだことが、伏流水のようにゾーヤとミーシャのなかに生き続けて、そして、傷ついたままおとなになったナターシャを溶かした。その愛情が、次の世代の赤ちゃんへ、新しい愛情へと繋がっていくという、見事さを感じます。
原発事故、放射能汚染という取り返しのつかない巨大な破壊と痛みから、どう回復して生きてくかというテーマが、この作品の中に流れているのではと思いました。作者が、カテリーナの番外編を書きたいと思っていると後書きにありますが、私もとても読みたいです。森のなかで1人で生き抜いていた、パルチザンであったカテリーナの物語を読みたい。『炎628』(監督エレム・クリモフ 1985年公開)というパルチザンの少年が、話すのもためらわれるほど悲惨なものを見る映画がありますが、戦争の時代に、ウクライナに生きていたパルチザンは、まさに辛酸を舐める経験をしたと思うんです。だから、彼女にとってロシアの若い兵士をだまくらかすなんて、きっと簡単なことだったろうなと思ったり。そういう背景を想像するのも楽しい作品でした。
花散里:本が刊行されたときにすぐに読みました。この本を最初に手に取った時に、タイトルから、福島のことを思い出し、ストーリーが予測されるように感じ、巻頭の「歴史に関する覚え書き」からも手に取りにくいという感じもありました。原発事故が起きた時のナターシャの章から、放射能に侵されたチェルノブイリの森に置き去りにされたゾーヤの子、ミーシャのことになってしまい、最初、展開にとまどいも感じましたが、ミーシャが生きていくために様々な困難と闘っていくストーリーはとても読み応えがありました。
巻頭の「物語の舞台」に本書の表記について記されていますが、本書が日本で刊行されたとき、キエフのことはキーウと呼ばれたことや、ウクライナの戦争が始まっていたことなど、「あとがき」で、全く触れていないことに、疑問を感じました。巻末の「作者インタビュー」よりも、大切なのではとないかと思います。
雪割草:おもしろかったです。私は新潟の出身で、父がずっと柏崎刈羽原発反対の活動をしていてチェルノブイリにも事故後すぐに視察にいきました。子どもの頃は、そんな父から原発の事故が人の生活や人体にどんな影響を与えるのかわかりやすく伝えている本を薦められて、私たち兄弟は読んでいました。だから、原発事故の怖さはすっかり沁み込んでいて、福島の事故が起きたときは、私は若かったし一目散に東京から南へ避難したほどです。そんなこともあって、チェルノブイリの事故がどんなふうに描かれているんだろうと期待しながらこの作品を読みはじめましたが、チェルノブイリの事故は枠物語のようになっていて、メインの犬たちのストーリーにはそんなに表現されていないので少しがっかりしました。
けれども読み終えて、犬たちのストーリーに、繰り広げられる生き残るための死闘が、原発事故という人間がつくったものが招く死の理不尽さを浮き立たせていると感じました。犬たちのストーリーの細やかな描写は見事で、すっかり感情移入してしまったので、サルーキやブルタンに死が迫ってきたところは、つらくて仕方がありませんでした。犬たちの集団が、それぞれの犬に個性があって多様なところもいいなと思いました。カタリーナが住んでいるところは、映画「アレクセイと泉」を思い出しました。
しじみ71個分:私とてもおもしろかったです。マゴーワンは、前に読んだ『荒野にヒバリをさがして』(野口絵美訳 徳間書店)が、4巻シリーズの最終巻のみしか日本語になっていなかったからかもしれないですが、とてもおもしろかったのに、どこか食い足りなさを感じたので、今回はどうなんだろうというと思って読み始めました。自分自身、動物に人間の感情を重ねるような書き方はあまり好きじゃないので、最初は、犬同士の兄弟愛が人間っぽく書かれていたので、引っかかったのですが、読み進めるうちにそんなことは忘れてしまって、ミーシャに感情移入して読み、最後には感動してしまいました。
原発の事故によって、人間のいない危険な世界が生まれ、その中でさまざまな命がたくましく生きていく姿を描いて圧巻でした。野生動物たちが生き抜く世界は本当に過酷に情け容赦なく、食って食われてが描かれますが、迫力があって本当に魅力的でした。犬の20年くらいの一生でしょうか、それがとてつもなくドラマチックに、大河ドラマのように描かれていて、すばらしいなと思いました。また、ミーシャが年老いて命が消えていく場面も、体がどんどん軽くなって、命の根源に向かって走っていき、走馬灯のように美しいイメージが連ねられて、本当に美しかったですね。スーザン・バーレイの絵本『わすれられないおくりもの』(小川仁央訳 評論社)をちょっと思い出しました。1か所、p310に「空き地」がつつみこむというところの「空き地」って何だろうとわからなかったのですが、そんなことは構わず感動しました。
あと、「怪物」の章だけ、怪物の視点のような気がしたのですが、これはどんな意味があったのでしょう? それと、なんで最初からウナギだと言わなかったのかもよくわからなかったのですが、もしかして、マゴ―ワンはすごいサービス精神のある作家で、子どもたちをドキドキさせてやろうという気持ちでここは怪物にしたのかな?などと思いました。犬が狩りをするような荒々しい姿は日常的に見ることはないですが、マゴ―ワンも人の消えた世界で、死闘を繰り返しながら生き抜いていく命のたくましさに大いに惹かれたんじゃないでしょうか。本当におもしろかったです。
エーデルワイス:私も、とてもおもしろく読みました。最後の場面でミーシャ、ブラタン他仲間の犬たちが天国(と思われる)へと走る場面は、やはり犬の視点で描かれた『パップという名の犬』(ジル・ルイス作 さくまゆみこ訳 評論社)の最後の場面とよく似ています。少女ナターシャと別れた子犬のゾーヤがどのように生きていったのかだんだんわかってくる仕組みも巧みです。ゾーヤの子どもミーシャ物語からから始まるので。
犬たちが懸命に生き抜いていきますが、チェルノブイリ原発事故の影響が出ないかとハラハラして読み進めました。ゾーヤ、ミーシャ、ブラタンはオオカミの血が入っているサモエド犬。私自身犬は好きですが詳しくないので、犬の種類特徴についても書いてもらえたらよかったと思いました。オオカミとの戦いの助っ人にブラタンが馴染みの熊を誘導する場面は、ファンタジーだと思いました(ちょっと都合がよすぎる)。ミーシャの子孫が森でたくさん育っていると思うと感慨深いです。殻に閉じこもったままおとなになったナターシャが、ゾーヤの子ミーシャと巡り会って本当によかったと思いました。
ハル:今月の本は、「追体験」のインパクトが強かった2冊でした。この本は、最初は「あ、主人公はこっち? 犬?」というとまどいと同時に、ミーシャって誰? とか、犬になりきって人が書いてる⋯⋯とか、この世界に入り込むまでに時間がかかるかもしれませんが(私がそうでした)、子どもの読者のみなさんにもなんとかそこを乗り越えて、だんだん感情が動物の体に入り込んでいく感覚を楽しんでみてほしいです! 農場でのオオカミとの戦いの場面は、オールキャスト集結っていう感じで手に汗にぎる思いで読みました(「伝説の幽霊馬になった」ってどういう意味でしょう 笑)。死の迎え方、描き方も印象的でした。一生懸命生きたあとに死を迎えることは、恐ろしいことではないのかもしれないなと思わせてくれた本でもありました。
ハリネズミ:犬の視点で書かれているところは、いかにも犬の五感を通して見ているようで、おもしろかったです。チェルノブイリに置き去りにされたペットは、ほとんどが射殺されてしまったんですね。福島でも、置き去りにされた(そうせざるをえなかった)点は、チェルノブイリと同じですが、射殺はされなかったので、動物レスキューの人が入ったりしていて、そこが違いますね。人間が入れないところが動物・植物の天下になるという部分は、イ・オクベさんの『非武装地帯に春がくると』(おおたけきよみ訳 童心社)という絵本を思い出しました。
この物語では、ナターリアが原発事故の被害を受けただけではなく、人間に飼われていた動物たちも、野生化して生きざるを得なかったり、弱い者はすぐに命を落としたりして被害をこうむっています。作者は「おもしろい物語」を書こうと思ったと書いているかもしれませんが、生きとし生ける者がみんな被害を受けたということはちゃんと書いていると思います。ワディムさんのところも、いつ会いにきてもいいと言ってもらったので、私はそんなに気になりませんでした。私が唯一気になったのは、オオカミが悪役として登場するところです。オオカミは必要以上に殺したりはしないので、生態系の維持に役立っていたという説があり、だからオオカミを呼び戻して自然の循環を健全に保とうとしている人たちもいます。この本だと、オオカミがやたらに殺戮に走っているようで、それが気になりました。
きなこみみ:p232の、巨大なウナギのいる湖に降ってきた「石粒のようなもの」は、いったいなんだったのでしょう?
しじみ71個分:私は人間が撒いていた餌じゃないかと思ったのですが⋯⋯?
ニャニャンガ:養殖されていたウナギが、事故のせいで人がいなくなり野生化したのだと思います。
(2024年11月の「子どもの本で言いたい放題」より)