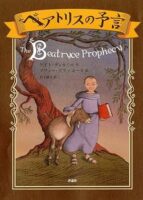
ケイト・ディカミロ/作 ソフィー・ブラッコール/絵 宮下嶺夫/訳
評論社
2023.04
ハル:最初から言いづらいのですが、もう、勇気を出して白状すると、p150くらいまで、何が書いてあるのか全然頭に入ってきませんでした。p150くらいからだんだんおもしろくなってきたけれど、開き直ると、そのあとも眠気との戦いでした。テーマはよくわかりますし、文字を覚えていく場面はわくわくしまし、きっと読む人が読めば良い本なんだと思いながらも……私の読書力の限界。「彼女」が繰り返し出てくるところや(母親のこともベアトリスは「彼女」と呼んでいましたし)、国王がベアトリスを呼ぶのは「あんた」でいいのかなぁ、とか、なんとなくキャラクターがつかみづらかったです。
アンヌ:ファンタジー世界の作りがとても雑な気がして、読みながら次々に疑問がわいきてしまいました。「悲しみの年代記」に書かれる予言はどうやって王室に伝わるのを一般市民は知るのか?女性が文字の読み書きができないと信じられてる国ならば、ベアトリスの母はどうやって文字を知ったか?人魚は何をしたくて外に出たか?等々です。でも、それと同時に、タリバン統治下で学校に行くことを禁じられたアフガニスタンの女の子たちはどうなってしまうのだろうと思わされたので、この物語に今の現実が反映されていると感じました。
サンザシ:物語はおもしろく、記憶を喪失していたベアトリス、頑固なヤギのアンスウェリカ、読み書きはできないが機転のきく素朴な少年ジャック・ドリー、森の中でクラス元の王エーレンガード(カノック)、修道院で予言の書を文字にしていたエディック修道士と、それぞれ違う立場、違う文化を背負っているキャラクターが、会ってすぐに勘が働いて親しくなるのもいいし、ベアトリスの人魚の物語が本編をなぞっていくのもいいですね。ただし翻訳は、彼、彼女、それ、きみ、といった不必要な代名詞が頻出するので、読みにくく、スムーズは物語の流れを阻んでいるように思いました。イラストもいいのに、残念ですね。それと、エディック修道士の一人称が、「ぼく」と「わたし」の2通りになっていました。
エーデルワイス;久しぶりの厚いファンタジーの本にわくわくして読みました。飾り文字、挿絵、装丁どれも素敵です。読みやすい文章だと思いましたが、教訓めいた言葉ばかりで嫌気がさしてきました。また内容をただただ長くしているだけではと思ってしまいました。もっと別の構成があるのでは?と、思いました。
wind24:短い章立てになっていてお話がブツブツ切れてしまう印象ですが、子どもたちの読書力を考え、読みやすくしているのでしょうか。物語としては印象的なモチーフが散りばめられていているので易しく読み進めることができると思います。ヤギのアンスウェリカが狂言回し的役割でお話の全体を通して重要な位置にあると思います。ベアトリスのいる世界と王国での出来事が同時進行的に書かれているのはおもしろいと思いますが、王国での内容が予言が中心で、予言に出てくる少女を捜しだすことに終始しているので途中で飽きてきました。国民は反抗せずに王室の命令に従うべき存在で黙々と働き税金を納め、命令がでれば戦場に赴く…今も世界中、政府と国民の関係性は似ている国が多いのでは? 特に発展途上国には多いと感じます。
おしまいに新たな国王の座にベアトリスの母が就きますが、話の中で母親の存在が感じられなかっただけに、いささか唐突に思えました。本来ベアトリスが王座に就く流れと思いますが、もう少し見分を広め経験を積むまでのつなぎともいえるでしょうか。
最後に一番大切なものは「愛」で締めくくられていますが、それまでの内容に愛を感じさせるものがありませんでしたので、水戸黄門の紋所のようで違和感を覚えました。
コゲラ:小学生のころの私が読んだら、おもしろくて夢中になって、何度でも読みかえしたと思います。昔話風の物語で、謎の少女ベアトリスが目的地に向かう途中で魅力的な仲間がどんどん増えていくところも、昔話の定番。ある日、とつぜん王位を捨てたカノックやジャック・ドリーもいいけれど、なんといってもヤギのアンスウェリカが最高ですね。読み終えたあとも、短い毛の生えた柔らかい耳や、石みたいに固い頭の手ざわりが残っています。そんな昔話のような物語のなかに、女の子の読み書きを禁じることの残酷さや、手に持つと振るわずにいられない剣とか、作者にいいたいこと、現代的なテーマがきちんと込められている。イラストも、もちろん素敵だし。ただ、「彼」「彼女」を執拗に使っているのは、訳者のなにかこだわりがあるのかな? 日本語は主語がなくても成立する言葉だし、そのほうがずっと自然なのに……。
ニャニャンガ:同じヤギを指すのでも、原書でsheとなっているところは「彼女」、goatとなっているところは「ヤギ」とそのまま訳されています。
サンザシ:機械的に訳語をおきかえている、ということですか?
ニャニャンガ:もしや編集されていないのではと思ってしまうほどでした。
サンザシ:こういう訳し方にこだわったというわけではないんでしょうね。
ニャニャンガ:編集者さんが、翻訳家の方にコメントしづらい状況にあったのでしょうか。
サンザシ:ベテランの翻訳者の方なので、編集者もおかしいと思っても強くは言えなかったのかもしれませんね。
コゲラ:私は、こうすべきだっていう、なにか特別な思いが翻訳者にあるんじゃないかって思ってしまったわけ。それが残念だなあと思いました。この本が大好きな子には余計に。でも本好きの子は、そういうところをすっとばして読むかもしれませんね。原文で読みたくなりました。
ニャニャンガ:ケイト・ディカミロも、ソフィー・ブラッコールも大好きなので私は原書を読んでいて、邦訳が出るのを楽しみにしていました。ところが、児童書なのに「彼」「彼女」が頻出し、対象年齢の読者にとってわかりにくのではと心配になりました。訳者あとがきに「日本のおさない読者に読みやすいように」とありますが、そうは思えずとても残念です。悔しいというのも変ですけど、もっとよい作品になっていたはずです。原書で読んだときは、登場人物がそれぞれ特徴的であり魅力的だったので、感情移入して読みましたし、物語にとても愛を感じました。ベアトリスの記憶がなかったときからはじまり、断片的な記憶がもどっていく過程で、大切なものは何かが伝わってくる、胸が熱くなるお話でした。日本語訳で読んで気づいた点としては、この国の王は世襲制ではないのですね。最後にアベラール家のベアトリスのお母さんが王になるのは少しだけ意外な気がしました。
シア:ニャニャンガさんのご指摘なんですが、話の途中でアベラール一家が城に住んでいる描写が出てくるので、公爵あたりの王に近い血筋なのかなと思いました。さて、この本は1ページ目から妙なんですよね。全部夢の中なのかなと思えるほど、安易で奇妙な世界なんです。ヤギのあたりのくだりなどギャグでしかありませんでした。文章は小さい子向けだと思います。訳者が「なるべく、すらすら読んでほしいという思いから」このようにしたみたいですが、なんとも古く、往年の児童文学を思い起こさせる雰囲気でした。ロアルド・ダールの訳を手掛けていたみたいですし、お年を召した方なんですね。その年代の書き方なのかもしれません。訳文の奇妙さもありますが、内容もどう読んでいいのかわかりませんでした。例えばベアトリスが正体を隠しているはずが突然名乗ったり、p94で「『わたしは絶対におそれない』ベアトリスはまた言いました」とありますが、その直後のp95で「しかし、彼女はおそれました」と、早々に前言撤回されたので、おそれるんかーい! と、お笑い芸人のようなツッコミをしてしまいました。関西風ツッコミを入れざるを得ない箇所が多い上に、とにかく古臭いんです。つまらないやり取りをする英語や道徳の教科書かというレベルで、おもしろくありません。なぜふいにギャグ調になるのかもわかりません。p128「その人はぐるりと宙をまわってからもどってきて着地し、そのまま横たわっていました。男でした」とあるんですが、ヤギに攻撃されて突然男がぐるりと宙をまわるという表現が読んでいてなんとも居心地が悪く、続けて「男でした」とぼそっと入ってくるところで思わず苦笑していました。p132「ジャック・ドリーは木の枝の上に立っていました。そのとなりにはベアトリス。木の根もとにはヤギと得体の知れない男。ジャック・ドリーは剣を手にしています。鳥たちがさえずっています」という風に、文章が台本みたいにたたみかけてくるんですよね。ちょっと読みにくいと感じました。登場人物たちも行動に矛盾点が多く、行動に一貫性がありません。ご都合主義な展開ばかりで読んでいてつらかったです。ラストで囚われていただけの母親が女王になるなど、もう噴飯ものです。p296「愛。そして愛を描くさまざまな物語。それらが世界を変えるのです」と締めくくっていますが、ハッピーエンド至上主義のディズニーだって、こんなに子どもだましではありません。こんな感じでモヤモヤしながらあとがきに入ったら、p299「主人公がすばらしい。この本のすべてがすばらしい。だれもがこの本を好きになってしまうだろう」(〈ニューヨークタイムズ・ブックレビュー〉)なんて書かれていたので、もうニューヨークタイムズのブックレビューは信じません。映画化されるとありましたがどうなることやら。オシャレな装丁やさしい絵は良かったです。そこが救いでした。
ルパン:みなさんのコメントのとおり、としか言いようがありません。発言の順番が最初の方だったら、今までのご意見、ぜんぶ私が言ったのに、という感じです。最後の「愛」も、ぎゃふんという感じでした。原書で読めばおもしろいというお話があったのですが、訳がうまくてもカバーしきれない部分はあったのでは
メインの登場人物のなかで、成長しているらしいのはエディック修道士でしょうか。主人公も、直感だけに頼って行動し、結局は都合よく助けられるので、どこがどう成長したのかわからない。王様だったカノックに至っては、ある日、突然お城を出て行って王冠を池に捨てちゃう。その理由もわからないし、無責任きわまりないですよね。ヤギも何者なのか。どうしてヤギがこんなヤギなのかも説明がない。いろんな人やいろんなもの、いろんな場面が次々現れるけれど、とりとめのない感じで、私はあまりおもしろいとは思いませんでした。
花散里:子どもたちに本を手渡す立場の者として、海外の優れた絵本、児童文学を翻訳者の方が選んで訳してくださり、編集者の方との協働により刊行してくださることによって、私たちは子どもたちに外国文学を手渡すことが出来るのだと思っています。より良い海外の作品を子どもたちに手渡したいと思います。本作は小学校高学年でも、読書力のない子には読みにくい作品だと感じました。登場人物、ひとりひとりはすごく魅力的で、特にヤギの行動について興味深く感じました。ファンタジーと言えるのかどうかと思いましたが、物語の展開がおもしろいのと、装丁、挿絵が素敵だと感じました。そういう意味からも、「この本、おもしろいよ」と手渡せるような、よい訳文で読みたかったと思いました。
雪割草:私は読みやすかいと思ったのですが、内容は正直よくわかりませんでした。読み終わって、よかったところを考えたときに、絵だけだと思ってしまいました。p296に「結局、重要なのは予言などではないということです」とありますが、この話自体が予言を軸に展開していて、登場人物らも予言に突き動かされていると思ったので、どうも腑に落ちませんでした。世界を変えるのは「愛」というメッセージも、心に入ってくるように描けているとは思えませんでした。人魚の物語もどう作用しているのでしょうか。この訳者の『マチルダは大天才』(評論社)は小学生のときに読んで好きでした。おとなになってから読み直していないのではっきりしたことは言えませんが、この作品では訳がとても気になりました。ヤギを「彼女」と訳されているのを読んだとき、読み間違えかと思って前後読み直しましたし、わざとなのだろうと理解していますが、たぶん意図した効果は子どもには伝わりづらく、人と同等に扱いたいのであれば、主語以外でどうにかした方がよかったのでは思いました。またp289にあるように、文末に「です」が多用されており、実況中継みたいで落ち着きませんでした。それから、4人が簡単にお城に侵入できたり、母は捕まっても殺されずにいたり、物語としても甘さ、ゆるさを感じました。
きなこみみ:まず、装丁が美しいことに惹かれました。見返しも表題紙も挿絵も、細かいところまで神経が行き届いていて、「本」への愛情がまず感じられます。物語は世界観が作りこまれたハイファンタジーというより、寓話のような物語で、タイトルと装丁を考えると、この本そのものが、予言書のような形でディカミロは書いたのではと思うんです。だから、物語としてはつじつまが合いにくかったり、わかりにくいところもあるんですが、今の時代への問いかけ、ジェンダーの問題を含め、この世界の暴力にどうやって立ち向かえばよいのか、という問いかけだと思います。印象的な場面がたくさんあって、たとえばベアトリスがヤギの片耳を握って眠っているシーンや、空が真っ青で光り輝いているときに、啓示が下りてくると感じられたりする、そういう詩のような場面やイメージを積み重ねることで、ディカミロは強いメッセージをこの物語に込めたかったのではないかな、と思いながら読みました。だから、みなさんのおっしゃるように、訳がもっと良ければ、全く違った物語になったんじゃないかなと残念です。
後書きを読むと、ディカミロは児童文学大使を務めていて、アメリカの児童文学会の重鎮としての役割を果たしてらっしゃるので、p88の「だれもが自由に読み書きし、さまざまな意見を発表する」ことへの抑圧に屈しないための励ましや、ひょっとしたら宣言みたいな気持ちもあったのではないかと思うのです。「女の子は読み書きしてはならない」という縛りは今も世界中にあって、他ならない自分の国の内閣も男の人ばっかりずらっと並んだ光景を見ると、ああ、私もこのベアトリスの世界に住んでいるんだなあと思ったりするんです。私はヤギのアンスウェリカがとても好きなんですが、ベアトリスとヤギの結びつきが、全く言葉を必要としない繋がりで、それがずっとこの物語の根底にある。それは体の温かさを通じた強い愛情です。そして、ベアトリス、ジャック・ドリ―、エディック修道士との関係も、絵や、口笛や、歌などの「美」で繋がった仲間たちと、支配的な暴力に向かい合う。そういう構図になっています。ジャック・ドリーが、人殺しの剣を手にしたとき、復讐の殺意が芽生えるところ。武器というものを手にしたときの人間の心の動きが描かれているところ。そこを、言葉の力で乗り越えるのが、強いメッセージだなと思います。ラストの「愛。そして愛を描くさまざまな物語。それらが世界を変えるのです」というところ、どうも評判が悪いのですが、そこまでのメッセージを訳文がちゃんと伝えられていたら、もっと違う感動があったのかもしれないです。
アンヌ:ニャニャンガさんにお伺いしたいのですが、原文はもっと韻を踏んでいるとか詩的な感じですか?
ニャンガニャンガ:韻を踏んでいた印象はないです。ディカミロは、子どもの頃にお父さんに暴力を振るわれていたそうなので、暴力に打ち勝つのは「愛だ」ということは伝えたかったのではないでしょうか。
アンヌ:確かに、エデイック修道士の頭の中に常に彼を否定する父親の声が響いていて、彼が生まれてからずっとDVを受けていて、父親が死んだ後もその影響を受けているのがわかりますね。
ニャニャンガ:それを乗り越えていくのを書きたかったのではと思います。ただ、昔話風の物語でありながら、セリフが今風な箇所があるのでアンバランスな印象を受けました。そのせいで余計読みづらいのではと思います。
サンザシ:原書どおりの直訳ではなくて、文章などは入れ替えて訳されていますね。そういうところには、工夫なさっているのでしょう。でも、イメージがくっきり浮かび上がってこなかったです。
コゲラ:原文は、現在形ですか?
サンザシ:アマゾンのサンプルを見ると、過去形のようです。
コアラ:私は選書係だったのですが、風刺を含んだファンタジーで、いろいろな解釈ができそうだと思って選びました。絵がすばらしいです。どういう時代でどういうタイプの物語なのか、絵が雄弁に物語っています。中世のヨーロッパを思わせる時代背景で、一般の人々は読み書きができなくて、p70の5行目に「村の人たちは、ジャック・ドリーに、古い物語を語ってほしいと頼みました」とあるように、物語を語って人々がそれを聞いて楽しむという文化がある設定になっています。この『ベアトリスの予言』も、ストーリーを先へ先へと進める展開になっていて、登場人物もストーリーのためだけに存在しているような書き方になっているところが、口承文芸のようだと思いました。言葉が重要な役割を果たしていて、p238あたりの場面ですが、ジャック・ドリーはベアトリスから文字を教わることで、無益な復讐をせずにすんだし、その後ベアトリス自身も、武器ではなく、物語を語ることで敵対する国王と対峙しました。p10の本文1行目に「この物語は、ある戦争の時代に起きたことです」とありますが、武力ではない、言葉の力、物語の力を感じることができた作品でした。p68で、ビブスピークおばばが、ジャック・ドリーに何度も自分の名前を言わせるところが、とても印象的でした。物語の展開が都合よすぎるのはどうかとも思いましたが、全体的に、美しさと、存在に対する肯定を感じる物語でした。
西山:私はとても楽しく読みました。ああ、おもしろかった、で特に言うことはない感じなんですけれど……。修道士を手玉に取るヤギがおもしろくて、冒頭から完全におとぎ話として読む構えができたので、細かいことは気にならなかったのだと思います。それでいて、今の戦争を思わせて、兵士の傷つき方、心の壊れ方が胸に迫りました。翻訳上の代名詞の件は私はそういう観点を知らなかったのですが、この作品の場合、あの乱暴で荒々しいヤギが「彼女」であること、つまり、女性であることを愉快に読んでいました。新しいタイプの戦争と平和を考えさせてくれる児童文学を読んだと感じています。
すあま:私は児童文学でもミステリーでも中世の修道院ものが好きなので、期待して読み始めたけれど、舞台としては物語の最初のところだけだったので残念でした。予言があって、そのとおりになっていくことを予想しながら読み進めました。途中で旅の仲間が増えていくのはおもしろいものの、キャラクターが次々と出てくるゲームのような感じもしました。登場人物がそれぞれに抱えている悲しみを、ベアトリスを救うことで癒していく物語。楽しいところもあるけれど、読んでいてつらいところもあり、特に兵士の懺悔をどうしてベアトリスに聞かせる必要があったのか、ちょっとひどいな、と思いました。読みながら、意味がわからないところにひっかかってしまい、子どもにも読みにくいように感じました。乱暴なヤギの活躍にも期待していたのに、途中からベアトリスを癒す役割になってしまい、もうちょっと暴れてほしかったかな。
(2023年09月の「子どもの本で言いたい放題」より)









