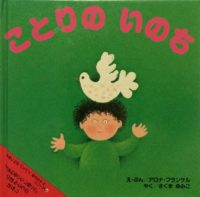マイケル・モーパーゴ/作 ないとうふみこ/訳
徳間書店
2023.03
アオジ:わたしは第一作の「巨人のネックレス」をSinging for Mrs.Pettigrew: A Storymaker’s Journey(Walker Books, 2007)というモーパーゴの短編集で既に読んでいたんです。タイトルにある『発電所のねむるまち』(あかね書房、2012)や『モーツァルトはおことわり』(岩崎書店、2010)等、邦訳されている作品を含む優れた短編を作者の言葉と共に載せている、とても良い短編集で、未訳の魅力的な短編も6つほど入っています。でも、「巨人のネックレス」だけはモーパーゴらしくなくて、なぜこんなに悲しい短編を書いたのか不思議に思っていました。女の子が好きなことを一所けんめいにやった結果がこれ?と思って。作者も、「子どものころゼナー近くの浜辺でタカラガイを集めた思い出から書いた」と述べているだけです。この短編は絵本にもなっており、amazonでは好意的なレビューもありますが、子どもに薦めたくないという意見もあります。という訳で、最初から素直な気持ちでは読みすすめられなかったというのが正直なところです。それに、2話から5話までの主人公が地元の自然のなかで生きている子どもたちなのに、ネックレスのチェリーは避暑でここに来ていた女の子なんですね。それで余計に疎外感を感じたのかもしれません。
「アザラシと泳いだ少年」も寂しいお話ですが、「西の果ての白馬」と「ネコにミルク」はさすがモーパーゴらしい、よくできた短編だと思いました。
訳文もなめらかだと思いましたが、「巨人のネックレス」のp36で、チェリーが「あなた、(溺れかけたひとを)たくさん助けたのね」というと、幽霊が「まあね。何人か」という。そのさみしそうな声にチェリーの胸がしめつけられて……という箇所ですが、“Singing for Mrs.Pettigrew”では、「何人か」と幽霊がうなずき、「何人か」と繰りかえす、その声が悲しそうなので、チェリーが元気づけようと思って……となっています。幽霊のほうはチェリーが死んでいるとわかっているのに、チェリーは気がついておらず幽霊を元気づけようと思っている……こういうところは本当に上手だなと思ったのですが。でも、モーパーゴは同じ作品を絵本にしたり、短編集のなかの一話として発表したものと単行本にしたものでは、文章を増やすなどして変えたりしているので、この部分も短編集にするときに変えたのかもしれませんね。
シマリス:とても魅力的な短編集でした。悲しいお話と、ハッピーエンドのお話の混ざり具合がいいな、と感じました。冒頭に「巨人のネックレス」があることで、次以降の作品も、ハッピーエンドとは限らない、とドキドキしながら読めました。「アザラシと泳いだ少年」は、今の時代だと、新しい作品として書きづらいかもしれないなと思います。モーパーゴであり、古い作品だから、許容されたのかなぁ、と。1982年に刊行されたものが、なぜ今のタイミングなのか、裏話をお聞きしたい気もしました。順番に読んでくれ、と書いてあるけれど、最後のお話だけ最後に読んでくれ、じゃだめなんですかね? 1つめから4つめまでの短編は、そんなに順番に読む必然性を感じなかったのですが、何か見落としているのかしら……。コーンウォール地方には行ったことがなくて、ネットで検索しました。頭のなかで想像していた風景とほぼ同じものが出てきて、うれしくなりました。コーンウォール地方に行かれた方がいたら、お話をうかがいたいです。
アオジ:児童文学の舞台としては、古いですけれど、スーザン・クーパーの『コーンウォールの聖杯』(武内孝夫訳 学研プラス、2002)がありますね。子どもたちアーサー王伝説にまつわる古文書を発見することから物語が始まると記憶していますが。コーンウォールは、ペンザンス、セントアイブス、エクセターなど何度か滞在したことがありますが、とても魅力的なところです。浜辺を歩いていて普通にアザラシに遭遇したり、沖にイルカが海水浴客と競争して泳いでいたりするようなところです。英国では唯一といっていいくらい陽光に恵まれたところなので、画家がおおぜい住んでいると聞きました。セントアイブスは、特に芸術家の集まっていたところで、バーナード・リーチの工房や、バーバラ・ヘップワースのアトリエ、テート・セントアイブスなどもあります。ヴァージニア・ウルフは、子どものころ休暇で滞在したセントアイブスの灯台を頭に描いて『灯台へ』を書いたといわれていますが、白く輝くその灯台を見て、時の流れと距離の関係が腑に落ちた(ような気がした!)のを覚えています。
サンザシ:私は、ロンドンで下宿させてもらっていた人がコーンウォールに山小屋をもっていて、2回はそこに行かせてもらったのと、1回は、友達と旅行で行きました。印象的だったのは、ゲール語系のコーンウォールの言葉を教育でも取り入れようとしていて、道路標識等も英語との併記になっていたことです。都会と違って荒々しいとも言える自然があって、アーサー王にまつわる場所もたくさんありました。
ルパン:この本ですが、どれもおもしろかったですが、やっぱり「巨人のネックレス」の読後感がよくなかったかな。海にとりのこされたチェリーの絶望感がつたわってきて、自分まで悲しくなりました。死んでしまったというのも残酷だし、その前に親は何していたんだとかも思っちゃって。海に子どもひとり残して帰るな、とか、なかなかもどってこなかったらすぐに迎えに行かなきゃ、とか。だから、つぎの「西の果ての白馬」も、きっと「一年と一日」の約束を忘れてひどいことになるんだろうと心配していたら、ちゃんと覚えていてよかったなと思いました。「ネコにミルク」も。さいごに「ミス・マーニー」を読んで、ああ、チェリーが死んだのはお話のなか、という設定なんだな、と思ってちょっとホッとしました。
ハル:私も、特に最初のお話なんか、昔話独特の気持ち悪さみたいなものも感じますし、どうしてあえてこのお話を……という気持ちもありますけれど、やっぱり、マイケル・モーパーゴってすごいなぁと思いました。伝承の、物語としての稚拙さを自然におぎないながら、1冊全体でエンターテインメントとしてきれいにまとまっている感じがしました。佐竹美保さんのカバーイラストも、特に表4、裏表紙側のイラスト(これは……何かちょっとわからなかったけど)に、いつもに増した凄みを感じます。
西山:私もこの「巨人のネックレス」のラストはショックでした。この展開はまったく予測していなくて不意打ちという感じです。そして、とにかく順番通りに読んでいくと、「巨人のネックレス」から始まっていなかったら、他の作品をここまでひやひやドキドキしながら読まなかったろうと思いました。また、残念なことになるんじゃないか、こわいことになるんじゃないかと油断できませんでしたね。してやられたという感じです。ですから最初と最後は不動で後は入れ替わっても大丈夫なのかなと。「アザラシと泳いだ少年」は、たしかに異様で不穏なイメージも覆っているのですが、たとえばp103のアザラシがぬっとあらわれて見つめあう場面や、p114のアザラシの面談の場面など、目に浮かんで笑えてくるほど好きでした。他の作品でも、動物の描写がゆかいで、『やまの動物病院』とペアにしたのはこういうことか! と勝手に納得していました。「ネコにミルク」の最後「いま話したら、きっとおまえは信じるだろうが、大人になってそのお話がほんとうに大切になるとき、信じようとしなくなるかもしれない」という言葉がとても新鮮でした。こういう言い伝えに幼いときに触れてそれを信じることはよいこと、という価値観を持っていたことに気づかされました。それにしても、ノッカーはなんて気がいいんでしょうね。
サンザシ:どのお話もおもしろく読みました。最初の「巨人のネックレス」の主人公が死んでいるとわかるところはびっくりしましたが、嫌だとは思いませんでした。コーンウォールは、伝説や昔話がいっぱいある場所なので。たしか「ゼナーのチェリー」という伝説もあったかと。モーパーゴはそういうのを下敷きにしているのかもしれませんし、普通に私たちが考える死とは違う部分もあるかもしれません。鉱山にいる親子も、生きている人たちのすぐとなりにいて、生きている者たちを見守っているみたいだし。2つ目の話と4つ目の話は、やっぱりこの順番で読むべきでしょう。以前は妖精やこびとを信じて折り合いをつけるのが大事だと考えていた人たちもたくさんいたのに、時代が下ると、そういう人は希少になると言っているので。ストーリーテラーとしてのうまさということで言うと、モーパーゴは随所に本筋とは一見関係がないエピソードを入れて、それぞれの人の暮らしの片鱗を垣間見せ、短いストーリーの中でも人物をうまく浮かび上がらせています。「巨人のネックレス」でも、4人の兄たちとチェリーのやりとりなどを入れて、物語に深みを持たせています。「西の果ての白馬」では、ノッカーという妖精がもたらした幸運だけではなく、村人たちの心配りも書いて、ベルーナさんが働き者で信望も厚いということを浮かび上がらせています。また、ノッカーから借りた馬との別れがつらいことを、「ペガサスの背にまたがったまましばらくいっしょに海をながめた」という文章で表現しています。「アザラシと泳いだ少年」では、すでに話に出ていますが、アザラシに話しかけたりする場面を入れることで、ウィリアムの人となりをあらわし、読者が感情移入できるようにしています。「ネコのミルク」では、さっき西山さんもおっしゃいましたが、「いま話したら、きっとおまえは信じるだろうが、大人になってそのお話がほんとうに大切になる時、信じようとしなくなるかもしれない」(p152)という部分に、モーパーゴらしさを感じました。世の常識やステレオタイプを超えた知恵を子どもに伝えようとしているのかな、と。
全体をとおして、超自然的な要素が登場し、数や効率や論理では割り切れないものが確かにあること、それを畏敬する感覚を子どもにも伝えようとしているのだと感じました。
「最後の一編を読んだとき、すべてのつながりが明らかになる」と訳者あとがきにありますが、1回読んだだけでは「すべて」のつながりは、まだよくわかりませんでした。それと、「はじめに」には、「この本に書いたのは昔話ではない」という著者の言葉があるので、モーパーゴが書いたのだと思って読み始めると、最後は、どの話もミス・マーニーが書いたということになっていて、物語世界の中に矛盾が生じていると思ってしまいました。
アンヌ:私も最初の「巨人のネックレス」の少女の死にショックを受けたのですが、前書きに順番に読んでほしいとあり出版社の内容解説にも「順番に最後まで読むとこころあたたまる」とあったので、きっと最後には大どんでん返しがあってチェリーが生き返るんじゃないか、それならどういう話になるんだろうとあれこれ想像しながら読んでいったので、最後まで読んで、がっかりしてしまいました。「アザラシと泳いだ少年」は主人公が幸福になった話とも読めますが、『ケルト民話集』(フィオナ・マクラウド著 荒俣宏訳 ちくま文庫)の「神の裁き」にある、アザラシになってしまった男の恐ろしい民話が背後にあるようで、異界に行ってしまった少年の物語として心がひやりとしました。だから、ノームを救ったり友達になったりする楽しい「西の果ての白馬」についても、いつかはアニーが白馬に乗ったまま海に入って帰れなくなるんじゃないかとか心配しています。「ネコにミルク」のノームは本当に農民に親切で、同じ土地に住んでいる者同士として環境を保全していくという作者のメッセージを感じましたが、ちょっとノームが自分で説明しすぎとも思いました。「ミス・マーニー」では、ケイトがおもしろい子で楽しい物語でしたが、マーニーの異能もいつかまた社会の中で排除される時が来るだろうなと感じ、全体を読み終わっても心温まるとは言えない感じがしました。翻訳で気になったのがp144の「お牛」で、一瞬なぜ丁寧語なんだろうと思いました。ここは「牡牛」にふりがなでいいと思います。
繁内:モーパーゴは結構、テーマ性がいつも強い作家だと思って読むんですけど。この作品は、ケルト文化のファンタジー要素がもとになっているので、物語としての豊かさがとても感じられる連作短編になっていると思います。「巨人のネックレス」で、確かにチェリーが死んでしまうのは、もうほんとにかわいそうなんですけど、チェリーが遭難するシーンとかが、すごい迫力があるなと思って。どの短編もそうなんですが、1回目に読むのと2回目に読むのとでは、おもしろさが違いました。チェリーの物語も1回目に読んだときは、最後まで死んでると思わなかったんですけど、2回目に読むと、ある時点から幽霊になってしまっているという小さな伏線がいっぱい書かれていて、そういう伏線の張り方を2回目に読む楽しみがありました。確かにチェリーが死んでしまうのはとてもつらいことなんですけど、これが最初に書かれていることでコーンウォールという場所自体が、なんだか生と死のあわいっていうんですか、境界線上のような場所だということを提示する役割になっているのではと。チェリーが壁を上りながら、集めた貝を、どこに置いたのは捜索隊が壁の途中で見つけているから、そこまでは生きてる。でも、どこで死んでしまったのか、ほんとうは定かではない。チェリーという、読み手には身近な感じの女の子が、ふっと、生と死のあわいというか、神話の強い磁場みたいなところに取り込まれてしまうということが、この物語全体のひとつの大きな伏線になっているのではと思いながら読みました。「西の果ての白馬」は、タイトルになっているんですけど、典型的な、なんというか、妖精に贈り物をして、それを返してくれるという話なんですけど。ノッカーは土地の顕現するものというか。土地の表しているもののような気がして。自然の力といっしょに生きるということを象徴していることが2番目に書かれていて、それが4番目の「ネコにミルク」と対になっているというところが、やっぱり上手だなと思いました。
「ネコにミルク」で、除草剤、殺虫剤をまかないでほしいというところも、モーパーゴらしい。環境問題にすごく関心があると思うので。さっき、サンザシさんもおっしゃってましたけど、時代とともに、土地とのつながりが薄れてしまうという、モーパーゴのひとつの問いかけなんだろうなと思いました。p135で、土地は誰のものでもない、生きているあいだ、この土地を拝借しているだけなのだ、というところが、いろんな意味で心にしみました。モーバーゴは原発の問題も取り上げてるので、土地についても強い思いがあるんだなと。「アザラシと泳いだ少年」も、辛いお話なんですけど。人間の世界で生きづらいウィリアムが、アザラシの世界にいってしまうんですが、これはセルキー神話ですよね。アザラシの皮をかぶったらアザラシになって、脱いだら人間になるっていう。障がいのある者への深い差別感が描かれているのでは。多分、土地との繋がりが深くて、地元にずっと生きてる人たちが、繋がりが強い分、違う人に対しては排斥しがちになる、というところがうまく書かれていると思うんです。お父さんがウィリアムを見下す気持ちの底に、男らしさっていうのか、自分がウィリアムの姿を見るたびに、自分が男としても人間としてもダメな奴だと思い知らされるような気がしてあまり関わらないようになるって書かれてるんですが、なんかこう、男らしさとかって、人間界の神話じゃないですか。人間の世界の思い込みや神話にとらわれているうちに、息子をあっちの世界に追いやってしまう切なさがあるなって。
いろんなおとぎ話の中に今の社会に対する批判も、取り入れているのも、モーパーゴらしいです。最後の「ミス・マーニー」は、さっきサンザシさんが、ミス・マーニーとモーパーゴと、作者がふたりいるんじゃないかとおっしゃっていましたけど、ミス・マーニーは女の人なんですけど、モーパーゴの分身の分身のような気がして。モーパーゴが分身として、この地にやってきて、語った物語が、この連作短編なんじゃないかなっていう風に思いながら読みました。マーニーが心の目で見たこの村のことが、モーパーゴが自分の胸に住まわせている、この土地への思いが集まったものがマーニーであって、彼女に語らせてるけど、本当はモーパーゴが語っているというか。分身じゃないかなと思いました。全体として、人間の豊かさは何なんですか、という問いかけがあるように思いました。今の時代しか見ない人に対して、それは豊かじゃないんじゃないかっていう、神話とか土地の歴史とか、厚みとか、それを子どもたちにミス・マーニーが受け継いで語っていくというのは、過去から未来への受け継ぎじゃないかと思いながら読みました。
wind24:今回紹介していただかなかったら読まなかった書籍かもしれません。良い機会をいただきありがとうございます。みなさんが言われるように、生と死の境界線がなく、さまざまないのちが交差した世界観だと思いました。
私の友人がコーンウォールにも近い南部デボン州のダートムーア国立公園内でペンションを営んでおり、数日でしたが滞在する機会がありました。荒涼とした原野や湿地、少し行けば赤土の崖がそびえる海が広がっていて霧が発生しやすく、その雰囲気が奇々怪々としていて多くの妖精伝説や魔女伝説があるのも納得の風土でした。
「巨人のネックレス」は、私も最後の最後までチェリーは生きていると信じて読み進めましたので、あっ、そうなんだ、と。この世の人ではなくなったチェリーに驚いたとともに、残念な気持ちでした。映画「シックスセンス」を彷彿とさせ、日本人の死者の描き方とはちがうなぁと感じました。また鉱山で出会う炭鉱夫の幽霊の会話文が少し耳障りでしたので、訳者が違えばどのような文体にされるかのかと思ったりしました。
この本に限っては順番通りに読んでくれと何度か書かれていたので、どんなどんでん返しが待っているのだろうか、と期待しながら読みましたが、「ミス・マーニー」は案外拍子抜けする展開でした。でもp195、おしまいにマーニーがケイトに「時間がなくてまだ書いていない物語がある。ミス・マーニーという変わり者のおばあさんのおはなしさ」といったことが書かれていて、モーパーゴさんのストーリーテラーとしての優れた一面をみた思いです。
印象に残っているのは「ネコにミルク」で好き勝手をするトーマスに老人が言うセリフがあります。「土地はだれのものでもない。おまえさんのものでも、わしらのものでもない。わしらはただ、生きているあいだこの土地を拝借しているだけなのだ。そしてまたつぎの者にひきわたすんじゃよ」。(p134)これはネイティブ・アメリカンはじめ多くの先住民族に共通する考え方。SDGsにも通じるこの知恵を今一度掘り起こし、次の世代に引き継いでいきたいと思いました。
花散里:中等部高等部の学校図書館に勤務しています。国語の授業でなるべく長編小説を読んでほしいという取り組みがあり、長編小説になかなか手の届かない生徒たちに短編小説を手渡したいという依頼を受けました。日本の短編小説、古典から新刊本、外国文学からも選書を行い、この『西の果ての白馬』も選びました。教員が広い机に短編小説を面出しして、テーマごとに並べたのですが、この作品はタイトルや佐竹美保さんの表紙画が良かったのか、借りられていました。5編の短編集の中から、「西の果ての白馬」がタイトルに選ばれたのがよかったのかと思いました。本書が刊行されてすぐに読みましたが、今回、読み返して、「西の果ての白馬」と最後の「ミス・マーニー」が強く印象に残りました。特に「ミス・マーニー」にはモーパーゴの作品に対する思いが詰まっていると感じました。『子どもと読書』(親子読書地域文庫全国連絡会発行)の編集を担当していますが、特集の「作品世界」に外国の作家として初めてモーパーゴを取り上げました(№431 2018年9・10月号)。その特集の中で、日本に翻訳されていない作品が多いということを記していただきました。本作も1982年の作品ですが、刊行されて本当によかったと思います。モーパーゴの作品には戦争を背景とした物語が多いのですが、本作のような妖精や幽霊など、昔話のおもしろさを描いたものも秀逸で、読み応えがあると思いました。「ネコにミルク」に書かれた 殺虫剤の使用についてなどを読んでいて、『沈黙の春』(レイチェル・カーソン著 新潮社他)第9章「死の川」で、DDT撒布でサケが大量に死んでしまったことなどを思い返しました。モーパーゴの伝えたいと思うこと、環境問題についてなども、どのように作品を子どもたちに手渡していくのかということも考えました。「アザラシと泳いだ少年」は、あまり印象に残っていなかったのですが、読み返してみて、いじめ、身体的な障害、海に入ったときに泳げるようになったことなど、「自分はアザラシに救われた」ということが、子どもたちに勇気を与えているのではないか、と感じました。外国の作品は、「知らない世界を知る」ということからも、子どもたちが読むことの意義は大きいと思います。本作の5編とも、子どもたちは心を寄せながら読めるのではないかと思います。短編の良さが詰まっている作品として、子どもたちに手渡して行きたいと思います。
雪割草:おもしろかったです。モーパーゴのストーリーテラーとしての巧みな語りに引き込まれました。それぞれのお話がゆるくつながっている、とモーパーゴのまえがきに書かれていたけれど、2、4、5話のつながり以外はよくわかりませんでした。個人的には、白馬やアザラシなど動物が出てくる話が好きでした。どのお話にも子どもが出てきて、おとなよりも自然に近い存在として描かれていると思いました。子どもたちは生きものへの愛情があって、心が通い合うさまがよく描かれていてよかったです。今の子どもも、こういうところに共感できたらいいなと思います。原書の初版は40年前のようですが、なんで今出したのか知りたいと思いました。土地に根ざした民話は、日本にもたくさんあると思うので、子ども向けによい作品が出たらいいなと思います。
コアラ:私も、原書は1982年刊行で40年前の本なので、どうして今出版したのかな、と思いました。でも、今読んでも、パソコンとかスマホとかテレビとか、時代をあらわすような「物」が出てこないので、古びることのない物語になっていると思います。全編にわたって、生き物に対する愛情や、自然を人間の支配下に置くのではなく共存するというような眼差しが感じられて、読んでいてやわらかい気持ちになりました。「はじめに」の最後に「順番どおりに読んでほしい」とあるので、どんな仕掛けが最後に待っているのかと楽しみにしていたのですが、ミス・マーニーのお話だった、というのは、ちょっと拍子抜けするものでした。p180で、ミス・マーニーがケイトに最初に話して聞かせた物語は、「巨人のネックレス」だけれど、翌日に話して聞かせた物語は、アザラシと少年の話で、この短編集では3番目になっています。話して聞かせた順番にはなっていないようなので、気になりました。結局「順番どおりに読んでほしい」というのはどういう意味なのか、自分なりにつながりを読み取っていきましたが、作者の意図がわかったかどうかいまいち自信がないままでした。でも、今みなさんのお話を聞いて、「巨人のネックレス」を最初にもってきたりとか、いろいろよく考えられているんだろうなと思いました。
さららん:「巨人のネックレス」、「西の果ての白馬」、「アザラシと泳いだ少年」……と、作者の言葉通り順番ごとに読み進むうち、体ごと、コーンウォールのゼナーの世界にもっていかれた印象がありました。なかでも印象が強かったのは、「巨人のネックレス」です。チェリーは死んでいるんだろうと途中でわかってきたけれど、私自身は嫌な感じというより、現実と伝承のあわいの、不思議な世界に投げ込まれた感じがしました。貝をつないで巨人のネックレスをつくる行為そのものに作者は象徴的な意味をこめたのかもしれない、そんなふうにも思えます――これからさまざまな話をつないでゼナーの自然(=巨人)に捧げる、というような。独特の地形や海の中から現れる不思議な存在がゼナーと言う未知の場所を形作り、陰影もふくめて、子どもの読者に出会ってほしい世界です。訳もこなれていて読みやすいのですが、「ネコにミルク」の章のp140「め牛」とp144「お牛」の表記で、おや?と思い、ここは「雌牛」「雄牛」にしてルビを振るなど別の選択肢もあったかも、と思いました。この章では、「牛たちが、じぶんの乳房をいきおくよく吸って乳を飲んでいたのだ」(p137)という描写がおもしろく、「ありえない!」と思いながら、牛の格好を想像して笑ってしまいました。調べないとわかりませんが、牛の乳の出が悪いとき、土地の人たちが言い合うお気に入りの冗談なのかもしません。人間にとっての悲劇をまえに、「ごぞんじのとおり、農場ではよくあることじゃ」(p145)と、しゃあしゃあといってのけるノッカーにはふてぶてしいユーモアさえあり、そんな細部にもモーパーゴのストーリーテラーとしての手腕を感じます。
しじみ71個分:モーバーゴは本当に物語がうまいなあと思います。今回も感服しました。前書きから話が進んでいくのは、『最後のオオカミ』(はらるい訳 文研出版)でも使われていた手法だと思います。その時は、モーパーゴと思しきマイケル・マクロードなる人物が孫娘にパソコンを教えてもらって家系について調べたら、ひいひいひいひいひいひいじいさんの回想録が見つかった、というところから物語を始めていますが、同じようにモーパーゴ自身のような人物を置いて、あたかも現実の問題から歴史や物語を紐解いていくようなスタイルが共通していると思います。それによって、読む人が現実のような現代の話から境界線や時代を緩やかに超えて、フィクションの世界に自然に没入していくことができるわけで、モーパーゴ自身を語り部として物語とフィクションをつないで行っているように思います。「巨人のネックレス」では、人の生き死にが、わりとそっけなく投げ出されている感じが、昔話や伝説の再話と同じような印象を与えます。遠野物語に共通しているようなところがあると思いました。昔話の中には、登場人物が死んでしまったのか、それとも行方不明になったのか、突き詰めて明確に描かず、不思議を不思議のまま残していく話もあります。この出だしの物語が、会話を現代調にすることで、リアリティを増しながら、昔話的世界にいきなり入って行かせる役割を果たしているように思いました。遠野もそうですが、このゼナーという土地も、おそらく厳しい自然との結びつきが強くて、こういう不思議な話がそこかしこに存在する場所なのではないかと思いました。厳しい自然とともに生きるところに、自然への怖れや敬意が生まれ、物語が残るというのは現代にも共通するものではないかなと思います。
(2023年07月の「子どもの本で言いたい放題」より)
-175x200.jpeg)