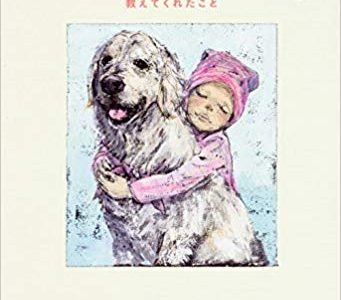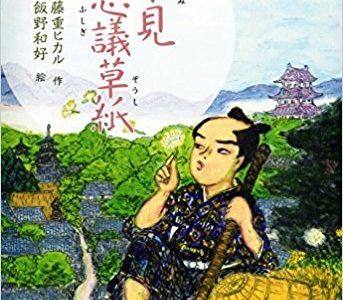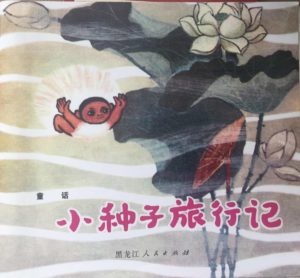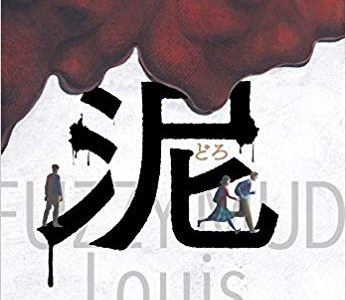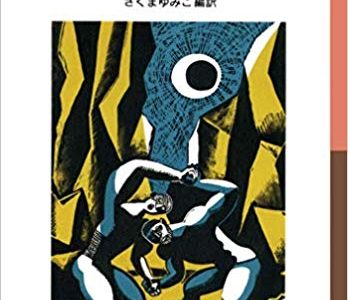『犬が来る病院〜命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと』をおすすめします。
聖路加国際病院の小児病棟の子どもたちを3年半にわたって取材したドキュメンタリー。日本で初めて小児病棟にセラピー犬を受け入れたこの病院で、犬の訪問活動をどうやって始めたのか、子どもたちの反応はどうだったのか、子どもたちが豊かな時間を過ごすための配慮がどう行われていたか、多くのスタッフがどう連携してトータルケアをめざしたのか、などについて述べられている。4人の子どもたちとその家族が、それぞれ病に直面して歩んだ軌跡も感動的。
(「おすすめ! 日本の子どもの本2018」<ノンフィクション>掲載)