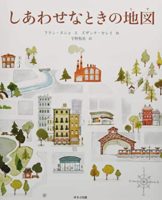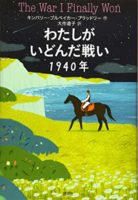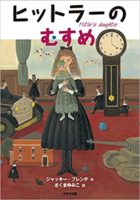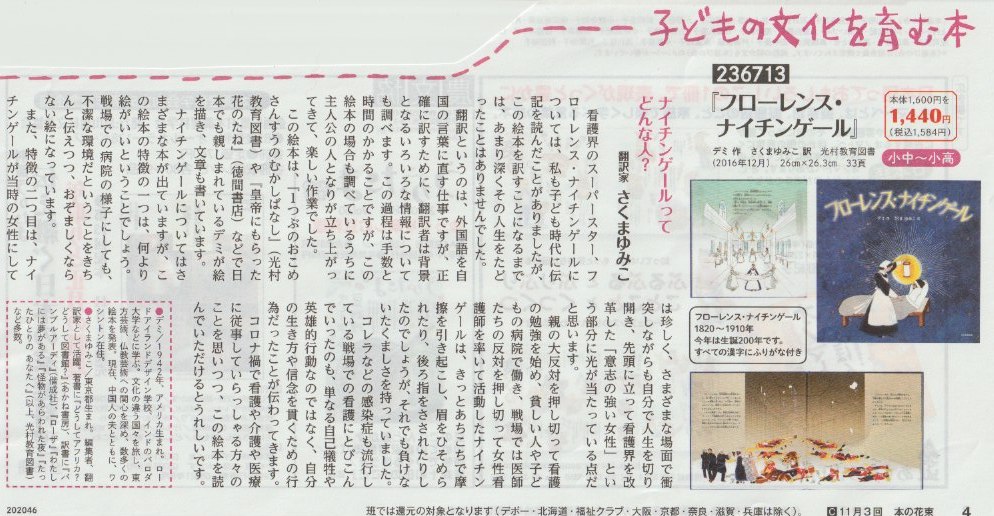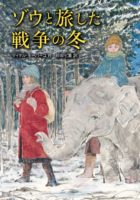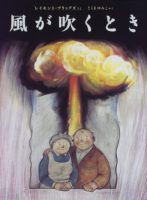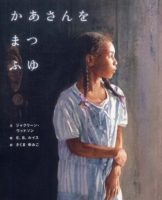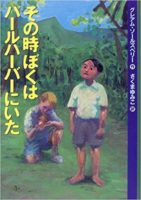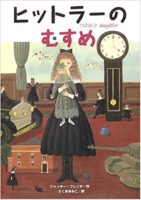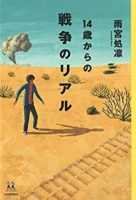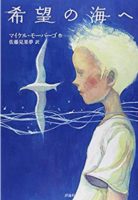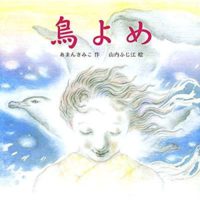マイケル・モーパーゴ/作 杉田七重/訳
小学館
2022.12
『ガリバーのむすこ』をおすすめします。
戦場となったアフガニスタンを出て難民になった少年オマールは、嵐の海でボートから投げ出され、意識を失う。やがてオマールは、自分は砂浜に寝ていて、まわりを小人たちが取り囲んでいることに気づく。そこは、かつてガリバーが訪れたリリパット国だった。オマールは「ガリバーのむすこ」と呼ばれ、小人たちと友だちになってお互いの言葉や文化を学びあい、愚かな戦争をやめさせる。巧みな語り口に引っ張られて一気に読めるし、考えるきっかけも提供してくれる。小学校高学年から(さくま)
(朝日新聞「子どもの本棚」2023年1月28日掲載)


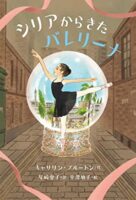



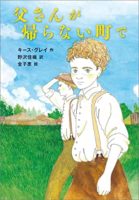
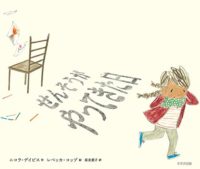
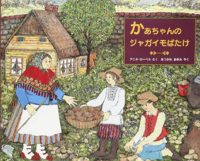
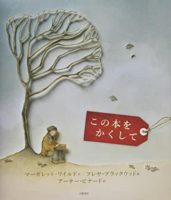
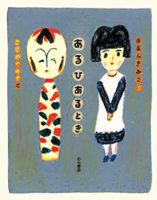
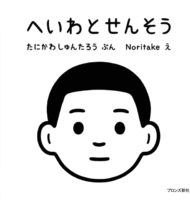
-138x200.jpeg)