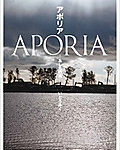アンナレーナ・ヘードマン/作 菱木晃子/訳 杉原知子/絵
徳間書店
2016.05
レジーナ:薪を積んで世界記録に挑戦するとか、八本足のテーブルで「スパイダー・クラブ」のひみつ会議をするとか、ユーモアのあるお話ですね。p33「わたしたちの脳みそ、ゆるんでたのか、とけてたのか?」など、主人公のちょっとした言葉づかいもおもしろくて、楽しく読みました。
よもぎ:とてもおもしろかった! おもしろい本をおもしろく訳すのって、なかなか難しいと思うのですが、さすがは菱木さんだと感心しました。子どもといっしょになってギネスに挑戦して、鼻の穴に棘を刺してしまうお母さんなんて、日本の物語には登場しませんよね? 主人公の女の子が養女だってことは最初に書いてあるのですが、後半になってスリランカから来た子どもだとわかる。そして、同じスウェーデンの南部から来たおじさんが「おまえとおれはよそものだ」という。日本の物語だとおおごとになりそうなことを、実にさらっと書いてあるところなんかいいですね。ああ、よその国ではこんな風に暮らしている人たち、家族もいるんだなと、小さな読者たちも自然に分かるんじゃないかしら。登場人物が多いけれど、それぞれキャラクターがはっきり描けているので、「あれ、この人は?」と迷わずに読めたのもうれしかった。
ルパン:これも、とってもおもしろかったです。挿絵の雰囲気が気に入りました。p63の、ストローを口いっぱいにくわえた顔とか、p155の、おじいさんたちが必死で薪を積んでいるところとか。お話とぴったり合っていると思います。薪を積むというミッションと、世界記録への挑戦を組み合わせたアイデアがいい。ただ、宝くじがあたって豪華客船の旅に出ているという設定はいらないんじゃないでしょうか。回想シーンにする必然性がなく、わかりにくくなるだけのような気がします。
ヒイラギ:旅行をしている間に回想したことを録音していくという設定ですよね?
アンヌ:最初の船旅のところで主人公と一緒に退屈してしまい、なかなか読み進めませんでした。村の話になってからは楽しく、北欧の生活や日本と違う価値観を知ることができてよかったと思いました。例えば、年金生活者のおじいさんがのんびりしていたり、けがをして働いていないロゲルも生活は保障されていたりするところ等ですね。後になって主人公が養女で肌の色も違うとわかり、船旅で娘だと思われなかったのはそのせいかと分かったりしました。
ヒイラギ:今回の3冊はどれも主人公が10歳という同じ年齢なのですが、テイストがずいぶん違いますね。この作品がいちばん子どもっぽい。アッベたちが、無邪気にギネス世界記録に挑戦するんですが、そこで自分たちも無理かな、とは思わないし、周囲の大人も無理だからやめろとか、せめて練習してから本番にのぞめ、なんて言わないんですね。お国柄かもしれませんが、今のスウェーデンは子どもらしい時期を大人がちゃんと保証しているってことかも、と思いました。最初のほうは常体と敬体が混じっているのですが、それに違和感を感じないですっと読めるのは、さすが菱木さんだと思いました。挿絵はおもしろかったのですが、主人公のアッベはスリランカから来たので肌の色も茶色いんですよね。その子が問題なく周囲にとけこんでいるようすをきちんと出すには、挿絵の肌ももう少し茶色だったいうことがわかるようにしておいたほうがよかったのではないかと思いました。表紙だけは少し色がついていますけどね。
マリンゴ:個人的なことなのですが、わたしはリンドグレーンの「やまかし村」シリーズが本当に大好きで。特に『やかまし村はいつもにぎやか』(大塚勇三訳 岩波書店)は、村の風景と子どもたちを描いた表紙で、少しだけこの本の装丁に似てるんですね。イラストのタッチは全然違うのですが。同じスウェーデンの作家ということもあり、そっちの方向で期待していたら、全然内容が違ったので、「コレじゃない感」がどうしてもありました(笑)。テンポよく、たくさんの登場人物がうまく書き分けされていると思います。また、子どもって先走ってどんどんしゃべってから意図を説明するような、そういうまだるっこしいしゃべり方をしがちですけど、それが文体に反映されていて、10歳の子らしい一人称だなと思いました。ただ、豪華客船の設定がうまく生かされていない気はします。普通に時系列じゃダメなのかな? 1年前の出来事と、今の豪華客船でのことがどこかでリンクする――たとえば気に食わない乗客のギュンターさんが実はギネスの記録保持者で少しだけ分かり合えるとか――そういう仕掛けがあるほうが、個人的には好みです。
西山:ルパンさんやマリンゴさんがおっしゃっていたのと一緒です。入れ子にして、回想にして、物語をわかりにくくしていると思います。豪華客船のクルーズという大枠に必要性を感じない。中でやっていることの単純明快さや、絵の雰囲気とから考えると、小学校中学年ぐらいの子が楽しく読めるはずの本だと思うので、複雑な構造はそぐわないと思いました。それはそれとして、スウェーデンの人の感性の違いを感じられたのはおもしろかったです。母親が娘のイベントの邪魔するのにはびっくりした。なんのかんの言っても、力を貸すとか何か展開があるかと思いきや、本気で対抗していて、本当にびっくり。「火薬のカッレ」の「本物の〈薪爺さん〉」ぶりも笑えましたね。p171の「どこが薪がたりないっていうのよ!」って、内心一緒になって突っ込み入れてました。いやぁ、なんか、本当にのどかなのんびり村でした。
ネズミ:私も、クルーズに出て、1年前の出来事を書くという設定がなくてもいいのに、と思いながら読みました。客船でのお母さんとギュンターのやりとりなどなしに、のんびり村の出来事を楽しめてもいいのにな、と。記録をつくろうとがんばるところとか、マムスマムスを食べて気分が悪くなるとか楽しかったです。おもしろさや子どもらしさは、リンドグレーンの『長くつ下のピッピ』に通じるところもあるかな。
ヒイラギ:この作品では、人種の違う養子がごく普通に受け入れられている。お母さんが娘と張り合うところも、日本だったら継母なのになんて思われるだろうと考えると、遠慮してこうは書かないですよね。そんなの一切関係なく、普通の遠慮のない親子関係になっているのが、またおもしろいと思いました。
エーデルワイス(メール参加):親が離婚しようが再婚しようが恋人ができようが明るくて、スウェーデンらしいおおらかさですね。「ギネス世界記録」に挑戦するところや、薪を積み上げるところが神泉です。親友のアントンがいじめにあうところは日本と変わらないなと思い、ナージャがアッベの一時的な正義感に意見を言うところではジンときました。p52で、マッチ棒を鼻の穴にいれるところは笑ってしまったし、p53の「ギャーギャーわめく人がいる家にはいられないもの。耳は大切にしないとね。とくに子どものときはね。」というアッベの台詞が気に入っています。会話をこんなふうにユーモアで返したいなあ。
(「子どもの本で言いたい放題」2017年11月の記録)