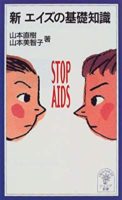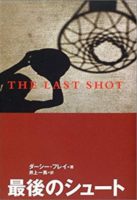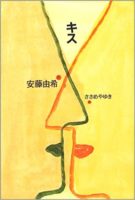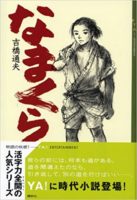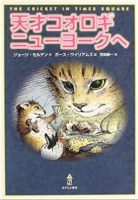ジェフリー・トリーズ/作 多賀京子/訳
福音館文庫
2006.06
きょん:すなおな冒険ストーリーで読みやすいので、どんどん読んでいきました。ボートを見つけて小島にわたるあたりまではよかったんですけど、宝探しがなかなか始まらない。出た当時は新鮮だったんでしょうか? 今読むと、とってつけたような結末で、ちょっとがっかりしました。
カーコ:今の読者向けに新しく出たのを評価している書評を読んだんですが、手にとってみると表紙の絵が古臭くて昔の本のようで、まず「えっ」と思いました。物語は、最後がどうなるのかに引かれて、思ったよりすらすらと読み進んでいけました。でも、やっぱり古くさい、一昔前の話だと思ってしまいました。この作品が出た1979年当時は、男の子が女の子に思いを寄せることをにおわせる場面があるというだけで、批判をあびたというけれど、今の子がワクワクして読むのかどうか疑問です。ただ、時代がかっているけれど、校長先生が尊敬できる人だと言うところだけは、いいなあと思いました。今の実情を照らし合わせると、こんなことはありえないのだけれど、日本の子どもの本では、たいがい先生や大人の影が薄いので。あと、会話のあちこちに、ひねりがあるのだろう、と思われる部分があったのだけれど、おもしろさが伝わってきませんでした。この本は、もともと難しい言葉で書かれているので、わざと同じように難しく訳しているのかと思ったほど。人に聞くと、イギリスの読み物は、アメリカの読み物よりも凝った文章のものが多いとは言われましたが。
アカシア:私は福武文庫で最初に読みました。そのときも古めかしい感じがしたんです。今度は新訳だから期待したんですが、もっと古めかしいですね。たとえばp171には「へえ、そりゃ、おことばだね」、p172には「してやったり」、p191には「はなはだ肉食のすぎる人に見受けられたわ」なんていう表現が続出します。今の子どもたちに読んでもらおうとするなら、ここまで時代色を出さなくてもいいのでは? 内容的にも、男女の役割分担がはっきりしていて、キャンプに行けば女の子が料理をするものと思われている。それに、アルフレッド卿という人が悪者というよりは軽蔑される対象になっているわけですが、イギリスの階級社会の中で商人の成り上がり者として下に見られている構図が見えて嫌らしい。そういう時代の枠組みを超えておもしろければそれでもいいのですが、話の運びもそうそうおもしろいわけではない。新訳でまたわざわざ出す意味がわかりませんでした。
エーデルワイス:ストーリーとしては結構おもしろかったんですけど、現在ではひと時代前のお話という印象。楽しくは読めました。シェークスピアの引用とか、千年前にノルマン人が来たとか、イギリスの子どもなら教養として知っているであろうことを前提に書いているのでしょう。裁判の場面、陪審員とのやりとりが、わかりにくかったですね。これも文化の問題かな。
アカシア:裁判のシーンのp324のところで、「もし〈埋蔵物〉ではないなら、国としてはそれ以上の関与はしない。発掘されたものは発見者の所有となる」とあるんですが、だとすると〈埋蔵物〉でないと証明されれば、発見者である子どもたちのものになるということですよね? だけどその後に「もしアルフレッド卿が、発掘された異物が〈埋蔵物〉ではないと証明することができたら、こちらとしてはひきさがるしかない」と出てきます。よくわからなくなっちゃうんです。このシーンは田中明子訳の福武文庫版の方がずっとよくわかります。
ウグイス:学研文庫で出たときのこの話は、少し前のいかにもイギリスらしい雰囲気を味わえるものとして人気があったんだと思います。古めかしい感じに良さあるので、新訳だからといってあまり今っぽくすると、逆に違和感が出てしまうんだと思うの。女の子はおしとやかにしてたほうがいいとか、古い価値観で描かれた部分があるので、訳文もある程度古くてもいいんじゃないかしら。女の子の言葉で、「…じゃないこと?」とか、「…ですわ」とか言っているのは、直したほうがいいけれど。しかしこの新訳には、わかりにくいところがたくさんあった。p191の4行目「そうすれば自転車で来るのもすこしはらくだと思うの」のせりふの意味がよくわからない。旧訳では、「自転車で往復しなくてすむし」となっていて、意味がよくわかる。p190の11行目で靴下を繕っているお母さんがジャガイモくらいある爪先の穴を見て「やれやれ、新ジャガの季節だものね」と言うんですが、これもわからない。学研文庫版は「そういう頃だものね」福武文庫版は「穴があくころなのよね」です。そろそろ穴があくころだったから仕方がない、というニュアンスなのでは? p76の4行目「するとアルフレッド卿は、まるで自分が保護区にいる…」も、わからない。旧訳よりわかりにくい訳になってしまったら、訳し直す意味がないのでは?
アカシア:歴史的に意味がある作品だというのはわかるけれど。
ウグイス:70年代に学研文庫で出たときは、当時としてはすごくおもしろかったのよ。だから、その頃からこの本が好きだった人は、ずっと手に入らなくなったのを残念に思ってたから、新しい版が出た、ウェルカムという感じなんじゃない? 図書館でも古いのはぼろぼろになったりしているから。
ミッケ:せっかくだからというので、旧訳と新訳を読み比べようと思って、まず旧訳を半分くらいまで読んだんです。それで、ふうん古くさいところもなくはないけれど、けっこうわかりやすい柔らかい訳だなあと思ったところで、時間切れであわてて新訳をまた最初から読み始めたら、なんかこの訳者は力はいりすぎてるみたいだ、これって男の子の一人称だからわざと堅くしたのかなあ、それにしてもちょっとやりすぎじゃあないかな、という感じで、結局、かえって古い訳のほうが読みやすいという結論に達しました。だから、皆さんがおっしゃったとおり、どうして新訳を出したの?という感じです。新訳は、よく意味の通らない箇所があるし……。さっきからお話を聞いていると、どうやら旧訳の訳者は、学研文庫の訳を福武の文庫本にするときにも、訳に手を入れているようで、ていねいだと思うけれど、新訳はちょっと……。アーサー・ランサムが一時期大好きだった人間からすると、同じ湖水地方の同じように湖と島の冒険なので、ついついランサムを思い出してしまうけれど、ランサムに比べると、かなり弱い気がします。
アカシア:私もランサムのほうがうまいと思う。ヨットの帆を操作する部分とか、情景とか、細かく目にうかぶように描かれていますよね。
ミッケ:たしかにランサムも、いかにも大英帝国という価値観とか、女性のあり方とか、今とはずれているところもがあって、古いといえばいえるけれど、でもやっぱりしっかり書けているからこそ、あれだけいろいろなエピソードが出てきて、物語が展開されていったわけで、それに比べるとこの作品はかなり見劣りがすると思う。
(「子どもの本で言いたい放題」2006年11月の記録)